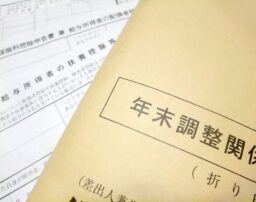労働者にとって、もっとも重要な労働条件のひとつが「給料(賃金)」でしょう。
給料が支払われない、あるいは未払いがあるとなれば一大事です。
給料の未払いがあった場合に、検討すべき相談先や、支払いに向けた対処法にはどのようなものがあるでしょうか。
給料に関する基本的な知識とあわせて、解説していきます。
賃金の未払いは労働基準法違反
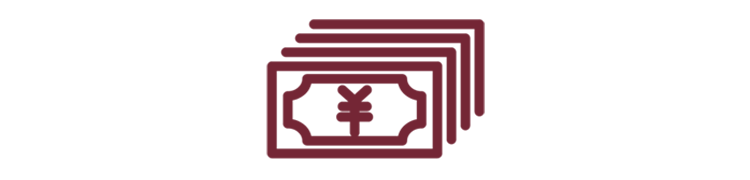
労働基準法では、会社が労働者に対して、基本給をはじめとする賃金を支払う際のルールが定められていますので、まずその点について説明いたします。
(1)会社が支払うべき「賃金」の種類
労働基準法では、「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を総称して「賃金」と呼んでいます(11条)。
具体的な賃金の種類としては、「基本給」「残業代(休日手当・深夜手当を含む)」「ボーナス」「退職金」「休業手当」「年次有給休暇取得時の賃金」等があります。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
引用:労働基準法11条
(2)会社が守るべき賃金支払いのルール
会社が賃金を支払う際には、守るべき4つのルールがあります。
1項本文 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
引用:労働基準法第24条
2項本文 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
- 通貨払いの原則
その趣旨は、安全・便利な方法で賃金を受領させることを保障することにあります。現物支給などによって代えることはできません。
- 直接払いの原則
その趣旨は、中間搾取の防止にあります。
- 全額払いの原則
その趣旨は、労働者の経済生活の安定にあります。分割払いなどによることはできません。
- 毎月1回以上定期払いの原則
その趣旨は、これも労働者の経済生活の安定にあります。複数月の分をまとめて支払うことはできません。これは年俸制の場合も同様です。
支払い遅れ等、これらのルールに違反した使用者には罰則が課される可能性があります。
(労働基準法120条1号)
賃金の支払いに関連して、以下に掲げる4つについて未払いがあった場合は、会社に付加金を請求できるケースがあります(労働基準法第114条)。
- 解雇予告手当(労働基準法第20条第1項)
- 休業手当(労働基準法第26条)
- 時間外休日労働等に対する割増賃金(労働基準法第37条)
- 年次有給休暇取得時の賃金(労働基準法第39条第9項)
また、賃金を支払う際には会社は給与明細書を交付しなければなりません(所得税法第231条)。
(3)賃金請求権には、時効がある

会社からの未払い賃金(就業規則等で定められた期日通りに支払いがされなかった賃金)があった場合は、さかのぼって請求できる可能性があります。
ただし、賃金請求権(退職手当を除く)には「2年」ないし「3年」という2種類の消滅時効期間があります。
具体的には、2020年4月1日より前に支払期日(給料日)の到来する賃金請求権については2年、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金請求権については3年が消滅時効期間となります。
給料の未払いがあった際の相談先
未払い賃金の請求には法務知識や交渉ノウハウ等が必要なため、なるべく早く弁護士や専門機関に相談することをおすすめします。
(1)労働トラブルに精通した弁護士
弁護士に相談すると、法律や判例等に基づいたアドバイスを得られるほか、会社との交渉を依頼することもできます。
その他、弁護士に相談・依頼する具体的なメリットとしては、以下のようなものがあります。
- 残業代の消滅時効期間を確認してもらえる
- 消滅時効期間の更新や完成猶予など、時効の完成を阻むための手続きをしてもらえる
- 支払われるべき賃金(正確な残業代等)を計算してもらえる
- 残業を含む労働実態の証拠収集を行なってもらえる 等
(2)その他の代表的な相談先
弁護士以外の相談先としては、以下のような公的機関の窓口があります。
- 管轄の労働基準監督署
- 各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」
- 厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」
- 全国労働組合総連合の「労働相談ホットライン」
- 日本労働組合総連合会の「なんでも労働相談ダイヤル」
給料未払いの対処法
ここからは、未払いの給料があった場合の対処法についてです。
(1)まずは証拠を集めよう
未払い賃金を請求するにあたっては、労働条件・労働時間の実態・支払い賃金の実態を示す証拠が必要となります。その観点から、以下のような証拠が有用といえます。
- 雇用契約書や就業規則
- 給与明細書
- タイムカードやPC使用時間等の客観的な記録
客観的な記録が難しい場合は、業務指示書やメール、研修資料や日報、オフィスビルへの入退館記録等も証拠として認められる可能性があります。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(2)会社に請求しよう
賃金の未払いへの対処法としては、大きく分けて以下の3つがあります。
- 会社に直接申し入れる
- 労働基準監督署に相談・申告する
- 法的手続きをとる(労働審判、支払督促、訴訟、民事調停)
ただし、労働基準監督署への相談・申告については、制度の改善に向けた効果は期待できるものの、個々のトラブルの解決を目的とした機関ではないため、給料未払いに対する効果は間接的なものといえます。
会社との交渉や、法的手続きの際には、証拠を取りそろえた上で、労働トラブルに精通した弁護士への相談・依頼することをおすすめします。
(3)会社が倒産した場合は「未払賃金立替払制度」の利用を
「未払賃金立替払制度」とは、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
「未払賃金立替払制度」を利用すると、最大で未払賃金の8割を国に立替払いしてもらえる可能性があります。限度額は、退職時点の年齢によって異なります。
立替払いの請求ができるのは、会社の倒産から2年以内となっています。
立替払を受けるためには、一定の要件をみたす必要があります。
未払賃金立替払制度に関して詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】未払い給料は弁護士や公的機関に早めの相談を
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 給料の支払いについては労働基準法でルール化されており、未払いの給料があった場合は、さかのぼって請求できる可能性があります。
- 未払い給料の請求手続きには、法務知識や交渉ノウハウが必要なため、なるべく早く弁護士や専門機関に相談することをおすすめします。
- 未払い給料の請求においては、証拠集めが重要となります。
- 未払い給料問題に対処するための方法には、大きく分けて「会社との直接交渉」「労働基準監督署への申告」「法的手続き」の3種類があります。
- 会社が倒産している場合には、国の「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性もあります。
給料の未払いでお悩みの方は、公的機関や弁護士などの専門家に相談ください。