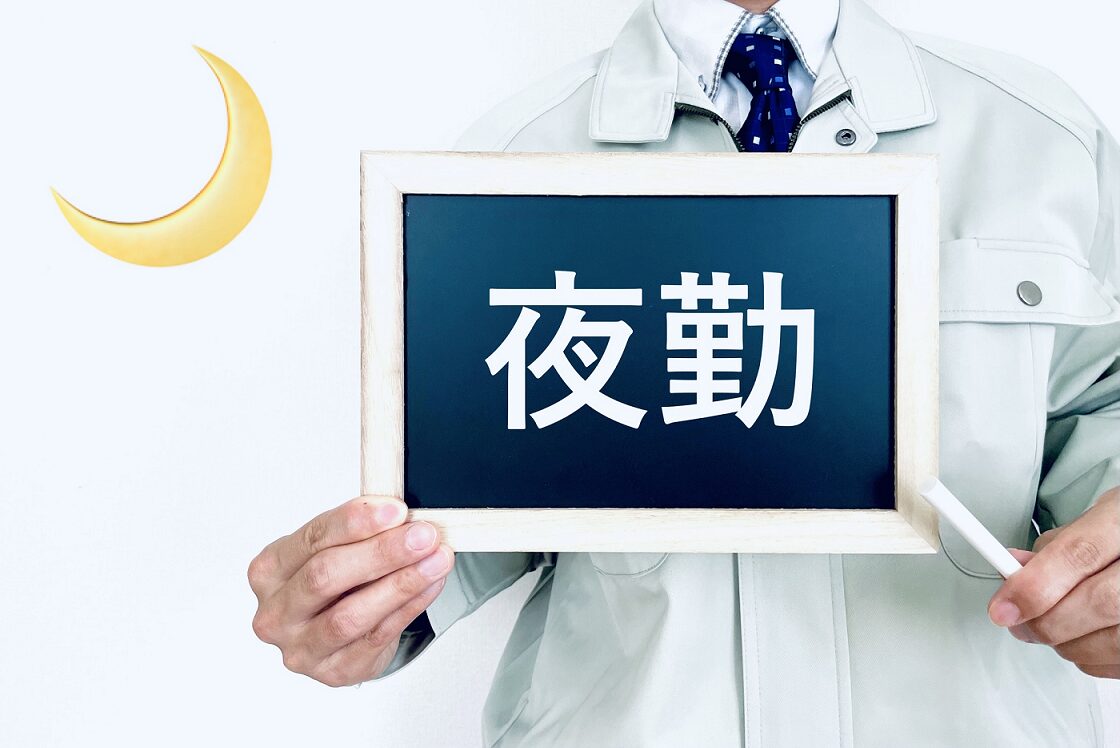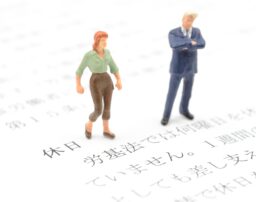夜勤は多くの業種で不可欠な労働形態ですが、その特殊性ゆえに様々な法的規制や注意点があります。
労働者の健康を守りつつ、効率的な業務運営を行うためには、夜勤に関する労働基準法の規定を正しく理解することが重要です。
本記事は、夜勤について特に注意したい、割増賃金と休日の考え方などについて説明しますので、参考にしてください。
この記事をよんでわかること
- 夜勤とは
- 深夜労働の割増賃金率
- 夜勤と休憩
- 夜勤と休日
- 夜勤と健康診断
ここを押さえればOK!
夜勤の労働時間計算では、日をまたぐ場合でも1日の勤務として扱われます。例えば午後8時から翌日午前6時までの勤務は、始業時刻のある日の労働として計算されます。
割増賃金は深夜労働だけでなく、時間外労働や休日労働と重なる場合はそれぞれの割増率を合算する必要があります。具体的な計算方法は勤務時間帯によって異なるため、正確な把握が重要です。
休憩については、6時間超の勤務で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩が必要です。休日は週1日以上または4週4日以上の付与が義務付けられています。
特定の労働者(妊産婦、未成年者、育児中の労働者)には夜勤の制限があります。また、常時夜勤に従事する労働者には6ヶ月ごとの健康診断実施が義務付けられています。
夜勤に関するトラブルが発生した場合は、社内での対話、労働組合への相談、労働基準監督署や労働局への相談、弁護士への相談など、段階的に対応することが効果的です。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
自宅でらくらく「おうち相談」
「仕事が忙しくて時間がない」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
夜勤とは
夜勤とは、一般的に夜から明け方までなど、日をまたいで勤務することを言います。
工場や介護施設、病院、コンビニエンスストアなどで多い働き方です。
「午後10時から午前5時まで」の労働は、深夜労働として、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。
また、勤務中に日にちが変わった場合には、2日の勤務と分けるのではなく、1日の勤務とされます。
例えば、8月7日の午後8時~翌8日の6時まで働く場合、始業時刻のある8月7日の労働として賃金計算が行われ、勤務日数は1日の扱いとなります。そのため、8時間連続で勤務するものとして、1時間の休憩が必要です。
参考:改正労働基準法の施行について(昭和六三年一月一日 基発第一号、婦発第一号)|厚生労働省
使用者は、夜勤シフトの作成や賃金計算の際に、このルールを念頭に置く必要があります。また、労働者も自身の権利を理解し、必要な休憩を取り、深夜労働に対する適切な報酬を受け取るようにしましょう。
夜勤に対する割増賃金の規定
労働基準法第37条は、夜勤時間帯(午後10時から午前5時まで)の労働に対して、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払うことを義務付けています。
また、1日8時間、1週40時間を超える時間外労働や休日労働と重なる場合は、それぞれの割増賃金を合算する必要があります(※)。
そのため、夜勤の給与計算は複雑になることがあります。
具体例でみていきましょう。
※時間外労働をさせるためには、36協定と呼ばれる労使協定が必要です。36協定により、原則月45時間、年360時間の時間外労働が可能となります(労働基準法36条4項)。
午後9時から翌午前8時まで働くケース(定時は午後9時~翌6時まで)
例えば、午後9時から翌午前8時まで11時間勤務した場合の割増率を考えます。
このケースの割増率は、基本的に以下のようになります。
- 午後9時~午後10時:割増なし
- 午後10時~午前1時:深夜労働として25%以上の割増率
- 午前1時~午前2時:休憩1時間
- 午前2時~午前5時:深夜労働として25%以上の割増率
- 午前5時~午前6時:割増なし
- 午前6時~午前8時:時間外労働として125%以上の割増率(※)
※ 時間外労働が月60時間を超えた部分は150%以上の割増率
使用者は、労働時間を把握し、適切な割増賃金を支払う義務があります。労働者も自身の賃金計算が正確に行われているか確認することが大切です。
午後6時から翌午前6時まで働くケース(定時は午後6時~翌3時まで)
例えば、午後6時から翌午前6時まで12時間勤務した場合の割増率を考えます。
このケースの割増率は、基本的に以下のようになります。
- 午後6時~午後10時:割増なし
- 午後10時~午後11時:休憩
- 午後11時~午前4時:深夜労働として25%以上の割増率
- 午前4時~午前5時:深夜労働と時間外労働として150%以上の割増率(※)
- 午前5時~午前6時:時間外労働として125%以上の割増率
※時間外労働が月60時間を超えた部分は150%以上の割増率
使用者は、労働時間を把握し、適切な割増賃金を支払う義務があります。労働者も自身の賃金計算が正確に行われているか確認することが大切です。
夜勤の休憩の考え方
労働基準法34条1項に基づき、夜勤中も適切な休憩時間を確保する必要があります。
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることが義務付けられています。
労働基準法第34条
第1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも四十五分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
また、この休憩時間は、雇用形態にかかわらず、原則としてその事業場の従業員に一斉に付与しなければなりません。ただし、例外は多いです。一度に休憩を与えなくてもいいとされる業種が施行規則で定められており(労働基準法施行規則31条)、また労使協定により別々に休憩を与えることも可能になります。
労働基準法第34条
第2項 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
さらに、労働者は自由に休憩時間を過ごすことができ、使用者が指示することはできません。
労働基準法第34条
第3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
例えば、午後10時から午前7時までの9時間勤務の場合、労働時間が8時間を超えていますので、原則1時間のまとまった休憩が必要です。
夜勤の休日の考え方
労働基準法は、夜勤について特別な休日を設けているわけではありません。
しかし、夜勤労働者に対しても、労働基準法35条に従い次のどちらかの休日を与える必要があります。
- 週1日以上の休日
- 4週4日以上の休日
労働基準法第35条
第1項 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
第2項 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
週1回の法定休日は、原則として0時からの継続した24時間である必要がある点に注意します(※)。
例えば、8月7日午後6時~8日午前6時の勤務で、8日午前6時から9日午前6時までの24時間を休日とし、9日の午前6時から勤務としても、法定休日を与えたことになりません。
このような勤務形態だと、35条に違反することになります。
この場合、夜勤明けの8日は休みとし、さらに翌9日の0時から24時までを法定休日としたうえで、10日からの出勤とする必要があります。
※この法定休日の考え方には例外もあります。
夜勤の労働時間計算:正確な管理と注意点
夜勤の労働時間計算は、暦日をまたぐため複雑になりがちですが、正確な管理が法令遵守と適切な賃金支払いの基本となります。
労働基準法に基づき、実労働時間を正確に把握し、適切に管理することが重要です。
夜勤の労働時間管理のポイント:
- 実労働時間の正確な記録
- 暦日をまたぐ場合の適切な計算
- 割増賃金の正確な計算
例えば、タイムカードやICカード、勤怠管理システムなどを活用し、出退勤時刻を正確に記録することが推奨されます。また、管理者は労働時間の集計方法を理解し、適切に処理する必要があります。
正確な労働時間管理は、労働者の権利保護と使用者のリスク管理の両面で重要です。適切な管理体制を構築し、定期的なチェックと見直しを行うことで、法令遵守と健全な労働環境の維持につながります。
特定の労働者に対する夜勤規制|夜勤ができない人
労働基準法は、特定の労働者に対し深夜労働に関する特別な規定を設けています。これは、特別に保護されるべきと考えられる労働者の健康を守るためです。
【夜勤ができない労働者】
- 妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない女性):本人が請求した場合は深夜労働不可(労働基準法66条3項)
- 未成年者(18歳未満):原則、深夜勤務不可。ただし、交代制で勤務する16歳以上の男性は別(労働基準法61条1項)
- 育児中の労働者(男女問わず):小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合は、原則深夜労働不可(育児・介護休業法19条1項)
これにより、例えば、妊娠中の女性労働者が夜勤免除を申し出た場合、使用者は原則としてその請求を拒否できません。
また、就学前の子を養育する労働者が夜勤免除を申し出た場合も、使用者は事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、原則として深夜労働をさせることはできません。ただし、雇用期間が1年未満、その子を養育できる同居の家族がいるケースなどでは、深夜勤務をさせることができます(育児・介護休業法19条1項)。
使用者は、これらの規制を遵守し、対象となる労働者に適切な配慮を行う必要があります。
同時に、他の労働者への負担増加を避けるため、適切な人員配置と業務分担を行うことが重要です。
夜勤労働者の健康管理|特別な健康診断
使用者は夜勤労働者に対して、次の健康診断を実施する義務があります(労働安全衛生規則45条、13条1項3号ヌ)。
健康診断の主なポイント:
- 実施頻度:6ヶ月以内ごとに1回
- 対象者:常時夜勤に従事する労働者
- 健診項目:同規則44条1項各号記載の下記内容
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
使用者は、健康診断の結果に基づき、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じる必要があります。これにより、夜勤労働者の健康リスクを早期に発見し、適切な対応を取ることができるでしょう。
夜勤に関するトラブル対応:相談先と解決方法
夜勤に関するトラブルが発生した場合、適切な相談先を知り、効果的な解決方法を選択することが重要です。主な対応方法は以下の通りです。
- 社内での対話
- 上司や人事部門との話し合い
- 労働組合への相談
- 組合がある場合、組合を通じた交渉
- 外部機関への相談
- 労働基準監督署:法令違反(36協定未締結、健康診断未実施など)の疑いがある場合
- 労働局の総合労働相談コーナー:労働問題全般(解雇、配置転換、給与引き下げ、パワハラ、セクハラなど)の相談
- 弁護士:状況を踏まえた具体的な法的アドバイスが必要な場合、未払い残業代を請求して欲しいなど希望が明確な場合 など
- 法的手段の検討
- 直接交渉
- 労働審判:裁判所での手続き。迅速な解決が特徴(原則3回以内の期日で審理)
- 民事訴訟:裁判所での手続き。長期化する可能性はあるが労働審判よりも詳細に心理。
例えば、割増賃金の未払いがある場合、まず会社と話し合い、改善されない場合は労働基準監督署や労働局に相談、代理で請求して欲しいときには弁護士など、段階的に対応することが効果的です。
割増賃金については、消滅時効があります。悩んでいるうちに消滅時効にかかって請求できなくなる可能性がありますので、なにか疑問や悩みがあるときには、早めに相談して解決を目指すことが重要です。
まとめ:労働基準法における夜勤の重要ポイント
- 夜勤と割増賃金
- 夜勤は一般的に日をまたいで勤務することを言い、深夜労働:午後10時から午前5時までの労働を含む。
- 深夜労働は、通常賃金の25%以上の割増賃金が必要
- 休憩と休日の取り扱い
- 夜勤中も適切な休憩時間の確保が必要
- 週1日以上の法定休日又は4週4日以上の休日の付与が義務付け
- 特定労働者への配慮
- 妊娠中・小学校入学前の子の育児中の労働者、未成年者に対する夜勤制限あり
- 健康管理の義務
- 6ヶ月ごとの健康診断の実施が義務付け
- 36協定の締結
- 夜勤を含む時間外労働には36協定の締結が必要
- トラブル対応
- 労働基準監督署への相談や指導を活用
夜勤労働者の健康と権利を守るためには、適切な労働時間管理、健康診断の実施、休憩時間及び休日が確保されている必要があります。
使用者は法令を遵守し、労働者は自身の権利を理解することが重要です。
本ガイドを参考に、あなたの職場の夜勤体制を見直してみましょう。休日が法律上のルール通りに与えられていない、妊娠しているのに夜勤を免除してもらえないなど、疑問や不安がある場合は、躊躇せず労働基準監督署などへ相談するようにしましょう。
具体的に未払いの割増賃金を請求したいという場合には、残業代請求を扱っている法律事務所に相談するとよいでしょう。
アディーレ法律事務所では、未払い残業代請求を扱っており、未払い残業代請求に関するご相談は何度でも無料です。
また、アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、着手金はいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2024年8月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください