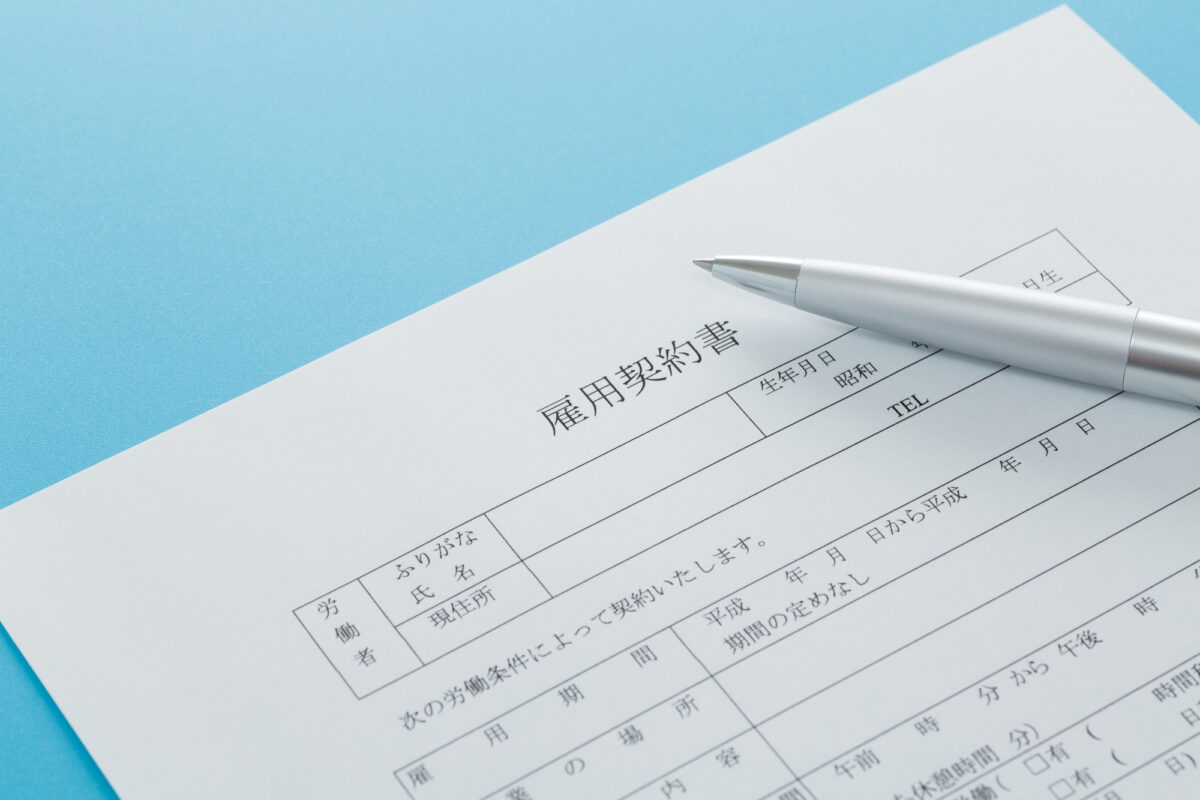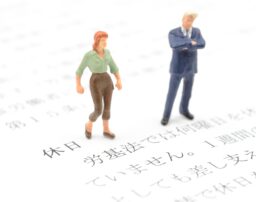ここを押さえればOK!
無期雇用との主な違いは、雇用期間の定めの有無です。2013年の労働契約法改正により、有期雇用から無期雇用への転換制度が導入されました。
労働契約法改正による3つの重要ルールは、無期労働契約への転換制度、雇止め法理の法定化、不合理な労働条件の禁止です。これらにより、有期雇用労働者の立場が強化されました。
有期雇用でも昇給や賞与、育児休業の取得が可能な場合があります。
なお、無期転換後の労働条件は、特別な定めがない限り転換前と同じになります。
有期雇用契約の基礎知識
まずは、有期雇用契約の基本的な特徴や、無期雇用との違いについて解説します。
(1)有期雇用契約とは?基本的な特徴
有期雇用契約とは、「契約期間1年」など、雇用期間を定めて締結する労働契約のことです。
この契約形態の主な特徴は以下の3点です。
- 契約期間が明確:雇用期間が「〇年〇月〇日~〇年〇月〇日」など明確に定められている
- 期間満了で自動終了:別段の定めがない限り、契約期間の満了とともに雇用関係が終了
- 更新の可能性:契約更新が行われる場合もある
有期雇用契約の期間は、原則として最長3年までと定められています(労働基準法第14条1項)。ただし、高度な専門知識を有する労働者や60歳以上の労働者については、最長5年まで認められています。
有期雇用契約は、企業にとって人材需要の変動に対応できる柔軟な雇用形態ですが、労働者の立場からは、雇用期間のない無期雇用と比べて、雇用の安定性に課題があります。
そのため、労働契約法では、無期転換ルールや雇止め法理の法定化など、有期雇用労働者を保護するための規定が設けられています。
(2)無期雇用との違い
有期雇用と無期雇用の最大の違いは、雇用期間の定めの有無です。
具体的には以下のような違いがあります。
【有期雇用と無期雇用の違い】
| 無期雇用 | 有期雇用 | |
|---|---|---|
| 雇用期間 | 期間の定めがない(定年まで継続) | 1年、6ヵ月など期間が明確に定められている |
| 契約更新 | 更新の概念がなく、原則として継続 | 期間満了時に更新するか終了するかを判断 |
| 雇用の安定性 | 原則として定年まで雇用が継続され、安定性が高い | 契約期間満了時に雇用が不安定になる可能性がある |
ただし、2013年の労働契約法改正により、有期雇用から無期雇用への転換制度が導入されました(労働契約法第18条1項)。同一の使用者との間で、有期雇用契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期雇用契約に転換できます。
これにより、長期的に働く有期雇用労働者の雇用安定化が図られています。
労働契約法改正による3つの重要ルール
2013年の労働契約法改正により、有期雇用労働者の立場が大幅に強化されました。
主な変更点について解説します。
(1)ルール1:無期労働契約への転換制度(無期転換ルール)
無期転換ルールは、有期雇用労働者の雇用安定化を図る重要な制度です。
無期転換の申込ができる条件は次の3つです。
- 同一の使用者との間で契約更新すること
- 1回以上の契約更新がなされている
- 有期労働契約の通算期間が5年を超えている
この条件を満たしている場合に、労働者が無期雇用契約への転換を申し込めば、使用者はその申し込みを承諾したとみなされます。
ただし、一度契約期間が終了した後、無契約期間が一定以上続いて、再度同じ使用者に有期雇用された場合には、それ以前の有期雇用期間は通算されずにリセットされます(クーリング、労働契約法第18条2項)。
また、一部の業種の有期雇用の場合、無期雇用転換のルールが異なることにも注意が必要です。
たとえば、大学等や研究開発法人での一定の研究者・技術者・教員は、通算期間は5年ではなく10年必要とされています(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」)。
(2)ルール2:雇止め法理の法定化による労働者保護の強化
「雇止め法理」とは、有期雇用労働契約をしている労働者を保護するため、「雇止めに一定の制限をかける」という考え方です。
元々は最高裁判所判決で、雇止め法理が示されてきましたが、労働契約法の改正で雇止め法理が明文化されました(労働契約法第19条)。
雇止め法理の法定化により、有期雇用労働者の雇用継続に対する期待が法的に保護されるようになりました。
具体的には次のいずれかの場合、期間満了前に労働者が契約の更新の申し込みをするか、期間満了後すぐに有期労働契約締結の申し込みをすると、使用者による雇止めは簡単には認められません。
- 過去に反復更新されており、無期雇用契約と実質的に同じ場合
- 労働者が、有期労働契約の更新を期待することが合理的な場合
これらの条件に該当する場合、雇止めをするには、使用者が労働者からの契約更新の申し込みなどを拒否することが、客観的に見て合理的な理由があり、社会通念上相当である必要があります。
これらの要件を満たさない雇止めは無効です。雇止めが無効となると、従前の有期労働契約と同じ労働条件で、雇用が継続することになります。
(3)ルール3:不合理な労働条件の禁止(同一労働同一賃金)
有期雇用労働者と無期雇用労働者との間で、不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されました(現在はパートタイム・有期雇用労働法第8条で定められています)。
待遇の違いが不合理と認められるかどうかについて、具体的には次の点が考慮されます。
- 職務の内容
- 職務の内容・配置の変更範囲
- その他の事情
たとえば、同じ仕事をしていて、職務の内容や配置の変更範囲も同じ、その他の事情もないのに、有期雇用というだけで、無期雇用者と賞与や退職金、各種手当てなどで大きな差をつけることは、不合理とされる可能性が高くなります。
国も、同一労働同一賃金ガイドラインを定め、不合理な待遇差をなくす取り組みを行っています。
参考:パートタイム・有期雇用労働法の概要|厚生労働省
参考:同一労働同一賃金ガイドライン|厚生労働省
契約期間と解除に関するルール
次に、雇用契約の期間と解除に関するルールについて解説します。
(1)契約期間の制限:原則3年、例外5年
前述したとおり、有期雇用契約の期間は原則として最長3年ですが、一部の例外では5年まで認められています。
具体的には次のとおりです。
- 原則:最長3年
- 一般の労働者に適用
例:事務職、販売職、製造業の現場労働者など
- 一般の労働者に適用
- 例外:最長5年
- 高度な専門的知識等を有する労働者
例:博士号取得者、公認会計士、弁護士など - 満60歳以上の労働者
- 高度な専門的知識等を有する労働者
これらの制限は、労働者の長期的な拘束を防ぐためのものです。ただし、この上限を超えて契約を更新すること自体は可能です。
また、前述のとおり、有期雇用期間が通算5年を超えると原則として無期転換の申込みが可能になります。
参考:有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準について|厚生労働省
(2)契約期間の途中解除(中途解約):「やむを得ない事由」が必要
基本的に、有期雇用契約の期間中は自分から退職することはできませんし、会社も解雇することはできません。
しかし、「やむを得ない事由」がある場合は、有期雇用契約の期間中の契約解除=退職や解雇が認められます(民法第628条、労働契約法第17条)。
具体例は次のとおりです。
- 労働者側の事由
- 病気・ケガ
- 介護
- 給料未払い など
- 使用者側の事由
- 会社の経営状況が著しく悪化し、事業継続が困難な場合
- 天災等による事業所の消失 など
仮に、会社による解雇が有効だとしても、1日契約や試用期間中などの例外を除いて、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要となります(労働基準法第20条1項)。
有期雇用に関するよくある質問と回答
(1)有期雇用でも昇給や賞与はありますか?
法律上のルールはないので、企業の方針によります。
一般的に、有期雇用であっても勤務期間や人事考課などを考慮して昇給や賞与のある企業が少なくありません。
(2)有期雇用でも育児休業は取得できますか?
申出の時点で次の条件を満たせば、有期雇用であっても育児休業を取得可能です。
- 子が1歳6ヵ月(または2歳)になるまでの間に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
以前は、「申出時点で、同一の使用者に引き続き雇用された期間が1年以上であること」という条件もありました。2022年の法改正によりこの条件がなくなり、有期雇用でも育児休業を取得しやすくなっています。
(3)無期転換後の労働条件はどうなりますか?
就業規則や雇用契約などで特別な定めがない場合には、転換前直前の労働条件が継続されます。
無期契約に転換したからといって、当然に、使用者が定義する「正社員(一般的には、無期雇用で直接雇用されていて、月給制のフルタイムの社員)」になれるわけではありません。
【まとめ】無期転換ルール・雇止め法理の法定化により、有期雇用の不安から解放されるかも!
有期雇用契約は、労働者にとって不安定な雇用契約ですが、通算期間が5年を超えると無期転換の申込みが可能になるなど、近年の法改正により労働者の権利が強化されています。
また、不合理な労働条件の禁止により、正社員との待遇差も是正されつつあります。
自身の雇用状況を今一度確認し、必要に応じて無期転換の申込みなどを検討してみましょう。