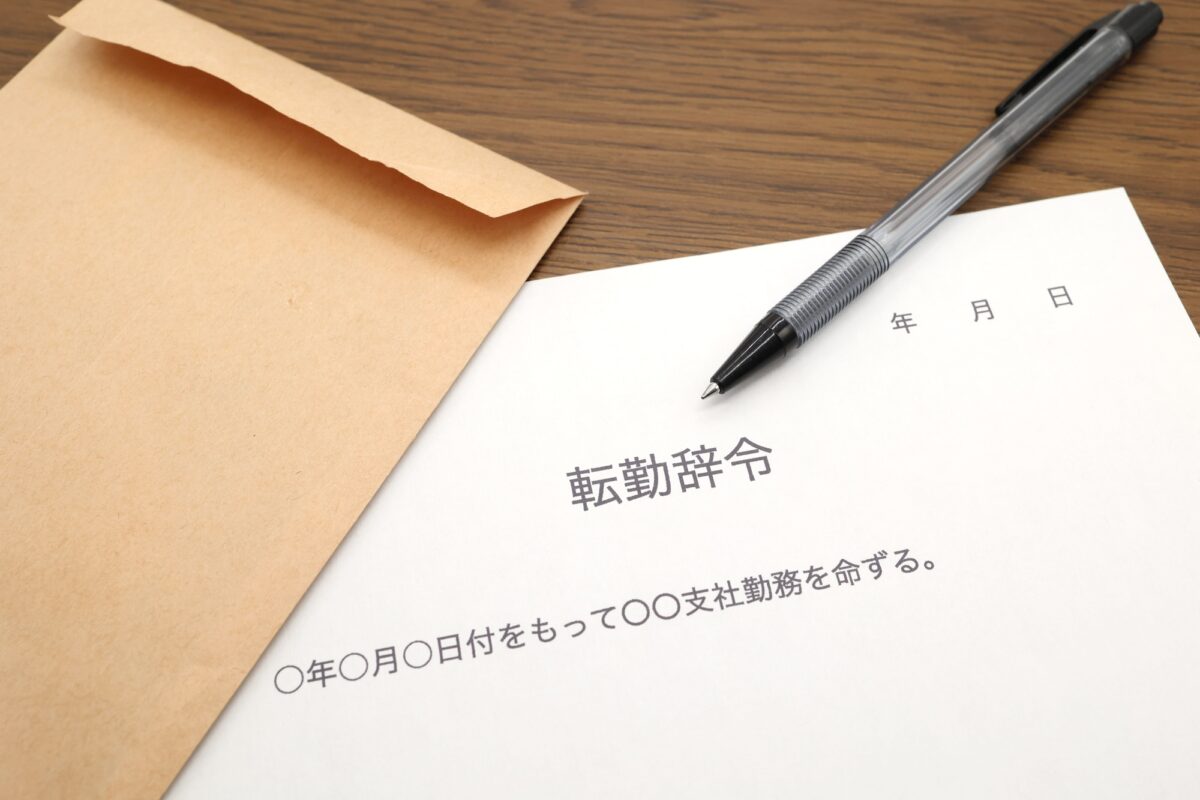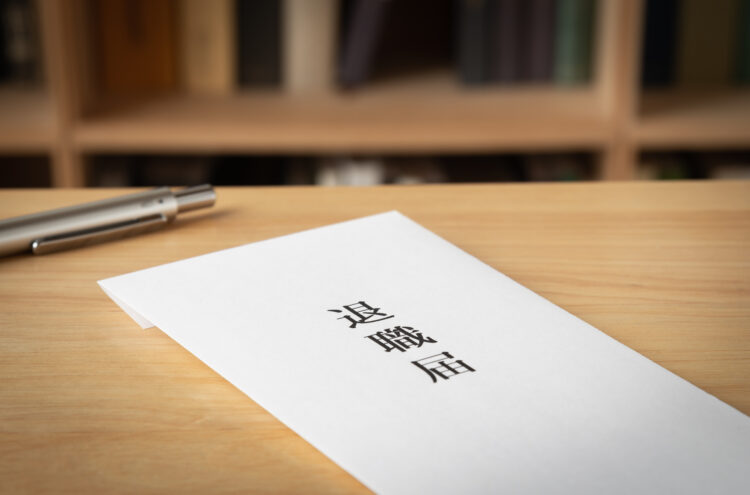突然、転勤を命じられて戸惑い、退職も視野に入れている方へ。
本記事では、法的な観点から、転勤を拒否できる正当な理由や、退職時の注意点などについて解説します。
なお、労働者には退職の自由があるため、会社には労働者を強制的に引き留める権利はありません。
ここを押さえればOK!
転勤の命令には業務上の必要性があり、労働者に不当な不利益を与えないことが必要と考えられています。
労働者側には、家族の事情(介護・育児)や健康上の理由など、転勤を拒否できる正当な理由があると認められる場合があります。ただし、具体的な根拠や証拠によってそれらを示すことが必要です。
転勤を拒否できない場合、労働者が退職を選択することもありますが、多くは自己都合退職となり、退職金や失業保険に影響があると考えられます。
受け容れ難い転勤の命令を受けた際は、就業規則を確認し、会社と冷静に話し合うことが重要です。
必要に応じて、専門家や社外の相談窓口を利用することも検討すべきでしょう。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
自宅でらくらく「おうち相談」
「仕事が忙しくて時間がない」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
転勤したくないから退職:法的な観点から解説
転勤の打診を受けて退職を考えている方は少なくありません。
基本的に労働者には退職の自由がありますが、転勤を理由に退職を検討している方にとって、法的な観点からの理解は非常に重要です。
まず、会社(使用者)には、事業を円滑に運営するために、特定の労働者の職務内容や勤務場所を変更する権限である「配転命令権」が認められています。
しかし、この配転命令権は無制限ではありません。
転勤の命令が、業務上の必要性がない、不当な動機・目的に基づくものである、労働者に著しい不利益を与えるという事情があれば、権利を濫用するものとして無効とされます。
たとえば、単なる嫌がらせや退職勧奨目的で転勤を命じることは無効とされる可能性が高いといえます。
転勤命令が無効、すなわち労働者側が転勤を拒否することに正当な理由があるとされるのは、具体的には以下のような場合です。
転勤を拒否できる正当な理由
転勤を拒否できる正当な理由として代表的なのが、家族の事情(介護・育児)や健康上の理由です。
(1)介護を必要とする家族の存在を理由とする転勤拒否
転勤拒否の正当な理由として認められる可能性のある事情として、介護が必要な家族がいる場合が挙げられます。
ただし、単に家族が転居を望まないという理由だけでは不十分であり、自分が転勤することで家族の介護に著しい支障が生じるとの客観的事情が求められます。
育児介護休業法第26条は、会社に対し、就業場所の変更によって働きながら子の養育又は家族を介護することが困難となる労働者がいるときは、その子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならないとしております。
会社側がそうした配慮、すなわち介護の具体的な状況を把握し、その負担を軽減する手段の提案などをしていた場合、それでも転勤によって労働者に著しい不利益が生じるといえる根拠を具体的に示す必要があるでしょう。
(2)健康上の理由による転勤拒否
健康上の理由は、転勤拒否の正当な理由として認められることがあります。
たとえば、本人や家族の持病の治療が現在の居住地でしか受けられない場合や、転勤によって病状に悪影響を及ぼす可能性が高い場合などがそれに当たるでしょう。
ただし、単なる不安や懸念ではなく、医師の診断書など客観的な証拠が必要です。
また、会社側が病状を把握し、適切な対策などを提案した場合には、それでも転勤をすることで病状に悪影響を及ぼす可能性が高いことを具体的に示す必要があるでしょう。
(3)その他の転勤拒否が認められる場合
ほかにも転勤拒否が認められる場合として、採用時の雇用契約と異なる転勤命令や、不当な動機による転勤命令があります。
たとえば、採用時に「転勤なし」と明確に約束されていたにもかかわらず転勤を命じられた場合、労働者は正当に拒否できる可能性が高くなるでしょう。
また、嫌がらせや退職勧奨を目的とした転勤、あるいは労働組合活動を理由とした転勤など、会社側の不当な動機が明らかな場合も拒否の正当性が認められやすくなります。
ただし、会社側に不当な目的があるといえるかどうかは、具体的な事情や証拠に基づいて判断されます。
転勤を拒否できる可能性があるケースについては、こちらの記事もご覧ください。
転勤を理由に退職する際の注意点
転勤を拒否できない場合には、転勤したくないことを理由に退職することもあるでしょう。
その際の注意点についてご説明します。
(1)退職の意思表示と手続きの流れ
転勤を理由に退職する場合、まず退職の意思を明確に会社に伝える必要があります。
口頭での申し出も有効ですが、通常は退職届を提出します。
退職日は、就業規則で定められた期間を考慮して設定しましょう。
就業規則では1ヵ月程度の期間が定められている会社も多いですが、民法上の原則では退職の2週間前に申入れをすればよいことになっています(民法第627条1項)。
その後、業務の引き継ぎや、有給休暇の消化申請などの手続きを進めます。
なお、退職理由を「転勤したくないから」と明記するかは慎重に検討し、必要に応じて専門家に相談するとよいでしょう。
会社から退職を拒否された場合についてはこちらの記事をご覧ください。
(2)退職金や有給休暇の取扱い
転勤を理由とする退職の場合、退職金や有給休暇の取扱いに注意が必要です。
通常、転勤の命令を受けたことがきっかけの退職は自己都合退職となるため、退職金が減額されたり、支給されなかったりする可能性があります。
ただし、会社都合と認められれば全額支給されることもあります。
有給休暇については、会社に未消化分の買い取り義務はありません。退職日前に消化することをおすすめします。
また、退職金規定や就業規則を確認し、不明点は人事部門に問い合わせるなど、自身の権利を適切に行使することが重要です。
転勤による退職のリスクと対策
受け容れ難い転勤は、当然退職の理由となるでしょうが、リスクもあります。
(1)自己都合退職となるケース
前述のとおり、転勤を理由とする退職は、多くの場合自己都合退職として扱われます。特に、会社の転勤命令に業務上の必要性が高く、労働者側に拒否する合理的な理由が認められない場合がこれに該当します。
自己都合退職となると退職金が減額されたり、失業保険の給付に1ヵ月以上の待機期間が発生したりする可能性があるため、退職の決断には慎重な判断が必要です。
(2)会社都合退職となる可能性
転勤を理由とする退職が会社都合と認められるケースもあります。
たとえば、明らかに業務上の必要がない、労働者に著しい不利益を与える無効な転勤命令を受けたことで退職を余儀なくされた場合がこれに該当します。
転勤命令が退職させることを目的とした手段として利用されている場合もこれに該当します。
会社都合退職と認められれば、退職金の全額支給や失業保険のほぼ即時の受給が可能になるケースもあるでしょう。
ただし、その判断は個別の状況に応じて行われるため、弁護士などの専門家や公的機関に相談することをおすすめします。
転勤で退職が頭をよぎったら…
急な転勤の命令に、退職が選択肢に入ることもあるでしょう。
その際に気を付けたいことについてご説明します。
(1)転勤に関する就業規則を確認
転勤に関する権利や義務を理解するには、まず就業規則の確認が不可欠です。
就業規則は通常、会社の人事部門や総務部門などで閲覧できます。多くの会社では、イントラネットや社内システムでも確認可能なことも多いです。
就業規則の「異動」「配置転換」「転勤」などの項目を注意深く読み、転勤の条件や手続き、拒否の可能性について確認しましょう。
また、不明点がある場合は人事部門に直接問い合わせることをおすすめします。
(2)不当な転勤命令への対処法
転勤命令が不当だと感じた場合、まず会社と冷静に話し合うことが重要です。
その際、転勤が困難な具体的な理由や証拠を提示し、代替案を提案することが効果的な場合もあります。
話合いで解決しない場合は、労働組合に相談するか、社外の労働相談窓口を利用することをおすすめします。
場合によっては、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談し、法的なアドバイスを受けることも検討しましょう。
最終的には、労働審判や訴訟という選択肢もありますが、これらの手続を採るのかは慎重に判断する必要があります。いずれの場合も、冷静な対応を心がけることが大切です。
【まとめ】
本記事では、転勤と退職に関する法的な観点から、転勤を拒否できる正当な理由、退職時の注意点、労働者の権利などについて解説しました。
転勤を理由に退職を決意するかは個々の状況によって異なり、慎重な判断が必要です。
また、退職を決意してその意思を伝えても、会社がなかなか受け容れてくれないケースもあります。
そんな時は、弁護士による退職代行サービスの利用も一つの選択肢です。
弁護士のサポートを受けることで、あなたの権利を守りながら、スムーズな退職手続きを進めることができるでしょう。
退職代行の利用を検討している方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。