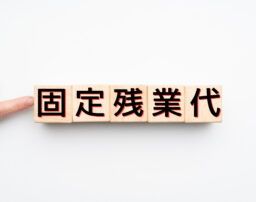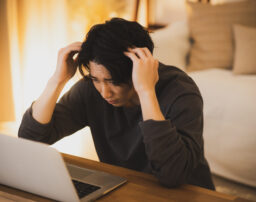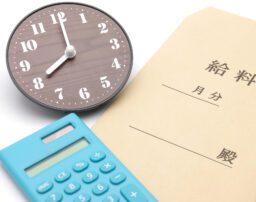裁量労働制では、労働時間に関する一定程度の裁量が労働者にあるため、残業が発生しないのではないかと考えている方がいるかもしれません。
確かに通常の働き方よりも残業は発生しにくいといえますが、まったく発生しないわけではないのです。
裁量労働制で損をすることがないよう、裁量労働制における残業について、理解を深めておきましょう。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
自宅でらくらく「おうち相談」
「仕事が忙しくて時間がない」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
裁量労働制の基礎知識
まず、裁量労働制の概要や適用業種、フレックスタイム制との違いといった点について、解説していきましょう。
(1)裁量労働制とは?
裁量労働制とは、業務の性質上、使用者による厳格な労働時間管理に馴染まないため、労働時間の具体的配分を労働者に委ね、実労働時間については労使協定又は労使委員会の決議で定められた時間の分だけ労働したものとみなす制度です。
みなし労働時間制の1つで、実際の労働時間には関係なく、一定時間にわたって働いたとみなされ、それに相当する報酬が支払われます。
(2)裁量労働制の種類と適用になる業種
裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」(労働基準法38条の3)と、「企画業務型裁量労働制」(同法38条の4)の2種類があります。
(2-1)専門業務型裁量労働制

業務の遂行手段や時間配分において、使用者の指示を与えるのが難しい職種に適用される制度です。
専門業務型裁量労働制を導入するにあたっては、労使協定を結び、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
適用の対象となる職種は、以下の19業務となっています。
- 新商品もしくは新技術の研究開発、人文科学もしくは自然科学の研究
- 情報処理システムの分析・設計
- 新聞・出版の取材もしくは編集、放送番組制作のための取材もしくは編集
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等のデザイナー
- 放送番組、映画等のプロデューサー・ディレクター
- コピーライター
- システムコンサルタント
- インテリアコーディネーター
- ゲーム用ソフトウェアの開発
- 証券アナリスト
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発
- 学校教育法に規定する大学における教授研究
- 公認会計士
- 弁護士
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 税理士
- 中小企業診断士
(2-2)企画業務型裁量労働制
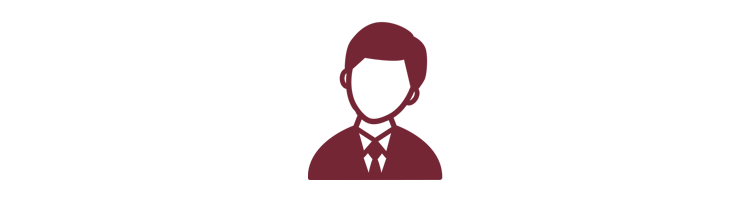
企画業務型裁量労働制は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその進行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の進行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」(労働基準法38条の4第1項第1号)を行う場合に、所定の手続きを踏むことによって導入することができます。
本社や本店などで経営に関与し、事業運営に関する企画、立案、調査、分析の業務を行う労働者が対象となる制度です。
導入にあたって必要な手続きとしては、会社内に「労使委員会」を組織した上で、委員の4/5以上の多数によって企画業務型裁量労働制の導入を決議し、労働基準監督署長に届け出ることとなります。
制度の対象となる労働者は、対象業務に従事する知識、経験等を有する労働者に限られます(同項2号)。また、対象労働者の個別の同意も必要となります。
裁量労働制について詳しくはこちらをご覧ください。
(3)裁量労働制とフレックスタイム制の違い
フレックスタイム制とは、一定の期間(「清算期間」と呼ばれます)を区切り、その期間の中で一定時間労働をすることとすれば、自由な時間に出勤や退勤をすることができ、1日の労働時間を自分で決めることができるという制度です。
フレックスタイム制では、必ず出勤する時間帯とされている「コアタイム」と、出退勤が自由な時間帯とされる「フレキシブルタイム」を分けて設定している企業もあります(設定は必須ではありません)。
裁量労働制との違いは、裁量労働制が成果に焦点を当てた制度であるのに対し、フレックスタイム制は自由な時間に効率的に働くことを目的としている制度であるという点です。
そのため、裁量労働制では実際の労働時間と関係なく成果に対応した分の時間を働いたとみなされるのに対し、フレックスタイム制ではあくまで実際に働いた時間が労働時間と扱われます。
また、制度を適用できる業務内容に関する制限がないという点も、裁量労働制と異なっています。
裁量労働制における残業代の計算方法
それでは、裁量労働制において残業が発生することはあるのか、あるとすればどのようなケースか、といった点について解説していきます。
(1)そもそも裁量労働制で残業は発生する?
裁量労働制は、実際の労働時間とは関係なく、一定の時間を働いたとみなされ、その「みなし労働時間」に相当する報酬が受け取れるという制度です。
したがって、所定労働時間を超えて働くという「残業」という概念は原則としてありません。
もっとも、一定の報酬に対応する「みなし労働時間」が、法定労働時間(原則として1日8時間・1週40時間)を超えている場合には、法定労働時間を超えた部分が時間外労働となり、所定の割増賃金が発生します。
また、休日労働(「原則週1回の法定休日」に行われた労働)および深夜労働(原則22~5時までに行われた労働)が行われた場合には、裁量労働制においてもそれぞれに対応する割増賃金が発生します。
さらに、法定外休日の労働についても、裁量労働制の対象外として、時間外労働の割増賃金が発生する可能性があります。
すなわち、法定外休日とは、原則週1回の法定休日以外に、使用者が与えている休日のことをいいます。例えば週休2日制の会社の場合、どちらか1日が法定外休日である可能性があります。
裁量労働制はあくまで所定労働日にだけ適用されるため、使用者の指示で法定外休日に労働させられた結果、原則1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働した場合には、超えた分につき時間外労働として割増賃金が発生します。
なお、裁量労働制においても、休憩時間に関する労働基準法34条の規制や、「1ヶ月45時間、1年間360時間」を原則とする「時間外労働の上限規制」については、それぞれ適用があります。
1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用:労働基準法34条
(2)裁量労働制で残業代が発生するケースと計算方法
それでは、裁量労働制で残業代(割増賃金)が発生する条件ごとに、計算方法を解説していきましょう。
(2-1)深夜労働をした場合
あらかじめ設定した「みなし労働時間」が、法定労働時間(原則として1日8時間・1週40時間)を超えるか否かにかかわらず、原則として22~5時の間に労働した場合、深夜割増賃金が発生します。
深夜労働に対する割増率は25%以上です。
1時間あたりの基礎賃金×割増率(0.25以上)×深夜時間帯の残業時間
1時間あたりの基礎賃金は、月給から、個人の事情に基づいて支給される「手当」を除外した額を、所定労働時間で割ることによって算出します。
「1時間あたりの賃金(基礎賃金)=(月給-手当)÷(月の平均所定労働時間)」
個人の事情に基づいて支給される手当とは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金がそれにあたります(労働基準法37条5項、同施行規則21条)。
1ヶ月あたりの平均所定労働時間は、
「(365日-年間の所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12」
という計算によって求められます。
(2-2)みなし労働時間が法定労働時間を超える場合
あらかじめ設定した「みなし労働時間」が、法定労働時間の1日8時間・1週40時間を超えた場合には、超えた部分が「時間外労働」となり、超過部分に応じた割増賃金が発生します。
この場合の割増賃金の計算式は、次の通り求められます。
1時間あたりの基礎賃金×割増率(1.25)×時間外労働時間
勤務先でみなし労働時間が何時間で設定されているか、労使協定で確認しておくと良いでしょう。
(2-3)休日労働をした場合
労働基準法35条は、使用者に対し「1週間あたり1日以上または4週間あたり4日以上」の法定休日を労働者に付与することを義務付けています。
法定休日は裁量労働制の適用外であって一定時間労働したとみなされる効果が及ばないため、法定休日に労働した場合には、35%の割増賃金が発生します。
休日労働に対する割増賃金は、次の通り求められます。
1時間あたりの基礎賃金×割増率(1.35)×休日労働の労働時間
(2-4)法定外休日に労働した結果、法定労働時間を超えた場合
法定外休日に対しては、裁量労働制の適用がありません。裁量労働制はあくまで所定労働日にだけ適用されるからです。
そのため法定外休日に労働した結果、法定労働時間を超えた場合は、時間外労働として割増賃金が発生します。
割増賃金の計算方法は次の通りとなります。
1時間あたりの基礎賃金×割増率(1.25以上)×時間外労働時間
簡単な質問に答えて、あなたの残業代がどのくらい未払いになっているのかチェックしよう!
以下の質問にお答えいただくだけで、あなたの残業代がいくらくらい未払いになっているのか簡単にチェックできます。
裁量労働制の未払い残業代を請求する方法
未払い残業代が確認できたら、証拠をもとに残業代の請求へと移りましょう。
(1)未払い残業の証拠を収集する
未払い残業を会社に請求するには、残業していたことを証明する証拠が必要となります。
基本的には、以下のようなものが有用とされます。
- 雇用契約書や就業規則(労働条件に関する証拠)
- 給与明細書(支払賃金の実態に関する証拠)
- タイムカードやWeb打刻等の客観的な記録(労働時間の実態に関する証拠)
もっとも、裁量労働制の場合、タイムカード等を使用しないことが多いと考えられるため、PCの使用時間記録に加えて、メールの送受信履歴や業務指示書などが証拠として有用となってくる可能性があります。
証拠を収集したら、上記の計算方法で残業代を算出しておきましょう。
(2)未払い残業を会社に請求する
まずは直属の上司や労務の担当部署に相談し、証拠を提示した上で、未払い残業代の支払いについての交渉を行います。
会社側が支払いに応じない場合には、内容証明郵便で残業代請求を通知するとよいでしょう。
内容証明郵便を送ることで、残業代請求権の消滅時効(残業代の支払時期に応じて2年ないし3年)を止めることが可能となります。
(3)労働審判・訴訟
会社との交渉がまとまらなかった場合には、労働審判や訴訟という裁判所を通じた法的手続きを検討します。
労働審判は、残業代の未払いなど労働関係の紛争を解決するための制度で、原則として期日は3回以内とされ、迅速な解決が期待できます。
労働審判の結果に対して当事者から異議申立てがあると、通常の訴訟に移行します。
参考:労働審判手続|裁判所 – Courts in Japan
(4)弁護士への相談
いずれの方法をとるにしても、残業代の未払いが発生している時点で、弁護士に相談するのがおすすめです。
適切な証拠収集に関するアドバイスを得ることができますし、複雑になりがちな残業代の正確な計算や会社との交渉を代行してもらうことにより、より多くの残業代を獲得できる可能性が高まります。
【まとめ】裁量労働制でも残業代は発生することはある
今回の記事のまとめは次のとおりです
- 裁量労働制は、実際に労働した時間にかかわらず一定時間労働したとみなされて契約した給料が支払われる制度で、特定の業種に対して適用されます。
- 裁量労働制は原則的に残業の概念がありませんが、みなし労働時間が法定労働時間を超えた場合や、休日労働・深夜労働等の場合には割増賃金が発生します。残業代は基本的に「1時間当たりの基礎賃金×割増率×残業時間」で計算されます。
- 未払い残業代がある場合には、会社との交渉で請求するほか、労働審判や訴訟といった法的手続きを検討することになります。弁護士に依頼するとより多くの残業代を獲得できる可能性が高まります。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年8月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。