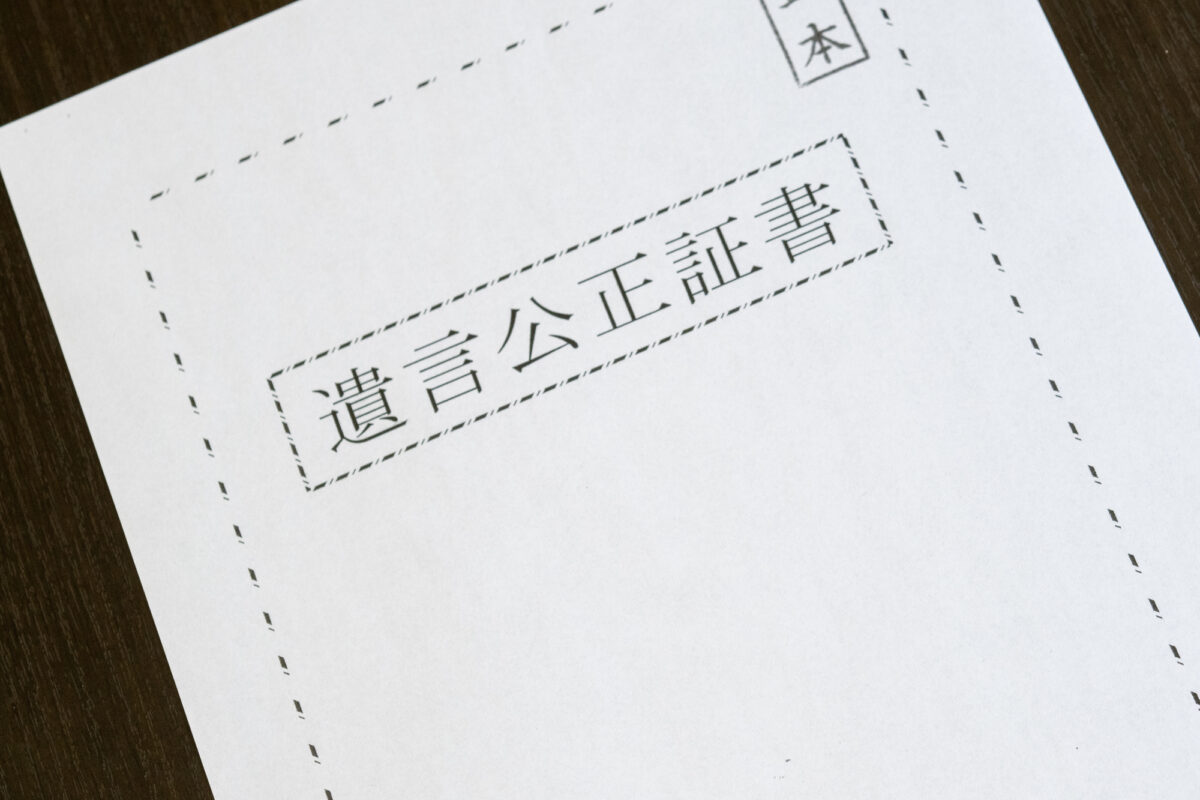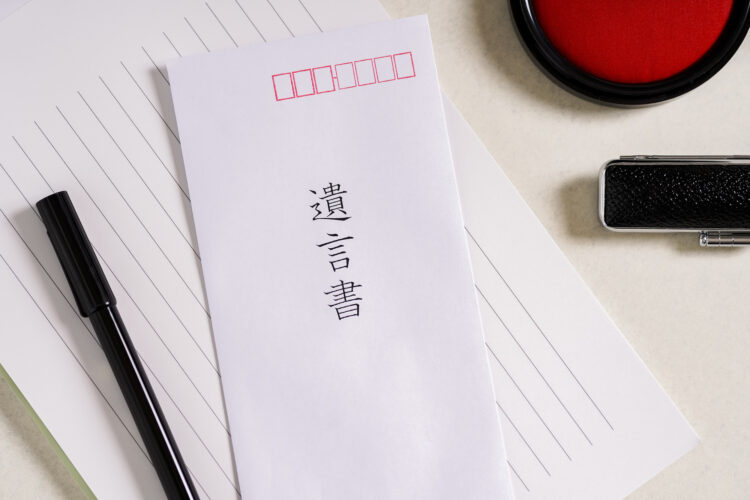遺産相続をめぐるトラブルを未然に防ぎたいと考えている方にとって、公正証書遺言は非常に有効な手段です。
公証人が作成するので無効になるリスクが低く、公証役場で保管されるため偽造や破棄されるリスクもほとんどないためです。
しかし、その作成には費用がかかるため、メリットとデメリットを考慮して判断することが重要です。
本記事では、公正証書遺言の作成にかかる具体的な費用、弁護士などに依頼する費用、手続きの流れなどについてご説明いたします。
この記事を読んでわかること
- 公正証書遺言作成にかかる費用
- 公正証書遺言を作成する流れ
- 公正証書遺言のメリットとデメリット
ここを押さえればOK!
作成には費用がかかり、具体的には公証人手数料、証人費用、必要書類の取得費用などが含まれます。公証人手数料は遺産の価額に応じて変動し、証人費用は1名あたり5000円~1万円程度です。
遺言作成の流れは、事前相談、証人の依頼、必要書類の準備、予約した日時に遺言書を作成、費用の支払い、正本と謄本の受領です。
公正証書遺言のメリットは、証明力が高く、紛失や改ざんの心配がなく、検認手続きが不要な点です。
一方、デメリットは費用がかかり、手続きが複雑で、プライバシーの問題があることです。
弁護士に依頼することで、遺言書の作成をサポートしてもらい、具体的な事情に応じた適切なアドバイスを受けることができます。
公正証書遺言を検討する際は、弁護士への相談も考慮すると良いでしょう。
遺言書の作成に関する無料相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
公正証書遺言とは
遺言の方式には、法律上自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類あります。
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことです。
希望すれば、遺言を公正証書で残すことができ、これを公正証書遺言といいます。
日本公証人連合会の発表によれば、令和6年1月から12月に全国で作成された公正証書遺言は、12万8378件でした。過去10年で最多の作成件数となっています。
参考:令和6年の遺言公正証書の作成件数について|日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2024.html)
(1)公証人が作成
公証人は、中立・公正な立場で公証事務を行う公務員ですが、裁判官や検察官を長年務めた後に公証人となるケースが多く、法的知識や経験を備えています。
全国に約300ヶ所ある公証役場で、公正証書遺言を作成することができます。
公正証書遺言は、本人が、公証人の前で、自分の希望する遺言の内容を説明し、公証人がそれに基づいて遺言を作成します。
公正証書遺言を作成するためには、原則として、当事者が公証役場に出向く必要があります。
しかし、高齢者や重い病で外出が難しいなどの事情がある場合には、公証人が出張して自宅などに出向いてくれる場合もあります。
(2)証人2人の立ち合いが必要
公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会が必要です。
自分で探せない場合には、公証役場で紹介してもらうことができます。
公正証書遺言の作成にかかる3つの費用
公正証書遺言の作成には、具体的な費用がかかります。
まず、公証人手数料が主要な費用項目です。これは遺言書に記載される財産の価額に応じて変動します。
例えば、財産の価額が100万円以下の場合は5000円、1億円を超える場合は43000円に超過額5000万円ごとに13000円が加算されます。
また、証人費用も必要で、公証役場で証人を手配する場合は1名あたり5000円~1万円程度が一般的です。
これらの3つの費用を理解することで、遺言作成にかかる費用の全体像を把握しやすくなります。
(1)公証人手数料
公証人手数料は、公正証書遺言の作成において最も基本的な費用項目です。
遺言書に記載される財産の価額に応じて、次の基準表のとおりに変動します(公証人手数料令9条別表)。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
具体的に手数料を計算するときは、次の点に注意してください。
(1-1)相続する人ごとに手数料を合算
手数料は、財産の相続又は、遺贈を受ける人ごとに財産の価額を計算し、その額で基準表に対応する手数料額をすべて合算します。
(1-2)財産1億円以下の加算
全体の財産が1億円以下のときは、上記で合計した手数料に1万1000円を加算します(遺言加算)。
(1-3)枚数に応じた加算
公正証書遺言は、原本、正本、謄本を各1部作成します。
原本については、枚数が法務省令で定める枚数の計算方法で4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときには、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。
また、正本および謄本の交付には、枚数1枚につき250 円の手数料が必要です。
(1-4)公証役場外で作成する場合の加算
病気で外出できないなどの事情があるときには、公証人が自宅などに出向いて公正証書遺言を作成できることがあります。
そのような場合、基準表で計算された手数料に、50%加算されることがあります。
また、出張した公証人の日当と交通費がかかります。
個別具体的な手数料の算定は、依頼しようとする公証役場で確認するようにしましょう。
(2)証人費用
公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要です。
多くの場合、成人である友人や知人に証人を依頼することになるでしょう。
ただし、未成年者や、推定される相続人とその配偶者、その直系血族などは証人になることはできません(民法974条)ので注意します。
依頼した証人には、謝礼や交通費などを支払う必要があるでしょう。
証人を探せない場合には、公証役場で証人を手配してもらうことができます。
その場合の費用は公証役場によって異なりますが、1名あたり5000円~1万円程度であることが多いようです。
証人を頼みたい場合には、事前に費用がどれくらいになるのか、個別に確認しましょう。
(3)必要書類の取得費用
公正証書遺言を作成するためには、次のように様々な書類が必要になります。その書類の取得費用がかかります。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者本人と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 預貯金の通帳の写し など
必要な書類は、遺言の内容によって異なってきますので、事前に弁護士などに相談するか、依頼しようと考えている公証役場に問い合わせて確認しましょう。
参考:公証事務11必要書類|日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow11)
遺言書作成のサポートを専門家に依頼するときの費用
遺言作成を専門家(士業)に依頼する場合、その費用は士業の種類や経験、遺言の複雑さによって異なります。
一般的に、弁護士、司法書士、行政書士が遺言作成のサポートを行っています。
士業への依頼費用は一見高額に感じるかもしれませんが、自分の意思を確実に遺言書に残し、将来の紛争防止や円滑な相続のための投資と考えれば、十分に価値があるといえるでしょう。
以下、各士業に依頼する場合の一般的な費用について説明します。
(1)弁護士
弁護士に遺言作成のサポートを依頼する場合、通常、相談料、遺言書作成料、公正証書にする場合の加算、出張が必要だった場合の日当、実費などがかかります。
相談料は、一般的に30分5500円(税込)程度ですが、相談料無料とする法律事務所も多いです。
遺言書作成費用は、法律事務所によって、また遺産の額によって異なります。
旧弁護士報酬基準によれば、非定形の遺言書の場合、経済的な利益の額が300万円以下の場合は20万円、3000万円以下の場合は1%+17万円、3億円以下の場合は0.3%+38万円、3億円を超える場合は0.1%+98万円となっています。
特に複雑な場合には、この計算式より高くなることもあります。
現在も、旧弁護士報酬基準に倣って報酬を定めている法律事務所は少なくありませんので、この基準が一定の目安になるでしょう。
公正証書にする場合には、3万円程度加算するところもあります。
日当は、出張した場合に係る費用です。1日だと5万円~10万円程度が多いです。
弁護士に依頼するメリットは、相続全般についての法律相談が可能なところ、また自分の望む遺産の分け方について、具体的な遺言書案を考えてもらえるところです。
特に、相続人や遺産が多く複雑なケースでは、弁護士の法律知識が非常に有用です。妻に自宅を残すためにはどうすればいいか、子の間で相続割合を変えたいが紛争を避けるために何ができるのかなど、具体的な懸念点に応じて適切な遺言を作成してもらうことができます。
費用は他の士業より高めなことが多いですが、総合的な相続対策を立てたい場合は弁護士への依頼を検討する価値があります。
(2)司法書士
司法書士に遺言作成のサポートを依頼する場合、通常、遺言書作成料、公正証書にする場合の加算、出張が必要だった場合の日当、実費などがかかります。
遺言書作成料は、弁護士に依頼するよりも安いようです。
一般的に全体として10万円~程度かかることが多いようですが、事務所や遺産額、出張の有無などによっても異なるでしょう。
(3)行政書士
行政書士に遺言作成のサポートを依頼する場合の費用は、一般的に、弁護士よりも安く、司法書士と同程度か少し安いことが多いようです。ただし、事務所や遺産額、出張の有無などによっても異なるでしょう。
費用だけで見るなら行政書士や司法書士、遺言の内容を含む相続について法律相談したかったり、相続トラブルが予想されたり、複雑な相続について遺言を残したりしたい場合には、弁護士に依頼するのがよさそうですね。
公正証書遺言を作成する流れ
公正証書遺言を作成する手続きについて説明します。
一般的な流れは、次のようになります。
- 事前相談(遺言書案の作成)
- 証人の依頼
- 必要書類の準備
- 予約した日時に遺言書を作成
- 手数料等費用の支払い
(1)希望する遺言について簡単にまとめる
まず初めに、簡単な相続人関係図を作成し、相続財産や、その分配の割合など、自分の希望する遺言について簡単にまとめておきます。
弁護士に依頼したり、公証人に相談する際に、このまとめ書きが役立ちます。
(2)打ち合わせ
弁護士などに遺言書作成を依頼する場合には、まずは弁護士などに希望する遺言書の内容について伝えます。
個別的な事情や希望を踏まえて、弁護士は遺産をどのように分けたらいいのか、法律的なアドバイスをして、具体的な遺言書の文言を考えてくれるでしょう。
弁護士は、依頼者のご希望に沿った内容で法的に有効な文言で、遺言書案を作成します。
その後、弁護士が公証人と連絡を取り合い、遺言書の案を確定します。
弁護士に依頼しない場合には、本人が直接公証人役場に連絡して、相談の日時を予約します。
公証人は中立的な立場で遺言書作成に必要な限りで相談に応じますので、弁護士とは異なり、遺産をどのように分けたらいいのかなどの法律相談は行いません。
打ち合わせは1度の場合もありますし、複数回ある場合もあります。
メールなどのやり取りも含め、最終的に遺言書の内容を確定します。
作成手数料についても、事前に教えてもらえます。
(3)必要書類の準備
遺言書作成に必要となる次のような資料を集めていきます。
弁護士に遺言書作成を依頼した場合、基本的には弁護士が収集します。
自分で集める場合には、公証人から必要書類が共有されますので、一つ一つ準備していきます。
- 戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書 等
収集した書類は、公証人役場に直接届けるか、書留郵便などで送付します。
(4)証人の依頼
公正証書遺言を作成するには、成人の証人2名が必要です。
事前にお願いしておく必要があります。
自分で探すのか、公証役場に紹介してもらうのか決めて、依頼しましょう。
証人がいなければ公正証書遺言は作成できませんので、作成日時と持ち物を正確に伝えて、遅れずに公証役場に来てもらうようにしましょう。
(5)予約した日時に遺言書を作成
実際に遺言書を作成する日時を、予約します。
弁護士に依頼すれば、公証役場と連絡を取ってスケジュールを調整し、確定した日時を知らせてくれます。
当日は、本人確認書類、実印、費用を支払うための現金(クレジットカード)を準備して持参します。
時間に余裕をもって出向きましょう。
受付後は、証人とともに待合室で待ちます。
準備ができたら呼ばれますので、担当する公証人のいる部屋まで向かいます。
そこで、公証人から遺言の流れについて説明があり、本人確認がなされます。
次に、公証人が、事前に打ち合わせた遺言の内容を読み上げるなどして、遺言内容に間違いがないかを確認します。
その後、遺言者と証人が、原本に署名、押印します。
(6)費用の支払い
公証役場に、手数料を現金またはクレジットカードで支払います。
公証人役場に証人の紹介を依頼した場合には、証人の費用も支払います。
自分で依頼した証人にも、報酬の支払いを約束した場合には報酬を支払います。
(7)公正証書遺言の正本と謄本を受領
その後、公正証書遺言正本と謄本を受け取ります。
公正証書遺言には、原本、正本、謄本があります。それぞれの意味は次の通りです。
(7-1)原本
遺言者本人、証人2名、公証人が署名・押印したもので、世界に1つしか存在しません。遺言者本人には渡されず、公証役場に長い間保存されます。
(7-2)正本
原本と同じ効力を持つ原本の写しです。公証人から遺言者本人に手渡されます。遺言者本人が亡くなられた後、相続人は正本があれば相続手続きを進めることができます。紛失した場合には、再発行が可能です。
(7-3)謄本
原本の写しで、原本が存在することの証拠にはなりますが、原本と同じ効力は持ちません。相続人は、謄本では預貯金の払い戻しや不動産登記の名義変更などの相続手続きを進めることはできません。紛失した場合には、再発行が可能です。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットを3点説明します。
(1)証明力がある
公証人は、豊富かつ高度な法的知識に基づいて、公正証書とする書面の記載内容を吟味して、法律上問題のない内容で作成します。
公証人は、遺言者本人の身元もしっかりと確認します。
また、遺言の際には証人が2名同席し、遺言できる能力があるかなども確認されます。
このように、プロである公証人が、厳密な手続きを経て作成した公正証書遺言には、強い証明力がある(裁判上で有力な証拠となる)と考えられています。
後々遺言書の内容でトラブルが生じて裁判になったとしても、公正証書遺言の有効性が否定されることは極めて少ないといってよいでしょう。
(2)紛失や改ざんの心配がない
作成された公正証書遺言の原本は公証役場で原則として20年間保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。
仮に、手元保管用の正本や謄本を紛失してしまっても、原本は公証役場に保管してありますので、再度正本などの交付を受けることができます(再交付の費用は別途かかります)。
(3)遺言の存在が明確で検認手続きが不要
公正証書遺言は公証役場のデータベースに登録されるため、その存在が明確です。これにより、相続人が遺言の存在や内容を知らないという事態を防ぐことができます。
また、公正証書遺言は法律に従って適正に作成されたと考えられるので、自筆証書遺言や秘密証書遺言で必要となる家庭裁判所の検認手続きは不要です(※)。
自筆証書遺言だと、預けた人が紛失してしまったり、保管した場所が不明だったりすると、せっかく記載した遺言書が発見されないこともあり得ます。
また、封がされている遺言書は開封せずに、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
参考:遺言書の検認|裁判所
※作成した自筆証書遺言を法務局に預かってもらう制度を利用すると、自筆証書遺言であっても家庭裁判所の検認手続きは不要です。
公正証書遺言のデメリット
一方で、公正証書遺言のデメリットも紹介します。
(1)費用がかかる
公正証書遺言の作成には、士業へ依頼するなら依頼料、公証人への手数料や証人への謝礼など、一定の費用が必要となります。
ほとんど費用がかからない自筆証書遺言と比較すると、経済的な負担がかかります。
(2)手続きが複雑
公証人との打ち合わせ、必要書類の収集や証人の手配など、公正証書遺言の作成には複数の手続きが必要です。
時間と労力がかかるため、1人でするのは難しいと感じるかもしれません。
そのような場合には、弁護士など遺言作成のサポートを行っている士業に依頼するとよいでしょう。
(3)プライバシーの問題
公正証書遺言の作成過程では、証人や公証人に遺言の内容を知られることになります。
公証人や公証人の紹介を受けた証人から、遺言書の内容が外に漏れることは考えられませんが、自分で探した証人から、内緒にしたいと思っている家族に伝わるリスクはゼロではありません。
自分が亡くなるまでは、遺言の内容を相続人に秘密にしたい方は、公証人の紹介、依頼した士業者や相続人と全くつながりのない証人を選ぶとよいでしょう。
「遺言どうしよう?」と思ったら弁護士に相続の相談を
遺言の作成には、法定相続人の範囲、法定相続分などの基本的な法律知識が必要です。
法定相続分よりも少ない遺産を相続させようと思ったら、相続人間の争いを避けるためにも、遺留分権利者や遺留分の割合の法律知識も必要でしょう。
「遺言書を残したいけど、どうすればいいか相談したい」と思ったら、一度弁護士に相続の相談をしてみてください。
弁護士は、あなたの個別具体的な事情を伺ったうえで、適切にアドバイスしてくれることでしょう。
【まとめ】公正証書遺言は一定の費用がかかるが、無効・改変・紛失のリスクは低い
公正証書遺言の作成には、公証人手数料や証人費用などの費用がかかりますが、無効となるリスクの低い遺言を残すことができます。
遺言書を作成したいと考えている方は、公正証書遺言も一つの選択肢として検討するとよいでしょう。
弁護士に遺言書について相談・依頼すると、本人の懸念点や具体的事情を踏まえたうえで、本人の意思を明確にした遺言書の作成をサポートしてくれるでしょう。
アディーレ法律事務所は、遺言について積極的にご相談・ご依頼を承っておりますので、一度お気軽にご相談ください。