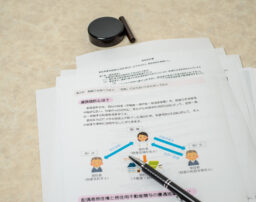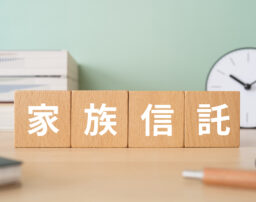相続の準備、あなたはもう始めていますか?「まだ先のこと」と思っていませんか?
元気に長生きできればいいですが、いつ亡くなるかわかりません。長生きできても、認知症などの病気にかかり、自分で相続の準備をすることが難しくなってしまうかもしれません。
相続の準備は、まだ余力のある今、してしまう方がよいでしょう。しっかりと相続準備をすることで、無用な相続トラブルを避け、家族の未来を守ることができます。
この記事では、弁護士が「相続の準備でやるべき10のこと」の前半5つをご紹介します。相続の準備を今から始めることで、将来の漠然とした不安を解消し、大切な家族との絆を守ることができるでしょう。
ここを押さえればOK!
相続の準備は、将来の不確実性に備え、家族の未来を守るために重要です。
1.まず、相続の基礎知識を理解し、法定相続人や相続税の基本を学びます。
2.次に、財産目録を作成し、資産と負債を把握します。
3.銀行口座と証券口座を整理し、可能な限り集約することで手続きを簡素化します。
4.不動産の状況を確認し、所有権や評価方法を把握します。
5.最後に、生命保険の受取人を見直し、非課税枠を有効に利用することを検討します。
これらのステップを早めに始めることで、将来の不安を軽減し、残された家族間の相続トラブルを防ぐことができるでしょう。
後編では、残りの5つのステップについて紹介します。遺言や相続の生前対策をお考えの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
遺言・遺産相続に関する無料相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
1.相続の基礎知識を理解する
相続の準備を始める前に、基本的な知識を身につけることが重要です。相続の定義や仕組み、相続税の基本を理解することで、適切に相続の準備をすることができるでしょう。以下、相続の基礎知識について詳しく解説します。
(1)相続とは何か
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や権利義務を、相続人が引き継ぐ制度です。相続は被相続人の亡くなったと同時に開始し、相続できるのが誰か、どれだけ相続するかは、法律で定められています。法律で遺産を取得できると定められている人のことを、法定相続人といいます。
(2)法定相続人と相続順位
被相続人の法定相続人は、次の通りです。
- 配偶者
- 第1順位:直系卑属(子、子が亡くなっているときは孫)
- 第2順位:直系尊属(父母、父母が亡くなっているときは祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪)
配偶者は常に相続人になります。
第1順位の法定相続人がいるときは、第2順位は相続しません。
第1順位の法定相続人がいないときは、第2順位が相続します。
第1順位と第2順位の法定相続人がいないときに、第3順位が相続します。
法定相続分は民法で定められていますが、遺言や相続人間の協議で変更することができます。
相続の対象は、預貯金、不動産、有価証券などの資産だけでなく、借金などの債務も相続の対象となります。
例えば、Aさん(仮名、被相続人)に妻と2人の子がいる場合、相続人は妻と2人の子供となり、法定相続分は妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。
(3)相続税の基本
相続税は、相続によって取得した遺産の価額が基礎控除額を超える場合に課税されます。現行の制度では、次の点が重要です。
基礎控除額:3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
税率:10%~55%の累進課税
申告期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
例えば、Bさん(仮名)の相続財産が1億円で、相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は4800万円(3000万円 + 600万円 × 3人)となります。課税対象となる相続財産は5200万円(1億円 – 4800万円)で、これに対して相続税が課税されます。
相続税の計算は複雑です。遺産の中でも、非課税となる財産もあります。自分で計算せず、税理士に相談することをお勧めします。
早めに相続税の概算額を把握することで、適切な対策を講じることができるでしょう。
2.財産目録を作成する
財産目録の作成は、相続手続きの基礎となる重要なステップです。被相続人のすべての資産と負債を把握することで、相続人全員が財産の全体像を理解し、公平な分割協議が可能になります。財産目録作成の詳細について解説します。
(1)相続対象となる財産の把握
相続の対象となる財産は、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の両方を含みます。主な相続対象財産は次の通りです。
- 不動産:土地、建物、マンションなど
- 金融資産:預貯金、株式、債券、投資信託など
- 現金、貴金属、美術品
- 生命保険金
- 自動車、船舶などの動産
- 事業用資産(個人事業の場合)
- 知的財産権(著作権、特許権など)
- デジタル資産(暗号資産、ポイント、オンラインアカウントのIDやパスワード等)
- 負債(住宅ローン、事業性借入金、個人間の借金など)
これらの財産を漏れなく把握することが、適切な相続手続きの第一歩となります。
(2)財産目録の作成方法
財産目録の作成には、次のステップを踏むことをお勧めします。
- 資料の収集:預金通帳、不動産登記簿、株券、保険証書、借用書などを集める
- 資産と負債の区分:プラスの財産とマイナスの財産を明確に分ける
- 評価額の記載:各財産の評価額を調べて記入する
- 一覧表の作成:すべての財産を種類別に整理し、一覧表にまとめる
具体例:
| 資産種類 | 項目 | 金額/評価額 |
|---|---|---|
| 不動産 | 自宅 | 5000万円 |
| 賃貸アパート | 3000万円 | |
| 預貯金 | A銀行普通預金 | 1000万円 |
| B信用金庫定期預金 | 500万円 | |
| 有価証券 | C証券株式口座 | 200万円 |
| 生命保険 | D生命保険(受取金額) | 2000万円 |
| 負債 | 住宅ローン残高 | 1000万円 |
財産目録は定期的に更新し、常に最新の状態を保つことが大切です。
(3)デジタル資産の管理
デジタル資産の管理は、現代の相続において重要性が増しています。デジタル資産には、暗号資産、各種ポイント、オンラインゲームのアイテム、SNSアカウントなどが含まれます。これらの管理には次の点に注意が必要です。
- 資産の把握:所有するデジタル資産を洗い出し、リスト化する
- アクセス情報の管理:パスワードや秘密鍵を安全に保管する
- 利用規約の確認:各サービスの相続に関する規定を確認する
- 定期的な更新:デジタル資産の種類や価値は変動しやすいため、定期的に情報を更新する
例えば、暗号資産の場合、秘密鍵を紛失すると資産にアクセスできなくなるため、適切な管理と相続人への引継ぎ方法を事前に検討しておくことが重要です。
3. 銀行口座と証券口座を整理する
銀行口座と証券口座の整理は、相続手続きをスムーズに進めるために重要なステップです。
複数の金融機関に分散している口座を把握し、可能な限り集約することで、相続時の手続きが簡素化されます。次では、口座整理の具体的な方法と注意点について解説します。
(1)口座の把握と集約
口座の把握と集約は、次の手順で行います。
- 全ての金融機関の口座を確認:通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの履歴などを確認
- 口座の種類を整理:普通預金、定期預金、投資信託、株式口座などを分類
- 残高と取引履歴の確認:各口座の残高と最近の取引履歴を確認
- 不要な口座の解約:利用頻度の低い口座や残高の少ない口座は解約を検討
- 主要な口座への集約:日常的に使用する1〜2行の口座に資金を集約
例えば、Cさん(仮名)は5つの銀行に口座を持っていましたが、次のように整理しました。
- メインバンクのB銀行に給与振込口座と貯蓄用口座を集約
- 投資用にC証券の口座を維持
- その他3行の口座は解約
このような整理により、相続時に残された遺族が行う手続きが大幅に簡素化されます。
(2)夫婦共通口座の取り扱い
銀行口座は、必ず個人名義で作成する必要があります。ただ、一方の名義でありながら、生活費を出し入れする口座として、夫婦が共有しているケースもあります。
共有している預金口座が亡くなった人名義である場合、銀行が亡くなったことを把握したらその人名義の口座は凍結されます。
凍結されると、その口座から生活費を下すことは難しくなりますので、事前に生活費を配偶者名義の口座に分けておくなどの対策が必要になるでしょう。
遺言・遺産相続に関する無料相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
4.不動産の状況を確認する
不動産は多くの場合、相続財産の中で最も価値が高い資産です。相続税の計算や遺産分割の際の基準となるため、その価値は正確な評価する必要があります。不動産の状況確認には、2つの重要なポイントがあります。
(1)不動産の所有権の確認
登記簿を確認し、所有権や抵当権の有無を確認します。昔相続で取得して所有者になったが、登記がまだなされていないというケースも少なくありません。
抵当権が設定されている場合、その金額も相続財産の計算に影響します。
(2)不動産の評価方法
相続税における不動産の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式は、主に市街地の土地に適用され、国税庁が定める路線価を基に計算します。一方、倍率方式は、主に郊外の土地に適用され、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。
例えば、東京都内の一戸建ての場合、通常は路線価方式で評価されます。具体的な計算方法は次の通りです。
- 路線価に対して奥行価格補正などの各種補正を行う
- 1に対して面積を掛ける
- 建物については、固定資産税評価額をベースに計算する
これらの計算を正確に行うことで、相続税評価額を算出できるでしょう。
(3)一般的な不動産価格との違い
相続税評価額は、一般的な不動産の市場価格とは異なることがあります。通常、相続税評価額は市場価格よりも低くなる傾向にあります。
不動産の所有や正確な評価額を把握していると、円滑な相続手続きにつなげることができます。税理士などのアドバイスを受けることで、より正確な評価が可能になります。
5. 生命保険の受取人を見直す
生命保険は相続対策として有効なツールですが、受取人の指定には注意が必要です。
適切な受取人の指定と定期的な見直しにより、遺族の生活保障と相続税対策の両立が可能になります。また、生命保険金が相続財産へ算入されるかどうか(つまり相続税の課税対象となるかどうか)は、受取人の指定方法によって大きく変わります。
次では、生命保険と相続の関係、および受取人の指定と変更について詳しく解説します。
(1)生命保険と相続との関係
生命保険と相続には、次のような関係があります:
- 相続財産との区別:生命保険金は原則として相続財産には含まれない
- 非課税枠の存在:法定相続人が受取人の場合、一定額まで相続税が非課税となる
- 相続税の計算への影響:相続税の計算上、一定の条件下で生命保険金が加算される
例えば、Dさん(仮名、被相続人)の遺族が妻と子2人で、Dさんが保険料を支払っていた生命保険金3000万円を妻が受け取る場合を考えます。相続税の非課税枠は1500万円(500万円×相続人3人)となります。
残りの1500万円は相続税の課税対象となりますが、みなし相続財産という位置づけであり、本来的な相続財産とは別に扱われます。このように、生命保険は相続税対策や遺族の生活保障に有効に活用できます。
(2)受取人の指定と変更
生命保険の受取人の指定と変更は、次の点に注意して行います。
- 指定の自由:契約者は受取人を規約に基づいて自由に指定できますが、通常は家族が指定される
- 変更の手続き:保険会社に所定の用紙を提出することで、いつでも変更可能
- 相続税対策:法定相続人を受取人にすることで、非課税枠を活用できる
- 家族構成の変化への対応:結婚、出産、離婚などに応じて見直しが必要
- 複数指定:複数の受取人を指定し、割合を決めることも可能
例えば、Eさん(仮名:60歳)のケースを考えます。Eさんは、20年前に加入した生命保険(死亡保険金3000万円)の受取人を長男にしていました。しかし、最近次男が生まれたため、受取人を妻に変更し、保険金を妻が公平に子どもたちのために使えるようにしました。
このように、家族構成の変化に応じて適切に受取人を見直すことが重要です。
まとめ:相続の準備は早めに始めることが大切(前編)
相続の準備で最も重要なのは、早めに始めることです。財産目録の作成、口座の整理、不動産の評価、生命保険の見直しなど、一つずつ着実に進めていくことで、将来の不安を軽減し、家族間のトラブルを防ぐことができます。
アディーレ法律事務所は、生前の相続対策である遺言書作成について積極的にご相談・ご依頼を承っております。遺言作成を検討している方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。