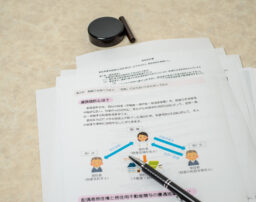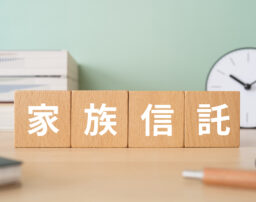「タンス預金」—— この言葉を聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか? 安全? リスク? それとも昔ながらの貯蓄方法?
日本の昨今の銀行の低金利や手元に現金がある安心感などを理由に、タンス預金を考えている方も多いでしょう。
でも、ちょっと待ってください!タンス預金には知られざるメリットとデメリットがあり、必ずしもおすすめする貯蓄方法ではないんです。
このコラムでは、あなたの大切な資産を守るために、タンス預金のメリット・デメリットからタンス預金がバレてトラブルになるケースなど弁護士が詳しく解説していきます。現在タンス預金をされている方またタンス預金を検討されている方必見です。
この記事を読んでわかること
- タンス預金とは
- タンス預金のメリット・デメリットとは
- タンス預金がバレてトラブルになるケースとは
- タンス預金がバレて、税の申告漏れが発覚した場合のペナルティとは
ここを押さえればOK!
メリットとしては、緊急時に即座に現金を用意できること、手数料がかからないこと、金融機関の破綻リスクを避けられることが挙げられます。
一方、デメリットとしては、災害や盗難のリスク、利子や運用益を受け取れないこと、相続時や離婚時のトラブルの可能性があります。
さらに、税務当局にタンス預金による税の申告漏れが発覚すると、加算税や延滞税などのペナルティが課されるリスクもあります。特に相続時や贈与時、申告した所得に見合わないお金の出入りがある場合には、税務署に疑われる可能性が高いです。
タンス預金のメリットとデメリットを踏まえて、適切な金額で行うことが重要です。また、税務申告をきちんと行うことも忘れないようにしましょう。
タンス預金とは?
タンス預金とは、銀行などの金融機関に預けずに、自宅で現金を保管する方法です。タンス預金と言っても、自宅のタンスだけではなく、会社や貸金庫に保管しているものも「タンス預金」に当たります。
タンス預金はいくらまでならOK?
タンス預金自体は悪いことではなく、法律上いくらまでならOK・NGということはありません。
緊急で現金が必要となることもあるので、ある程度のタンス預金は必要といえるかもしれません。しかし、タンス預金をしていると盗難や紛失のおそれがあるほか、トラブルの元にもなりますので、多額のタンス預金はやめておいた方がよいでしょう。
タンス預金のメリットとは?
銀行に預けても低金利でほとんど貯金額が増えない昨今では、タンス預金をしたいと思われる方がいるのも当然のことでしょう。実際、日本では数十兆円規模のタンス預金が存在するとも言われています。
まずは、タンス預金のメリットについて紹介しましょう。
(1)緊急時でもすぐ現金が用意できる
タンス預金の最大のメリットは、緊急時に即座に現金を用意できることです。銀行の営業時間やATMの利用制限に縛られず、24時間いつでも必要な金額を用意できます。
例えば、深夜の急な入院や事故の際の支払い、災害時の物資購入など緊急で現金が必要となったときでも対応できます。また、銀行システムトラブルなどで一定期間お金がおろせないという事態になっても、現金を用意することができます。
(2)手数料がかからない
現金を用意するために銀行預金を引き出す場合、手数料の有無が気になる方は多いでしょう。例えばコンビニのATMは24時間利用でき大変便利ですが、預金の引き出しには手数料がかかることも。
一方、タンス預金であれば、現金を用意する際に手数料は必要ありません。
(3)金融機関の破産などから資産を守れる
銀行などの金融機関の破綻などがあっても貯金を守ることができます。
銀行などの金融機関の破綻があった場合、預金者1人当たり1000万円までの元本と破綻日までの利息が保証される制度があります。しかし、1000万円を超えた分のお金については保証の対象外で、どうなるかわかりません。
タンス預金であれば、金融機関の破綻などがあっても資産を守ることができます。
タンス預金のデメリットとは?
確かに、手元にいつでも使える現金があるというのは安心材料にもなります。しかし、タンス預金には、次に紹介するデメリットもあるので、注意が必要です。
メリット・デメリットを踏まえて、タンス預金をするのか、するとしていくらぐらいするのかを考えておくとよいでしょう。
(1)災害・盗難・紛失などのリスクがある
タンス預金の最大のデメリットは、災害や盗難、紛失など資産を失ってしまうおそれがあるということです。
例えば地震や火災で家が倒壊し、タンス預金がなくなってしまうかもしれません。家に泥棒が入り盗難に遭うおそれもあります。
また、災害や盗難に遭わなくても、タンス預金を誤って捨ててしまったり、タンス預金の保管場所を忘れてしまったりなど人為的なミスで資産を失うおそれもあります。
(2)利子や運用益を受けとれない
タンス預金では、銀行預金や資産運用した場合と異なり、利子や運用益を得ることができません。
例えば、株式や投資信託などを購入するなど資産運用を行い、年5%程度の利回りを得る場合を考えてみましょう。
【10年後】
- タンス預金の場合:100万円のまま
- 年5%程度の利回りで運用していた場合:約162万円
長期的に見ると、タンス預金のまま置いておくと資産運用をした場合と比べて大きく損をしてしまう可能性があるのです。
(3)相続時や離婚時にトラブルになるおそれがある
タンス預金は、相続時や離婚時にトラブルになるおそれがあります。
例えば、あなたの死後に家族がタンス預金を発見し他の家族にそのことを報告せずに、自身の懐に隠してしまった場合を考えてみましょう。この場合、タンス預金を懐に入れてしまった人が、他の家族に隠れて資産を得たことになり、家族間でトラブルになってしまうおそれがあるのです。
また、離婚時の財産分与で、タンス預金があると夫婦が持つ資産を互いに把握できず、「もっと資産があるはず。財産分与の金額が足りない!」など夫婦が揉めてしまう原因にもなり得ます。
タンス預金はなぜバレる?バレてトラブルになるケースとは?
これまで説明した通りタンス預金自体は、法律上問題ありません。
しかし、税部当局などにタンス預金の存在がバレることで、税の申告漏れが発覚するなどトラブルになるケースもあります。
(1)相続時や贈与時にバレる
相続時や贈与時などに、タンス預金の存在が発覚し、税の申告漏れなどトラブルになるケースがあります。
例えば、税金対策としてタンス預金の存在を税務署に隠し、税務署に申告せずに相続や贈与をしてもバレないのではと思われるかもしれません。しかし、それは税務調査によってばれる可能性が高いので、やめておいたほうがいいでしょう。
国には国税総合管理システム(KSKシステム)といって、簡単にいうと、過去の申告情報や納税実績などを一元的に管理するシステムがあります。そのため、過去の収入状況と現在の財産を見比べたりすることで、タンス預金でもあっても税務署にバレてしまう危険が高いのです。
生前の相続対策は、弁護士のサポートを受けて行うことをお勧めします。
(2)申告した所得に見合わないお金の出入りがあるとバレる
税務署は、税金の申告がきちんと行われているかどうかを確認するため、納税者の預貯金の入出金状況を確認することがあります。
申告された所得に見合わない高額な買い物や預金への高額な入金があると、「所得がきちんと申告されていないのでは?」と疑われます。
このようにタンス預金をしていても、きちんとした税の申告がなければバレてしまう可能性が高いのです。タンス預金自体は悪いことではありませんが、タンス預金を行う際にはきちんと税務申告は行いましょう。
タンス預金がバレて、税の申告漏れが発覚した場合のペナルティとは?
タンス預金が発覚し、適切な申告がなされていなかった場合、次のようなペナルティが課される可能性があります。
<税の申告漏れが発覚した場合のペナルティ>
- 加算税:適切な申告・納税をしなかった場合のペナルティ
- 無申告加算税:期限内に申告をしなかった場合
- 過少申告加算税:納税額を少なく申告した場合
- 重加算税:申告するべき所得を隠したり、所得額を偽ったりした場合
- 延滞税:納付期限からの超過日数に比例して課されるペナルティ
悪質なケースの場合には、刑事告発され刑事罰を受けるおそれがあります。
【まとめ】タンス預金の税金逃れはバレる可能性が高い|メリット・デメリットも踏まえて考えよう
タンス預金は緊急時の資金確保や金融機関の破綻リスク回避などのメリットがありますが、災害・盗難リスクや運用益の損失、相続時のトラブルなどデメリットも存在します。多額のタンス預金はやめておいた方がよいでしょう。
また、税務調査でタンス預金による申告漏れが発覚すると、加算税や延滞税といったペナルティを課される可能性があります。タンス預金を行っていても、きちんと税務申告は行いましょう。