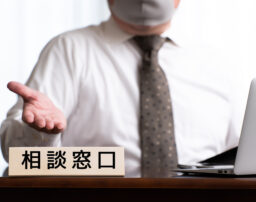週40時間以上働いているけど、残業代は請求できないの?
労働に対して適切な報酬が支払われるようにするため、労働基準法等の法律にはさまざまな規定が置かれています。
そうした規定の中で「残業」に関して最も重要なものが、「法定労働時間」に関する定めと、法定労働時間を超える「時間外労働」についての定めです。
法律的には、「原則として1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超える労働のことを「時間外労働」といいます。時間外労働に対しては、決められた割増率の残業代が支払われる必要があります。
残業代についてのルールを知っておくと、「働いたのに適切な残業代をもらえず損をした」という事態から自分の身を守ることにつながります。
この記事では、残業代が発生するケース、支払われないときの対処法などを説明します。
この記事を読んでわかること
- 法定労働時間や、時間外労働といった言葉の意味
- 残業代が発生するタイミング
- 残業代がもらえないときの対処法
ここを押さえればOK!
法定労働時間を超える労働には残業代が発生し、その計算方法は「基礎賃金×時間数×割増率」です。割増率は時間外労働が月60時間以内であれば1.25倍、深夜労働を含む場合は1.5倍です。休日労働も割増賃金が適用され、法定休日に労働した場合の割増率は1.35倍、深夜労働を含む場合は1.6倍です。パートやアルバイトなどの非正規雇用者も法定労働時間が適用され、残業代を請求する権利があります。
残業代が支払われない場合は、使用者に問い合わせる、労働基準監督署に相談する、弁護士に依頼するなどの対処法があります。証拠として雇用契約書やタイムカードなどを集めることが重要です。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
1週40時間は、労働時間の法律上の上限
労働時間は、労働基準法で「1日8時間・1週40時間以内」と定められています(労働基準法32条)。
この原則的な労働時間の上限の枠のことを、「法定労働時間」といいます。
例えば、始業時間が9時の場合は、途中に1時間の休憩を挟むので、18時までが法定労働時間(1日8時間)ですね。
これに対して、就業規則等で会社が独自に定める労働時間のことは、「所定労働時間」と呼ばれます。
例えば、「始業時間を9時、就業時間を17時、途中に休憩時間1時間」とすると、労働時間は7時間です。この場合、所定労働時間は7時間です。
所定労働時間は、法定労働時間を超えて、例えば「1日9時間」などと定めることはできません。
また、次のように、弾力的な法定労働時間の運用が認められている労働形態もあります。
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 裁量労働制
なお、一部の業種において、常時10人未満の労働者を使用する小規模事業所では、週の法定労働時間が「44時間以内」とされています。この場合、1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制でも、1週間の労働時間を44時間と定めることができます。
残業代の計算方法
次に、時間外労働をしたことで発生する残業代に
「1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超えて時間外労働を行うと、基本的に時間外労働について残業代を請求することができます。
法定時間外の残業代についての計算式は次の通りです。
残業代=1時間当たりの基礎賃金 × 法定時間外労働の時間数 × 法律で定められた割増率
基礎賃金は、所定労働時間に対する賃金から、一定の手当など(家族手当、通勤手当など)を差し引いたうえで、時給に直して計算します。
割増率の下限は、ケース別に法律で定められています。例えば、時間外労働が月60時間以内であれば1.25倍です。深夜労働も行っていると、1.5倍になります。
こちらのツールで残業代の簡易的な計算を行うことができますので、利用してみてください。
所定労働時間を超えているが、法定労働時間以内である場合も、会社が決めている割合の残業代を請求することができます。残業時間を計算するときは、所定労働時間を超えた分なのか、法定労働時間を超えた分なのか意識して分ける必要があることに注意しましょう。
残業第の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事ご覧ください。基礎賃金の計算方法、残業代計算の具体例を紹介しています。基礎賃金の計算方法、残業代計算の具体例を紹介しています。
休日労働したら割増賃金をもらえる?
使用者は労働者に対して、「1週間につき1日の休日」または「4週を通じて4日以上の休日」を与えなければなりません(労働基準法35条)。
このように、法律によって労働者に取得させることが義務付けられているこの休日のことを「法定休日」といいます。
例えば、週休2日制で土日休みという会社で、日曜日を法定休日とした場合、土曜日は所定休日と扱われることになります。
そして、法定休日に労働した場合は、法律上の「休日労働」として、一定の割増賃金を請求することができます。
休日労働の割増賃金の計算方法は、先ほど紹介した残業代の計算方法と同じです。
残業代=1時間当たりの基礎賃金 × 休日労働の時間数 × 法律で定められた割増率
休日労働の割増率の下限は、1.35倍です。深夜労働もしていると、1.6倍になります。
なお、所定休日(法定外休日)にした労働は「休日労働」にはあたりません。そこでの労働時間は、法定労働時間内での労働時間や、法定労働時間を超えている場合には時間外労働時間としてカウントされます。
休日労働についての割増賃金について詳しくは、こちらをご覧ください。具体的な計算例を紹介しています。
パートやアルバイトの非正規でも法定労働時間は1週40時間
パート従業員やアルバイト職員などのすべての労働者(は、労働時間・休憩・休日について規定した労働基準法の適用対象となります(※)。
そのため、1日8時間・週40時間の法定労働時間も、正社員と同じように適用されます。
つまり、法定労働時間を超えて残業していれば、非正規雇用であっても、残業代を請求することができるのです。
非正規雇用の場合、正社員より勤務時間が少ないことが多いですが、毎日のように働いていると法定労働時間を超えるケースもあります。
「先月はたくさん働いたのに、その前とあまり給与が変わらないな、残業代支払われているのかな」など疑問に思っている方は、残業代が支払われていないかもしれません。
こちらのツールで残業代の簡易的な計算を行うことができますので、利用してみてください。
※「労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と定義される管理監督者(労働基準法41条2号参照)等の一部の例外を除く
週40時間以上働いているのに、残業代が支払われないときの対処法
時間外残業や休日労働、深夜労働に対しては、会社は労働基準法で定められた割増賃金を労働者に支払わなければなりません。
あなたが時間外労働をしても残業代が得られない場合、この法律を根拠として、あなたには残業代を請求する権利があります。
適切な額の残業代が支払われていない場合の対処法には、次のようなものがあります。
- 使用者に問い合わせる
- 労働基準監督署に相談する
- 弁護士に相談・依頼する
(1)使用者に問い合わせる
「いつもはきちんと残業代が支払われているのに、なぜか今月分は支払われていない」というケースでは、単純に給与計算が間違っている可能性があります。
給与計算を行っている部署や、責任者に問い合わせてみるとよいでしょう。
給与計算が間違っていたら、再計算の上不足分を支給してもらえるでしょう。
もし支給されず、支給されない理由にも納得できない場合には、次の対処法を検討ください。
(2)労働基準監督署に相談する
次のように悪質だと思われるケースでは、労働基準監督署に相談するとよいでしょう。
・会社が法律で決められた残業代を支給してくれない
・残業代を支払うよう申し入れても対応してくれない
・サービス残業が当たり前になってしまっている
労働基準監督署は、会社が労働条件や安全衛生等の面について労働基準法等の法律に反しないようにするための指導や調査などを行う公的機関です。
労働基準監督署への相談を会社に内密で行いたい場合は、匿名で相談することも可能です。
参考:労働基準監督署の役割|厚生労働省
参考:全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省
労働基準監督署について詳しくはこちらをご覧ください。
(3)弁護士に相談・依頼する
次のようなケースでは、弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。
- 未払いの残業代を正確に計算して請求したい
弁護士であれば、資料から残業代を計算し、あなたの代わりに使用者に対して残業代を支払うよう交渉することができます。
また、弁護士は、あなたの代わりに使用者に退職の意思を伝えて、退職の際に有休を取得したいなどの交渉も行うことができます。
残業代を請求する際には、「どれだけ残業したのか」がわかる証拠が必要です。退職後に自分で証拠を収集するのは難しくなりますので、退職前に証拠をあらかじめ集めておくようにします。
一般的に、残業代請求に役立つ具体的な証拠は次の通りです。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 就業規則
- 賃金規程
- 給与明細
- 始業・終業時刻が記載された業務日報
- タイムカード
- ウェブ打刻 など
ご自身のケースではどのような証拠を集めたらよいかについては、弁護士に相談することで有益なアドバイスを得ることができるでしょう。
次の記事も参考にしながら、できるだけ多くの有効な証拠を集めておくことをおすすめします。
残業代請求で集めるべき証拠について、より詳しくはこちらの記事をご覧ください。できるだけ多くの有力な証拠を集めておくと、残業代請求の交渉でも強い立場で臨むことができるでしょう。
【まとめ】法定労働時間を超える時間外労働には所定の割増賃金(残業代)が発生する
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 労働基準法32条で、労働時間の上限は「1日8時間・週40時間」と定められており、この原則的な上限の枠のことを「法定労働時間」という。
- 法定労働時間を超える労働のことを「時間外労働」といい、法定休日における労働のことを「休日労働」といいます。
- 法定労働時間は、パート従業員やアルバイト職員等を含むすべての労働者(一部の例外を除く)に適用されるので、非正規雇用であっても法定労働時間を超えて働けば残業代を請求できる。
- 残業代が適切に支払われない場合には、使用者に問い合わせる、労働基準監督署に相談する、弁護士に相談・依頼するなどの対処法がある。
「1日8時間以上」や「週40時間以上」の勤務をしていれば、正社員であっても、非正規であっても、残業代を請求することができます。
残業代をもらうのは、労働者の法律上認められた権利です。
働いた分適切な対価をもらえないのは、使用者があなたの労働力を搾取していることにもなります。ご自分のためにも、残業代の未払いを許してはいけません。
未払いの残業代について請求したい、とお考えの方は、残業代請求を扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2025年2月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。務所へご相談ください。