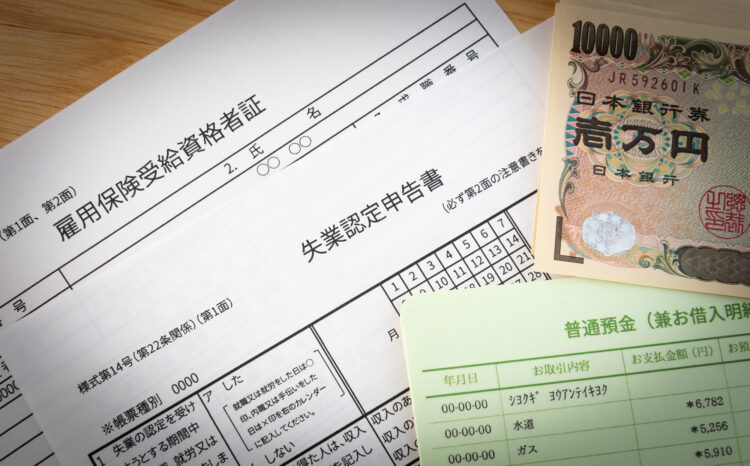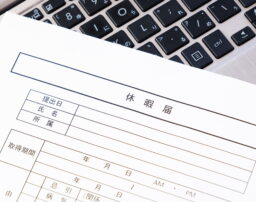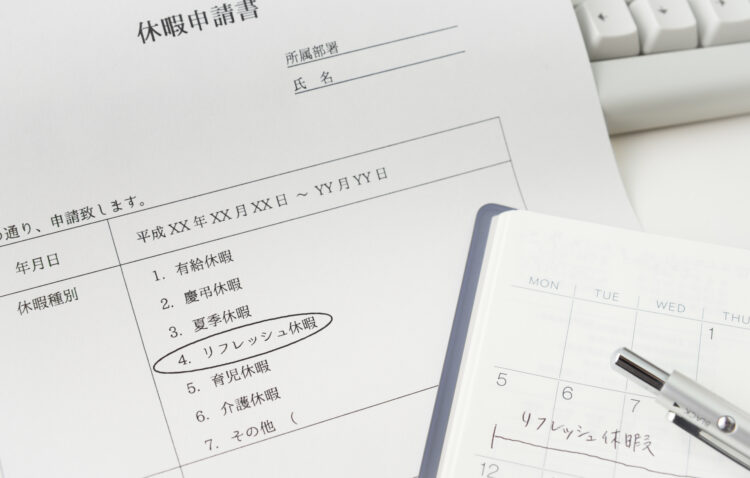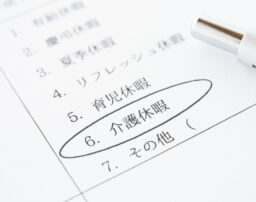「育児や介護が大変。仕事を休みたいけれど……」
育児介護休業法により、労働者は、育児や介護のために仕事を休むなど、さまざまな権利を認められます。一定の場合には育児休業・介護休業中に給付金を貰うこともできます。
また、育児介護休業法は2025年に改正され、育児や介護をする労働者がさらに働きやすい環境が整備されることを目指しています。
この記事では、育児介護休業法について、2025年の主な改正点、育児休業中・介護休業中に貰える給付金などについて、弁護士が解説します。
この記事を読んでわかること
- 育児介護休業法とは
- 育児休業の制度内容
- 子どもの看護休暇の制度内容
- 介護休暇・介護休業の制度内容
ここを押さえればOK!
育児介護休業法により、原則として1歳未満の子を養育する労働者が育児休業を取得可能です。分割して取得したり、産後パパ育休という休みを取得することもできます。育児休業中の収入保障として育児休業給付金という制度もあります。
また、2025年4月から子の看護休暇の対象者と取得理由が拡大されます。介護休業・介護休暇は要介護状態の家族を介護する労働者が取得可能です。
2025年の主な改正点には、残業免除対象者の拡大、テレワークによる育児・介護との両立支援、柔軟な働き方を実現する制度の充実、個別の意向聴取と配慮の義務化、介護離職防止のための環境整備が含まれます。
これらの改正により、育児・介護と仕事の両立がより容易になることが期待されます。
育児介護休業法とは?
「育児介護休業法」とは育児や介護をしなければならない労働者が「仕事と育児」「仕事と介護」を両立できるように支援する法律です。
育児介護休業法は1992年4月1日に施行されましたが、社会や働き方の変化によって複数回改正されています。
2025年には、より育児や介護と仕事との両立をしやすい社会を目指して、育児介護休業の改正法が4月と10月に段階的に施行されます。
育児休業の制度内容
「育児休業(育休)」とは、子どもが生まれた後に一定期間、育児をするために会社を休める制度です。男女問わず取得できます。
育児休業に関し、さまざまな権利が法によって保護され、休業中の収入減に対する給付制度(育児休業給付金)もあります。
(1)育児休業を取得できる労働者の範囲
育児休業を取得できるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です(日々雇い入れられる者は除く)。
バイトやパートなど、期間を定めて雇用される者は、育児休業取得の申出時点において、子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合は、育児休業を取得することができます。
また、労使協定により一定の労働者の育休取得が拒否されることもあります。具体的には、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者について労使協定で育休取得できないと定めた場合、会社は育休取得の申し出を拒否することができます。
参考:育児休業制度|厚生労働省
(2)育児休業を取得できる期間
育児休業を取得できる期間は、原則として次の通りです。
・女性労働者は、育児休業開始日(出産日から数えて58日目)~子どもが1歳の誕生日の前日まで。
・男性労働者は、出産予定日~子どもが1歳の誕生日の前日の期間中の1年間(ただし、育児休業給付の開始日は、出産日以降)。
※パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合には、一定の要件を満たせば、原則1歳2ヶ月(出産日から1年2ヶ月後)の前日まで育児休業休暇を取得できます(ただし、育児休業を取得できる期間は、原則1年)。
保育所に入れないといった特別な理由がある場合は、子どもが1歳6ヶ月に達するまで育休を延長できます。さらに同様の理由で再延長も可能で、最長2年まで育休期間を延長できます。
(3)育休は分割して2回取得できる
育休は、夫婦とも分割して2回育児休業を所得することができます(取得の際にそれぞれ申し出ることが必要)。
例えば、分割することで、夫婦で順番に交代して育児休業を取得することができるようになっています。
(4)産後パパ育休も取得できる
産後パパ育休は、父親が、子どもが生まれてから8週間以内に取得できる特別な育休です。この期間中に最大4週間の育休を取得することができます。
申出期間は、原則休業希望日の2週間前までで、分割して2回取得可能です。
育休中は働くことはできませんが、産後パパ育休については、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に働くことが可能です。
(5)育休中にもらえる様々な給付金
育児休業中は、仕事は休業しますので基本的に給料は支払われません。
しかし、育休中は、一定の要件を満たすと、雇用保険から次のような給付金が支給されます。
(5-1)育児休業給付金
育児休業給付金として、次の金額が支給されます。
・育児休業開始から6ヶ月⇒賃金の67%(原則)
・それ以降⇒賃金の50%(原則)
(※育児休業中に賃金を得ると、育児休業給付金が減額されたり、不支給となることがあります)
1ヶ月あたりの支給額は、原則として次のような計算式で求められます。
【育児休業開始から180日まで】
休業開始時の賃金日額(※1)×支給日数(※2)×67%
【育児休業開始から181日以降】
休業開始時の賃金日額×支給日数×50%
※1 「休業開始時の賃金日額」は申請時に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をもとに、育児休業を開始する前6ヶ月間の賃金を180で割った金額のことです。
この場合の賃金とは、保険料などが控除される前の「総支給額」のことで、手取り金額ではありません。
また、ここでいう賃金には賞与は含まれません。
※2 支給日数は30日
ただし、育児休業終了日の属する支給対象期間は、当該支給対象期間の日数が支給日数となります。
なお、1ヶ月あたりの支給額には、次の上限額があります(毎年8月に改定)
• 180日までが31万5369円
• 181日目以降が23万5350円
(2024年8月1日~2025年7月31日まで)
参考:令和6年8月1日から支給限度額が変更になります。|厚生労働省
(5-2)出生時育児休業給付金
子どもの父親が産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、一定の条件を満たすと、出生時育児休業給付金を受け取ることができます。
最大28日間、賃金の67%が支給されます。
計算式は次の通りです。
休業開始時の賃金日額×支給日数(上限は28日)×67%
出生時育児給付金の支給上限額は、29万4344円です(2024年8月1日~2025年7月31日まで)。
参考:令和6年8月1日から支給限度額が変更になります。|厚生労働省
(5-3)【2025年4月から】出生後休業支援給付金
2025年4月1日から、共働きと共子育てを推進するため、「出生後休業支援給付金」が支給されることになりました。
これは、子どもの出生直後の一定期間に、パパママともに(一方が働いていない場合には本人が)14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金にあわせて、最大28日間支給されます。
支給額は、休業開始時賃金日額×休業日数(28日上限)×13%です。
別途支給される育児休業給付金又は出生時育児休業給付金と併せて考えると、育休中は健康保険料・厚生年金保険料の支払いが免除されることもあり、育休取得前の手取り額とほぼ同額の収入が得られることになります。
参考:2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します|厚生労働省
(5-4)【2025年4月から】育児時短就業給付金
また、2025年4月1日から、2歳未満の子どもを養育するために所定の労働時間を短縮して、時短で就業した場合に、次の要件を満たすと、雇用保険から「育児時短就業給付金」を受給できる資格があります。
要件① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
要件② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、 又は、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。
支給額は、原則として次の通りです。
育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 最大10%
※ただし支給額と賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように調整されます。また、支給額と賃金額の合計額には支給限度額があります。
妊娠・出産・子育てによる収入減のダメージを減らすために、あたらしい給付金制度の受給も視野に入れて、収入の見込みをたてるとよいでしょう。
参考:育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省
参考:育児時短就業給付の内容と支給申請手続|厚生労働省
【2025年4月~】子どもの看護休暇の対象者などが拡大
「子どもの看護休暇」とは、子どもが病気やケガをして看護が必要な時に利用できる制度です。(育児介護休業法第16条の2)
子どもが小学校に入学するまで、看病や通院、検診、予防接種などのシーンで、1年度で対象となる子ども一人当たり5日間(2人以上の場合は10日間)利用できます。基本的には、時間単位での取得が可能です(ただし法律上、業務➡看護休暇➡業務戻る、という中抜けの権利までは法律上保証されていません。会社によって認めるかどうかは異なります)。
2025年4月からは、次のように対象者と休暇を取得できる理由が拡大され、名称も「子の監護等休暇」となります。より、子どものための看護等の休暇がとりやすくなるでしょう。
【対象者】
小学校3年生修了まで
【取得理由】
① 病気・けが
② 予防接種・健康診断
③ 感染症に伴う学級閉鎖など
④ 入園(入学)式、卒園式
(1)【2025年4月から】子どもの看護休暇をとれる人も拡大
子どもの看護休暇を取ることができるのは、その子どもを養育する労働者です(日雇い労働者を除く)。
また、2025年3月までは、労使協定により、次の労働者を看護休暇から除外することが可能でしたが、2025年4月からは「入社6ヶ月未満の労働者」が撤廃されます。入社6ヶ月未満であっても、所定労働日数の要件を満たしていてれば、看護等休暇が取得できるようになります。
- 入社6ヶ月未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
(2)看護休暇を取ったら給料はどうなる?
育児介護休業法では、看護休暇を取ったことに対し、給料を支払うよう定めていないので、会社によって、給料が貰えるかどうかは異なります。
就業規則を確認してみましょう。
育児と仕事を両立してより働きやすい社会とするために
2025年4月1日から、段階的に、育児と仕事を両立してより働きやすい社会を実現するために、次のような制度が始まります。
(1)【2025年4月から】残業免除の対象者が拡大する
一定の年齢までの子どもを育てる労働者は、会社へ申し出ることで、所定労働時間を超える労働(残業)が原則免除となります。
今回の改正により、その残業免除の対象者が「3歳までの子どもを育てる労働者」から、「小学校就学前の子どもを育てる労働者」に拡大されました。
(2)【2025年4月から】テレワークにより育児と仕事を両立できる可能性
法律上、3歳未満の子どもを育てる労働者には、時短勤務を利用できるようにし、時短勤務を利用できない業務につく労働者に対しては、代替措置をとる必要がありました。
今回の育児介護休業法の改正に伴い、その代替措置としてテレワークが新たに追加されます。
また、会社に対して、3歳未満の子どもを育てる労働者がテレワークを選択できるように措置を講じる努力義務が課されます。
これらにより、時短勤務ができない労働者も育児のためのテレワークがしやすくなる可能性があります。
(3)【2025年10月から】柔軟な働き方を実現するための制度が充実
会社は、3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者を対象に、次の内容から2つ以上選択して実施する必要があります。労働者はそのうち1つを選択して利用できます。
- 始業時刻などの変更(次のいずれかの措置)
- フレックスタイム制
- 始業または終業時刻の繰り上げまたは繰り下げ
- テレワークなど(10日以上/月)
- 保育施設などの設置運営など
- 保育施設などの設置運営
- ベビーシッターの手配および費用負担
- 就業しつつ子どもを養育することを用意にするための休暇の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
会社は、子どもが3歳になるまでに、その労働者に対し、適切な時期にこれらの措置の内容を周知し、利用するかどうかの意向を確認する必要があります。労働者から「利用したい」との申し出があれば、会社は労働者にその措置を利用させなければなりません。
(4)【2025年10月から】育児と仕事を両立するための個別の意向聴取
会社は、労働者が本人または妻の妊娠・出産などを申し出た時と、3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関して、個別に意向を聞き、配慮する必要があります。
<具体的な配慮の例>
• 勤務時間帯、勤務地の配慮
• 両立支援制度などの利用期間などの見直し
• 業務量の調整
• 労働条件の見直し など
介護休業、介護休暇の制度内容

育児介護休業法では、介護休暇と介護休業の2つの制度があり、休暇と休業で取得できる日数が異なります。
また、介護休業の場合は、雇用保険から一定の場合に給付金が貰えますが、介護休暇の場合は給付金を貰えないという違いもあります。
(1)介護休業
「介護休業」は病気やケガ、もしくは身体・精神の障害などの理由で2週間以上の「常時介護が必要」(※)な家族を介護する場合に取得できる休暇です(育児介護休業法第11条)。
※「常時介護が必要」な状態と認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。
介護休業の対象となる「家族」とは、配偶者(事実婚を含む)、両親、子(養子を含む)、配偶者の両親、祖父母、兄弟姉妹、孫のことをいいます。
介護休業の対象となる家族1人につき3回まで、通算93日まで取得可能です。
(1-1)介護休業をとれる人は誰?
介護休業を取ることができるのは、対象家族を介護する労働者です(日雇い労働者を除く)。
パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている労働者は、介護休業の取得の申し出時点で、次のいずれにも該当すれば、介護休業をとることができます。
① 1年以上雇用されている
② 取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間に(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
ただし、労使協定により次の一定の労働者に介護休業の対象外とすることができます。
- 入社1年未満
- 申出の日から93日以内に雇用期間が終了
- 1週間の所定労働日数が2日以下
会社が独自の制度を設けている場合もありますので、まずは担当部署に相談してみるとよいでしょう。
参考:介護休業制度|厚生労働省
(1-2)介護休業給付金の金額
介護休業中は、賃金をもらえない人も多いですが、一定の要件を満たした場合、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。
これにより、おおよそ、賃金の67%を貰うことができます。
具体的には、介護休業給付金は次の通り計算します(原則)。
休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
ただし、給付額には一定の上限があり、現在は月34万7127円です(2024年8月1日~2025年7月31日)。
また、介護休業期間中に賃金が支払われていると減額されたり、不支給となる場合があります。正確な金額はハローワークに確認しましょう。
参考:Q&A~介護休業給付~|厚生労働省
参考:令和6年8月1日から支給限度額が変更になります。|厚生労働省
(2)介護休暇
介護休暇は病気やケガ、高齢などの理由で要介護状態になった家族を介護や世話をする労働者に対して与えられる休暇です(育児介護休業法第16条の5)。
要介護状態にある対象家族1人につき、最大年5日、1日単位又は時間単位で介護休暇を取得できます(対象家族が2人以上の場合は、最大年10日まで)
ただし、時間単位での取得が困難と認められている業務に従事している労働者については、労使協定により、1日単位でしか介護休暇を取得できないとすることもできます。
また、時間単位で介護休暇を取得する場合、業務の途中で抜けて介護休暇を取る権利までは法律上、認められていません。
この中抜けが許されるかどうかは会社によって異なります。
(2-1)【2024年4月から】介護休暇をとれる人が拡大
介護休暇を取ることができるのは、対象家族を介護する労働者です(日雇い労働者は除く)。
また、会社によっては、労使協定により以下のいずれかに該当する労働者に介護休業を取らせないことができましたが、2024年4月からは1が撤廃されますので、介護休暇を取れる人が拡大します。
- 入社6ヶ月未満
- 1週間の所定労働日数が2日以下
(2-2)介護休暇を取ったら給料はどうなる?
育児介護休業法では、介護休暇中に、給料を支払うよう定めていないので、会社によって、給料が貰えるかどうかは異なります。
就業規則を確認してみましょう。
(3)【2025年4月から】介護離職防止、介護と仕事の両立を目指して
ままた、2025年4月から、介護と仕事の両立を目指し、介護離職を防止するために、法改正により会社は次のような措置を取る必要があります。
(3-1)介護離職防止のための環境を整備
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、会社は以下のいずれかの措置をとる必要があります。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修を実施する
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制を整備する(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例を収集し提供する
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針を周知する
(3-2)労働者に対する情報提供・意向確認
会社は、介護に直面したとの申出をした労働者に対し、介護休業制度に関する情報を提供し、介護休業や介護両立支援制度を利用するかどうか、個別に聞く必要があります。
<介護休業や介護両立支援制度に関して提供すべき情報>
- 介護休業や介護両立支援制度などの制度内容
- 介護休業や介護両立支援制度などを利用する場合の申出先
- 介護休業給付金の内容
さらに、介護に直面する前の段階の労働者に対しても、介護休業などに関する情報を提供する必要があります。
<情報を提供すべき期間(いずれか)>
- 労働者が40歳に達する翌日から1年間
- 労働者が40歳に達する日に属する年度
(3-3)テレワーク導入の努力義務
会社に対して、要介護状態の家族を介護する労働者に対し、テレワークできる環境を提供する努力義務が定められました。
【まとめ】労働者は育児・介護のために休業できる
育児介護休業法は育児や介護を目的とした休業を支援する制度で、さまざまな労働者の権利が保障されています。
また、一定の場合には休業中に給付金などが支給されます。
企業によって申請方法などは多少異なりますが、基本的に育児・介護休業や子どもの看護休暇・介護休暇を事業者は断れず、これらの休業や休暇を理由に不当な解雇をすることはできません。
育児・介護を目的とした休業に関し不安な方は、まず会社の担当窓口に相談してみましょう。