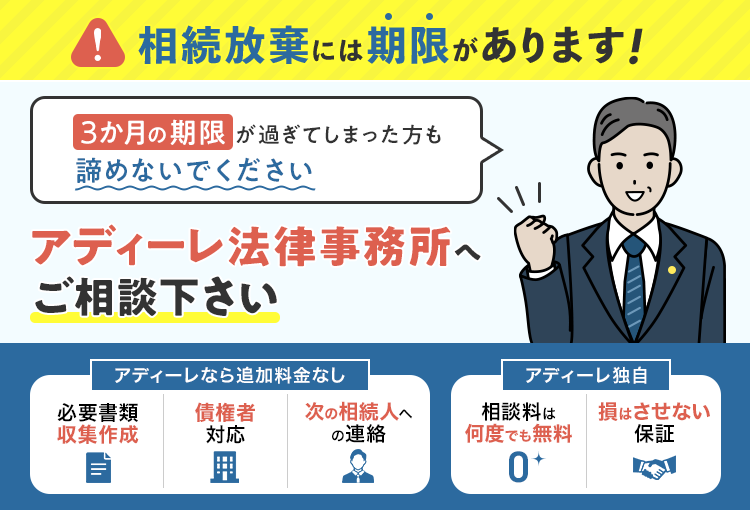連れ子は、実親の再婚相手と一緒に親子として暮らしていたとしても、再婚相手の遺産を相続する権利はありません。
再婚相手と連れ子が本当の親子のように暮らしていて、お互いに愛情を注いでいたとしても、法律上の親子関係は生じていないためです。
しかし、通常の親子と同じように生活しているにもかからわらず、いざというときに相続できず何も財産を受け取れないのは、不合理と思われる方もいます。
この記事では連れ子と実親の再婚相手との関係、連れ子に実親の再婚相手の財産を与える方法についてわかりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
- 連れ子にその実親の再婚相手の相続権はないことがわかる
- 連れ子にその実親の再婚相手の財産を分ける方法3つがわかる
- 連れ子とその実親の再婚相手が養子縁組すれば相続税対策になることがわかる
ここを押さえればOK!
養子縁組をすれば、法律上の親子関係が生じ、連れ子は再婚相手の遺産を相続することができます。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、通常は普通養子縁組が選ばれます。
遺言書で連れ子に遺産を与える場合、特定遺贈や包括遺贈の方法がありますが、他の法定相続人の遺留分を侵害しないように注意が必要です。遺言書の作成は弁護士に相談・依頼することが推奨されます。
生前贈与は、相続や遺贈ではなく、生きている間に連れ子に財産を贈与する方法です。ただし、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。
最終的に、連れ子に財産を残す方法として、養子縁組、遺贈、生前贈与のいずれかを選ぶことができますが、家族間での話し合いや弁護士への相談を通じて、事前に相続トラブルを避けることが重要です。
アディーレ法律事務所では、遺言書作成の相談を無料で受け付けていますので、お悩みの方はぜひご相談ください。
連れ子に相続権はない
「連れ子」とは、再婚時に相手に元夫・元妻との間の子どもがいて、再婚後その子どもと同居して一緒に生活するときに、その子どもを指して使われる言葉です。
連れ子とその実親の再婚相手が、本当の親子のように暮らしていても、それだけでは、連れ子は実親の再婚相手の遺産を相続する権利はありません。
その理由と、再婚後生まれた子どもとの違いを説明します。
(1)連れ子は法定相続人にはあたらない
民法のルールに基づいて、亡くなった方=被相続人の遺産を相続する権利を有する人のことを、法定相続人と言います。
民法で定められた法定相続人以外の人は、被相続人の財産を相続しません。
連れ子は、実親の再婚相手と一緒に親子のように暮らしていたとしても、再婚相手の法定相続人ではないため、再婚相手の遺産を相続することはありません。
仮に父が亡くなった場合、法定相続人は、配偶者である母と、父の子Bの2人であり、この2人が父の遺産を相続します。相続分は、母2分の1、子B2分の1です。
父と連れ子Aが同居して家族として生活していても、連れ子Aに父の遺産を相続する権利はありません。
(2)再婚しても連れ子と法律上の親子関係はない
再婚して、実親と再婚相手と連れ子とで家族として一緒に生活していれば、事実上の親子関係は認められるかもしれません。
しかし、それだけでは、連れ子と実親の再婚相手との間に法律上の親子関係は生じないので、民法上の法定相続人にもならないのです。
(3)再婚したあとに生まれた子には相続権がある
再婚したあとに子が生まれた場合には、親とその子との間には法律上の親子関係があります。
同じように父が亡くなったケースです。
再婚後に子Cが生まれた場合、連れ子Aとの関係をそのままにしておくと、連れ子Aは父の遺産を相続できない一方で、子Cは父の遺産を相続することになり、同居している子の間で差が生まれることになります。
法定相続人は、母、子B、子Cの3人であり、相続分は母2分の1、子B4分の1、子C4分の1です。
連れ子に財産を分ける方法
連れ子は、親の再婚相手と一緒に親子として暮らしていたとしても、親の再婚相手の遺産を相続する権利はありません。
連れ子に、その実親の再婚相手の財産を分けるためには、養子縁組する、遺言書で遺産を引き継がせる、生前に贈与する、という3つの方法があります。
順に説明します。
(1)連れ子と養子縁組をする
再婚相手と連れ子が養子縁組すれば、法律上の親子関係が生じますので、連れ子は再婚相手の遺産を相続することができます。
父が亡くなったケースで、父と連れ子が養子縁組していると、相続人は母、連れ子A、子Bの3人になります。相続分は、母2分の1、連れ子A4分の1、子B4分の1です(再婚後に生まれた子どもはいない場合) 。
養子となった連れ子Aと子Bの相続分は同じです。養子だからと言って、実子と比べて相続分が少ないということはありません。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あります。大きな違いは、普通養子縁組では実親との親子関係はそのままであるのに対し、特別養子縁組は実親との親子関係が消滅する点にあります。
通常は、普通養子縁組をすることになると思われます。
普通養子縁組と特別養子縁組について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
(2)遺言書で連れ子に遺産を与える
遺言書で、法定相続人ではない、特定の人に遺産を渡すことができます。
ですので、連れ子と養子縁組をしていなくても、遺言書で連れ子に遺産を与えることが可能です。
この場合、遺産を与えることを「遺贈」(いぞう)、遺贈を受ける人を「受遺者」(じゅいしゃ)といいます。
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類あります。
特定遺贈とは、例えば、「〇区〇丁目〇番地の不動産を遺贈する」(実際はもっと細かく特定します)など、特定の財産を譲ることをいいます。
また、包括遺贈とは、「遺産の4分の1を遺贈する」など、遺産の一定割合を譲ることをいいます。
遺贈は、相続とは異なりますので、遺言書に「相続させる」という言葉は使わないように注意しましょう。
(2-1)遺留分を侵害しないように注意する
遺言書で連れ子に遺産を与える際には、他の法定相続人の遺留分を侵害しないように注意しましょう。
遺留分とは、一定の相続人について、被相続人の相続財産から、法律上取得できることが保障されている最低限の取り分のことです。
この遺留分を侵害して連れ子に遺産を与えると、遺留分が認められる相続人は、連れ子に対して、「遺留分を侵害している分についてお金を下さい」と請求することができます(これを、遺留分侵害額請求といいます)。
お金で子ども同士が仲たがいしトラブルになることもあります。
トラブルを生じさせないためにも、遺言書を作成する際には法定相続人の遺留分に注意しましょう。
遺留分について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2-2)遺言書作成の際には弁護士に相談を
遺言の方式には次の3種類あります。
| 自筆証書遺言 | 被相続人自身が自筆で作成する遺言書 |
| 秘密証書遺言 | 被相続人が作成し、封印したものを公証人と証人に提出する遺言書 |
| 公正証書遺言 | 被相続人と証人立ち合いのもと公証人が作成する遺言書 |
秘密証書遺言は実務上あまり利用されていませんので、自筆証書遺言と公正証書遺言について簡単に説明します。
自筆証書遺言は、自分で作成することができますが、法律上決められたルールを守らなければ、無効となってしまうリスクがあります。後で誰かに改ざんされたり、紛失してしまったりするリスクもあります。
一方で、公正証書遺言は、費用はかかりますが、公証人が法律上問題のないように遺言書を作成しますので、無効となるリスクはほとんどありません。公正証書遺言は公証役場に保管されますので、改ざんや紛失のリスクもありません。
ただし、公証人は遺言書を作成することが業務であり、遺言書の作成を希望する人の法律相談を行ったり、アドバイスをしたりすることは基本的に行いません。
遺言書を作成するためには、財産の洗い出し(資料集め)、法定相続人は誰か、どの遺産を誰に残すか、遺留分を侵害しないのはどの程度かなどを調査して検討する必要があります。弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の代わりに必要な資料を集め、依頼者の希望を汲んで法律上有効な遺言書となるように文案を作成することができます。公正証書遺言としたい方は、弁護士が公証人との事前協議、当日の立ち合いなどを行い、作成までトータルサポートします。
相続が始まった後に家族間の無用なトラブルを避けたい方は、一度遺言書作成について弁護士に相談してみるとよいでしょう。
アディーレ法律事務所は、遺言書作成についてのご相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。
(3)連れ子に生前贈与する
亡くなった後に遺産を分ける相続や遺贈ではなく、生きている間に、連れ子に対して財産を贈与することで、財産を分けることができます。
つまり、生きている間に、相手が必要な時に財産を分けてあげることができるのです。これを生前贈与といいます。
相続権のある法定相続人は法律で決まっていますが、財産を贈与する人は、自由に選ぶことができます。
贈与は、書面がなくても送る人と貰う人の合意で成立しますが、後々家族間のトラブルや税金のトラブルをさけるためにも、毎年、贈与契約書を作成して保管しておくとよいでしょう。
年間(1月1日から12月31日まで)110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与を受けた側が、贈与税を支払う必要がありますので注意が必要です。
また、例えば年間100万円であっても、それが今後10年間定期的に贈与される契約などとされると、贈与税の課税対象となります。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁
なお、被相続人から相続や遺贈などで財産を得た人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与された財産については、年間110万円以下であっても、生前贈与加算として相続税の課税対象となる点もご注意ください。
参考:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁
連れ子に遺産を相続させる場合の注意点
相続権がない連れ子に対して、財産を相続させる方法、遺贈する方法、生前贈与する方法などで財産を与える手段を説明してきました。
しかし、相続権がある法定相続人が相続するケースとは異なり、いくつか注意してほしい点がありますので、ご説明します。
(1)養子縁組をしないと相続税が2割加算される
相続税には、基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」ありますので、相続税を支払わなければならない人はそう多くありません。
しかし、遺産が多く、相続税を支払う必要がある場合には、2割加算に注意する必要があります。
被相続人の一親等の血族(子など)及び配偶者以外の人が、相続や遺贈などで財産を受け取ると、相続税が2割加算されます。つまり、養子縁組していない連れ子に遺贈で財産を与えると、相続税が2割加算されるのです。
連れ子と養子縁組をしていると、連れ子は一親等の血族(子など)になりますので、2割加算の対象ではありません。
参考:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁
(2)特に実子と相続トラブルが生じやすい
連れ子に相続や遺贈で再婚相手の財産を与えようとする際には、再婚相手の元配偶者との間に実子がいる場合など、他の法定相続人との関係が悪化しないように気を配る必要があるでしょう。
特に実子と離れて交流もないよう場合、実子やその親(元配偶者)が連れ子をうらやむなどし、連れ子に財産を残すことをよしとせず、亡くなった後で相続トラブルが生じるおそれがあります。
当事者同士で冷静に話し合うことで解決すればよいですが、「家族」「お金」という面が問題になると、感情的になりやすく、お互いに罵りあったり意見を譲らなかったりして話し合いで解決せず裁判に発展することもあります。
死後、大切にしていた家族間で大きなトラブルが生じてしまいかねません。
事前に連れ子・実子の心情を理解し、説明を尽くすことで、家族間の感情的なすれ違いや誤解を避けることができるでしょう。
連れ子と養子縁組すれば相続税対策になる?
相続税の基礎控除額の計算式は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額は増えますので、その意味では連れ子と養子縁組すると相続税対策となります。
ただし、相続税の計算において、養子が法定相続人となるのは限度があります。
実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までです。
ただし、配偶者の連れ子を養子縁組した場合には、この限度は適用されず、すべて法定相続人の数に含むことができます。
参考:No. 4170 相続人の中に養子がいるとき|国税庁
【まとめ】連れ子には相続権はない!養子縁組や遺贈で遺産を残すことが可能
連れ子には相続権はありませんが、養子縁組すれば相続人として相続させることができます。
養子縁組すれば、相続税の基礎控除額が増えますので、相続税対策にもなります。
養子縁組しなくても、遺贈や生前贈与という方法で、財産を残すこともできます。
どのような形で誰に、どれだけ遺産を残すかは、遺言を残す人が決めることができますが、事前に配偶者や子どもと話し合ったうえで決めていくと相続トラブルを避けることができるでしょう。
なくなった後、家族間での相続トラブルを避けるためにも、誰に何を引き継いでほしいのかを遺言書に残しておくことをお勧めします。
アディーレ法律事務所では、遺言書作成を扱っております。
遺言書作成の法律相談は電話ですることができ、何度でも無料です(2025年5月時点)。
「家族が遺産でもめないようにしたい」とお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所(フリーコール:0120-554―212)にご相談ください。