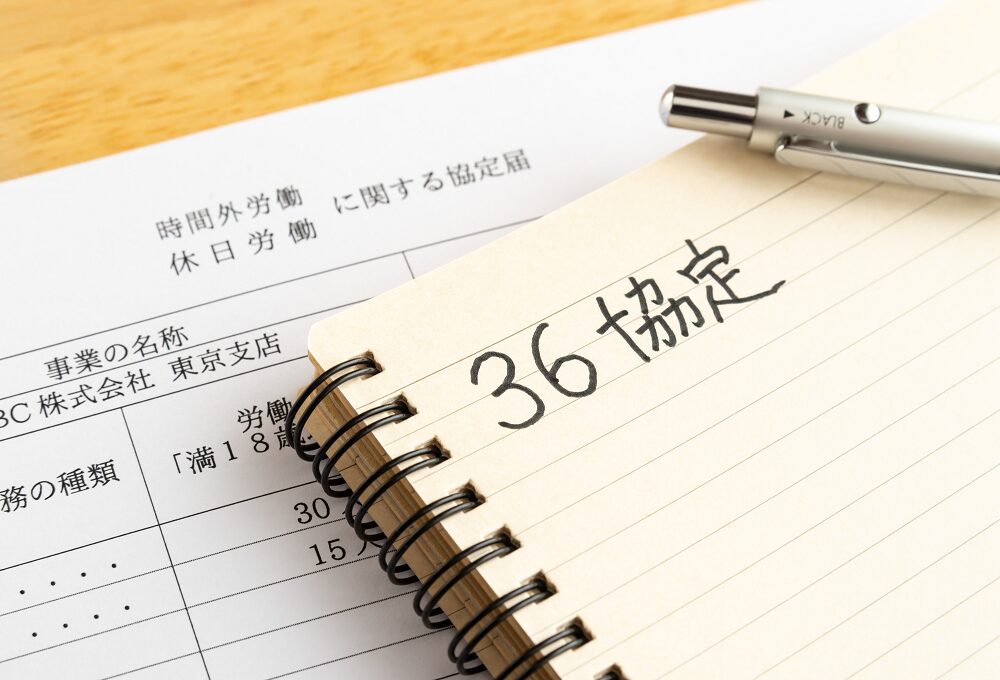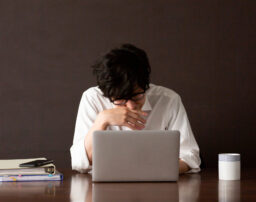この記事を読んでわかること
- 36協定は、労使間で締結する時間外労働と休日労働に関する協定で、労使で締結し、労働基準監督署に届出をすることで、法定労働時間を超える時間外労働が可能となる
- 特別条項付き36協定の場合でも、年間720時間、単月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内という制限がある
- 月80時間を超える残業をした従業員は、面接指導制度を利用して医師の面談を受ける権利がある
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
自宅でらくらく「おうち相談」
「仕事が忙しくて時間がない」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
36協定の基本と月80時間の上限規制
36協定と月80時間の上限規制は、労働時間管理の要となる重要な制度です。
36協定は労使間で締結する時間外労働の取り決めであり、月80時間の上限規制は働き方改革による新たな制限です。
特別条項付き36協定の場合でも、上限が設けられています。
以下、各項目について詳しく解説します。
(1) 36協定とは:労使間の時間外労働の取り決め
36(さぶろく、さんろく)協定は、労働基準法第36条に基づく、時間外労働と休日労働に関する労使間の協定です。
主な特徴は以下の通りです。
- 労使で締結:使用者と全労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で締結
- 労働基準監督署への届出が必要
36協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ提出することで、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働が可能となります。
36協定や届出をすることなく、時間外労働や、休日労働をさせると、原則として、労働基準法32条違反となり、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるおそれがあります(労働基準法119条1号)。
なお、36協定と届出だけでは、従業員に時間外労働や休日労働を義務付けることはできません。
実際に従業員に時間外労働を義務付けるためには、労働協約や就業規則において、「業務上必要があるときには、36協定の範囲内で、時間外労働や休日労働を義務付ける」旨、明記されている必要があります。
(2)月80時間の上限規制:働き方改革による新たな制限
2019年4月の労働基準法改正により、一部業種を除いて、法律による時間外労働の上限規制が導入されました(中小企業への適用は2020年4月から)。
主なポイントは以下の通りです。
- 原則:月45時間、年360時間
週休2日制で、月20日程度の勤務日があるケースだと、1日平均で2時間程度の残業ができる計算になります。
上記に違反した場合は、6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、この上限を超えて時間外労働が可能ですが、その場合にも上限があります。
次に、特別条項がある場合の上限について説明します。
(3)特別条項付き36協定の場合の上限規制
特別条項付き36協定とは、法定で原則とされる上限を超えて労働時間を延長できる特別な取り決めです。
ただし、以下の制限があります。
- 年間の上限:720時間
- 単月の上限:100時間未満(休日労働含む)
- 2~6ケ月平均:80時間以内(休日労働含む)
- 原則である月45時間の限度を超えられるのは年6ケ月まで
特別条項を適用する場合には、臨時的に限度を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定める必要があります。
また、時間外労働・休日労働はできる限り短期間・小規模となるよう努めることが求められます。また、36協定の範囲内であっても、使用者は労働者に対する安全配慮義務があり、労働時間が長くなるほど労働者の健康管理に特に注意を払う必要があります。
月80時間を超える残業の法的問題点
特別条項付きの36協定があっても、2~6ケ月平均月80時間を超える残業させることは、労働基準法違反となり、企業に深刻な法的責任が生じる可能性があります。
また、80時間を超える残業は、従業員の健康被害のリスクも高まり、過労死ラインとして認識されています。
これらの問題点を理解し、適切な労務管理を行うことが企業にとって極めて重要です。
(1)労働基準法違反のリスク:企業が負う法的責任
特別条項付きの36協定のない月80時間を超える残業は、労働基準法違反です。もし、違法な残業により過労死等が発生すると、企業は以下のような法的責任を負う可能性があります。
- 是正勧告:労働基準監督署からの是正指導
- 企業名公表:違法な長時間労働を行った企業として公表される
- 民事責任:従業員からの損害賠償請求
- 刑事責任:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法119条)。両罰規定により、違反行為を行った従業員だけでなく、法人も処罰の対象(同法121条)
過去実際に、過労死が発生した会社に対して、企業名が公表され、労働基準法違反で書類送検され刑事責任を負った例があります。企業は、このようなリスクを回避するため、適切な労働時間管理と従業員の健康管理を徹底する必要があります。
(2)過労死ラインとしての月80時間:健康被害のリスク
厚生労働省の通達により、次のいずれかの時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連性が強いものとされています(いわゆる、過労死ライン)。
- 発症前1ケ月におおむね100時間を超える時間外労働
- 発症前2~6ヶ月間にわたって、1ケ月あたり80時間を超える時間外労働
このような時間を超えて残業し従業員が過労死した場合には、労災が認められる可能性が高いです。
また、過労死ラインを超えていなくても、過労死ラインに近い時間外労働を行った場合には、労働時間以外の負荷要因(休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短いことなど)も考慮して労災が判定されます。
参考:「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(平成13年12⽉12⽇付け基発第1063号厚 ⽣労働省労働基準局⻑通達)
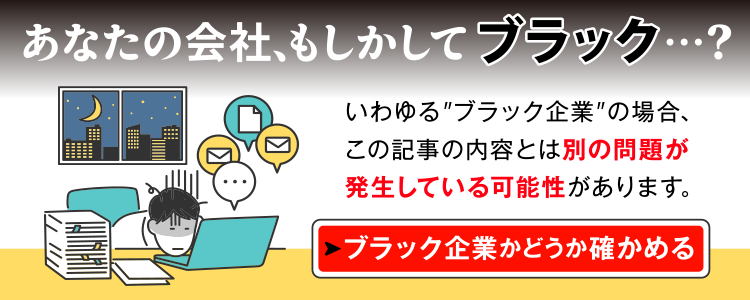
月80時間の残業上限が適用されない場合
月80時間の残業上限規制には、一部適用除外となる労働者が存在します。
主に管理監督者、専門業務型裁量労働制の適用者、そして公務員がこれに該当します。
ただし、これらの労働者にも健康管理は必要であり、過度な長時間労働は避けるべきです。
以下、各カテゴリーについて詳しく解説します。
(1)管理監督者:適用除外となる条件
管理監督者は、労働時間規制の適用除外となりますが(労働基準法41条2号)、大切なのは肩書ではなく、労働の実態です。
次の3つの判断要素から、管理監督者であるかどうかが判断されます。
- 経営者と一体性を持つような職務権限を有していること
- 出退勤について自由裁量があること
- 賃金等の待遇面でその地位にふさわしい待遇を受けていること
企業は、管理監督者の認定を慎重に行い、過度な長時間労働を避けるよう配慮する必要があります。
(2)専門業務型裁量労働制の適用者:規制の違い
専門業務型裁量労働制の適用者は、通常の労働時間規制とは異なる扱いを受けます。
対象業務は、新商品又は新技術の研究開発、情報処理システムの分析・設計など一定の業務に限定されています。
その特徴は次の通りです。
- 実際の労働時間に関わらず、一定の時間働いたものとみなす
- 労働時間の管理は労働者の裁量に委ねられる
裁量労働制であっても、無制限に長時間労働を強いることはできません。企業は、健康管理など安全配慮義務を負うことは変わりがありません。
(3)公務員への適用:異なる規制の内容
公務員の労働時間規制は、一般の労働者とは異なる法律で定められています:
- 国家公務員:人事院規則で規定
- 地方公務員:地方公務員法で規定
主な特徴:
- 原則として、週38時間45分勤務
- 時間外勤務命令の上限:原則月45時間、年360時間
注意点:
- 地方公務員の労働時間などについては条例で定める。
- 災害対応等の特例業務は上限規制の適用除外
例えば、警察官や消防士などは、緊急時の対応が必要なため、一般の労働者とは異なる規制が適用されます。ただし、公務員の過労死問題も指摘されており、法律上も、国や地方自治体は特例業務を適切に管理することが求められています。
従業員が知っておくべき権利と対処法
従業員は、長時間労働から身を守って自身の健康を確保するために、長時間労働に関する知識を持って適切に対処することが重要です。
労働者に認められた権利と対処法は以下の3点です。
- 面接指導制度の利用
- 残業代請求権の行使
- 健康管理の実践
これらの権利を適切に行使し、自身の健康を守ることで、長期的なキャリア形成と充実した私生活の両立が可能となります。
(1)面接指導制度:月80時間超の残業時の医師面談
面接指導制度は、長時間労働による労働者の健康被害を防ぐための重要な制度です。
主なポイント:
- 対象:月80時間を超える残業をした従業員
- 内容:医師による面談と健康状態の確認
- 申出権:従業員には面接指導を申し出る権利があり、事業者は申出があれば遅滞なく面接指導を行わなければならない
手順:
- 企業から対象者あてに面接指導の案内をする
- 従業員が申し出る(申出は義務ではない)
- 医師との面談を受ける
- 医師の意見を踏まえ、必要な措置を講じる
注意点:
- 面接指導の結果は、労働時間の短縮や配置転換などに反映される可能性がある
80時間以上の労働をしている方は、この制度を積極的に利用することで、自身の健康状態を客観的に把握し、過労による健康被害の予防に役立つ可能性があります。
(2)残業代請求権:適切な残業代を受け取るために
残業代請求権は、労働の対価を適切に受け取るための重要な権利です。
残業しているのに残業代が支払われていない場合には、残業代を請求できるかもしれません。
主なポイント:
- 残業代請求権の時効:3年間
- 残業代の計算方法:1日8時間、週40時間を超える時間外労働について通常賃金の25%以上増し(深夜労働や休日労働はまた別に計算する)
- 管理監督者は対象外(深夜労働については対象となる)
請求の手順:
- 残業時間の証拠を集める(就業規則、タイムカードのコピーなど)
- 給与明細と実際の労働時間を照合する
- 未払いがある場合、会社に請求する
- 解決しない場合、労働基準監督署や弁護士に相談する
注意点:
- サービス残業は違法であり、強要されてはならない
- 残業代未払いを労働基準監督署に相談したことによる不利益取扱いは禁止されている
今までの使用者との関係から、残業代を請求しにくいという事情があるかもしれません。
しかし、働いた分給与をもらうというのは、生きていくうえで、労働者として非常に重要な権利です。
使用者があなたの労働力を搾取することを許していては、健全な労使関係は築けません。
特に、残業代は3年という時効がありますので、請求したいと思ったら早めに残業代請求を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。
(3)健康管理:長時間労働によるリスクと自己防衛策
長時間労働は様々な健康リスクをもたらすため、自己防衛策を講じることが重要です。
主なリスク:
- 心血管疾患(脳卒中、心筋梗塞など)
- メンタルヘルス問題(うつ病、バーンアウトなど)
- 生活習慣病(糖尿病、高血圧など)
- 睡眠障害
自己防衛策:
- 定期的な健康診断の受診と結果の確認
- 会社のストレスチェックの活用
- 適度な運動と休息の確保
- 例:週2回30分のウォーキング、休日の十分な睡眠
- バランスの取れた食事
- 上司や人事部門への相談
- 必要に応じて産業医への相談
これらの自己防衛策を実践することで、長時間労働のリスクを軽減し、健康的な職業生活を送る可能性を高めることができるでしょう。
36協定と月80時間上限規制の今後の展望
今後も働き方改革の進展により、月の労働時間の上限がさらに引き下げられる可能性はゼロではありません。
現在、時間外労働の割増賃金は基本的に25%以上ですが、月60時間を超える場合には50%以上に加算されています。
そのため、一部の企業では独自につき60時間上限を導入しているケースもあるようです。
今後の変化に適応するため、企業は長期的視点での労働時間管理戦略の見直しが必要となるでしょう。
よくある質問と回答
36協定について、よくある質問と回答はこちらをご覧ください。
【まとめ】
36協定と月80時間上限規制は、持続可能な労働環境を実現するための重要な制度であり、その意義を十分に理解し活用することが求められます。
労働時間の規制を理解し、適切に対応することで、企業は法令遵守と生産性向上を両立し、従業員は健康的でワークライフバランスの取れた生活を送ることができるでしょう。
まず自身の労働時間を見直し、必要に応じて上司や人事部門に相談してください。健康的で生産性の高い職場づくりは、あなた自身の行動から始まります。
もし、「退職したいけど言い出せない」とお悩みの方は、退職代行を扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。