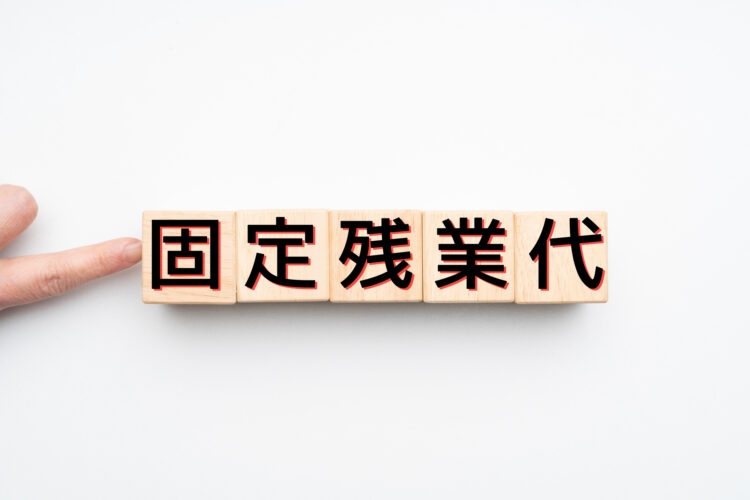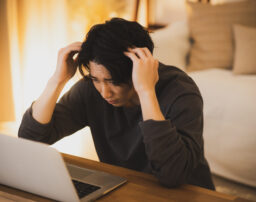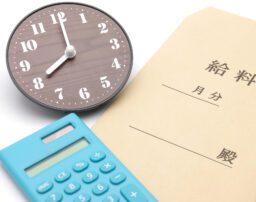働き方の多様化とともに、変形労働時間制という労働時間制度を導入する企業が多くなっています。ただ、変形労働時間制というと、自由に労働させることができ、また残業代も発生しないとのイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
しかし、変形労働時間制といっても時間外労働が発生する場合には36協定の締結が必要となります。また、当然残業代も発生します。
ここでは、変形労働時間制と36協定、変形労働時間制で残業代が発生する場合について説明します。この記事を読んで、「実は適切な残業代を受けとっていない」「本当は不当な残業をさせられている」という事態を回避しましょう。
この記事を読んでわかること
- 変形労働時間制には3種類ある
- 変形労働時間制であっても時間外労働が発生する場合には36協定が必要になる
- 変形労働時間制であっても残業代が必要なケースがある
- 変形労働時間制で一度決めた労働時間は変更できない
- 変形労働時間制とシフト制やフレックスタイム制には違いがある
ここを押さえればOK!
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や休日労働を行う場合、36協定を締結し所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。変形労働時間制でも、法定休日や時間外労働、深夜労働には割増賃金が適用されます。一度決めた労働時間は変更できず、変更する場合は就業規則の変更と労働基準監督署への届け出が必要です。
変形労働時間制は、フレックスタイム制やシフト制と異なり、労働時間の柔軟性や勤務の仕方に違いがあります。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、特定の期間(1か月、1年、1週間など)の総労働時間を一定とし、その期間内で労働時間を柔軟に配分できる制度です。
例えば、特定の日や週に法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)を超えても、期間内の週あたりの平均労働時間が週の法定労働時間(原則40時間)に収まっていれば、時間外労働にはなりません。
つまり、忙しい日や週があったとしても、他の日の労働を短く調整すれば、時間外労働にはならないということです(時間外労働が発生しないということではありません)。
会社側としては、繁忙期と閑散期に応じて労働時間を調整することで、効率的に人件費を管理できるというメリットがあります。一方、労働者側としても繁忙期と閑散期に応じた労働時間の調整により、個々のライフスタイルに合った働き方が可能です。
変形労働時間制の種類とは
変形労働時間制には、1か月単位、1年単位、1週間単位の3つの種類があります。これらの制度によって、それぞれ異なる期間で労働時間を柔軟に調整することが可能になります。
(1)1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間は、月初め、月末、特定の週などの業務が忙しい場合にとる方法です。
1ヶ月以内の一定の期間で平均し、1週間当たりの労働時間が原則40時間の範囲で、特定された週又は日において1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができます。
1ヶ月単位の変形労働時間制の導入は、労使協定ではなく就業規則などよって行うことも可能です。
(2)1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間は、特定の季節、特定の月などの業務が忙しい場合にとる方法です。
1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲で、特定された週又は日において1週40時間又は1日8時間を超えた労働をさせることができます。
ただし、1年単位の変形労働時間には、次の制限があります。
- 対象期間中の労働時間は、平均して1週間あたり40時間以内
- 対象期間が3ヵ月を超える場合、対象期間内の所定労働日数は原則として1年あたり280日が上限
- 1日の労働時間は原則10時間まで
- 1週間の労働時間は52時間まで
- 対象期間が3ヵ月を超える場合、労働時間が48時間を超える週が連続するのは3週まで
1年単位の変形労働時間制の導入には、労使協定と当該労使協定を所轄の労働基準監督署に提出することが必要です。
(3)1週間単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間は、業務の忙しさが直前までわからないなどの場合であって、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業で常時使用する労働者が30人未満であるときに、とる方法です。
1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができ、一定の要件を満たせば1日について10時間まで労働させることができます。
1週間単位の変形労働時間制の導入には、労使協定と当該労使協定を所轄の労働基準監督署に提出することが必要です。
変形労働時間制と36協定とは
36協定とは、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を労働者にさせる場合に必要な労使協定のことです。
使用者が労働者との間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出れば、36協定で定めた基準を超えない範囲の時間外労働又は休日労働を労働者にさせることができるようになります。
- 36協定(一般条項)の上限:時間外労働は月45時間・年360時間が上限
また、特別な事情がある場合に限り、1ヶ月の時間外労働の上限を80時間まで延長することができますが、これも厳しい条件が付されています(一部の事業・業務を除く)。
- 特別条項付き36協定:1ヶ月の時間外労働は80時間が上限
- 条件
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働及び休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働及び休日労働の合計が、複数月平均で80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
変形労働時間制は、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限り、1週40時間又は1日8時間を超えた労働をさせることができる制度です。しかし、変形労働時間制を採用している企業でも、休日労働や時間外労働が発生するのであれば、36協定の締結が必要になります。
変形労働時間制での残業代の計算方法
変形労働時間制であっても残業代が発生することがあります。
例えば、休日労働や深夜労働、時間外労働が発生する場合には、変形労働時間制であっても残業代を払う必要があります。
(1)変形労働時間制での休日労働
休日労働とは、法定休日の労働をいいます。
法定休日とは、労働者に週1回休日を与えるものとしており、この週1回の休日のことです。週休2日(土曜日と日曜日が休日)の会社であれば、日曜日が「法定休日」とされているケースことが一般的です。
そして、変形労働時間制であっても、法定休日に行われた労働は休日労働と扱われ、割増賃金の適用対象となります。
- 法定休日に勤務させたとき:割増率35%以上
例えば、会社が週休2日制を採用し、日曜日を法定休日と定めている場合に日曜出勤をした場合を考えてみましょう。この場合、基礎賃金(各種手当を除いた賃金)より35%以上増しの割増賃金を払う必要があります。
(2)変形労働時間制での時間外労働
時間外労働が行われた場合、使用者は労働者に対して、割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければなりません。それは、変形労働時間制であっても同じです。
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき:割増率25%以上
- 時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき:割増率50%以上
変形労働時間制の場合でも、時間外労働が発生する場合があり、時間外労働をさせる場合には36協定の締結及び届出が必要となります。
変形労働時間制における時間外労働の時間は、「1日単位」「週単位」「単位期間の全体」という3段階の計算を合計することによって算出されます。
| 時間外労働の時間 | |
|---|---|
| (ア)1日単位 | ・所定労働時間が8時間を超えて設定された日についてはそれを超えて労働した時間 ・所定労働時間が8時間以内に設定された日については8時間を超えて労働した時間 |
| (イ)週単位 | (ア)で時間外労働として計算された時間を除き、 ・所定労働時間が40時間(上記した一部の業種では44時間、以下同じ)を超えて設定された週についてはそれを超えて労働した時間 ・所定労働時間が40時間以内に設定された週については40時間を超えて労働した時間 |
| (ウ)単位期間全体 | (ア)(イ)で時間外労働とされた時間を除き、 ・単位期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間 ※例えば、1ヶ月の法定労働時間の総枠は、1ヶ月が28日の月であれば160時間、31日の月であれば177.1時間となります。 |
(3)変形労働時間制と深夜労働
深夜労働をさせるのに36協定の締結は必要ありません。
しかし、深夜労働が行われた場合、使用者は労働者に対して、割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければなりません。それは、変形労働時間制であっても同じです。
- 深夜労働(22時から5時に勤務)をしたとき:割増率25%以上
変形労働時間制についてよくある質問(Q&A)
最後に、変形労働時間制についてよくある質問を回答します。
(1)一度決めた労働日・労働時間は変更できる?
一度決めた労働日・労働時間は、会社が業務の都合によって任意に変更することはできません。
例えば、一か月単位の変形労働時間制を採用し、その内容を変更する場合には、それに関連して就業規則を変更し、その変更届が労働基準監督署に届け出ることが必要になります。
(2)フレックスタイム制やシフト制との違いは?
変形労働時間制は、フレックスタイム制やシフト制と似ている制度ではありますが、全く別の制度です。変形労働時間制とフレックスタイム制やシフト制との違いは、次のとおりです。
- フレックスタイム制:一定の期間のなかで、一定時間労働することを条件として、始業時間と終業時間を自由に決められる制度です。しかし、変形労働時間制は、自由な時間の出退勤が認められているわけではないという点で、フレックスタイム制と異なります。
- シフト制:シフトパターンごとに従業員が交替で勤務する制度です。しかし、変形労働時間制では、必ずしも従業員が交替で勤務するわけではない、という点でシフト制とは異なります。
【まとめ】変形労働時間制とは労働時間を柔軟に配分できる制度
変形労働時間制には1か月単位、1年単位、1週間単位の3種類があり、それぞれの制度に応じた労働時間の調整が可能です。変形労働時間制を導入していても、時間外労働が発生する場合には36協定の締結が必要であり、残業代も発生します。36協定の締結や法的要件を理解し、適切な運用を行うことで、法令遵守とリスク回避が可能です。
変形労働時間制を採用していて、「適切な残業代がもらえていないのでは?」と不安がある方は、ぜひアディーレ法律事務所へご相談ください。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配なく、ご依頼いただけます。
※以上につき、2024年11月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。