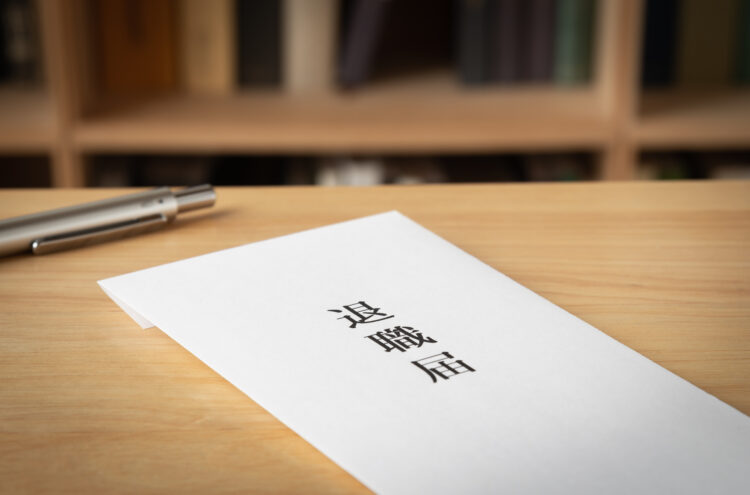退職後、何をすれば良いのか不安に感じていませんか?
仕事を辞める決断をしたあなたには、次のステップに進むための重要な手続きが待っています。
このコラムでは、退職後に必要な手続きや書類を具体的に解説します。
これを読み、退職後の手続きについて期限や重要な書類をしっかりと把握することで、安心して新生活に進めるでしょう。さあ、一緒に確認していきましょう。
ここを押さえればOK!
・住民税の切り替え: 退職前後に実施。
・失業保険の申請: 退職後すぐにハローワークで手続きを。
・年金切り替え: 退職後14日以内に年金手続きが必要。
・健康保険の切り替え: 退職後14日もしくは20日以内に行う。
・確定申告: 年末までに転職しなかった場合に必要。
・給料未払いの確認: 支払期日から3年以内に確認。
必要な書類
・雇用保険被保険者証: 転職先で必要。
・年金手帳: 年金受給に重要。
・源泉徴収票: 年末調整や確定申告に必要。
・離職票: 失業手当の申請に必要。
・退職証明書: 国民健康保険や年金手続きに使用。
・健康保険資格喪失証明書: 国民健康保険加入時に必要。
これらの手続きや書類を把握しておくことで、退職後の新生活に安心して進むことができます。特に、手続きの期限には注意が必要です。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
退職後にやるべき手続きと必要な書類
まず、退職にやるべき手続きと必要になる書類をチェックしておきましょう。
(1)退職後にやるべき手続き
退職後にやるべき手続きは次の5つです。すべき時期についても確認しておきましょう。
- 住民税の切り替えの手続き:退職前後
- 失業保険の申請手続き:退職後すぐ
- 年金切り替えの手続き:退職後14日以内
- 健康保険の切り替えの手続き:退職後14日もしくは20日以内
- 確定申告の手続き:年末までに転職しなかった場合に必要
- 給料未払いの有無の確認:賃金の支払期日から3年以内
(2)退職時に必要となる書類
次に、退職時に必要となる書類についてもチェックしておきましょう。
- 雇用保険被保険者証:転職先が雇用保険を引き継ぐために必要となります。雇用保険の加入時に発行され、会社に預けている場合は受け取るようにしましょう。
- 年金手帳:将来の年金受給に関わる重要な書類です。入社時に会社に預けていた場合は受け取るようにしましょう。
- 源泉徴収票:次の職場での年末調整や確定申告に必要です。退職後1ヶ月以内に会社が発行してくれます。
- 離職票:失業手当の受給申請に必要な書類です。事業主が必要書類を提出し、ハローワークが発行するものとされています。
- 退職証明書:転職までに期間が空く場合に、国民健康保険や国民年金の手続きで必要になる書類です。
- 健康保険の資格喪失証明書:国民健康保険への加入手続きに必要な書類です。
退職後にやるべき手続きや必要となる書類をしっかり把握しておくことは、退職後の手続きを円滑に進めるための第一歩です。
住民税の切り替えの手続き
住民税は前年の所得に対して課税されるもので、6月から翌年5月にかけて支払います。退職後1ヶ月以内に転職する場合と転職までに期間が空く場合とで対応が異なります。
(1)退職後1ヶ月以内に転職する場合
転職先が決まっている場合は、新しい勤務先にて住民税の特別徴収(給料からの天引き)が継続されます。転職先の人事部などの担当者に住民税の特別徴収の手続きを依頼し、給与所得者異動届出書を提出するようにしましょう。
給与所得者異動届出書は転職前の会社に必要事項を記入してもらう必要があります。退職前に済ませておきましょう。
(2)転職までに期間が空く場合
転職までに期間が空く場合は、退職時期によってとるべき対応が異なります。
(2-1)1~5月に退職する
退職した月から5月までの間の住民税を退職月の給与から一括して特別徴収されます。
例:3月に退職→3月分・4月分・5月分の住民税を3月分の給与から天引き
住民税の額が退職の月の給与等の額より大きかった場合には、普通徴収(納税通知書等を使って個人で納付する方法)に切り替わり、未納分を普通徴収で納付することになります。
(2-2)6~12月に退職する
退職するまでの住民税は給与から特別徴収されます。退職後の住民税は、原則として、普通徴収に切り替わるため、自身で納付する必要があります。
ただし、会社に希望すれば、退職月から翌年5月分までの住民税を、退職月の給与から特別徴収して納付することも可能です。
失業手当の申請手続き
会社を退職した場合、一定の条件を満たすことによって、雇用保険から失業手当を受給することができます。
【失業手当を受給するための条件】
- ハローワークで求職の申込をおこない、積極的に転職活動している
- 雇用保険の被保険者期間が過去2年間で通算して12ヶ月以上ある
※ 特別な事情がある場合は過去1年間で通算6ヶ月以上
失業手当を受給するには、ハローワークでの手続きが必要になります。失業保険の支給は会社都合退職で手続きをしてから8日以降、自己都合退職で手続きをしてから2ヶ月もしくは3ヶ月以降です。少しでも早く失業手当を受け取りたい方は、離職票が届き次第早めに手続きをしましょう。
年金の手続き
国民年金とは、国民年金法によって規定されている公的年金をいいます。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者は、すべて国民年金に加入しなければならないとされています。
(1)退職後1ヶ月以内に転職する場合
退職後1ヶ月以内に転職する場合、転職先で引き続き厚生年金に加入できます。
転職先の人事課など担当者に年金手帳を提出すれば、会社が手続きを行ってくれます。
(2)転職までに期間が空く場合
在職中は、厚生年金(第二号保険者)に加入していることに多いですが、退職するとそれまで加入していた厚生年金から自動的に脱退することになります。そのため、退職して離職期間がある方は、第一号被保険者または第三号被保険者へ移行する必要があります。
(2-1)第一号被保険者への変更する
退職して自営業や無職となる場合、国民年金の第一号被保険者に変更します。市区町村役場で手続きを行い、必要書類として年金手帳と本人確認書類を準備します。
(2-2)第三号被保険者への変更する
配偶者が厚生年金に加入している場合、その扶養に入り第三号被保険者となることが可能です。手続きは配偶者の勤務先で行い、必要書類として、配偶者の保険証や住民票などを提出します。
(3)年金免除申請する
失業状態にある場合、申請をすれば年金保険料の免除を受けることができます。
保険料の免除が承認された期間は年金の受給資格期間に算入されますので、免除の申請をするメリットは大きいです。免除の申請には期間制限もあるので、必ず免除申請をするようにしましょう。
健康保険の切り替えの手続き
会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格を喪失してしまうため、切り替えをする必要があります。切り替えには健康保険資格喪失証明書が必要です。健康保険証を返却した際に受け取るようにしましょう。
健康保険被保険者資格喪失後にとるべき方法は、次の4つです。
- 転職先の健康保険に加入する
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続被保険者制度を利用する
- 被保険者の被扶養者となる
それぞれ見ていきましょう。
(1)転職先の健康保険に加入する
新しい職場が決まっている場合は、転職先の健康保険に加入するのが最も簡単です。入社時に必要書類を提出することで、新しい会社の担当者が切り替え手続きを行ってくれます。
(2)国民健康保険に加入する
転職先が決まっていない場合は、退職日の翌日から14日以内市区町村役場で国民健康保険に加入します。手続きは、住んでいる地域の市区町村役所で行います。
国民健康保険は誰でも加入できますが、扶養家族の制度がなく、所得次第では保険料が高額になることがあります。
(3)任意継続被保険者制度を利用する
任意継続被保険者制度とは、一定の条件を満たす場合に、健康保険の加入条件「適用事業所に常時使用されること」を満たさなくても引き続き健康保険に加入し続けることができる制度です。
この制度を利用する場合、退職日の翌日から20日以内に任意継続の手続きを行います。保険料は全額負担ですので従来の保険料の2倍程度となりますが、保険料に上限があるため、収入が高くても保険料を抑えることができます。
ただし、利用期間は2年間ですので、注意してください。
(4)配偶者の扶養に加入する
配偶者が健康保険に加入し、年収が130万円未満である場合、その扶養に入るという選択肢もあります。配偶者の勤務先で必要書類を提出することで、扶養手続きが進められます。
確定申告の手続き
確定申告の手続きは、大きく分けると、退職した年に転職した場合と、退職した年に転職しなかった場合とで異なります。
(1)転職した年に退職した場合
年内に転職した場合、転職先での年末調整により所得税が清算されます。必要な手続きは、前職の源泉徴収票を転職先に提出することです。
ただし、12月頃に転職した場合、年末調整の手続きが間に合わない可能性もありますので、事前に転職先に確認しておきましょう。
(2)退職した年に転職しなかった場合
退職した年に転職しなかった場合には、原則として確定申告をする必要があります。
確定申告する場合、どれくらいの所得があったかということと、どれくらいの額の所得税が源泉徴収されたかを申告する必要があるので、源泉徴収票が必要となってきます。
確定申告を適切に行うことで、払い過ぎた税金の還付を受けることができます。
給料未払いの有無の確認
退職後に忘れてはいけないのが、給料未払いの有無の確認です。
実は、適切に払われていると思っていた給料が払われていないというケースが少なくありません。未払い給料請求の時効は支払期日から3年間です。早めに請求がおすすめです。
- 給与明細の確認: 給与や残業代が正しく支払われているかを確認します。
- 退職金の確認: 会社の就業規則に基づき、退職金が正確に計算されているかを確認します。
- 解雇予告手当の確認: 解雇予告手当とは会社から30日前に解雇を予告されていない場合に請求できるものです。この場合に解雇予告手当を受け取っていない場合には請求しましょう。
【まとめ】退職後にやるべきことは6つ!期限には注意!
退職後に必要な手続きは、退職後の生活を支える重要なステップです。住民税や健康保険、年金の手続き、失業手当の申請、確定申告、そして給料未払いの確認を確実に行うことで、将来の不安を解消し、新しい生活の一歩を踏み出せます。
これらを適切に進めることで、安心して新たなキャリアに集中できる環境を整えましょう。
給料の未払いがあれば、アディーレ法律事務所にご相談ください。弁護士にご依頼いただければ、会社とのやり取りは弁護士に任せることができます。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません(※以上につき、2024年12月時点)。
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。