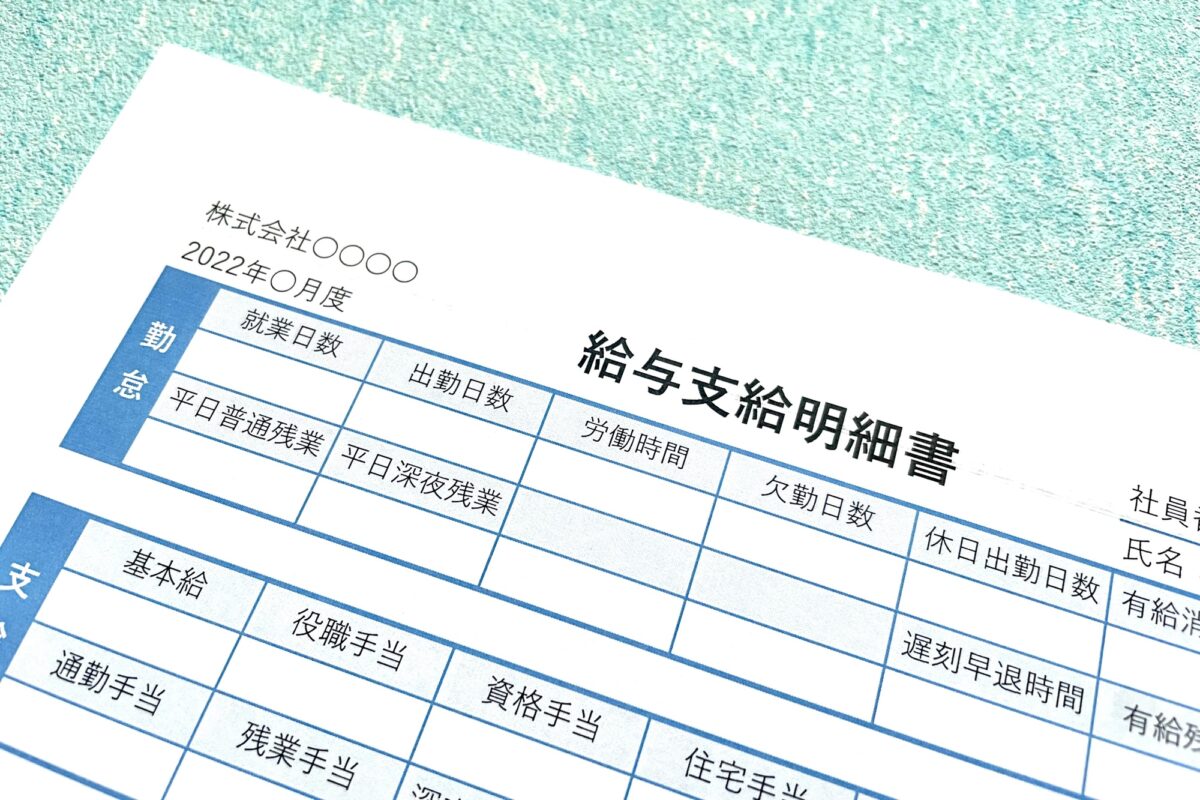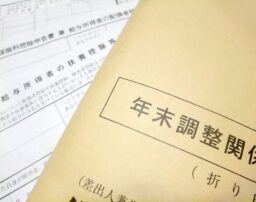働く人々にとって、労働条件の透明性は非常に重要です。
しかし、「月平均所定労働日数」という言葉に馴染みがない方も多いでしょう。
このコラムでは、その基礎からくわしく解説し、残業代の算定にどのように用いられるのか明らかにします。
具体的な計算方法や法律上のポイントを理解することで、ご自身の残業代がどのくらいになるのか把握することができるようになります。
この記事を読んでわかること
- 月平均所定労働日数とは(実労働日数、所定労働時間との違い)
- 月平均所定労働日数の計算方法
- 月平均所定労働日数が必要な理由(残業代を確認する)
- 月平均労働日数の確認方法・上限
ここを押さえればOK!
月平均所定労働日数は、主に残業代の計算に利用されます。
残業代計算では、法定時間外や深夜、休日労働に対する割増賃金が発生し、月平均所定労働日数をもとに1時間あたりの基礎賃金を算出します。これにより、適切な賃金計算が可能になります。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
月平均所定労働日数とは?
月平均所定労働日数は、給与計算や労働条件を決定する際に重要な基準となります。
ここでは、月平均所定労働日数について簡単に説明します。
(1)所定労働日数とは
所定労働日数とは、企業が就業規則や労働契約で定めた労働日数を指します。
通常は、週や月、年単位で設定されます。
そして、月平均所定労働日数とは、年間の所定労働日数を12か月で割って算出した、1か月あたりの平均の所定労働日数のことをいいます。
(2)実労働日数との違いとは
実労働日数とは、実際に労働した日数を指します。
例えば、有給休暇や特別休暇を取得した場合、所定労働日数には含まれますが、実労働日数には含まれません。つまり、所定労働日数より実労働日数が少なくなる場合があります。
一方で、所定休日や法定休日などに働いた場合は、実労働日数が所定労働日数より多くなることもあります。
(3)所定労働時間との違いは
所定労働時間は、1日または1週間の会社が自由に設定できる労働時間を指します。
労働基準法に基づき1日8時間、週40時間を超えないよう設定されます。
例えば、所定労働日数が20日で、所定労働時間が8時間の場合、月間所定労働時間は160時間となります。
月平均所定労働日数の計算方法とは
次に、月平均所定労働日数の計算方法について説明します。
- 年間所定労働日数を計算する
1年間の暦日数から年間休日(法定休日+法定外休日)を引くことで計算できます。
年間所定労働日数=365日-年間休日 - 年間所定労働日数を12で割る
年間所定労働日数を12ヶ月で割り、月平均を計算します。
有給休暇やリフレッシュ休暇などの「休暇」は所定労働日数に含まれますので、1年間の暦日数からは引きません。
所定労働日数を利用して有給休暇の付与条件を確認する
上記のとおり、月平均所定労働日数を計算するには、所定労働日数を正確に把握する必要がありますが、所定労働日数は、有給休暇の付与条件や付与日数を確認する場合に利用されます。
そもそも会社は、次の2つの要件を満たす場合、原則として10日の有給休暇を与えなければなりません。
- 労働者が雇い入れの日から6か月継続して雇われていること
- 労働者が6か月間の全労働日(すなわち所定労働日数)の8割以上出勤していること
このルールは、フルタイムで働く従業員に限らず、パート従業員やアルバイト従業員であっても同様に適用されます。もっとも、パート従業員やアルバイト従業員など労働日が少ない労働者については、適用条件などが変わってきます。
【フルタイム従業員】
| 雇入日からの勤続日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
| 付与される年次有給休暇日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
【パート・アルバイト従業員】
| 週の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数(※) | 雇入日からの勤続日数に応じた年次有給休暇日数 | ||||||
| 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 | ||
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
特にパート・アルバイト従業員の場合、所定労働日数によって付与される有給休暇日数が変わってきます。
月平均所定労働日数を利用して残業代(割増賃金)の計算する
次のケースの場合、割増賃金が発生します。割増賃金の計算に当たっては、月平均労働日数が必要となります。
【割増賃金が発生する場合】
- 法定労働時間を超える残業(時間外労働):基礎賃金の1.25倍以上(※)
- 法定休日での残業(休日労働):基礎賃金の1.35倍以上
- 深夜労働(22時~5時):基礎賃金の1.25倍以上
※ 時間外労働が月60時間を超えた場合には、基礎賃金の1.5倍以上となります。
【残業代の基本的な計算式】
残業代=1時間あたりの基礎賃金×残業時間×割増率
このうち、1時間あたりの基礎賃金を計算するときに月平均所定労働時間が必要になります。月平均所定労働時間は、月平均所定労働日数に1日の所定労働時間を乗じて算定されます。具体的には以下のとおりとなります。
【1時間あたりの基礎賃金】
1ヶ月の平均所定労働時間=月平均所定労働日数×1日の所定労働時間
1時間当たりの基礎賃金=月給の基礎賃金÷月平均所定労働時間
このように月給制の場合には、月平均所定労働日数をもとに、法定時間外、深夜及び休日労働の残業代などを計算することになります。
【まとめ】月平均所定労働日数から残業代がどのくらいになるのか把握できる!
「月平均所定労働日数」は、残業代を正確に計算するためには重要なものです。
ご自身の残業代がどのくらいになるのか把握することで、会社から残業時間に応じた残業代が支払われているのか知ることができます。
また、「月平均所定労働日数」を計算する過程で、所定労働日数を把握することが必要とされますが、所定労働日数を把握することで、有給休暇が付与されているのか、付与されているとして、どのくらいの日数の有給休暇が付与されているのか知ることもできます。
月平均所定労働日数からで残業代を計算して、未払いがあった方はアディーレ法律事務所への相談がおすすめです。
アディーレ法律事務所は、未払いの残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。(※以上につき、2025年1月時点)
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。