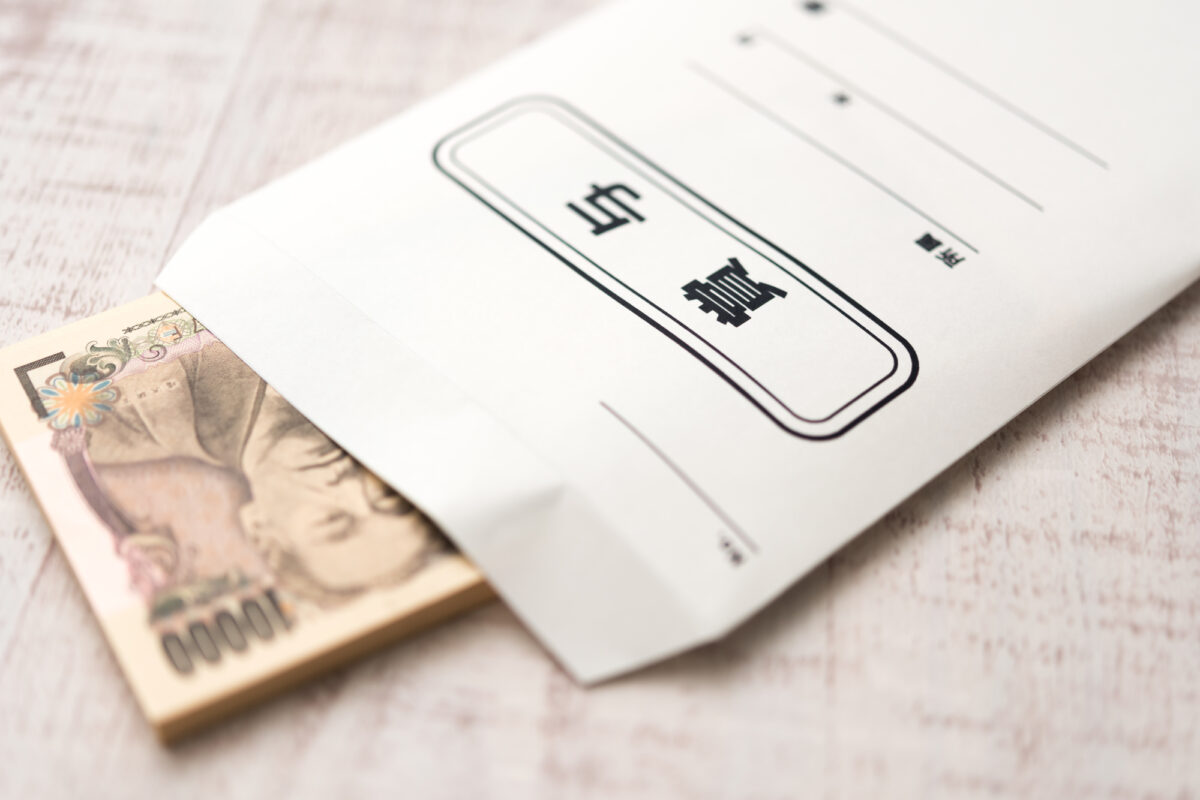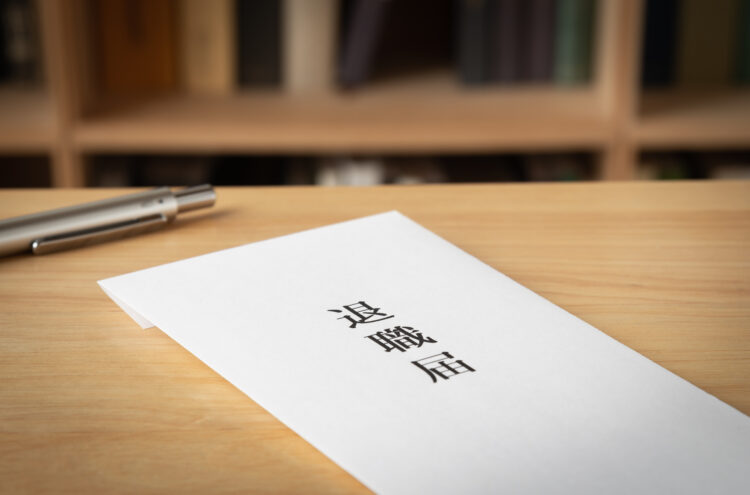退職を考える際に、ボーナスのタイミングも考慮することは、非常に重要です。
ボーマスが支給される時期に退職を考えている方は、退職日をいつにするかは事前にしっかり検討しましょう。
ボーナスを受け取らずにボーナス前に退職してしまうと、多くの人が「もらって辞めればよかったのに、もったいない」と感じるでしょう。
ボーナスを確実に受け取り、損をせずに円満に退職するためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
本記事では、ボーナス前に退職すると損する理由、ボーナスをもらってから退職するための具体的な方法について解説します。さらに、ボーナスを気にせず退職を検討すべき場合や、退職時のボーナスに関するよくある質問にもお答えします。
この記事が、退職に関する不安を解消し、次のステップに進むための準備に繋がれば幸いです。
この記事を読んでわかること
- ボーナス前の退職がもったいない理由
- ボーナスをもらって損せずに円満退職する方法
- ボーナスを考慮せず退職を検討した方がいいケース
- ボーナスと退職でよくある質問
ここを押さえればOK!
ボーナス支給日に在籍していることが支給条件となっている企業が多く、支給日前に退職するとボーナスを受け取れないことがあるためです。
また、退職予定者に対してボーナスを減額する規定がある企業もあります。
ボーナスを確実に受け取り、損をせずに退職するためには、就業規則や給与規程を確認し、ボーナス支給後に退職の意思を伝えることが重要です。
しかし、勤務が精神的に困難な場合やボーナスが少額である場合など、ボーナスを気にせず退職を検討すべき場合もあります。
退職を考える際には、自分の状況を見極め、ボーナスをもらい損ねることがないように最適なタイミングで行動することが大切です。
「自分では退職を伝えにくい」という方は、弁護士が行う退職代行サービスの利用を検討しましょう。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
ボーナス前の退職がもったいない理由
退職を考えるとき、ボーナスの支給時期についても考慮した方が良いです。
なぜなら、ボーナス前に退職すると、ボーナス支給時期に勤めていればもらえていたボーナスが全額もらえなかったり、減額されたりするケースがあるためです。
ボーナスは、大きな金額となりうるため、これを失うことで退職後の生活資金が不十分となってしまうリスクがあります。
(1)ボーナスが支給されないケースがある
多くの企業では、ボーナス=賞与の支給日に在籍していることがボーナス支給の条件となっています。
これを「支給日在籍要件」と言ったりします。
したがって、支給日在籍要件がある場合、ボーナス支給日前に退職してしまうと、ボーナスを受け取ることができなくなってしまうのです。
厚生労働省の調査による、調査産業全体の令和5年年末の平均ボーナス額は、39万5647円でした。
業種や企業によりボーナス額に差はありますが、退職日に気を付ければもらえたはずのボーナスを、もらえなかったという事態に陥るのは避けなければなりません。
そこで、退職を考える際には、まず自分の会社のボーナス支給条件を確認することが重要です。
ボーナスの制度がある場合、企業は要件を就業規則に記載する必要がありますので(労働基準法89条2号)、事前に就業規則(賃金規程の場合もある)を確認するようにしましょう。
参考:毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果速報等|厚生労働省
(2)ボーナスが減額されるケースがある
企業によっては、退職予定者に対してボーナスを減額する規定が設けられている場合があります。
このような会社では、ボーナスを決定する要素として将来の活躍への期待を考慮していることがあり、近く退職する者はこの期待が小さくなることから、結果としてボーナス額が低額になってしまうのです。
事前に、就業規則や給与規程を確認し、ボーナスに関する規定をしっかり把握することが大切です。
ボーナスをもらって損せずに円満退職する方法
ボーナスをもらってから退職するためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。順に説明します。
(1)就業規則や給与規程でボーナスに関する記載を確認
まず、最初に行うべきことは、就業規則や給与規程を確認することです。
これにより、ボーナスの支給条件や支給日を正確に把握することができます。
多くの企業では、ボーナス支給日に在籍していることが支給の条件となっているため、この情報を正確に把握することは、非常に重要です。
企業は、就業規則は、従業員が自由にみられるような状態にしておかなければなりません(労働基準法106条1項)。デジタルデータとして、パソコンで見られるケースが多いですが、紙媒体のモノを閲覧するケースもあります。
就業規則や給与規程がどこで確認できるかわからない場合には、人事部に問い合わせましょう。確認したい理由まで伝える必要はありません。
(2)実際にボーナスが支給された後に退職の意思を伝える
ボーナス支給日を把握したら、ボーナスを確実に受け取るためには、ボーナス支給後に退職の意思を伝えましょう。
「ボーナス支給日に在籍していれば、ボーナス支給日前に退職の意思を伝えてもよいのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、退職予定者として、ボーナスの金額が減額されてしまうかもしれません。
また、多くの会社では、ボーナス支給日が延期できる旨のルールが定められていることにも注意が必要です。
事情があってボーナス支給日が延期され、結果として支給日にすでに退職してしまっていた場合には、ボーナスを受け取ることができない可能性があります。
したがって、ボーナスをもらえないリスクを下げるためには、ボーナスを支給されてから、退職の意思を伝えた方がよいでしょう。
(3)退職日を決める
正社員であれば、通常、期間の定めのない労働契約を締結しています。
その場合、原則として2週間前に退職の申し出をすれば、2週間後に退職することができます。
法律上は、書面は要求されていないので、口頭での退職申し出でも有効です。
ただし、就業規則などで「1ケ月」という予告期間が必要と定められていたり、退職届の提出が必要とされていたりする場合もあります。
厚生労働省は、基本的な方向性として、2週間を超える解約予告期間を設定した場合は無効と解するとしています。
参考:7-1 「辞職」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性│厚生労働省
ただし、解雇予告期間の有効性を会社と争うと円満退職は難しくなりますし、もはや退職する会社と労力をかけて争うメリットがあるのかどうかは、慎重に考える必要があります。
「1ケ月程度の予告なら勤務もできるし、転職にも影響しない」というのであれば、就業規則に従った方が円満退職はしやすくなります。
就業規則で退職届の出し方や予告期間についても、事前に確認しておくようにしましょう。
(4)業務の引継ぎを行う
円満退職のためには、業務の引継ぎをしっかり行うことが重要です。
引継ぎを怠ると、上司や同僚に迷惑をかけることになります。引継ぎの計画を立て、必要な情報や資料を整理し、後任者にスムーズに業務を引き継ぐことが大切です。
(5)計画的に有給を取得する
有給が残っている場合、退職日までに取得しないと消滅してしまいます。
せっかく取得できる権利がありますので、退職までに取得したいところです。
業務の引継ぎを考慮して、計画的に有給を取得するようにします。
ボーナスを気にせず退職を検討した方がいい場合
一般的に、貰えるボーナスは貰ってから辞めた方がよいですが、ボーナスを気にせず退職を検討すべき場合もあります。
(1)勤務が精神的に限界である場合
精神的なストレスにより、精神的な健康を害することがあります。
もし、長時間労働、パワハラなどが理由で、勤務の継続が精神的にも困難だと感じる場合、無理をして働き続けることは避けるべきでしょう。
一度、うつ病などの精神的な病を発症してしまうと、回復に時間がかかってしまうことがあります。
このような場合、ボーナスを気にせず、早めに退職を検討することが賢明です。
(2)ボーナスが少額である場合
業種によっては、ボーナスがなかったり、ボーナスが出ても少額である場合もあります。
例えば、厚労省の調査によれば、飲食サービス業等の令和5年度年末のボーナス平均額は、6万9234円と、他業種に比べて少なくなっています。
もし、転職活動が成功して希望の仕事に就くことができ、なるべく早く新しい環境で勤務開始したいときは、一定額のボーナスが受け取れなくても、新しい環境で勤務を開始した方が、将来的なキャリア形成につながる可能性があります。
参考:毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果速報等|厚生労働省
退職時のボーナスについてよくある質問
退職時のボーナスに関して、よくある質問にお答えします。
(1)退職するなら支給したボーナスを返せと言われたら、返す必要がありますか
法律上、従業員が退職するからといって、支給されたボーナスを会社に返す義務はありません。
また、会社が従業員に対してそのようなルールを課すことは、労働基準法・民法違反と考えられ、無効と解されます。
従業員と会社との合意で、従業員が任意にボーナスを返還することまでは、法律で禁止されていません。
しかし、従業員にボーナスを返還する義務はありませんので、「返還しろ」という要求は、毅然と断った方がよいでしょう。
例外的に、就業規則などでボーナスの計算方法として「将来の活躍に対する期待を加味」することを明確にしている場合、退職予定者への支払いすぎたボーナスについて返還が認められることがあります。ただボーナスには労働の対価としての性質もありますので、全額の返金が認められる可能性は低いでしょう。
(2)ボーナスが振り込まれなかったらどうすればいいですか?
まだ在籍していれば、会社に確認しましょう。ボーナス支給日に何らかの問題が発生したかもしれません。
「有給消化中にボーナス支給日になり、そのまま退職となったが、ボーナスが振り込まれていない」というケースもあるかもしれません。
退職後であっても、退職前の会社の窓口に問い合わせることは可能です。窓口に問い合わせたうえで、状況を確認しましょう。
【まとめ】ボーナス前の退職はもったいない!事前に就業規則などでもらえる条件の確認を
ボーナス前に退職することは、ボーナスが支給されない、減額されるというデメリットがあるケースがあります。
これを避けるためには、就業規則や給与規程のボーナス支給に関する記載を確認したうえで、ボーナス支給後に退職の意思を伝えることが重要です。
もし、勤務継続が精神的肉体的に困難だったり、新しい職場でのキャリアアップが見込める場合は、ボーナスを気にせず退職を検討することも賢明です。
退職を考える際には、まず自分の状況をしっかりと見極め、最適なタイミングで行動することが大切です。
「退職を伝えにくい」という方は、退職代行サービスを利用して退職する方法もあります。
弁護士であれば、有給取得や未払い給与などの交渉も可能ですし、もし不当な要求があっても毅然と対処してくれるでしょう。
アディーレ法律事務所では退職代行に関する相談料は何度でも無料ですので(2025年2月時点)、一度ご相談ください