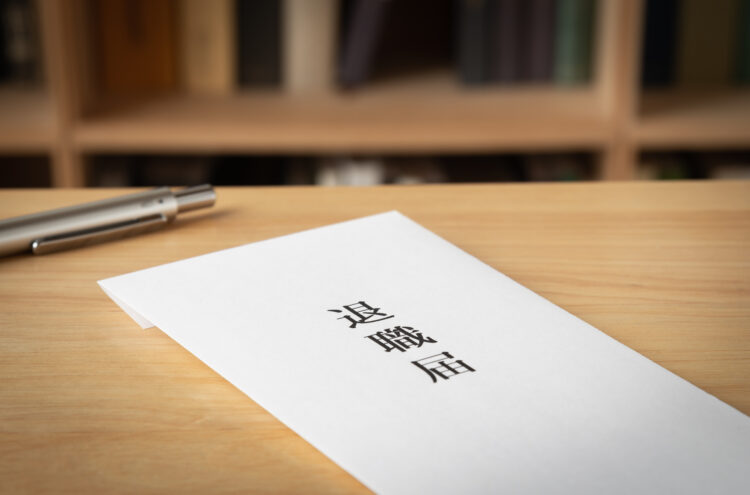職場環境のギャップやパワハラなど、様々な理由で退職を考える新卒者がいます。
新卒で入った会社をすぐ退職することは、人生の大きな決断かもしれません。
そんなとき、退職代行は、円滑かつストレスを軽減した退職をサポートしてくれる有効なツールです。
利用するかどうか、利用するとしてどの退職代行を利用するかは、慎重に検討しましょう。
退職を考えている新卒の方は、この記事の内容を是非参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 新卒でも退職代行の利用をお勧めするケース
- 新卒が退職代行を利用するメリット・デメリット
- 新卒が退職代行を利用する際の注意点
- 退職代行の流れ
ここを押さえればOK!
退職代行のメリットとしては、心理的負担の軽減、迅速な退職手続き、法的リスクの回避がありますが、費用がかかることや将来の転職活動に影響する可能性もあります。信頼できるサービスを選び、サービス内容と料金を事前に確認することが重要です。
新卒者が退職代行を利用する際の流れとしては、まず相談し、契約・依頼費用の支払い、会社への連絡、退職日を迎える、といった手順となります。 退職代行は、適切に利用すれば、本人が受けるストレスを軽減し、円滑な退職を可能にする有効なツールです。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
新卒の退職代行とは?利用が増加する背景
近年、新卒が退職代行を利用して退職するケースを紹介するニュースやSNSの投稿を見かけます。
新卒が退職代行を利用する背景について、説明します。
(1)新卒も1年で10人に1人が退職する
厚生労働省の調査によれば、令和3年3月に大学を卒業した新卒者で就職した方(大卒)の3年以内の離職率は、次のようになっています。
- 1年目 12.3%
- 2年目 12.3%
- 3年目 10.3%
1年目でも、およそ10人に1人が退職しています。3年で考えると、34.9%もの人が退職しています。
この離職率は事業所の規模や産業によって異なります。例えば、事業所規模が小さいほど離職率が高くなる傾向にあります。具体的にいうと、大卒の新卒者の3年以内の離職率は、5人未満の事業所規模だと59.1%、1000人以上の事業所規模だと28.2%です。
また、離職率の一番高い産業(大卒)は、宿泊業・飲食サービス業の56.6%です。この産業では、3年で半数以上の人が退職していることになります。
新卒の退職も、珍しくないことが分かりますね。
「初めての会社だしもう少し頑張ってみよう」と考えるのは正しいかもしれません。
しかし、合わない仕事や会社に何年も我慢するより、転職活動をして、第二新卒という立場でより良い職場を見つけた方が良いと思いませんか。
参考:新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
(2)様々な退職代行の存在
労働期間について期限の定めのない雇用契約を結んでいる従業員、つまり一般的な正社員の場合、基本的に、2週間前に退職の意思を伝えれば退職できます。
このように、労働者には、退職の自由が保障されています(民法627条)。
しかし、実際の退職プロセスでは様々な困難に直面することがあります。
特に新卒だと、次のような理由から、自分から退職の意思を伝えることが難しいと感じる方もいるようです。
- 十分に上司とのコミュニケーションがとれていない
- 自分の主張をはっきりと伝えられない
- 社会的な経験が少なく上司に言いくるめられてしまう
退職代行サービスは複数存在し、その運営主体も、弁護士、労働組合、民間企業など様々です。退職代行は、労働者の退職にかかる手間や労力を省くことができる手段として、新卒の方も利用しています。
新卒こそ退職代行を利用すべき!?退職代行の利用をお勧めする3つのケース
自分で「退職します」と伝えることができれば、他人に依頼する必要もないですし、費用もかかりません。
費用をかけてまで、退職代行の利用を検討する理由は人によって様々です。
次のような職場だと、悩みながら働き続けるよりも、退職代行を利用して離れた方が、長期的なキャリア形成の観点からもプラスに働くかもしれません。
(1)労働条件や業務が入社前の説明と異なる場合
入社後、実際の労働条件や業務が採用の際の説明と異なる場合、労働基準法違反となります。
労働基準法15条には次のような定めがあり、違反した場合30万円以下の罰金に処されることがあります(労働基準法120条1号)。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
具体的には、使用者は、主に次の労働条件について書面や電子メール等で明示する義務があります(労働基準法施行規則5条1項、3項)。
- 労働契約の期間に関する事項
- 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所、従事すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日など
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期
- 退職に関する事項
(※明示すべき事項は、締結する労働契約の内容によって異なります)
このように、採用の際に示された上記等に関する労働条件と、実際の労働条件が異なる場合には、2週間の退職予告期間は不要で、即座に退職することができます。
ただし、採用時に知らされた労働条件と異なる条件で働かせるような会社だと、退職の意思を伝えても応じなかったり、引き止めにあったり、働く環境が悪化したりするおそれもあります。
このようなリスクを回避するためにも、退職代行サービスを利用して、上司や会社と直接話すことなく退職することを検討してもいいかもしれません。
(2)パワハラやいじめなど職場環境に問題がある場合
全ての事業主は、法律上、パワーハラスメントの防止措置を取る義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。
しかし、令和5年度の厚生労働省の調査によれば、過去3年間にパワハラの相談があった企業は64.2%に上っています。また、労働者の約5人に1人が「過去3年間にパワハラを受けたことがある」と答え、またその約半数で勤務先は「何も対応しなかった」と答えています。
つまり、法律でパワハラが規制され、企業に防止措置を取る義務があっても、実際はパワハラが相当数存在し、企業が把握しても効果的な対策が取られるとは限らないことがわかります。
深刻なパワハラやいじめで労働環境が悪化し、対応部署に連絡しても改善しないような場合には、自分の心身の健康を守るためにも、退職代行を利用して速やかに職場から離れることが有効な選択肢となります。
参考:職場のハラスメントに関する実態調査について|厚生労働省
参考:NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント | 政府広報オンライン
(3)会社が引き留めて退職を認めない場合
労働者には退職の自由がありますが、会社が引き留めたり、退職を認めないケースもあります。
このような場合、退職代行を利用して、弁護士が毅然と「退職します」と伝え、必要な法的説明を行えば、退職手続きに応じる会社も多くあります。
また、弁護士に依頼した場合、会社が退職手続きに応じなかった場合の対応について、アドバイスやサポートを受けられます。
新卒が退職代行を利用するメリット
退職代行サービスの運営主体は、主に民間企業、労働組合、弁護士の3つがありますが、ここでは、弁護士の退職代行の利用をお勧めします。
新卒が、弁護士の退職代行を利用する主なメリットは以下の3点です。
(1)心理的負担を軽減
まだ社会経験の少ない新卒が、上司や会社と対等に話し合うのは難しく、緊張してストレスを感じるのは当然です。
退職代行を利用すれば、上司や人事と対面・直接に退職の意思を告げることを避けられるため、退職に伴う精神的ストレスを大幅に軽減できる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、未払いの残業代や、有給消化の交渉なども本人の代わりにやってもらえます(※)。特に新卒者にとっては、この心理的サポートが大きな意味を持つでしょう。
※弁護士でない民間企業が運営する退職代行は、本人の代わりに法律問題について会社と交渉することはできません。非弁行為として弁護士法違反となるためです。
参考:退職代行サービスと弁護士法違反 – 東京弁護士会 (https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/fyi/column/post_3.html)
(2)迅速な退職手続きが可能
特に弁護士が行う退職代行は、法律の知識、経験や実務に基づいており、効率的に退職手続きを進めることができるでしょう。
弁護士は本人の代理人として交渉することができますので、会社側も、「この退職代行業者は違法ではないか」といいう疑問や不安を持たず、退職手続きに応じてくれることがほとんどです。
弁護士との契約内容にもよりますが、退職の意思を伝えるだけでなく、有給消化や未払い残業代の交渉、会社が損害賠償請求すると言っている場合の対応なども依頼することができます。
これにより、新卒者は次のキャリアステップに早く移行できるでしょう。
(3)法的リスクを回避できる
民間企業が行う退職代行業者は、法的な問題について、本人の代わりに会社と交渉することはできません。非弁行為として、弁護士法違反となるためです。
また、労働組合は団体交渉として組合員について交渉できますが、内容が複雑化したり、争点が法律の専門的な内容に及んだりした場合に、それ以上の対応ができないというケースもあります。
民間企業に退職代行を依頼したところ、法的な問題の交渉が発生したので民間企業が退職代行の手続きから撤退したという事例もあります(東京地方裁判所判決令和2年2月3日)。依頼した方からみれば、最後まで手続きをしてくれると思って依頼したのに、途中で「もうできません」といわれるのは、さらなるストレス・心労を抱えることになってしまいます。
途中で法的な問題が生じたとしても、最後までしっかりと対応可能な弁護士の退職代行を選ぶことをお勧めします。
参考:退職代行サービスと弁護士法違反 – 東京弁護士会 (https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/fyi/column/post_3.html)
新卒が退職代行を利用する際のデメリット
退職代行サービスの利用には、以下の2つのデメリットがあります。
(1)費用がかかる
退職代行サービスには、一定の費用がかかります。運営元やサービスの内容によって費用は異なりますので、事前にサイトの費用体系を確認する、電話で問い合わせるなどして確認しましょう。
相談は無料とするところも多いので、一度相談だけでもしてみるといいかもしれません。
(2)将来の転職活動に影響する可能性
弁護士に退職代行を依頼した場合、弁護士は法律上守秘義務を負っていますので、弁護士から他の企業等に退職代行を利用したという情報が洩れることはありません。
しかし、転職先の企業によっては、本人の同意を得たうえで、前に所属していた企業に対して、本人の評判や業務態度を確認するために連絡をすることがあります。その際に、退職代行を利用したことが共有されると、転職先の企業がそれをマイナスに評価するリスクがあります。
その際には、退職代行の利用を選んだ理由について、自分なりにまとめて説明できるとよいでしょう。
(3)利用するサービスによっては本人や親族に連絡がくることも
民間企業や労働組合が運営する退職代行を利用すると、企業側が「本人ではないが話し合いができるのか、違法なのではないか」と疑問に思うことがあります。
民間企業や労働組合が行う退職代行は、本人の代理人ではないので、企業は本人や身元保証人である親族に連絡が必要だと考えれば、本人や親族に連絡することがあります。
弁護士が行う退職代行であれば、本人の代理人として会社と話し合うことができます。弁護士が会社に連絡する際には、弁護士が代理するので本人には連絡しないよう伝えます。
新卒が退職代行を利用する際の注意点
新卒が退職代行サービスを利用する際は、以下の点に注意が必要です。
(1)信頼できるサービスを選ぶ
退職代行サービスは、民間企業、労働組合、弁護士など様々な運営母体があります。
民間企業の中には、非弁行為となるような交渉を行うところもあるようですので、サービス内容にはよく注意しましょう。
また、一般的かつ良心的な民間企業の退職代行は、法的問題の交渉が必要となったら、非弁行為を避けるために、撤退します。
最近は、不当解雇など会社とのトラブルがあった後に、企業に関わらず一人でも加入できる労働組合(このような労働組合を一般労働組合とか、合同労働組合と言います)に加入して、トラブルの解決を目指すこともあります。
退職代行を依頼するだけのために、労働組合に加入して組合費用を支払い、終了したら労働組合を退会するというのは、面倒だと考える方もいるでしょう。
弁護士は、契約内容にもよりますが、退職代行だけでなく有給取得や残業代請求など交渉が必要な法的な問題についても、本人の代理人として会社と交渉することができます。依頼者は労働組合に別途加入する必要はありません。弁護士は本人の利益のために尽力します。
退職代行サービスの運営者の違いに注意して、信頼できるところを選ぶようにしましょう。
(2)サービス内容と料金を確認する
退職代行のサービス内容と料金について、事前にしっかりと確認しましょう。
かかる費用が合計でいくらなのか、契約したら行ってもらえるサービス内容の範囲はどこまでなのか、不明点があれば事前に質問するようにしましょう。
また、退職できなかった場合に支払った費用が返金される返金制度があるところだと、安心です。
新卒が退職代行で退職するまでの流れ
弁護士が行う退職代行サービスを利用して、実際に退職するまでに流れを説明します。
(1)相談する
対面や電話、WEB、LINEなど、法律事務所によって相談できる媒体は異なります。
電話などで相談・依頼から退職まで対応可能な法律事務所もありますので、ご自身が利用しやすいサービスを提供している法律事務所を選びます。
話したいことや聞きたいことを事前にメモしたうえで、相談に臨みましょう。
初回相談では、依頼者の次のような状況を詳しく把握し、今後の方針を決定します。
- 退職意思の確認
- 希望する退職日の確認
- 雇用契約や就業規則の確認
- 未払い賃金や退職金の有無の確認
- 有給取得の交渉など退職意思を告げるほかに希望があるかを確認
初回相談で、通常、期間の定めのない雇用契約であれば2週間の予告で退職できることなどの説明を受けることができるでしょう。
(2)契約し、依頼費用を支払う
初回相談の後、退職代行を依頼する場合は契約を締結し、必要書類を提出します。
その際に、依頼内容(例えば退職の意思を伝えるだけなのか、有給消化などの交渉も依頼するのかなど)をしっかりと確認しましょう。
依頼したくなければ、もちろん契約する必要はありません。
契約内容や弁護士費用などの説明を受け、書面や電子手続きで契約を締結します。その後、弁護士費用を支払います。分割の支払いが可能な法律事務所もありますので、分割希望の方は聞いてみるとよいでしょう。
(3)弁護士から会社へ連絡する
その後、弁護士から会社へ退職の意思を通知します。
主な内容は以下の通りです。
- 退職の意思表示
- 希望退職日の通知
- 今後の連絡は弁護士を通じて行う旨の伝達
この通知は、電話やFAXなどで行われます。
依頼者は会社との直接のやり取りを避けることができ、「退職したいけど伝えにくい」という心理的負担が大幅に軽減されるでしょう。
万が一会社から連絡があっても、「弁護士に一任しています」と答えるだけで十分です。
弁護士との契約の範囲内のことであれば、会社からの連絡は全て弁護士が対応します。
必要に応じて、弁護士は退職金の確認や、未払い賃金の請求、私物などの取次などの交渉を行います。
会社との話し合いの内容や、進捗状況はその度に共有されます。
(4)退職日を迎える
退職代行の契約は、一般的に、無事退職できれば終了します。
会社から一切連絡がなくても、期間の定めのない雇用契約の場合には退職通知が届いた2週間後に退職の効果が発生します。
退職に関連して会社に対して伝えてほしいことがあれば、退職日前に弁護士に連絡して、会社に伝えてもらうようにしましょう。
会社に返却すべきものがある場合には、弁護士に確認したうえで、直接会社に送るケースが多いかと思います。
【まとめ】新卒でも退職代行を利用できる!即日退職が可能なケースも
新卒の方であっても、何年も働いた方と同じように、退職代行を利用することができます。
適切に利用すれば、本人が受けるストレスを軽減して円滑な退職を可能にする有効なツールです。
もちろん可能であれば、まずは自力での問題解決を試み、それが困難な場合に退職代行の利用を検討するのが望ましいでしょう。
しかし、「退職代行を利用したい」と考えている方は、すでに自力での対応が不可能なほど精神的に追い詰められていたり、会社への不信感がいっぱいだったりすることが少なくありません。
そのような場合には、退職代行を利用して退職した方が、自分を守るという意味でも、長期的なキャリア形成という意味でも有益でしょう。
本記事の情報を参考に、自身の状況に最適だと思われる退職代行を探し、信頼できるところに依頼していただければと思います。
アディーレ法律事務所では、退職代行に関するご相談は何度でも無料です。
一度、そのお悩みをアディーレにお聞かせいただけませんか。
退職でお悩みの方は、退職代行を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。