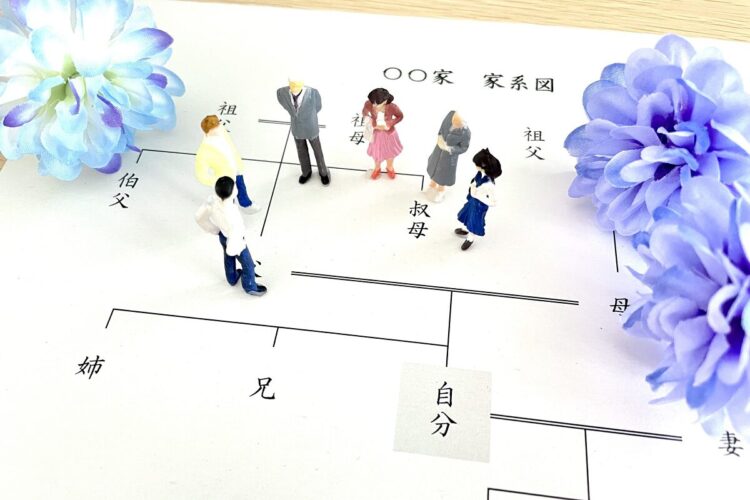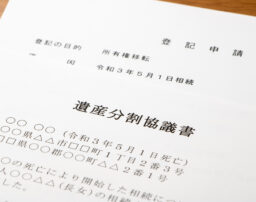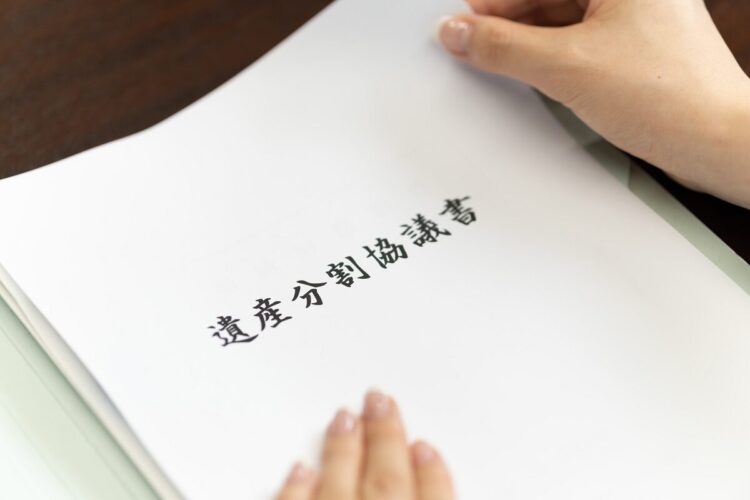「父が亡くなり遺産分割のことも考えなければならなくなったが、詳しい手続きが分からない。遺産分割の基本的な事柄が知りたい」
ご親族が亡くなり大変な中、遺産分割のことも考えなければならないのはなおさら大変ですよね。
遺産分割とは、法律で定められた相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合って決める手続きのことです。
遺産分割の基本的な進め方を把握して、滞りなく遺産を分けられるようにしましょう。
この記事を読んでわかること
- 遺産分割の手続きとは何か
- 遺産分割協議の進め方
- 遺産分割の4つの方法
ここを押さえればOK!
【遺産分割の進め方】
・遺言書の確認: 故人が遺言書を残しているかを確認します。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けますが、相続人全員の同意があれば異なる分割も可能です。遺言書がなければ、相続人全員で話し合って決めます。
・相続人の確定: 故人の戸籍を出生までさかのぼって確認し、誰が相続人かを正確に把握します。相続人全員が参加しないと、遺産分割協議は無効になる可能性があります。
・遺産の調査: 故人のプラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)をすべて洗い出します。
・遺産分割協議: 相続人全員で遺産の分け方について話し合います。話し合いの方法に決まりはなく、電話やオンラインでの話し合いも可能です。相続税の申告期限(死亡から10ヶ月以内)を考慮し、なるべく早く合意を目指しましょう。もし話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることもできます。
・遺産分割協議書の作成: 合意した内容を文書(遺産分割協議書)にし、相続人全員が署名・押印します。これは、後のトラブルを防ぐために非常に重要です。
遺産分割には、主に以下の4つの方法があります。
現物分割: 遺産をそのままの形で分ける方法です(例: 土地は長女、預金は長男)。
代償分割: 特定の相続人が多めに財産を受け取る代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法です。
換価分割: 遺産を売却してお金に換え、そのお金を分ける方法です。
共有分割: 遺産を相続人全員の共有名義にする方法です。
遺産分割は、相続人の関係性や遺産の内容によって複雑になることがあります。もしご不明な点があれば、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
遺産分割の手続きとは
遺産分割とは、法律上の相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合い、どのように分けるのかを決める手続きのことです(民法907条1項)。
この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割は、相続人間の協議で合意が形成できないときなどには、家庭裁判所の手続きで行われることもあります(民法907条2項)。
この家庭裁判所の手続きを「遺産分割調停」と言います。
家庭裁判所で扱われた遺産分割事件の数は、2020年度だけで1万1303件あります(2020年度中に事件が終了したものの総数)。
参考:遺産分割調停 | 裁判所 – Courts in Japan
参考:令和2年度司法統計 遺産分割事件数 終局区分別 家庭裁判所別|裁判所 – Courts in Japan
「故人の遺産分割協議をしたい」という手紙が、親族から突然届きました。故人は名前も知らないくらい遠縁の親戚で、遺産にも興味はありません。私は遺産分割協議に参加しなければならないのでしょうか?
相続人であっても、法律上遺産を相続しないことができます(相続放棄)。相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになるため、遺産を相続することはなく、遺産分割協議に参加する必要もありません。
相続放棄について、詳しくはこちらをご覧ください。
(1)遺言書がある場合|遺言書の内容に従って遺産分割
遺言書がある場合には、基本的には遺言書の内容に従って遺産分割を行います。
遺言の中に漏れている遺産がある場合には、その部分は相続人全員で話し合って遺産分割をします。
遺言書で相続する財産がゼロとされていました。確かに父親とは不仲でしたが、あまりにもひどいと思います。全く相続できないのでしょうか?
一定の相続人には、法律上最低限相続できる財産(遺留分)が保障されているため、全く相続できないとは限りません。遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害する額について請求ができます(遺留分侵害額請求 ※ただし、消滅時効があります)。遺留分の割合は、誰が相続人となっているかによって異なります。
遺留分について、詳しくはこちらをご覧ください。
遺言には必ず従わなければいけないのでしょうか?遺言で私は自宅を相続するように言われましたが、他の兄弟が自宅の相続を希望しており、私も自宅より預金の方がありがたいのですが。
遺言をのこした方が特に遺言と異なる遺産分割を禁じた場合を除いて、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも基本的には許されます。
(2)遺言書がない場合|相続人全員で話し合って遺産分割
遺言書がない場合には、相続人全員で話し合って遺産分割をします(遺産分割協議)。
法律で定められている法定相続分の割合で遺産分割をするのが一般的ですが、法定相続分と異なる遺産分割をすることもできます。
法定相続分と異なる取り分を主張する相続人がいたり、不動産がある場合には「私がほしい」「売却して売却代金を分けるべき」などとそれぞれが主張して方針が定まらず、もめることもあります。
法定相続人の範囲や法定相続分について、詳しくはこちらをご覧ください。
私は亡き母親と同居し、生活費を出すなど面倒をみてきました。何も協力しなかった兄弟と同じ相続分になることはなんだか納得できませんが、なんとかなりませんか?
「寄与分」という、他の相続人よりも多く財産を相続できることを主張できることがありますが、絶対ではありません。寄与分が認められるのは、法律上の扶養義務(民法877条1項)を超えて特に財産上の利益を与えたような「特別の寄与」を行った場合などに限られます。
私の妻は仕事もせずに私の母親を自宅介護してくれていたのですが、私の妻が亡くなった私の母親の遺産をもらうことはできませんか?
あなたの妻はあなたの母親の相続人ではありませんので、遺産を相続することはできません。しかし、「特別寄与者」として、相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できる可能性があります(民法1050条1項)。「特別寄与者」にあたるかどうかは、療養介護期間、要介護認定のレベル、介護の内容、相続人が介護の対価を受け取っていたかなど、さまざまな事情を考慮して判断されますので、「仕事もせずに自宅介護していた」からといってただちに特別寄与者にあたるとは限りません。
生前、父親から多額の援助を受けて家を建てた兄弟がいます。それなのに、父親が亡くなった際の相続分が私と同じとなると、なんだか不平等な感じがします。うまく調整できませんか?
このような特別に利益を受けた相続人がいる場合、相続人間の不公平を是正するために受け継ぐ財産の額を調整する「特別受益」という制度があります(民法903条1項)。被相続人から生前贈与等を受けて特別の利益を受けた場合、「特別受益」となる場合があります。そして、この利益の額は、相続開始の時に実際に残されていた相続財産の額と合算し、一定の計算に従い算出された相続分から、その生前贈与等の価額を除いた残額が、生前贈与等を受けた相続人の相続分となる場合があります。
遺産分割協議の進め方
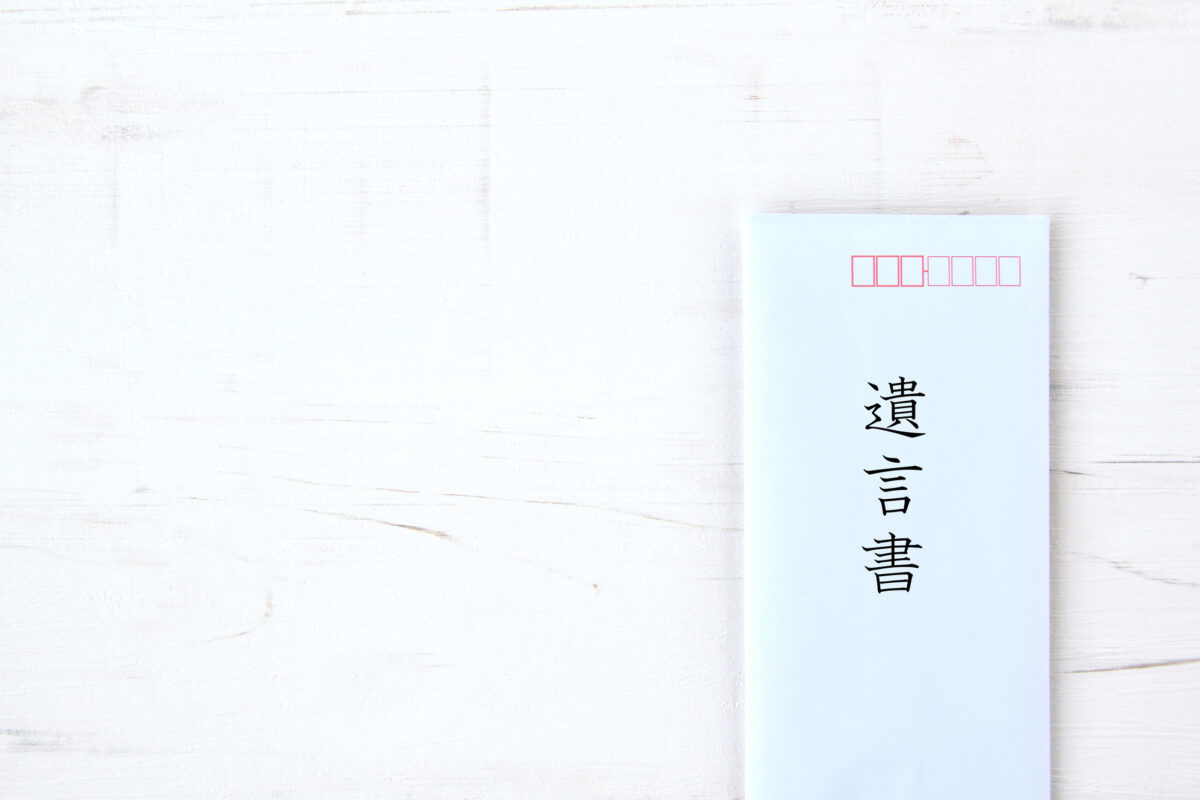
遺産分割協議の進め方には、法律上のルールがあるわけではありません。
もっとも、相続人と遺産が具体的に分からなければ話し合い自体ができないため、先に相続人と遺産を探すのが一般的です。
遺産分割協議は、次の手順で進めます。
遺言書があるかどうかを確認
相続人は誰かを確定
相続する遺産を調査
実際に遺産分割協議を行う
合意した内容で遺産分割協議書を作成する
これらについてご説明します。
(1)手順1|遺言書があるかどうかを確認
先ほどご説明したとおり、遺言書の有無により、そもそも遺産分割協議が必要なのかどうかが異なるため、まずは遺言書があるかどうかを確認します。
遺言が「公正証書遺言」という公証役場が関与してつくられたものである場合には、公証役場の「遺言検索システム」で公正証書遺言があるかどうかを調べることができます(ただし、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言に限られます)。
遺言が「自筆証書遺言」という自分だけで書いたものである場合には、亡くなった方の住まいなどに保管されていないかをしっかりと探す必要があります。
このほか、故人が法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使って法務局に遺言を預けているケースもあるため、遺言書が法務局に預けられていないかを最寄りの法務局に確認することも必要です。
ここからは、遺言書がない場合の一般的な遺産分割協議の進め方をご説明します。
(2)手順2|相続人は誰かを確定
遺産分割協議をするにあたっては、相続人は誰かを確定しなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員で行うものであり、欠けていると有効に行うことができませんし、欠けていた場合には後でトラブルになる可能性もあります。
相続人を調査して、誰が相続人かを確定するのは重要な作業です。
相続人の確定は、基本的には、亡くなった方の戸籍を死亡時から出生時までさかのぼって取得して行います。
亡くなった方の戸籍の取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
(3)手順3|相続する遺産を調査
相続人の確定と同時並行で、相続する遺産を調査していきます。
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(借金等)を全て調査します。
ただし、被相続人だけが受け取れるお金など一身に専属するもの(年金受給権など)は、遺産にはならないので相続しません。
法律上、遺産の全てが遺産分割協議の対象になるわけではありません。
対象になるもの、対象にならないもの、対象にならないが合意によって対象にできるものがあります。
| 対象となるもの | 対象外だが合意により対象にできるもの |
|---|---|
| ・預金債権 ・不動産 ・現金 ・車 ・宝石等の動産 など | ・金銭債権(例:被相続人が誰かにお金を貸しており、返済を求めることができる権利など) ・金銭債務(例:被相続人がお金を借りており、返済する義務など) ・祭具(仏壇・位牌など)、墓などの祭祀財産(民法897条1項) ・香典 など |
(4)手順4|実際に遺産分割協議を行う
相続人を確定し、遺産の調査が完了したら、実際に遺産分割協議を行います。
どの遺産についてどのように分けるのかなどについて、相続人同士で納得できるまで話し合います。
話し合いの方法に決まりはありません。
実際に会って話し合いをするほか、電話や手紙、映像通話などで話し合いを成立させても構いません。
法律上は「いつまでに遺産分割協議を成立させなければならない」という期限はありません。
もっとも、相続税の申告納税期限が死亡から10ヶ月後、不動産の相続登記は3年以内(2024年4月1日からのルール)という期限があるため、できれば亡くなってから10ヶ月以内に遺産分割協議を成立させることができれば、相続税の納税などその他の手続きもスムーズに行えるでしょう。
話し合いは面倒ですし、少し話し合ってみたもののうまくまとまらなそうで、ついつい放置してしまっています。良くないでしょうか?
そのような理由であっても長期間放置するのはトラブルのリスクが高まり、望ましくありません。
例えば、山林を放置すると、管理しないことによる土砂崩れなどにより他人に損害を与えるリスクがあります。
また、家屋を放置すると、漏電による火事や地震・台風による崩壊によって他人に損害を与えるリスクがあります。
さらに、時間が経つことで相続人が亡くなりさらに相続が発生し、相続人がどんどん増えてしまい、後から遺産分割協議をまとめようと思ってももはやまとまらなくなるということもあります。
私としても長期間放置したくはないのですが、うまく話し合いができない場合には、どうすればいいですか?
弁護士に依頼して代わりに話し合ってもらうこともできますので、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、代わりに話し合いをしてくれます。
また、相続人が多すぎて話し合いそのものが難しかったり、複雑にもめてしまって合意できないような場合には、通常は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てて遺産分割の手続きを進めます。
遺産分割でもめてしまったので、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになりました。調停では何をするのでしょうか?
調停でも、話し合いでの合意を目指します。もめていたケースでも、第三者である調停委員の仲介の下、必要な資料が提出されたり冷静になって話し合いができたりして調停で合意が成立するケースも多いです。調停でも意見が対立して合意できなければ、自動的に審判に移行し、裁判所が相続分や分割方法などを決定して遺産分割の審判を行います。
(5)手順5|合意した内容で遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で合意ができたら、合意した内容で遺産分割協議書を作成します。
一般的な遺産分割協議書には、次の事項を記載します。
- 被相続人の氏名、生年月日、死亡日
- 被相続人の最後の本籍地と住所
- 特定した遺産の内容
- 遺産分割についての合意内容
- 相続人全員の氏名(署名)・住所、実印の押印(実印の印鑑証明書の添付)
実際の遺産分割協議書の内容は、遺産の内容や遺産分割の内容によって異なります。
相続人自身が作成し、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書も、それだけで無効になるというルールはありません。
しかし、法律のプロである弁護士に依頼して作成してもらったほうが後々のトラブル(例えば、「遺産分割が無効だ」と言われて預金が下せなかったり不動産登記が出来なかったりするなど)を防げる可能性が高まります。
いったん遺産分割協議は成立したのですが、内容を変更したいということになりました。もう一度遺産分割協議をやり直すことはできますか?
相続人全員で遺産分割協議を合意解除し、再分割することは可能です(最判平成2年9月27日民集44巻6号995頁)。このため、相続人全員の話し合いのうえでやり直すことはできます。
もっとも、税務上、再分割が分割後の贈与であると認定されると贈与税を課されるリスクもあります。
参考:最判平成2年9月27日民集44巻6号995頁|裁判所 – Courts in Japan
遺産分割の4つの方法
最後に、遺産分割協議で実際に遺産を分ける4つの方法をご説明します。
いずれの分け方にするかについては、それぞれメリット・デメリットがあり、個々のケースに応じて最適な分け方が異なります。
このため、最も適した分け方で分けることができるように、遺産相続に詳しい弁護士に相談することもひとつの方法です。
(1)方法1|現物分割
現物分割とは、遺産を現物のまま(お金などに形を変えないで)各相続人に分ける方法です。
例えば、「土地建物は長女(姉)、預金は長男(弟)」という分け方などです。
(2)方法2|代償分割
代償分割とは、相続人の一部に法定相続分を超えた財産を分け与えることとしたうえで、この超えた分についてお金を支払ってもらって清算するという方法です。
例えば、相続人が相続人の子2人(長女と長男)だけ、遺産が1000万円の土地だけである場合に、唯一の遺産である1000万円の土地を長男が受け継ぐ代わりに長男が長女に500万円を支払うという分け方などです。
(3)方法3|換価分割
換価分割とは、遺産を売ってお金に換えたうえで、そのお金を分けるという方法です。
例えば、相続人が相続人の子2人(長女と長男)だけ、遺産が1000万円の土地だけである場合に、唯一の遺産である1000万円の土地を売却してお金に換え、その1000万円のお金を500万円ずつ長女と長男で分けるという分け方などです。
(4)方法4|共有分割
共有分割とは、遺産を法定相続分で共有して遺産分割としてしまうという方法です。
例えば、相続人が相続人の子2人(長女と長男)だけ、遺産が1000万円の土地だけである場合に、土地について持ち分2分の1ずつの共有権を取得することとして分けるという分け方などです。
【まとめ】遺産分割とは法定相続人全員で遺産の分け方を決める手続き
遺産分割は、弁護士に相談・依頼したほうがうまくいくケースも多くあります。
少しでも自分たちだけではうまく遺産分割ができないと感じたら、ためらわずに、遺産相続に詳しい弁護士に相談・依頼するようにしましょう。
アディーレ法律事務所には、相続放棄、相続税、遺言書作成など、複雑な遺産相続の手続をまとめて依頼できます。相続問題でお悩みの方は、早めに、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。