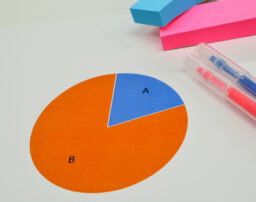横断歩道事故の歩行者と車の過失割合はどのくらいになるのでしょうか?
「過失割合」とは、簡単に言うと、誰がどのくらい事故の責任を負うかということをいいます。例えば、加害者側が60%、被害者側が40%悪い、というような事故もあります。
被害者側も事故の責任がある場合には、被害者が最終的に受け取れる慰謝料が減額されてしまいます(法律の世界では「過失相殺」といいます)。
このように、過失割合がどのくらいになるかは交通事故被害者にとってとても重要な関心事です。
横断歩道では基本的に歩行者が優先されます(車が悪いとされます)。しかし、事故の状況によっては歩行者が悪いとされる場合もあります。
加害者に対して賠償金を請求する前に、横断歩道事故における過失割合について知っておき、賠償金が減額されてしまう可能性があるのかを知っておきましょう。
この記事では、
- 横断歩道上の歩行者と車両の交通事故の過失割合
について弁護士が詳しく解説します。
ここを押さえればOK!
ただし、歩行者にもルール違反があったり、事故発生の具体的状況から修正要素が存在したりすることもある場合には、車両側の過失割合が100になるとは限りません。
また、歩行者が幼児、高齢者の場合、事故の現場が住宅街や夜間である場合には、10~20%程度過失割合が修正される場合があります。
歩行中に交通事故に遭い、治療や保険会社との交渉でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
自宅でらくらく「おうち相談」
「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
横断歩道では歩行者が優先される
横断歩道に歩行者がいる場合には、車両は横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げてはならないとされ、歩行者が優先されます(道路交通法38条1項第2文、以下単に「道交法」といいます)。
このように、横断歩道歩行中の歩行者優先のルールがありますので、横断歩道上の交通事故の過失割合は、原則として車両側がより大きくなります。
横断歩道付近における交通ルール
車両と歩行者それぞれが守らなければならない横断歩道付近における交通ルールがあります。
(1)運転者側の主な交通ルール
- 横断歩道に接近する場合には、横断歩道により前方を横断しようとする歩行者又は自転車がいないことが明らかな場合を除き、その横断歩道の手前で停止できるような速度で進行しなければならない(道交法38条1項第1文)。
- 車両は、横断歩道やその手前で停車している車両がある場合、その側方を通過して前に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない(道交法38条2項)。
- 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、原則として前方の車を追い越したり、追い抜いたりしてはならない(道交法38条3項、30条3号)。
- 車両は、横断歩道上や横断歩道の前後5メートル以内の場所には、法令の規定や危険防止のための一時停止など例外的な場合を除き、停車も駐車もしてはならない(道交法44条1項)。
横断歩行者の通行を妨害することを「歩行者妨害」といいます。歩行者妨害について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(2)歩行者側のおもな交通ルール
- 歩行者は、信号機の表示に従わなければならず(道交法7条)、歩行者用信号機が設置されているときはその表示に従わなければならない(道交法施行令2条1項及び同4項)。
- 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある付近ではその横断歩道によって道路を横断しなければならない(道交法12条1項)。
- 歩行者は、車両等の直前直後で道路を横断してはならない。ただし横断歩道によって道路を横断するときや信号に従って横断するときなどは除く(道交法13条1項)。
【事故のパターン別】信号機が設置されている横断歩道上の事故の過失割合

車両及び歩行者は、双方が信号機の表示に従う義務があります。そのため、信号機の設置される横断歩道では、その信号の表示がどうなっていたかが過失割合の判断には重要となります。
そこで、信号機の設置の有無に分けて、それぞれの過失割合を検討します。
信号機が設置されている横断歩道上の交通事故の基本の過失割合(※)は、次のようになります。
※横断歩道上の事故の過失割合は、安全地帯(横断歩道が長く、途中で歩行者用信号が黄色や赤色に代わってしまったときに、歩行者が安全に待機できる地帯)がある場合とない場合とで分けられて考えられています。ここでは、安全地帯がない場合を前提に説明します。
(1)歩行者が青信号で横断を開始した場合
交差道路の車両が赤信号で進入、直進したことにより事故が発生した場合の過失割合は、直進車に信号無視という重大な過失もあり、車両:100%、歩行者:0%となります。
車両が青信号で進入して、不注意で右左折したことにより、横断歩道上の歩行者に衝突して事故が発生した場合の過失割合は、右左折車が横断歩道上の歩行者優先ルールに反しているという過失がありますので、車両:100%、歩行者:0%となります。
歩行者が青信号で横断を開始したが、黄信号、赤信号でも横断を終わらず横断を続けていた場合はどうでしょうか。
このような場合であっても、基本的に歩行者側に落ち度はないと考えられています。
したがって、このように青信号で横断開始した歩行者側の信号が途中で変わり、交通事故が発生しても、車両側の信号無視に変わりがなければ、横断歩道上の歩行者優先のルールがありますので、基本的に歩行者の過失割合は増えません。
ただし、歩行者側の信号が横断途中で赤信号になった後に、さらに交差道路の信号機が青色信号に変わり、車両が青信号で進入、直進して、交通事故が発生した場合には、車両側の信号無視はなく、歩行者の側も速やかに横断する義務に違反したとして過失割合は修正され、車両:80%、歩行者:20%となります。
歩行者が青信号で横断した場合についてまとめると、次のようになります。
| 歩行者 | 車両 | 過失割合 |
|---|---|---|
| 青信号 | 赤信号 | 車両:100%、歩行者:0% |
| 青信号 | 青信号で進入し、右左折 | 車両:100%、歩行者:0% |
| 青信号→黄信号、赤信号 | 赤信号 | 車両:100%、歩行者:0% |
| 青信号→赤信号 | 青信号(信号無視なし) | 車両:80%、歩行者20% |
(2)歩行者が黄信号で横断を開始した場合
車両が赤信号で進入、直進したことにより交通事故が発生した場合の過失割合は、歩行者にも黄色信号(青点滅信号も同じ)無視という一定の過失がありますので、車両:90%、歩行者:10%となります。
黄色信号(青点滅)の場合、歩行者は横断開始してはならないというルールがあり(道交法施行令2条1項及び同4項)、青信号で横断開始した場合と差をつける交通政策上の必要もありますので、10%の過失ありとされています。
一方、車両が青信号で進入、右左折したことにより交通事故が発生した場合の過失割合は、車両が信号を守っている一方で歩行者には黄色信号無視という一定の過失がありますので、車両:70%、歩行者:30%となります。
車両が黄信号で進入、右左折したことにより交通事故が発生した場合の過失割合は、車両にも黄信号無視という過失がありますので、車両:80%、歩行者:20%となります。
歩行者が黄信号で横断した場合についてまとめると、次のようになります。
| 歩行者 | 車両 | 過失割合 |
|---|---|---|
| 黄信号(青点滅) | 赤信号 | 車両:90%、歩行者:10% |
| 黄信号(青点滅) | 青信号で進入し、右左折 | 車両:70%、歩行者:30% |
| 黄信号(青点滅) | 黄信号で進入し、右左折 | 車両:80%、歩行者:20% |
(3)歩行者が赤信号で横断を開始した場合
歩行者が赤色信号で横断開始しており、そこに車両が青信号で進入、直進したことにより交通事故が発生した場合の過失割合は、歩行者に赤信号無視という重大な過失がありますので、車両:30%、歩行者:70%となります。
「赤信号無視の歩行者が悪いのに、交通ルールを守っている運転者側に30%とはいえ過失がつくのはおかしい」と思われるかもしれません。
しかし、車両の運転者には、歩行者を保護する安全運転の義務(道交法70条)が課せられており、赤信号横断中の歩行者だからと言ってこの安全運転義務が免除されるものではなく、車両の運転者に一定の過失が認められることになります。
一方、車両が黄信号で進入、直進した時には、車両側にも黄信号無視という過失がありますので、車両:50%、歩行者:50%となります。
車両が赤信号で進入、直進した時には、双方に赤信号無視という重大な過失があるものの、歩行者優先のルールから、車両の過失の方が大きくなり、車両:80%、歩行者:20%となります。
歩行者が赤信号で横断した場合についてまとめると、次のようになります。
| 歩行者 | 車両 | 過失割合 |
|---|---|---|
| 赤信号 | 青信号 | 車両:30%、歩行者:70% |
| 赤信号 | 黄信号 | 車両:50%、歩行者:50% |
| 赤信号 | 赤信号 | 車両:80%、歩行者:20% |
(4)歩行者が赤信号で横断を開始し、その後青信号に変わった場合
歩行者が赤信号で横断を開始し、その後青信号に変わったのに対し、車両が赤信号で進入し、交通事故が発生した場合の過失割合は、車両:90%、歩行者:10%となります。
<コラム>歩行者と車両の運転者との間で信号機の表示に争いがある場合にはどうすればいい?
事故当時の信号機の表示で過失割合が変わってくるため、歩行者と車両の運転者との間で、信号機の表示が何色であったかで言い争いになることがあります。
事故の目撃者の証言で信号機の表示を明らかにする方法もありますが、歩行者が横断歩道を渡り始めたタイミングの信号機の色まで覚えている目撃者は少ない場合もあります。
そのような場合には、事故当時の信号機サイクルを調査したりして、衝突の瞬間から渡り始めの瞬間をさかのぼって信号機の色を特定することになります。また、車両側がドライブレコーダーを搭載していれば、録画データを確認して信号機の色がわかればそれで特定します。
信号機のない横断歩道上の事故の過失割合
信号機のない横断歩道を通過する車両には、横断する歩行者がいないことが明らかな場合を除き、直前で停止できるスピードで進行しなければなりません。
さらに、歩行者がいる場合には停止して通行を妨げなければならないという重い注意義務があります。
したがって、信号機が設置されていない横断歩道上であっても、基本的に交通事故の過失責任は車両側にあり、車両:100%、歩行者:0%となります。
道路上のひし形「◇」表示は、「この先に(信号機のない)横断歩道または自転車横断帯あり」のマークです。このマークを見かけたら、前方に歩行者がいないか注意するようにしましょう。
横断歩道上に歩行者が寝ていた場合の過失割合
歩行者が横断歩道を通行中の事故ではないので、横断歩道上であっても路上であっても、歩行者が寝ていた場合には次のような過失割合になります。
昼間の場合は、車両から路上に寝ている人物の発見は比較的容易であることから、基本の過失割合は車両:70%、歩行者:30%となります。
一方、夜間の場合は、昼間と比較して人物の発見が困難であることから、基本の過失割合は車両:50%、歩行者:50%となります。
加害者側の保険会社から提案された示談額が適切かどうかはわかりにくいものです。
過失割合が適正かどうか、交渉により増額可能性があるのかどうかなど、示談に応じる前に弁護士へ相談されることをおすすめします。
歩行者が幼児・高齢者の場合、過失割合が変わる可能性あり!
信号の色や、車両の進行方向別の基本的な過失割合は説明したとおりですが、個々の交通事故の発生状況や環境などにより、基本の過失割合が変わってしまうケースも少なくありません。
実際に過失割合を判断する際には、基本の過失割合をベースにして、その過失割合が変わってしまう要素の有無も確認する必要があります。
基本の過失割合が変わってしまう主な要素としては、次のようなものがあります。
(1)車の過失割合が増えてしまう4つの要素
- 歩行者が幼児(6歳未満)、児童(6歳以上13歳未満)、高齢者(65歳以上)など
(歩行者の中でも判断能力や行動能力が低い社は特に保護する必要があるため) - 歩行者の集団横断(車からの発見が容易であるため)
- 住宅街・商店街(人の横断が激しく、車両は歩行者により注意すべき)
- 酒気帯び運転やハンドル操作の著しいミス、居眠り運転、無免許運転など重い過失
(2)歩行者の過失割合が増えてしまう3つの要素
- 夜間(ライトにより歩行者が車の存在に気づきやすいため)
- 幹線道路(車両の通行が激しい車幅14メートル以上の幹線道路は歩行者がより横断に注意すべきと考えられるため)
- 歩行者による車両の直前直後横断、特段の事情のない立ち止まりや後退
(歩行者のルール違反や通常と異なる行動には車両の対応が困難なため)
【まとめ】歩行者と車の事故の場合、基本的に車側の責任が重い
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 横断歩道上の交通事故は、歩行者優先のルールがあり歩行者が強く保護されているので、原則として車両の過失割合が大きくなる傾向にある。
- 歩行者にもルール違反があったり、事故発生の具体的状況から修正要素が存在したりすることもある場合には、車両側の過失割合が100になるとは限らない。
- 歩行者が幼児、高齢者の場合、事故の現場が住宅街や夜間である場合には、10~20%程度過失割合が修正される場合がある。
示談交渉は保険会社に任せておけば大丈夫と思っている方もいるかもしれません。
しかし、保険会社の提示する金額が、弁護士が提示する金額よりも少ないことも少なくありません。知らず知らずのうちにあなたが損してしまっている可能性もあります。
弁護士に相談することで、保険会社から提示された過失割合が適正か、また、賠償金額に増額ができる余地がないか検討します。
弁護士に相談し、保険会社が提示した金額よりも増額した解決事例もありますので、保険会社に示談交渉を任せてしまうのではなく、一度弁護士への相談をおすすめします。
横断歩道事故の被害にあって賠償金請求のことでお困りの方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
また、弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。
(以上につき、2024年9月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。