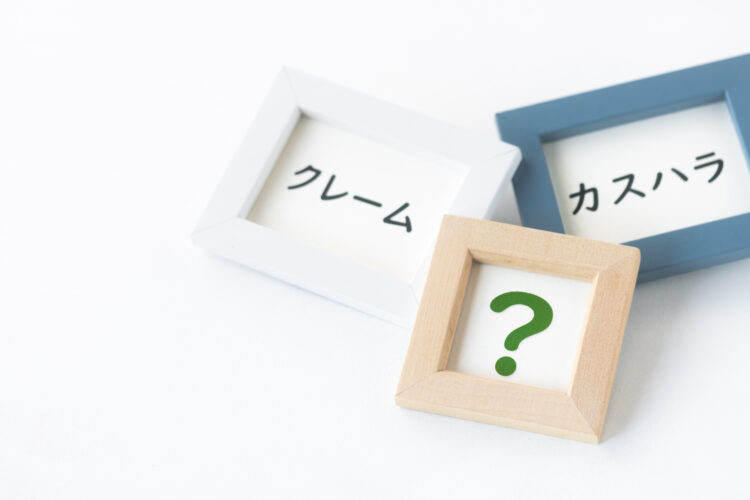「上司の言動、パワハラかも……でもパワハラって具体的にどんな言動のこと?」
実は、職場でのパワハラ(パワーハラスメント)とはどのような行為なのかについては、法律に規定があります。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- パワハラの定義
- パワハラの種類と具体例
- パワハラを受けた場合の対策
ここを押さえればOK!
パワハラ行為は「身体的・精神的攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大・過小な要求」「個の侵害」などに分類されます。
予防策としては、普段から周囲とコミュニケーションを取り、できないことは断ることが挙げられます。万が一被害に遭った場合は、加害者本人や社内の相談窓口、労働局などの外部機関へ相談するほか、あっせんや民事調停、最終的には証拠を集めて裁判を起こすといった対処法があります。
パワハラ(パワーハラスメント)の定義
職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)とは、権力や立場を利用した、部下や同僚、上司などへの嫌がらせのことをいいます。
職場におけるパワハラ対策は、労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)によって、会社に義務付けられています。
労働施策総合推進法によるパワハラ対策の義務化
都道府県労働局等の総合労働相談コーナーに寄せられる、「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は長年増加傾向にあり、パワハラは深刻な社会問題になっています。
そこで、2019年5月に、労働施策総合推進法が改正され、初めて職場におけるパワハラ対策が会社の法律上の義務とされました。大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から職場におけるパワハラ対策が全面的に義務化されました。
参考:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!|厚生労働省
しかし、改正法施行後も相談件数は高止まりしています。
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は、12年連続で最多となっており、依然として深刻な状況が続いています。
参考:「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します|厚生労働省
パワハラの行為(種類)と具体例
職場におけるパワハラにあたる行為とは、次の3つの要素をすべて満たすものです。(労働施策総合推進法30条の2第1項)
(a)職場における優越的な関係を背景とした言動であること
(b)必要かつ相当な範囲を超えておこなわれること
(c)(a)と(b)により、雇用する労働者の就業環境が害されること
(b)の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」かどうかが、「指導」との最も重要な線引きであり、近年の裁判でも厳しく判断されています。
では具体的にどのような行為がパワハラに該当するのでしょうか。
6つのタイプに分けて具体例をご説明します。
(1)身体的な攻撃……暴行、傷害

例えば、上司が部下に対して、殴ったり蹴ったりする行為がパワハラにあたります。
また、酒を強要する行為もパワハラです(東京高裁判決平成25年2月27日)。
他方で、業務上関係のない単に同じ企業の同僚間の喧嘩はパワハラにはあたりません。
(a)優越的な関係が背景になく、(b)業務も関係ないためです。
(2)精神的な攻撃……脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

例えば、上司が部下に対し、「お前は馬鹿だ」など人格を否定するような発言を日常的に行うと、パワハラになります(東京地裁判決平成26年7月31日)。
他方で、禁煙の場所における喫煙など、マナー違反に対し注意する行為はパワハラにはあたりません。
(b)業務上必要かつ相当な範囲を超えていませんし、(c)就業環境も害されていないからです。
(3)人間関係からの切り離し……隔離・仲間外れ・無視

例えば、意に沿わない社員に対し、長期間にわたり、仕事を取り上げた上で、一人部屋へ席を移動させたり、自宅研修等をさせたりする行為は、パワハラになります(東京高裁判決平成5年11月12日)。
他方で、短期間、別室に席を移動させて新人研修することはパワハラにはあたりません。
(b)業務上必要かつ相当な範囲を超えていないからです。
(4)過大な要求……業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

例えば、達成困難な過剰なノルマを強要し、未達成に対し強く叱責する行為はパワハラになり得ます。
社員の教育のため、少し高いレベルの仕事をさせることはパワハラにあたりません。(b)業務上必要かつ相当な範囲を超えていないからです。
(5)過小な要求……業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
例えば、管理職である部下を、退職させるために、清掃作業などに配置転換するとパワハラにあたります(山口地裁周南支部判決平成30年5月28日参照)。
他方で、労働者の能力に応じて、業務量を減らすことはパワハラにあたりません(福井地裁判決平成21年4月22日)。
(b)業務上必要かつ相当な範囲を超えていないからです。
(6)個の侵害……私的なことに過度に立ち入ること
例えば、思想や信条を理由として、集団で特定の社員を監視し、ロッカーを無断で点検する行為はパワハラになります(最高裁第三小法廷判決平成7年9月5日)。
異動先など、労働者へ配慮するために、労働者の家族関係について聴取することはパワハラになりません。
(b)業務上必要かつ相当な範囲を超えておらず、(c)就業環境も害されていないからです。
パワハラを受けないために自分でできる対策
パワハラを受けないために、自分でできる対策があります。
具体的には、次のようなものがあります。
- 周囲とコミュニケーションを取る
- できないことは断る
(1)周囲とコミュニケーションを取る
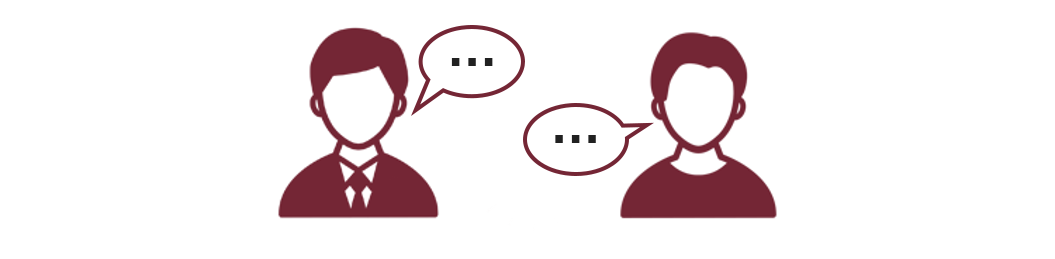
孤立している人はパワハラのターゲットになりやすいです。
普段から会話を増やして周囲と信頼関係を構築することで、パワハラを防ぐことができます。
また、「~と言われるとツラいです」「~のように言っていただけると助かります」と表現を柔らかくして、相手になるべく敵対心を持たせないようにしましょう。
(2)できないことは断る

自分にとって何が不快なのかを考え、業務とパワハラ行為の線引きをしましょう。
業務としてするべきことはするが、断るべきことは、きっぱりと断ることが大切です。
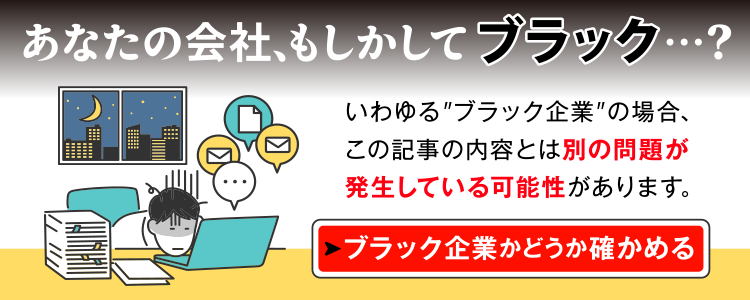
対策してもパワハラがなくならないとき
自分ではどうしてもパワハラを解決できないときは、次のような行動をとってみましょう。
(1)上司(加害者)と話す
パワハラしている上司(加害者)に、「こういう行為で苦しんでいます。やめていただきたいのですが」と直接話してみると、効果がある場合があります。
加害者がパワハラをしているという自覚がない場合があるからです。
パワハラを自覚した加害者がパワハラを止めてくれることがあります。
ただし、直接パワハラの苦情を伝えると、かえって加害行為が悪化しそうな加害者の場合は、次に紹介する第三者や外部機関への相談を検討しましょう。
(2)信頼できる上司や人事・労務に相談する
2022年4月から、企業規模にかかわらず、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、企業には「相談窓口の設置」や「相談に対する適切な対応」などの防止措置が法律で義務付けられています。
信頼できる上司のほか、人事部や労務部といった社内のハラスメント相談窓口に相談してみる方法が、まずは第一選択肢となるでしょう。
企業が相談を放置したり、相談したことで不利益な扱いをしたりすることは法律で禁じられており、もし企業が適切な対応を怠れば、企業自身の法的責任(安全配慮義務違反など)が問われることになります。
(3)外部機関にパワハラを相談する
次のような外部機関への相談も検討してみましょう。
- 各地の労働局や労働基準監督署にある「総合労働相談コーナー」
- 最寄りの法務局や地方法務局に電話がつながる「みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)」
参考:みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)|法務省
(4)紛争調整委員会によるあっせんを利用する
都道府県労働局において設置されている、紛争調整委員会によるあっせんを利用する方法もあります。
紛争当事者(パワハラでいえば加害者と被害者)の間に、労働の専門家であるあっせん委員が介入して、話し合いをする制度です。
無料で行うことができ、裁判に比べれば簡易迅速にできます。
相手が話し合いに応じなければ合意がないまま終了してしまいます。
また、合意には判決と同じ効力はありません。
そのため合意が守られない場合は、別途、公正証書化したり、裁判するなど、強制的に合意を守らせるための手段を取る必要があります。
参考:個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)|厚生労働省
(5)裁判官も関与する民事調停を利用する
パワハラを受けた場合、民事調停をすることもできます。
紛争当事者の間に、裁判官と調停委員が間に介入して、話し合いをする制度です。
申立て手数料は有料ですが、裁判に比べれば安くなっています。
合意に至れば、判決と同じ効力を持つ調停調書が作られます。
相手が納得しなければ調停不成立で終わってしまいます。
また、裁判に比べると簡易迅速な手続きです。
参考:「民事調停で解決」しませんか?|公益財団法人日本調停協会連合会
(6)裁判でパワハラを訴える
裁判に持ち込むこともできます。
裁判の場合、他の手続きに比べて、パワハラの証拠が重要となってきます。
パワハラの証拠としては、録音・録画データ、パワハラを受けた日時や場所、相手の言動がわかるメール履歴や日記などがあります。
相手方が納得するかどうかにかかわらず、判決が出ます。
裁判では、加害者の行為がパワハラに当たるか否か白黒をつけ、慰謝料の支払いなどを命じてもらうことができます。
裁判は手続きが複雑ですので、裁判をする場合には、弁護士への相談をお勧めします。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
パワハラに関する近年の主な裁判事例
パワハラの裁判例としては、既に挙げたものの他、次のようなものもあります。
- 深刻ないじめ・暴行の事例(高額な慰謝料):
コンビニの運営会社代表者と店長が、コンビニの従業員に対し、1年3ヶ月にわたり、日常的に暴力的ないじめをした行為(※)がパワハラであるとして、慰謝料570万円を含む約930万円が被害者の損害として認められた例(東京地裁判決平成28年12月20日)。
※タバコの火を鼻に押し付ける、殴る蹴る、エアガンで撃つ、売れ残り品の買い取りを強要するなど
- 精神疾患・自殺との因果関係:
社員が仕事のミスをするたびに、社長が暴言・暴行(頭を叩く、汚い言葉で大声で怒鳴るなど)を行った上、退職強要をするなどしたために、当該社員が急性ストレス反応で自殺した事件において、慰謝料として2800万円がみとめられた例(※)(名古屋地裁判決平成26年1月15日)。
※他の損害等を足し引きして、最終的に合計約3600万円が損害として認められています。 - 加害者への厳正な処分:
加害者への厳正な処分: 約10年間にわたり、多数の部下・同僚職員に対し約80件のパワハラ行為(人格否定、罵倒など)を繰り返した消防職員に対する分限免職処分について、裁判所は処分を適法と判断しました(最高裁判決 令和4年9月13日)。
【まとめ】職場におけるパワハラとは、権力や立場を利用した、部下や同僚、上司などへの嫌がらせのこと
パワハラにはさまざまな種類があります。
パワハラ防止法により相談しやすい環境になっていくことが期待されていますが、まだまだ社内の対応だけでは不十分なことも起こり得ます。
パワハラでお困りの方は、次のような公的相談窓口などにご相談ください。