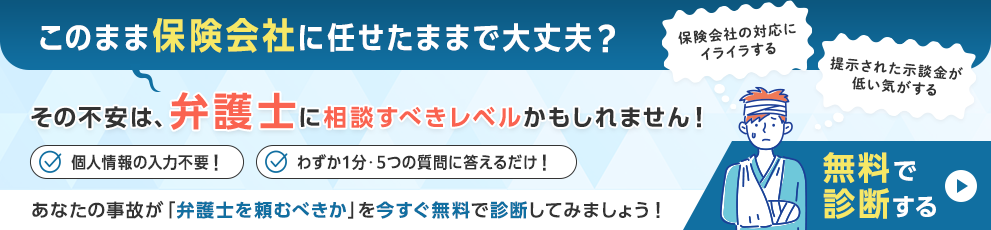交通事故による後遺症のつらさは、ご本人にしかわからない部分も多いものです。
「認定された後遺障害等級が、実際の症状より軽い気がする……」と、悔しい思いをされていませんか?
実は、等級がひとつ変わるだけで、受け取れる賠償金の目安が大きく変わるケースも少なくありません。
もし認定結果に疑問を感じているのであれば、諦めずに「異議申立て」という手続きで再審査を求めることができます。
そこでこのコラムでは、異議申立てを行うための具体的な3つの方法と、審査の行方を左右するカギとなる書類「陳述書」の効果的な書き方について、わかりやすく解説します。 納得のいく結果を得て、適正な補償を受け取るためのヒントとして、ぜひお役立てください。
ここを押さえればOK!
不服申立ての際は、被害者の主張をまとめた「陳述書」を提出する場合があり、日常生活のつらさや不便さなど、被害者本人にしか分からない状態を説明します。少しでも不服申し立てを認められるようにするには、陳述書の作成や資料集めなどコツが必要です。後遺障害等級認定でお困りの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
自宅でらくらく「おうち相談」
「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
交通事故の後遺障害の異議申立てとは?
後遺障害等級は、症状の程度に応じて1~14級(および要介護1級・2級)に分類されますが、等級がひとつ違うだけで、後遺症慰謝料の金額が大きく変わってきます。
後遺障害の認定は、所定の機関(損害保険料率算出機構など)が行いますが、認定された等級に納得がいかないとき、あるいは非該当となったときには、不服申立てをすることができます。
不服申立ての方法には3つあります。それぞれ見ていきましょう。
(1)損害保険料率算出機構に対する異議申立て
損害保険料率算出機構により後遺障害等級認定がなされた場合、同機構に対して異議申立てをすることができます。この場合、自賠責保険審査会で審査がされます。
審査結果に不服があれば、再度の異議申立ても可能です。
(2)一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停(紛争処理)の申立て
紛争処理を申立てると、紛争処理委員が審査します。
紛争処理機構に対する申立ては1回しかできませんので、結果に納得がいかなくても、それ以上異議申立てはできません。
認定結果に不服がある場合には、裁判で訴えることになります。
(3)裁判所への訴訟提起
司法に判断を委ねる方法です。当初の等級認定や、他の2つ(損害料率算出機構に対する異議申立てや自賠責紛争処理機構に対する調停申立て)の審査結果に左右されず、裁判所独自の視点で等級を判断してもらうことができます。
後遺障害の陳述書とは?異議申し立てでの役割や書き方とは?
それでは、後遺障害等級認定の不服申立てで作成する陳述書の役割や書き方について見てみましょう。
(1)後遺障害認定の異議申立てにおける陳述書の役割
陳述書とは、後遺障害等級認定の不服申立ての資料として、被害者本人が作成する書類のことをいいます。
異議申立てや裁判において、被害者が自らの主張を訴える方法の一つであり、不服申立てが認められる確率を高める手段の一つと言えます。
(2)陳述書に書く内容
不服申立てにおいて特に争いになるのは、「後遺障害の症状が原因で、事故前と比べて働けなくなっているかどうか、働けなくなっているとしたらどの程度か」という点です。
陳述書を書くにあたって大切なのは、後遺症により仕事や日常生活の場面でどのような支障があるのか、その状況をできるだけ具体的に書くことです。被害者本人しか分からない、後遺症による支障を具体的に伝え、相手に理解してもらうことが陳述書の目的と言えます。
(2)陳述書を書くときの注意点
被害者ご本人が陳述書を書くときの注意点を具体的に解説します。
(2-1)5W1Hでわかりやすく書く
事故の発生から受傷、現在に至るまでの症状の経緯を書きます。「いつ、誰が、どこで、何を、どのように、どうした」(=5W1H)にあてはめ、時系列に沿って書くことを意識しましょう。
この「5W1H」についてはあくまでも実際に起こった客観的な事実を書き、自分の思いや感想など、主観的なものとは分けて書くことがポイントです。
(2-2)加害者への不満を書かない
特に裁判の場合ですが、加害者を攻撃するような言葉を書くと、裁判官に悪い印象を与えてしまうおそれがあるため控えましょう。また、当初の認定結果に対する不満を長々と述べるのも避けるほうが無難です。
(3)後遺障害の異議申立てにおける陳述書の例文
これらのポイントを踏まえ、実際の陳述書の記載例は次のようになります。
| 陳述書 〇〇年〇月〇日 氏名 1 △△年△月△日午後△時ごろ、私は買い物のため〇〇市内の商店街を自動車で運転中、加害者の運転する自動車に後ろから追突されました。その衝撃で首を強く揺さぶられたため、その日のうちに□□医院を受診したところ、頸椎捻挫の診断を受けました。 2 事故の翌日から右手にしびれを感じました。その後週3回ほど、約3ヶ月にわたり通院治療を続けましたが、右手のしびれはおさまらず、×月×日に医師より症状固定の診断を受けました。 3 私はパソコンによる顧客データや売上伝票の入力の仕事をしていますが、右手のしびれにより、具体的に次のような支障が生じています。 (1)キーボード入力に時間がかかる しびれにより、右手の中指から小指にかけて感覚がありません。これにより、パソコンのキーボードの打ち間違えが増え、受傷前に比べて作業に2倍ほどの時間がかかるようになりました。 (2)作業による疲労が増えた … |
後遺障害の陳述書と意見書の違いとは?
陳述書と似ている書面に、意見書があります。意見書とは、等級認定の不服申立ての際、医師や弁護士が作成する書類です。当初の等級認定の不当さについて、医学的・法律的観点から意見を述べるものです。
必ず提出しなければならないものではありませんが、不服申立てが認められる可能性を高める書類の一つと言えます。
陳述書の作成で悩んだら弁護士に相談がおすすめ!
後遺障害等級の不服申立てでは、日常生活のつらさや不便さなど、被害者本人にしか分からない状態を説明する必要があります。ただし、それらを読み手(審査員や裁判官など)に正しく伝えるためには、相当程度の技術や労力を要します。
弁護士に相談することで、後遺障害の陳述書に書くべきこと・書くべきことではないことののアドバイスを受けることができるほか、集めるべき資料や受けるべき検査のアドバイスも受けることができます。
異議申立てによって実際に等級変更が認められることは、なかなかハードルが高い傾向にあります。少しでも異議申し立てが認められるようにするために、弁護士への相談を受けておくのがよいでしょう。
【まとめ】後遺障害の異議申立てが認められるのは難しい|弁護士へ相談を
後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、異議申立てを行うことで、より実態に即した適正な等級へ変更される可能性があります。
なかでも、被害者であるあなたの具体的な痛みや、日常生活でどのような支障が出ているかを伝える「陳述書」は、審査において非常に重要な役割を果たします。 しかし、読み手に状況が正確に伝わる書類を作成し、厳しい審査基準をクリアして主張を認めてもらうには、医学的・法的な専門知識が必要になる場面も多々あります。
適正な等級の獲得を目指すためにも、専門家である弁護士のサポートを受けることを検討してみてはいかがでしょうか。 アディーレ法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方に寄り添い、資料の収集から書類作成までトータルでサポートいたします。
「少し話を聞いてみたい」というだけでも構いませんので、まずは一度、お気軽にご相談ください。