運転中、ウトウトしてしまい危険を感じた経験のある方は、少なくありません。
眠気は注意力を散漫にし、交通事故発生の原因になりますので、運転する上では大敵です。
居眠り運転の交通事故で人をケガさせてしまった場合には、居眠り運転の原因(アルコール、薬物など)や程度、運転態様などにより、次のような罰則を受ける可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)。
- 危険運転致死罪(1年以上20年以下の懲役(※)、同法2条・刑法12条)
- 危険運転致傷罪(1ヶ月以上15年以下の懲役、同法2条・刑法12条)
- 過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金、同法5条)
意外と刑罰が重いという印象を持たれたかもしれません。しかし、居眠り運転で交通事故を起こしてしまったときに、適切な対応を取ることができないと、他の違反行為をしたとして、ここで示した以上にさらに罰則が重くなる可能性があります。
※2022年6月に懲役と禁錮を廃止し「拘禁刑」に一本化する改正刑法が成立しました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。
このような刑罰を受けることがないように居眠り運転で交通事故を起こさない防止法を知ると同時に、万が一居眠り運転で交通事故を起こしてしまった場合に備えて適切な対処法も知っておきましょう。
この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。
- 居眠り運転によって受ける可能性がある違反点数と罰則
- 万が一居眠り運転で交通事故を起こしてしまった場合の対処法
- 居眠り運転の防止法
「居眠り運転」は交通事故に多い原因の1つ
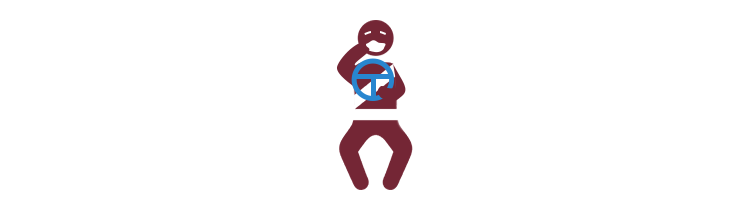
居眠り運転をしてしまうと、前方に注意してタイミングよくブレーキをかけて衝突を避けたり、危険を察知したりするのが遅くなりますので、交通事故を起こしやすくなります。
特に、自動車運送事業においては、運転時間が長い、十分な休みを取れない、過労気味であるなどの事情から、居眠り運転による重大な事故が発生し、居眠り運転防止が社会的な問題となっています。
道路交通法に直接的に居眠り運転を規制したものはなく、居眠り運転を要因とする交通事故は、次の2つに分類されていると考えられます。
- 「過労運転」(道路交通法66条、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で運転)
- 「安全運転義務違反」(道路交通法70条)のいずれか(「漫然運転(ぼんやりして注意散漫な状態で運転)」など)
警察庁「令和3年(2021)中の交通事故の発生状況」によると、過労運転による事故件数は424件で前年比+60件、漫然運転の事故件数は2万2318件で前年比-756件となっています。
漫然運転については減少傾向にあるものの、漫然運転は事故原因としては4位と高くなっています。
また、警察庁「令和3年(2021)中の交通事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」によれば、死亡事故に限ってみると、漫然運転による死亡事故は345件で第1位となっています。
このように、居眠り運転を含む漫然運転は死亡事故になりかねない危険な行為ですので、ドライバーは細心の注意が必要です。
居眠り運転で交通事故を起こしてしまった場合の違反点数と罰則
居眠り運転をしたら、交通事故を起さなくても発見された時点で安全運転義務違反(漫然運転など)や過労運転として処分される可能性があります。
安全義務違反の場合は違反点数2点ですが、過労運転の場合は違反点数25点と高く、違反歴がなくても免許取り消しの行政処分を受けます。
また、居眠り運転で物損事故を起こした場合には、道路交通法上の刑事処分を受ける可能性があります。
- 安全運転義務違反による事故の場合には反則金9000円(普通車)で、実務上、反則金を支払えば刑事訴追されることはまずありません。
- 事故の原因が過労運転とされた場合には、反則金はなく、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第7号)。
ただし、覚せい剤などの薬物の影響による過労運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法117条の2第3号)。
一方、居眠り運転で人身事故を起こした場合には、刑事処分の内容は物損事故よりも重くなります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律では、居眠り運転の原因(アルコール、薬物など)や程度、運転態様などにより、次のような罰則が定められています。
- 危険運転致死罪(1年以上20年以下の懲役、同法2条・刑法12条)
- 危険運転致傷罪(1ヶ月以上15年以下の懲役、同法2条・刑法12条)
- 過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金、同法5条)
居眠り運転は、事故の原因や運転の態様によっては非常に重い罰則を受ける可能性があります。
万が一居眠り運転で交通事故を起こしてしまった場合の対処法
居眠り運転で交通事故を起こしてしまったときに適切な対応を取ることができないと、他の違反行為をしたとして、さらに罰則が重くなる可能性があります。
事故後に取るべき行動は次のとおりです。冷静に対応するようにしましょう。
まず身の回りの安全を確認
ケガをした人がいた場合には救護を行う
警察への通報
保険会社に連絡
それぞれ説明します。
(1)まず身の回りの安全を確認
事故を起こした場合には、直ちに車を停止させます。
可能であれば、後続車の事故を誘発しないように、路肩などに車を寄せて、ハザードランプを付けたままにしたり、三角表示板を置いたりするなど、後続車に事故の発生を知らせるとよいでしょう(道路交通法72条1項前段、危険防止等措置義務)。
| 危険防止等措置義務違反 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 (道路交通法117条の5第1号) |
(2)ケガをした人がいた場合には救護を行う
相手の車に人が乗っている場合には、事故の結果ケガを負っていないか、安全を確認するようにしましょう。
もちろん自分がケガを負っていないかどうかも確認しましょう。
ケガ人がいる場合には、人命最優先ですので、まずは救急に連絡するようにしましょう(道路交通法117条2項、72条1項前段、救護義務)。
| 救護義務違反 | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (道路交通法117条2項、72条1項前段) |
なお、事故直後だと、気が動転していて、本人がケガを把握していなかったり、痛みを感じにくかったりします。したがって、医療従事者でない限り、安易にケガの軽傷重症を判断するのは危険です。
軽傷に見えても、実際のケガの程度は分かりませんから、救急に連絡して病院で診察を受けたほうがよいでしょう。
(3)警察への通報
このような二次的な交通事故の発生を防ぐ措置を講じたら、直ちに警察に連絡し、交通事故について説明します(道路交通法72条第1項後段、警察への報告義務)。
もし、この義務を怠った場合には、次の罰則に処される可能性があります。
| 警察官への報告義務違反 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法119条1項第10号) |
事故を起こして気が動転していると思いますが、停車せずに逃げることはやめましょう。
(4)保険会社に連絡
加入している自動車保険会社に対して、事故の発生や状況、事故原因などを伝え、保険を利用できるかどうかを確認するようにしましょう。
居眠り運転で交通事故を起さないための5つの対策
居眠り運転で交通事故を起こさないための5つの対策としては次の5つの方法が挙げられます。
- 十分な睡眠時間の確保
- 過労の原因を取り除く
- 長距離の運転では2時間に1度休息を取る
- カフェインの効果を上手く活用する
- 居眠り運転対策グッズを活用する
最近ではドライバーの眠気を検知するAIなどが開発され、技術的に居眠り運転を防止する方法も活用され始めています。
5つの対策についてそれぞれ説明します。
(1)十分な睡眠時間の確保
居眠り運転の大きな要因に「睡眠不足」「不規則な生活」が挙げられます。
厚生労働省の調査によると、睡眠5時間未満の運転者は、5時間以上の運転者に比べて、居眠りのヒヤリハット体験をした人が2.3倍に上っています。
十分な睡眠時間を確保するためにも、不規則な生活を正して睡眠時間を確保し、眠りを妨げている原因を考えるなど生活習慣の見直しをすることが大切です。
(2)過労の原因を取り除く
過労の兆候は、注意力散漫、疲労感の増大、眠気が三大症状と言われており、居眠り運転の原因となっています。
運転前に十分な休養がとれているか、6~7時間の連続した睡眠を確保できているかなど、運転の際には自分の体調に向き合い、運転可能かどうかをチェックするようにしましょう。
(3)長距離の運転では2時間に1度休息を取る
眠気を覚ますためにも長距離運転中は最低でも2時間に1回は休憩を取るようにするとよいでしょう。
運転は単調な作業である側面もあります。特に高速道路の運転では、信号がなく歩行者もおりませんので、運転がさらに単調となります。
人間は、同じことを継続していると体や意識が慣れてしまい眠気を催すことがあります。
休憩を取る際には、車外に出て外の空気を吸ったりするなど、危険のない範囲で気分転換ができるとよいですね。
(4)カフェインの効果を上手く活用する
カフェインには覚醒作用があるので、眠くならないようにカフェインを摂取する方法もあります。
カフェインは、コーヒー、紅茶、緑茶、栄養・健康ドリンクに多く含まれており、覚醒作用は3時間程度です。
ただし、カフェインの効果は人によって異なります。
眠さや疲れを感じた時には、カフェインに頼ることなく、安全な場所に車を停車して仮眠したり休んだりするようにしましょう。
(5)居眠り運転対策グッズを活用する
最近は、多様な居眠り運転防止グッズがありますので、自分に合ったものを探すのもいいかもしれません。
例えば、瞳の動きを感知して目を閉じる時間によって警告音を発する機器、瞳孔の変化から眠気を検知すると警告音を発する機器、耳にかけて頭の傾きに反応して警告音が鳴る機器などがあります。
居眠り運転の原因は睡眠不足や過労などが多いことから、居眠り運転による交通事故を起こさないためには、生活習慣の改善や体調管理、業務量の調整も重要となります。
【まとめ】居眠り運転で人身事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪もしくは過失運転致死傷罪に当たる可能性あり!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 居眠り運転で物損事故を起こした場合に受ける可能性のある違反点数と罰則
- 安全運転義務違反による事故の場合には反則金9000円(普通車)で、実務上、反則金を支払えば刑事訴追されることはまずありません。
- 事故の原因が過労運転とされた場合には、反則金はなく、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第7号)。
- 居眠り運転で人身事故を起こした場合に受ける可能性のある罰則(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)
- 危険運転致死罪(1年以上20年以下の懲役、同法2条・刑法12条)
- 危険運転致傷罪(1ヶ月以上15年以下の懲役、同法2条・刑法12条)
- 過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金、同法5条)
- 居眠り運転で交通事故を起こしてしまった場合の対処法
- 身の回りの安全を確認
- ケガをした人がいた場合には救護を行う
- 警察への通報
- 保険会社に連絡
- 居眠り運転で交通事故を起さないための5つの対策
- 十分な睡眠時間の確保
- 過労の原因を取り除く
- 長距離の運転では2時間に1度休息を取る
- カフェインの効果を上手く活用する
- 居眠り運転対策グッズを活用する
運転の際には、睡眠を十分にとるなど居眠り運転を起こさないための注意が必要です。
それでも居眠り運転で事故を起こしてしまった場合には、法律に従った適切な対応をとることが大切となります。


























