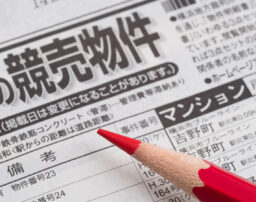近隣トラブルは、日常生活の中で、誰もが経験する可能性のある問題です。
騒音、ペットの飼育、ごみの堆積など、さまざまな原因で近隣トラブルが発生し、精神的なストレスを感じることもあるかもしれません。
しかし、適切な対処法と相談先を知ることで、トラブルを予防したり、トラブルを解決して良好な近隣関係を築くことができたりする可能性があります。
本記事では、よくある近隣トラブルの事例から具体的な対処法、そして相談先までをわかりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
- 近隣トラブルのよくある事例5選
- 近隣トラブルで受忍すべき限度
- 近隣トラブルの対処法
- 近隣トラブルの相談先
ここを押さえればOK!
よくある近隣トラブルの事例としては、騒音、ペットの飼育、ごみの堆積、漏水、共有部分の利用方法があります。
具体的な対処法としては、トラブルを深刻化させないための自衛策の検討、証拠の録音・録画、改善してほしいことを相手に伝える方法があります。
さらに、相談先としては、賃貸の場合は大家や管理会社、分譲の場合は管理組合、戸建ての場合は自治会や町内会があります。共通して警察、弁護士に相談することも可能です。
問題が深刻化する前に早めの対処と相談を心掛けましょう。
近隣トラブルのよくある事例5選
近隣トラブルは、日常生活で誰もが直面し得る問題です。
以下に代表的な5つの事例を挙げます。
(1)騒音
楽器の演奏、深夜の音楽や足音などの生活音、工事の騒音などが原因となります。
特に夜間の騒音は睡眠を妨げ、健康に悪影響を及ぼすこともあるため深刻です。
騒音を規制する法律としては、騒音規制法や各自治体の騒音条例があります。建設工事や自動車の騒音で悩んでいる場合、騒音規制法などで定められている音量以上の音量が出ているときは、違法とされ一定の罰則もあります。
しかし、分譲マンションで問題が多い階上からの騒音などの生活騒音は、これらの法律の適用対象外です。後で説明する受忍限度を超える騒音についてのみ、相手に損害賠償などを求めることができます。
(2)ペットの飼育
マンションの規約により、「ペットは飼育禁止」という定めがあるのに、ルールを守らず買っている住人がいることがあります。
また、適切に飼育されずに、鳴き声や糞尿処理などの問題で周囲に迷惑がかかるケースもあります。
(3)ごみの堆積・悪臭
ごみの出し方が守られない、共有部分にごみを置くので悪臭が発生するなどの問題です。
特に夏場は悪臭が強くなり、衛生面でも問題が生じます。
(4)漏水
分譲マンションや賃貸で、上階からの漏水が自宅に被害を及ぼすケースです。
漏水の場所や程度によっては生活自体が困難になりますし、建物の構造に影響を与えることもあるため、早急な対応が必要です。
(5)共有部分の利用方法
マンションの共有部分の使い方を巡るトラブルです。
分譲マンションなどの区分所有建物は、専有部分(各住居)以外の廊下、エレベーター室や屋根、屋上、ロビー等は、共有部分とされています。共有部分は、区分所有者全員の共有になりますので、私物を置いたりするのは、原則できません。
バルコニーも、一般的に共有部分です。通常、バルコニーに接する住居の所有者に専用使用権がありますが、マンションの管理規約で利用のルールが定められていたら、そのルールを守る必要があります。
近隣トラブルで受忍すべき限度とは
近隣トラブルにおいて、法律上「受忍限度」という概念があります。
近隣トラブルで相手の責任を問いたい場合、トラブルの内容にもよりますが、不法行為を理由とする損害賠償を請求することが多いです。
その場合、裁判所は、一般的に、「社会生活上受忍限度を超える場合には不法行為が成立する」と判断します。これを受忍限度論といいます。
特に騒音トラブルで問題になります。
騒音に悩まされている側からすれば、我慢できず受忍限度を超えていると思うからこそ「騒音に気を付けてほしい」と伝えたり、訴訟を起こしたりするわけです。
しかし、音の感じ方は人それぞれで個人差があります。裁判所が必ずしも「社会生活上受忍限度を超える騒音である」と認めるとは限りませんので、注意が必要です。
近隣トラブルの対処法
近隣トラブルは本当に悩ましい問題です。そこに住み続ける以上近隣であることは変わりませんので、どうしても無視して通れないケースがあります。
問題を解決するための具体的な対処法を、以下に示します。
(1)自衛策をとれないか検討する
騒音が問題であれば、当事者は、次のような自衛策をとることが考えられます。
【騒音に悩んでいる側】
- ノイズキャンセリングのイヤホン
- 防音カーテン
【騒音を出さないように注意したい側】
- 椅子を引きずらない(椅子の足に防音用のカバーを付ける)
- 床に防音マットや絨毯を敷く
- 特に夜間は大きな音を出さないようにする
- 低重音は響くので夜間音楽を聴くときには音量に気を付ける
- 飛び跳ねない
- ドアやふすまは静かに閉める
(2)録音や録画で証拠を残す
「騒音など出していない」「気にしすぎだ」と反論されたときに、騒音の証拠があると有利です。
また、第三者に相談するときにも、証拠があれば、騒音の事実確認に役立ちます。
次のような様々な方法で、騒音が事実あることの証拠を残しましょう。
- 毎日日記を書いて騒音について記載する
- 録音する(録音機、録音方法・場所、録音者、録音日時なども記録を残す)
- 録画する(録画した機器、録画方法・場所、録画した者、録画した日時なども記録を残す)
- 同じ騒音で困っている人の証言
- 騒音について相談した人の証言
- 騒音で病気になったときは医師の診断書
- 騒音を聞いたら直ちに管理組合などに連絡し、第三者に騒音を聞いてもらう
裁判では、自分で測定した音のデータでは測定状況等が明確でなく、信用できないとされてしまうことがあります。
裁判まで見据えているときは、専門業者に騒音の測定を依頼した方がよいですが、費用が掛かります。訴訟で言い分が認められるのかどうか見通しを建てたうえで(必要であれば騒音の近隣トラブル問題を扱う弁護士に相談し)、慎重に検討しましょう。
(3)改善して欲しいと伝える
近隣トラブルの相手方と直接話ができるときには、直接改善して欲しいと伝える方法があります。
騒音を長い間我慢していると、体調を崩してしまったり、相手と話すときに感情的・攻撃的になってしまったりすることがあります。あまり長い間我慢せず、早めに伝える方がよいでしょう。
そのときには、感情的にならずになるべく冷静に下記のポイントを伝えるようにします。
- 音に悩んでいる事実
- 具体的な騒音について説明(時間帯、音の内容、音のする場所などわかる範囲で)
- 具体的に対応して欲しいこと(夜10時以降は音楽の音量を下げてほしいなど)
ただし、賃貸や分譲マンションに住んでいるときは、大家(管理会社)や管理組合に相談する方法もあります。
直接話し合うと、すぐに相手に伝えられる点はよいですが、感情的になって話し合いが決裂してしまうリスクもあります。共同生活の場で、直接話し合うことで決裂し、居住者同士敵対するのは望ましくありません。
大家(管理会社)や管理組合などから一般的に注意喚起してもらうなどの方法も検討しましょう。
近隣トラブルの相談先
近隣トラブルについては、次のような相談先があります。
(1)住所別の相談先
(1-1)賃貸の場合
大家や、管理会社に相談します。
騒音問題を大家や管理会社に伝え、改善を依頼します。
騒音が実際に発生していて悩んでいることを理解してもらうために、集めた証拠があれば、整理して示すとよいでしょう。
大家や管理会社が介入することで、問題解決がスムーズに進むことが期待されます。
(1-2)分譲の場合
管理組合に相談します。
このときも、騒音が実際に発生していて悩んでいることを理解してもらうために、集めた証拠があれば、整理して示すとよいでしょう。
管理組合は、一般的に、事実確認を行ったうえで、社会生活上受忍限度を超える騒音が発生しているときには、一般的な注意喚起や、個別に対象者に対して是正の依頼など、解決に繋がる対応を取ることになるでしょう。
(1-3)戸建ての場合
自治会や町内会に相談してみましょう。
このときも、騒音が実際に発生していて悩んでいることを理解してもらうために、集めた証拠があれば、整理して示すとよいでしょう。
以前の住民や、トラブルの相手方について、有意義な情報を聞けるかもしれません。
自治会が騒音問題を把握したら、一般的に、回覧板などで騒音について注意喚起をしてもらうなどで解決につながることもあります。
(2)警察
騒音や嫌がらせ行為については、警察に相談する事もできます。
もし、管理組合や大家などに相談しても解決しない場合には、警察に相談してみましょう。
警察に相談するときは、特にしっかりと証拠を準備して示せるようにしておくとよいでしょう。
警察は原則民事不介入ですが、口頭注意などしてくれることもあります。
警察が直接相手方に注意をしてくれれば、相手方も問題の大きさを自覚して対応するかもしれません。
もし、騒音などをやめてほしいと伝えた相手との関係が極めて悪化しており、脅されたりした場合には、躊躇せず相談しましょう。
ひどい騒音のために睡眠障害などを発症した場合、騒音を起こす行為が傷害罪として、犯罪となることもあります。
「これくらいで警察への相談はためらわれる」と感じるかもしれませんが、一度警察に相談してみると解決の糸口が見つかるかもしれません。
(3)弁護士
隣人トラブルに悩んでいる場合、そのような問題を扱っている弁護士に相談して法的なアドバイスや対応を求めることもできます。
例えば騒音問題で、騒音が社会生活上受任できる範囲を超えており、精神的苦痛を受けている場合には、損害賠償請求などができる可能性があります。
トラブルの証拠や診断書などを準備したうえで、相談するとよいでしょう。
【まとめ】
近隣トラブルは誰もが直面し得る問題ですが、適切な対処法と相談先を知ることで解決の糸口が見つかるかもしれません。
問題が深刻化する前に、早めの対処と相談を心掛けましょう。
1人で悩まず、早めに大家・管理会社や管理組合、自治会などに相談する事で、トラブルが大きくなることを防ぎ、解決に繋がる可能性があります。
この記事が、隣人トラブルで悩む方の安心で快適な生活を取り戻すきっかけになれば幸いです。