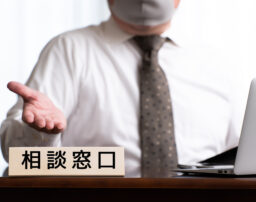働き方改革の大きな目的のひとつは、違法・不当な長時間労働の防止にあります。
そのために新しく導入ないし厳格化されたのが「時間外労働の上限規制」です。
上限規制とはどのようなものか、どういった場合に違反となるのか、そして規制超過の可能性がある場合にはどう対処すべきでしょうか。
違法・不当な長時間労働から自分の身を守るためにも、「時間外労働の上限規制」について、その内容・対処法などを十分に理解しておきましょう。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
自宅でらくらく「おうち相談」
「仕事が忙しくて時間がない」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
会社は、「時間外労働の上限規制」を超過して従業員を働かせてはいけない
まず、「時間外労働の上限規制」の概略について説明していきます。
(1)時間外労働の上限は、原則、月45時間・年360時間
労働基準法32条が定める法定労働時間(原則として「1日8時間・1週40時間」)を超える労働を「時間外労働」といいます。
また、同法35条が労働者への付与を使用者に義務付けている「1週間当たり1日もしくは4週間当たり4日」の休日のことを「法定休日」といい、法定休日に行う労働のことを「休日労働」と呼んでいます。
使用者が、労働者の代表との間で労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることによって、時間外労働や休日労働を労働者にさせることができるようになります。
もっとも、36協定の内容として定めることのできる時間外労働や休日労働には、法律上の上限規制が設けられています。
36協定で設定できる時間外労働の上限は、原則として、「月45時間・年360時間」とされています(労働基準法36条4項)。この上限規制は、大企業が2019年4月から、中小企業が2020年4月から適用されています。
参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(2)特別条項付き36協定を結べば時間外労働の上限を引き上げられるが、上限規制がある
36協定に「特別条項」を設けて締結している場合には、繁忙期やトラブル対応といった「臨時的な特別の事情」があれば、原則として「月45時間・年360時間」という時間外労働の上限規制を一定の範囲で引き上げることができます。
もっとも、臨時的な特別の事情があって特別条項に労使が合意する場合でも、以下のような上限規制は必ず守らなくてはなりません。
- 時間外労働は年720時間以内(労働基準法36条5項かっこ書き)
- 時間外労働及び休日労働の合計が、複数月(2~6ヶ月のすべて)平均で80時間以内(同法36条6項3号)
- 時間外労働及び休日労働の合計が、1ヶ月当たり100時間未満(同法36条6項2号)
- 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられるのは1年につき6ヶ月以内(同法36条5項かっこ書き)
これらの上限規制に違反した場合には、使用者に6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(同法119条)。
(3)一部の事業や業務に従事する労働者などは、例外的に「時間外労働の上限規制」の適用が猶予または除外されている
特定の事業や業務においては、時間外労働の上限規制が適用除外される、または改正法施行の5年後までの適用猶予が認められる場合があります。
【適用猶予・除外の事業・業務】
| 自動車運転の業務 | 2024年4月1日から、上限規制を適用します。 (ただし、適用後の上限時間は、年960時間とします。また、時間外労働・休日労働の合計について月100時間未満・2~6ヶ月平均80時間以内とする規制および時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月までとする規制は適用されません。) |
| 建設事業 | 2024年4月1日から、災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制を適用します。 (ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均80時間以内・1ヶ月100時間未満の要件は適用しません。) |
| 医師 | 2024年4月1日から、上限規制を適用します。 (ただし、一般的な医師の時間外労働・休日労働の上限は年960時間・月100時間未満(例外あり)とし、特定の医療機関については上限が年1860時間・月100時間未満(例外あり)とされます。) |
| 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 2024年4月1日から、上限規制を適用します。 |
| 新技術・新商品等の研究開発業務 | 医師の面接指導(※)、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しません。 ※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととします。 |
上記の表のとおり、「建設事業」「自転車運転の業務」「医師」「鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業」については、改正法施行後5年間(2024年3月末日まで)は適用が猶予され、「新技術・新商品等の研究開発業務」については適用除外となります。
また、「管理監督者」(労働基準法41条2号)に該当する場合には、労働時間・休憩・休日に関する労働基準法の規制が適用除外となり、使用者は時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払い義務を負いません(深夜労働に対する割増賃金の支払いは必要です)。
「管理監督者」とは、行政解釈によれば、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」のことをいうとされています。またそれは、名称や肩書き、就業規則の定めのいかんにとらわれず、実態に即して客観的に判断されるべきであるとされます。
これらに加えて、働き方改革関連法の施行(2019年4月1日)に伴う労働基準法改正によって導入された「高度プロフェッショナル制度」の適用者も、「時間外労働の上限規制」の適用除外となります(労働基準法41条の2)。
ただし、同制度の適用対象とされるには、年間賃金額1075万円以上などの厳格な要件をみたす必要があります。
労働時間が「時間外労働の上限規制」を超過していませんか?主なケースと対処法
まず、そもそも、「時間外・休日労働に関する労使協定」(いわゆる36協定)が締結・届出されていないにもかかわらず、使用者が労働者に時間外労働や休日労働を課すことは、労働基準法32条や35条に違反することとなります。
以下では、36協定を締結・届出していても、不適切な労働時間の管理や運営によって実態として「時間外労働の上限規制」を超過している場合があるため、そうしたケースの典型例や対処法について解説していきます。
(1)不適切な労働時間の管理運営によって、「時間外労働の上限規制」超過の可能性がある典型的なケース
不適切な労働時間の管理運営の典型例としては、以下に挙げたようなものがあります。
- サービス残業が常態化しており、適切な割増賃金の支払いがされていない
- 課長や部長などの肩書きが与えられているため「管理監督者」として扱われ、労働時間規制が除外されているが、職務権限、勤務態様、待遇などからみて管理監督者に相当する実態がなく、いわゆる「名ばかり管理職」である
- 変則的な労働時間制(フレックスタイム制、裁量労働制、変形労働時間制、みなし残業時間制(固定残業代制度))を導入しているとの理由で、「残業代は発生しない」ものとして扱われる
(2)「時間外労働の上限規制」超過の可能性があれば、弁護士や専門機関に相談しよう
会社が「時間外労働の上限規制」に違反している可能性があるにもかかわらず、個人で改善等の申し入れをしても応じてもらえない場合や、話がまとまらない場合の対処法としては、所轄の労働基準監督署に対して相談・申告を行うことが考えられます。
労働基準監督署は、全国各地に321署がある、厚生労働省の第一線機関です。
労働基準監督署の重要な役割としては、管轄内の会社(事業場)に労働基準法を遵守させることがあります。会社が労働基準法等に違反していると疑われる場合に、労働者からの申告や相談を受け付けます。そうした申告等に基づいて、会社(事業場)に立ち入り調査を行い、必要に応じて、是正勧告や再発防止、改善のための行政指導を行います。
参考:労働基準監督署の役割|厚生労働省
参考:全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
一方で、労働基準監督署は、個別の労働トラブルの解決を目的とした機関ではないため、何より個々のトラブルを解決したいという場合には、法務知識やノウハウを持ち合わせた弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
あるいは、法テラスのサポートダイヤルに問い合わせると、お悩みごとの解決に役に立つ法制度や相談窓口に関する情報の案内を受けることができます。
それ以外にも、以下のような公的な専門機関が相談窓口を設けています。
- 管轄の労働基準監督署や各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」
- 厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」
- 全国労働組合総連合(全労連)の「労働相談ホットライン」
- 日本労働組合総連合会(連合)の「なんでも労働相談ダイヤル」
(3)サービス残業等によって未払いの残業代があるなら、まず会社に請求しよう
未払いの残業代(割増賃金)がある場合には、一定期間であればさかのぼって請求することができます。
会社に対し、残業代が未払いになっているとして支払いを申し入れても取り合ってくれないような場合には、労働基準監督署に相談したり、訴訟を起こしたりして請求するのが現実的な対処法となるでしょう。
未払いの残業代の請求については、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
残業代の計算は複雑なものになりがちですし、会社との交渉や訴訟においては適切な証拠に基づいた十分な主張・立証をすることが求められます。
また、残業代請求権の消滅時効期間の確認や、消滅時効期間の更新・完成猶予といった時効完成を阻止するための法的手続きを依頼することもできます。
違法な時間外労働や未払いの割増賃金があるという事実を立証するためには、有効な証拠を集めることが非常に重要です。
弁護士に証拠収集についてのアドバイスや手助けを受けるなどして、まずは、違法な事実の証明につながる証拠を集めることを心がけましょう。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
なお、アディーレ法律事務所のウェブサイトには「残業代メーター」という請求可能な残業代を簡単に計算できるページがあります。
ただし、簡易的に計算するものであるため、実際の請求額とは異なることがあります。
【まとめ】「時間外労働の上限規制」超過の可能性がある場合は、労働基準監督署などの公的機関や弁護士にご相談ください
今回の記事のまとめは以下のとおりです。
- 使用者が労働者に時間外労働をさせる場合には36協定の適用及び届出が必要となりますが、協定の内容は時間外労働の上限規制に沿うものでなければなりません。「月45時間・年360時間」を原則とする上限規制は働き方改革の一環で厳格化され、臨時的な特別の事情があるとして特別条項付きの36協定を結んだ場合でも「年720時間以内」「月45時間を超えられるのは年6回まで」「休日労働との合計は月100時間未満かつ複数月平均がすべて80時間以内」という時間外労働の上限規制に服することになります。
- 時間外労働の上限規制に違反している疑いがあれば、証拠を揃えて労働基準監督署などの公的機関や弁護士に相談するのがおすすめです。
違法な長時間労働でお悩みの方や、未払いの残業代があって請求を検討している方は、残業代請求を扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。