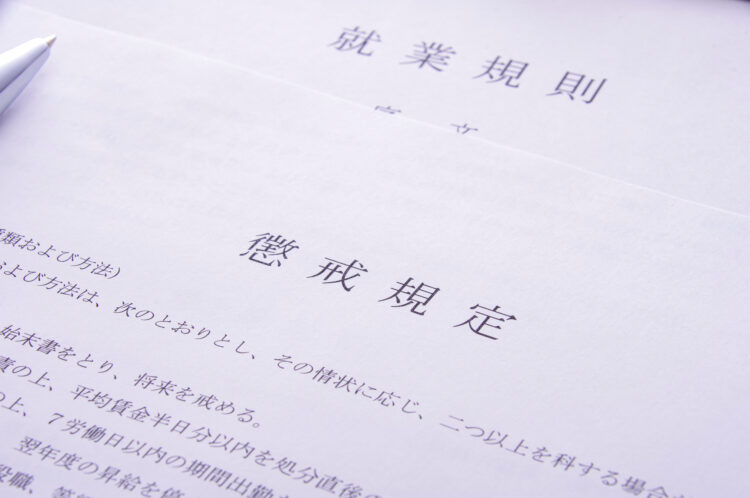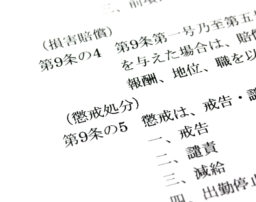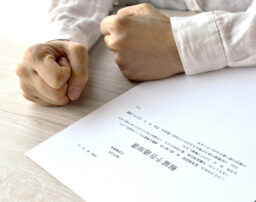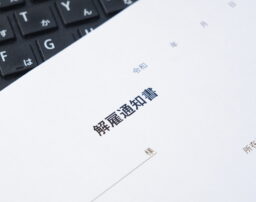突然の解雇通告。
「これって不当な解雇では?」そんな疑問や不安を抱えていませんか?
不当解雇から自身の権利を守り、職場復帰を果たすための方法が、「地位確認請求」です。
本記事では、不当解雇による地位確認請求の基礎知識から具体的な手順、さらには金銭的な解決まで、労働者が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
- 地位確認請求の基礎知識
- 地位確認請求の具体的手順
- 金銭的解決という方法
ここを押さえればOK!
解雇されたけれども、理由が分からない、理由に納得できないという場合、まず解雇理由証明書の交付を会社に請求し、具体的な理由を把握します。その後、交渉による解決を試みます。交渉が不調に終わった場合、労働審判または訴訟による地位確認請求を行います。
労働審判は迅速な解決を目指し、原則3回以内の期日で調停または審判が行われます。訴訟はより詳細な審理を行いますが、解決までに時間がかかります。
地位確認請求では職場復帰と未払い賃金の支払いを求めることができますが、労使関係の悪化や精神的負担を考慮し、金銭解決を選択する労働者も多くいます。
どちらの方法を選択するかは、個々の状況や目標によって異なります。職場環境、キャリアプラン、経済的必要性、精神的負担などを考慮して決定することが重要です。
不当解雇の可能性がある場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
地位確認請求とは?
地位確認請求とは、使用者から解雇された労働者が、解雇は違法で無効であり、労働者の地位を有することの確認を求める手続きです。
地位確認請求が裁判所に認められた場合、労働者は職場復帰が可能となるだけではなく、基本的に解雇以降の未払い賃金の支払いを請求することができます。そのため、解雇された労働者は、通常、地位確認請求にあわせて未払い賃金の支払いも求めます。
不当解雇を見分けるためのチェックポイント
日本では、使用者による解雇は自由に行うことができません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、権利の濫用として無効とされます(労働契約法第16条)。
よくある能力不足といった労働者側の事情を理由とする解雇の場合、次のような点を考慮して、解雇に客観的合理性があるのか、社会通念上相当であるといえるのか、を検討します。
- 労働者の能力不足を理由とする場合、その内容や程度、改善可能性の有無
- 労働契約上求められた能力があれば、その能力適正と現実との乖離
- 労働者の能力の向上の可能性
- 会社が解雇回避措置をとったかどうか
- 解雇の動機に不当な面がないか
- 解雇にあたり話し合いをしたか
- 他の従業員との均衡 など
これらのポイントを慎重に検討することで、自身の解雇が不当である可能性の程度についてある程度把握することができるでしょう。
ただし、不当解雇の可能性があるかどうかについて判断するためには、判例や他の法的要素についての知識が必要です。自己判断は避け、労働問題を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。
不当解雇が争われた事例
(1)不当解雇が無効とされた事例
平成24年10月5日東京地方裁判所判決の事案を簡易化して説明します。
勤務能力及び適格性の低下(所在不明や記事執筆のスピードが遅い、協力関係が構築できないなど)を理由として解雇された労働者が、不当解雇であるとして地位確認及び未払い賃金の支払いを求めた事案です。
裁判所は、次のように、勤務能力ないし適格性の低下を理由とする解雇において検討すべき事情について説明したうえで、解雇は無効であると判断しました。
「勤務能力ないし適格性の低下を理由とする解雇に「客観的に合理的な理由」(労働契約法16条)があるか否かについては、まず、当該労働契約上、当該労働者に求められている職務能力の内容を検討した上で、当該職務能力の低下が、当該労働契約の継続を期待することができない程に重大なものであるか否か、使用者側が当該労働者に改善矯正を促し、努力反省の機会を与えたのに改善がされなかったか否か、今後の指導による改善可能性の見込みの有無等の事情を総合考慮して決すべきである。」
そして、所在不明や記事執筆のスピードの遅さ、協力関係が構築できないなどの解雇理由を一つ一つ検討したうえで、労働契約の継続を期待することができない程に重大なものであるとまでは認められず、解雇は無効と判断しました。
(2)解雇が有効とされた事例
平成17年11月30日東京高等裁判所判決の事案を簡易化して説明します。
この事件では、労働者は、就業規則など従業員が守るべき複数のルールに反し、また許可を得てから行動するよう事前に注意されていたにもかかわらず、許可を得ることなく行動したことなどが問題となりました。
その結果、会社は謹慎処分を経て解雇を行いましたが、従業員は不服として、地位確認請求や賃金の支払いを求めて、会社を訴えました。
第1審は、懲戒解雇は無効と判断しましたが、控訴審は次のように判断し、第1審を覆して懲戒解雇を有効としました。
「エグゼクティブ・ディレクターという高い地位にある控訴人(注:解雇された労働者のこと、以下同じ)が、被控訴人(注:会社)の組織体としての検討や方針を離れ、その指揮命令に服することを拒否してこのような一連の行動に出ることにより、被控訴人の対外的信用も少なからず毀損されたものということができる。そして、指揮命令には服さないという控訴人の姿勢は明確かつ強固であるから、企業秩序維持の観点からは、控訴人をそのまま従業員として被控訴人の組織内にとどめることは困難であるといわなければならない。
したがって、それが退職金の不支給という効果をもたらすものであることを考慮に入れても、控訴人の非違行為に対する懲戒処分として懲戒解雇を選択することは相当であるというべきであり、これをもって懲戒権の濫用ということはできない。」
裁判所は、労働者が守るべきルールを一つ一つ検討し、それに違反したかどうか、違反の程度などを考慮したうえで、解雇が有効か無効かを判断しています。
解雇を争いたいときには、解雇理由証明書の交付請求を
「解雇されたけれども、理由がよくわからない」「会社の言っている解雇理由はおかしい、争いたい」という方は、会社が正式にどのような理由で解雇したのか把握するために、基本的には解雇日までの間に、会社に対して解雇理由証明書の発行を請求しましょう(解雇日以後も発行してくれる会社も多いので、解雇日後であってもあきらめずに請求してみるとよいでしょう)。
会社は、労働者が解雇理由証明書の発行を請求した場合には、遅滞なく発行する法的義務があります。
会社が自主的に発行するものではありませんので、必ず請求するようにしましょう。
解雇理由証明書には、具体的な解雇理由や、それが就業規則など特定のルールに違反することなどが記載されます。後で地位確認請求をするにあたって、その理由を事前に把握しておくことは大変重要です。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
自宅でらくらく「おうち相談」
「仕事が忙しくて時間がない」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
地位確認請求の具体的な手順
まずは、交渉で、話し合いによる解決を求めます。特に職場復帰を希望する場合、速やかに出勤していた頃の状態に戻った方がよいので、交渉での早期解決が重要になってきます。
交渉がうまくいかなかった場合の裁判手続きとしては、労働審判と訴訟の2つの方法があります。
労働審判は、原則最大3回の期日での解決を目指す手続きであり、迅速な解決が期待できますが、裁判所での話し合いがまとまらなかったり、審判に対して異議が申し立てられた場合、結局訴訟を行うことになってしまうため、自分にとってどちらの手続きがよいか、よく検討しましょう。
(1)労働審判による地位確認請求
労働審判は、労働者と使用者が直接裁判所に赴き、裁判所の進行に従いながら、主に話し合い(調停)での解決を目指す手続きです。
訴訟と異なり、手続きは非公開で行われます。場所も、通常の法廷ではなく、話しやすいラウンド型のテーブルが配置された審判廷で行うことが多いです。
早ければ初回期日で調停が成立します。2回目、3回目の期日での解決となった場合にも、初回期日から3ヶ月程度で手続が終わります。
話し合いで解決できなかった場合、裁判所が審判という判断を下します。
審判が最終判断というわけではなく、当事者が異議申し立てをすることで通常訴訟に移行しますが、多くは審判の段階で解決します。
労働審判の具体的な手順は以下の通りです。
- 労働審判申立前の当事者間交渉
- 当事者交渉決裂
- 労働審判申立書の作成と地方裁判所へ提出
o 原則3回の期日での解決が予定されているため、最初の段階で、相手側の主張や反論も踏まえて申立書を作成し、証拠を準備する必要がある - 原則申立から40日以内に第1回期日の指定
- 審理(原則3回以内)
- 調停又は審判
調停は話し合いによる解決、つまり妥協して着地点を探すことを目指します。したがって、会社側が、「職場復帰は認められないが、金銭的解決は可能」という態度をとることもあります。
参考:労働審判手続|裁判所
参考:労働審判規則|裁判所
(2) 訴訟による地位確認請求
労働審判での解決の可能性が低く、強い姿勢で地位確認を求める場合や、労働審判に不服がある場合は、地位確認請求訴訟を提起します。
訴訟は、より詳細な審理を通じて解決を目指す手続きです。
労働審判と異なり、回数制限がないため、解決までの期間は長くなります。第1審判決が出るまでに、1年以上かかることもよくあります。
その期間、給与は支払われませんので、雇用保険の失業給付などの手当を受けられるか確認するようにしましょう。手当を受けられる見込みがなく貯金もないという場合には、労働審判や訴訟の提起を前提とした地位保全と賃金仮払いの仮処分という手続きを検討します。
第1審判決で地位の確認が認められても、会社側が不服として控訴すればさらに裁判は続くことになります。
訴訟の手続きは通常以下の通りです。
- 訴状の作成と提出
- 裁判所による初回期日(口頭弁論)の指定
- 口頭弁論(複数回)
o 書面や証拠の提出
o 争点の整理
o 証拠調べなど - 和解勧奨
o 裁判所が和解案を示して和解を勧めることも - 和解又は判決
o 和解又は裁判所による判決
労働審判も訴訟も、法律や実務の運用の知識や書面作成スキルなどの能力が必要です。自分で対応することに不安がある人は、地位確認請求を扱っている弁護士への相談・依頼をお勧めします。
H2: 職場復帰と解決金による解決の比較
不当解雇に直面した際、労働者には主に、あくまで復職を望むのか、それとも退職は仕方ないが解決金の支払いを求めるのか、という2つの選択肢があります。
どちらを選ぶかは、個々の状況や目標によって異なります。
選択の際は、以下の点を考慮することが重要です。
- 職場環境や人間関係
:争いになった時点で労使関係が悪化しており、職場復帰よりも一定の解決金を得て再就職することを希望する労働者も多い。一方で、解雇を決定した上層部と労働者の就業場所が離れている場合など、引き続き職場復帰を目指す労働者もいる - キャリアプラン
:キャリアの継続を優先して今後も勤めるのか、再就職して新たなスタートを切るのかを考える - 経済的な必要性
:裁判手続きに至った場合、解決までに時間がかかる。生活のために転職活動が必要な人も。 - 精神的な負担
:会社側と解雇を争うとなると、労働者の人格を非難するような口頭・書面でのやり取りが行われることがあり、当初職場復帰を希望していても、途中で解決金による解決に変更する労働者も多い。一方で、職場復帰により自尊心を回復することを目指すという考え方もあるどちらを希望として優先するかは、弁護士と話し合って決めるとよいでしょう。
突然解雇をされてしまった場合、まずは金銭面や生活面でどうすればよいのか戸惑うことも多いと思いますが、そもそも解雇は有効なものなのか、使用者に何か請求できることはないのかという点も意識することが必要です。会社との交渉や裁判では、労働問題を扱っている弁護士に依頼してサポートを受けることが望ましいでしょう。
【まとめ】地位確認請求は、不当解雇から労働者の権利を守る重要な法的手段です
地位確認を求めることで、職場復帰や解雇期間中の賃金支払いを求めることができます。
地位確認を求めていても、途中で和解し、解決金の支払いなどで解決することも多いです。
「解雇されたけど、これって不当解雇かも?」と思ったら、不当解雇を扱っている弁護士に相談するようにしましょう。
アディーレ法律事務所では、不当解雇に関するご相談は、何度でも無料です(2024年11月時点)。
不当解雇でお悩みの方は、不当解雇を積極的に扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。