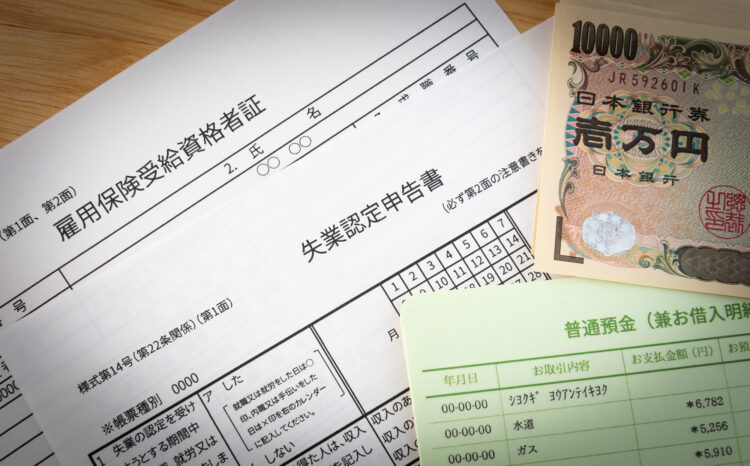雇用保険法等の一部を改正する法律が、2024年5月に成立しました。
改正内容のうちの多くが、2025年4月1日から施行されることとなっています(例外あり)。
雇用保険法の改正は、現代の労働市場の変化や社会的ニーズに対応するために行われました。
たとえば、パートタイム労働者や短時間労働者、フリーランスなど多様な働き方をする労働者が増加する中で、より多くの労働者が雇用保険の恩恵を受けられるようにすることなどを目的としています。
また、自己都合離職者の給付制限の見直しや、育児休業給付の拡充など、労働者が安心して働き続けるための環境整備が進められています。
この記事を読んでわかること
- 雇用保険法改正の背景と目的
- 雇用保険法の改正内容
この改正により、多様な働き方を選択できる環境が整い、労働市場の流動性が高まることなどが期待されているといえるでしょう。
ここを押さえればOK!
具体的な改正内容は次のとおりです。
(1)雇用保険の適用拡大
(2)自己都合離職者の給付制限の見直し
(3)育児休業給付の拡充
(4)その他雇用保険制度の見直し
雇用保険法改正の背景と目的
雇用保険法の改正は、現代の労働市場の変化や社会的なニーズに対応するために行われました。まずは、その背景と目的について解説します。
(1)労働市場の変化
近年、労働市場は大きな変化を遂げています。特に、非正規雇用の増加やフリーランス、ギグワーカーといった新しい働き方をする人が増えています。
これにより、従来の雇用保険制度ではカバーしきれない労働者が増加しているのが現状です。たとえば、パートタイム労働者や短時間労働者は、従来の雇用保険の適用範囲外であることが多くあり、これが社会的な問題となっていました。
こうした背景から、雇用保険の適用範囲を拡大し、より多くの労働者が安心して働ける環境を整えることが求められました。
(2)働き方改革の推進
政府は働き方改革を推進しており、その一環として雇用保険法の改正が行われた面もあります。
働き方改革の主な目的は、労働者が多様な働き方を選択できるようにすること、そして労働環境の改善を図ることです。具体的には、長時間労働の是正や、育児・介護と仕事の両立支援などが挙げられるでしょう。
これにより、労働者が安心して働ける環境を整えるとともに、企業にとっても労働力の確保が容易になることが期待されています。
(3)高齢化社会への対応
日本では急速に高齢化が進んでおり、高齢者の雇用促進が重要な課題となっています。
高齢者が働き続けるためには、雇用保険制度の充実が不可欠です。たとえば、高齢者向けの再就職支援や職業訓練の充実などが挙げられるでしょう。
また、高齢者が働きやすい環境を整えるために、企業側にも柔軟な働き方の導入が求められています。
これにより、高齢者が社会に貢献し続けることができるとともに、労働力不足の解消にもつながると期待されています。
雇用保険法の改正内容
では、今回の具体的な改正内容について見ていきましょう。
参照:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省
参照:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について|厚生労働省
(1)雇用保険の適用拡大
雇用保険法の改正により、雇用保険の適用範囲が大幅に拡大されました。
これまで適用外だったパートタイム労働者や短時間労働者も、新たに雇用保険の対象となります。
具体的には、改正前は週の所定労働時間が「20時間以上」だということが、雇用保険の被保険者となる要件のひとつだったのが、「10時間以上」に要件が緩和されました。
(この点について、2028年10月1日施行)
これにより、より多くの労働者が雇用保険の恩恵を受けられるようになり、安心して働ける環境が整えられることが期待されています。
(2)自己都合離職者の給付制限の見直し
雇用保険法の改正により、自己都合離職者に対する給付制限が見直されました。
これまで、自己都合で退職した場合、失業給付の支給開始までに原則2ヵ月の給付制限期間が設けられていましたが、1ヵ月に短縮されます。
ただし、5年間で3回以上、自己都合退職をしている場合は、給付制限期間を3ヵ月とすることになっています。
また、自己都合で退職した方が、自ら雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。
(この点について、2025年4月1日施行)
この改正は、自己都合での離職の多い現代の労働市場に対応するための措置であり、再就職活動を迅速に進めるための支援策といえるでしょう。
これにより、労働市場の流動性が高まることが期待されています。
(3)育児休業給付の拡充
雇用保険法の改正により、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保が目指されています。
具体的には、昨今の男性の育休取得増加に対応するため、育児休業給付を支える財政基盤を強化します。
内容は次のとおりです。
- 暫定措置として80分の1とされていた国庫負担割合を2024年度から8分の1まで引き上げ
- 保険料率は2025年度から0.5%に引き上げたうえ、実際の保険料率を状況に応じて弾力的に調整できる仕組みを導入
(4)その他雇用保険制度の見直し
雇用保険法の改正により、その他の雇用保険制度も見直しが行われました。
まず、教育訓練支援給付金(失業者が再就職のための教育訓練を受けながら生活できるようにするため生活費を支援する制度)について、令和7年3月31日までの暫定措置とされておりましたが、更に2年間延長されることになりました。もっとも、その給付率が、基本手当の80%から60%に引下げられます。
これまでの再就職活動の支援策としての効果を踏まえ検討された結果、上記のとおり教育訓練支援給付金の内容が見直されることになりました。
また、就業手当が廃止され、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げられます。
就業手当は、失業保険の受給資格者が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上 を残して就業をした場合で、 1年を超える期間の雇用が見込まれるとはいえない職業に就いた者に支給される手当です。
就業促進定着手当は、失業保険の受給者が早期に再就職し、再就職後6カ月間定着したものの、前職より再就職後の賃金が低下した者に対し、低下した賃金の6か月分が支給される手当です。
いずれも、より低い労働条件への転職支援となってしまい、より高い労働条件の雇用移動を促すとことにはならないということで、上記のとおり、見直されることになりました。
【まとめ】
雇用保険法が改正され、その多くが2025年4月1日から施行されます。
主な改正内容として、雇用保険の適用範囲の拡大、自己都合離職者の給付制限の見直し、育児休業給付の拡充などが挙げられます。
この改正は、パートタイム労働者やフリーランスなど、より多くの労働者が雇用保険の恩恵を受けられるようになることを目指しています。
また、労働者が安心して働き続けることができる環境が整えられ、企業にとっても労働力の確保が容易になることが期待されています。