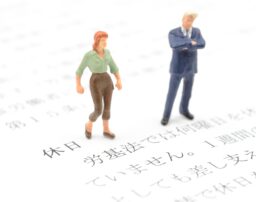「就業規則」
これは多くの労働者にとって聞き慣れない言葉かもしれません。
しかし、安心して働くためには非常に重要な役割を果たします。
特に、従業員が店舗や営業所などに常時10人以上いる会社には、就業規則の存在が法律で義務付けられていることをご存じでしょうか?
本記事では、就業規則がないことによる影響から、作成・周知の方法まで、あなたが知っておくべき情報をくわしく解説します。
この記事を読んでわかること
- 従業員が常時10人以上いる事業場がある会社は、就業規則がないと違法となる
- 就業規則がないと労働者にも会社にもデメリット・リスクがある
- 就業規則の作成には労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者からの意見聴取と労働基準監督署の提出が必要となる
- 就業規則を見せてくれない場合や就業規則がない場合には、労働基準監督署などの公的機関への相談がおすすめ
ここを押さえればOK!
就業規則には、労働条件や服務規律などを明確に記載し、労働組合や労働者代表からの意見を聴取し、労働基準監督署に提出する必要があります。
また、周知も義務で、掲示または備え付け、書面交付、デジタルデータを閲覧可能な状態にするなどのいずれかが求められます。
就業規則がない、または見せてもらえない場合は、労働基準監督署への相談がおすすめです。就業規則を整備し、安心して働ける職場環境を作ることが大切です。
就業規則がない会社は違法なの?
まず、就業規則がない会社が違法になる場合とならない場合について説明します。
(1)従業員が常時10人以上:違法
常時10人以上の労働者がいる使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています(労働基準法第89条)。
従業員が常時10人以上いる使用者が就業規則を作成しないことは、違法です。義務違反には30万円以下の罰金が科される可能性があります。
従業員常時10人以上とは
従業員常時10人以上とは、パート・アルバイトや非正規職員などを含めて通常10人以上いることをいいます(派遣先会社との関係では派遣社員を含まない)。一時的に10人未満になることがあっても、通常10人以上いれば、就業規則を作成する必要があります。
そして、従業員は事業場(営業所や店舗、工場、支店など)ごとにカウントします。
例えば、会社全体の従業員数が10人以上であっても、営業所や店舗ごとの従業員数が10人未満であれば就業規則を作成する必要はありません。
(2)従業員が10人未満:違法ではない
従業員が10人未満の場合、法律上、就業規則を作成する義務はありません。
しかし、就業規則をないと次に紹介するデメリットやリスクが発生する可能性がありますので、従業員数が10人未満であっても就業規則の作成をおすすめします。
就業規則がないとどうなるの?
就業規則がないと、労働者の権利が守られにくくなります。
例えば、労働者にとって、次のようなデメリットやリスクがあるでしょう。
- 労働条件の不明確さ: 労働時間や賃金、休暇制度が曖昧であると、労働者の権利が侵害される恐れがある
- トラブルの増加: 労働条件が明文化されていないため、トラブルが発生しやすくなる
一方、就業規則がないと、会社にも次のようなデメリットやリスクがあります。
- 服務規律を明確にできない:従業員が守るべきルールが曖昧だと、従業員が混乱する可能性がある
- 問題のある社員を懲戒処分できない: 懲戒処分は就業規則に従う必要があるため、就業規則がないと懲戒処分できない
- 定年退職の制度を使えない:雇用契約に定年制度を定めなかった場合、就業規則に定年制度を定めないと定年制度を使うことができない
- 政府からの助成金をもらえない:就業規則が助成金の条件となっていることもあり、就業規則がないと助成金がもらえない可能性がある
就業規則は安心して働ける職場環境を整えるための基本です。労働者にとっても会社にとっても就業規則の整備は必要不可欠です。
就業規則の作成と周知の方法とは?
次に、就業規則の作成と周知方法について説明します。
(1)就業規則に記載すべきこと
就業規則には、労働条件を明確にするための情報が含まれます。これにより、安心して働ける職場環境が整います。
(1-1)必ず就業規則に入れなければならない事項
必ず就業規則に入れなければならない事項(絶対的必要記載事項)について挙げます。
- 始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
- 交代労働制の場合には、就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項
(1-2)相対的記載事項
次に、制度として定める場合、必ず就業規則に入れなければならない事項(相対的必要記載事項)について挙げます。
- 退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払い方法、支払時期)
- 臨時の賃金と最低賃金額に関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰や制裁に関する事項
(1-3)任意記載事項
絶対的必要記載事項、相対的記載事項のほかにも、就業規則にさまざまなことを、任意に記載することができます。
- 企業の理念
- 社内規則
- 福利厚生 など
(2)労働基準監督署への届出手順
まず、就業規則を作成し、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者からの意見を聴取します。その後、意見書を添付して労働基準監督署に提出します。
(3)就業規則を周知する方法
就業規則は従業員に周知される必要があります。
方法としては、次の手段が考えられます。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示、備え付ける
- 書面を交付する
- デジタルデータとして記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常に確認できる機器(コンピューターなど)を設置する
口頭説明のみでは周知義務を満たしているとはいえません。
就業規則に関するよくある質問
最後に、就業規則に関してよくある質問についてQ&A方式で回答します。
(1)Q就業規則を見せてもらえない場合や就業規則がない場合はどうしたらいい?
就業規則がない・閲覧できない会社でトラブルに巻き込まれたときには、労働基準監督署などの公的機関に相談することがおすすめです。
労働基準監督署に相談すると、会社に対し是正指導・勧告をしてくれることがあります。
(2)Q就業規則がなくても、労働者は権利を主張できる?
就業規則がなくても、労働基準法や労働契約に基づき労働者の権利は守られます。例えば、労働時間や賃金については法律が最低基準を定めています。したがって、就業規則がなくても基本的な権利を主張することは可能です。
ただし、具体的な取り決めがないとトラブルが生じる可能性があるため、就業規則の整備は重要です。
(3)Q就業規則が作成されていても届出されていなかった場合どうなる?
就業規則が作成されても労働基準監督署に届出されていない場合、その効力は制限される可能性があります。届出は法的義務であり、これを怠ると労働者との間でトラブルが発生した際に不利になることがあります。
ただし、労働基準監督署に届け出ていない就業規則も、社内で周知されていれば就業規則としての効力が認められる可能性が高いでしょう。
(4)Q就業規則が勝手に変更された場合、その就業規則は有効?
就業規則を変更する場合も、作成の時と同様に、労働者の意見聴取+労働基準監督署への届け出+労働者への周知の手続が必要です。勝手に変更された場合、その変更は無効となる可能性があります。
【まとめ】就業規則がないと労働者や会社にデメリット|公的機関に相談を
就業規則は、常時10人以上の従業員が事業場にいる会社では、法律で作成が義務付けられています。就業規則がないと、労働条件の不明確さやトラブルの増加といったリスクが生じます。就業規則の作成には労働者の意見聴取と労働基準監督署への届け出が必要です。
まずは就業規則を確認し、必要なら労働基準監督署に相談して、安心して働ける環境を築きましょう。