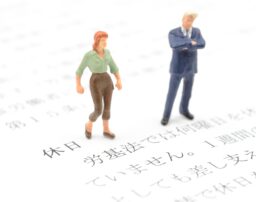あなたが働く会社の年間休日は100日以下ですか?
もしそうなら、法律違反の可能性があるかもしれません。
本記事では、年間休日100日以下の労働環境における法的問題と、労働者が取るべき対処法などを詳しく解説します。
ワークライフバランスの改善や労働条件の向上を目指す方は、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでわかること
- 休日とは
- 休日の種類
- 年間休日100日以下は違法の可能性があること
- 日本企業の年間休日の平均
- 年間休日100日以下の会社で悩んでいるときの対処法
ここを押さえればOK!
労働基準法では、週1日以上または4週で4日以上の休日を与えることが義務付けられており、年間最低52-53日の休日が必要となります。
また、1日8時間、週40時間を超える労働を原則禁止しているため、結果として、年間休日は105日程度が適切とされます。
日本企業の平均年間休日数は約107日で、100日以下の企業は13.2%と少数派です(令和5年度)。
年間休日100日以下の労働環境で、休日が少ない分の割増賃金が支払われていない場合、賃金不払いとして労働基準法違反となる可能性があります。
この問題に対する対処法として、労働基準監督署への相談と是正勧告の活用、労働組合への相談、弁護士への相談、転職があります。
自身の状況に応じて相談先を選ぶようにしましょう。また、未払い残業代があって転職を考える場合は、残業代発生の証拠を集めてから行動することが望ましいです。
「休日」の定義と種類
労働基準法における「休日」とは、労働者が労働契約上、労働義務のない日を指します。
労働者に休日労働を行わせた場合には、割増賃金を支払ったり代わりの休日を取得させたりする必要があります。
休日には、以下の4つの種類があります。
- 法定休日:毎週少なくとも1日もしくは4週を通じて4日以上の休日が必要
- 法定外休日:法定休日とは別に、会社が定めた休日
- 振替休日:前もって休日を労働日とする代わりに、別の労働日に定める休日(休日出勤は割増賃金の対象ではない)
- 代休:休日に労働した代わりに事後に別の日に定めた休日(休日出勤は割増賃金の対象になる)
年間休日100日以下の問題点
年間休日100日以下の労働環境は、労働基準法違反の可能性が高いです。
労働基準法35条では、使用者は労働者に週1日以上又は4週を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めています。
この決まりによれば、1年間の週数は52.1週(365日÷7日)なので、年間最低52日から53日の休日が必要となります。
しかし、労働基準法32条では、1日8時間、週40時間を超える労働を原則として禁止しているため、1日の労働時間が8時間の場合、1年に働ける日数は260日です。
したがって、この場合、基本給で労働者を働かせることができるのは、年260日程度に限られるので、年間休日は105日程度になります。
つまり、年間休日100日以下の労働環境で、休日が少ない分の割増賃金が支払われていないときは、賃金不払いとして労働基準法違反の可能性があるのです。
36協定を締結している場合の例外
36協定を締結している場合には、1日8時間以上、週40時間以上働かせることができますが、それでも原則1ケ月45時間及び1年360時間が限度です。
特別条項付きの36協定の場合、それ以上働かせることができますが、上限は1ケ月100時間未満かつ2ケ月ないし6ケ月平均で80時間以内、1年720時間以内、月45時間を超えることができる月は1年のうち6ケ月以内となっています。
36協定を締結していても、上限を超えて働かせたり、割増賃金を払わなかったりするのは労働基準法違反で違法です。
日本企業の平均年間休日
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、日本企業の平均年間休日数は約107日です。この平均と比較すると、年間休日100日以下の企業は明らかに少ない休日数であることがわかります。
【年間休日数の分布】
- 69日以下:1.9%
- 70~79日:1.6%
- 80~89日:3.5%
- 90~99日:6.2%
- 100~109日:31.4%
- 110~119日:21.1%
- 120~129日:32.4%
- 130日以上:1.7%
この調査から、年間休日100日に満たない企業は13.2%であり、少数派であることがわかります。
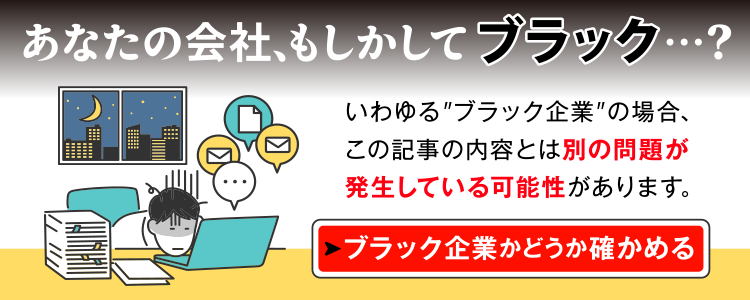
年間休日100日以下の労働環境改善のための対処法
年間休日100日以下の労働環境を改善する対処法として、4つ紹介します。
(1)労働基準監督署への相談と是正勧告の活用
労働基準監督署は、企業が労働基準法などの法令に違反していないかを監督する公的機関です。
年間休日100日以下で、1日8時間週40時間を超える労働に対して残業代が払われていない、休日出勤の割増賃金が払われていないなどの事情がある場合には、労働基準法違反の可能性が高いです。
労働基準監督署は、労働者からの労働問題に関する相談を受け付けており、アドバイスをもらえることがあります。また、実際に企業が法律違反を行っていた場合には、是正指導を行うこともあります。
労働者が労働基準法違反の事実を労働基準監督署に相談したからといって、企業は解雇その他不利益な取り扱いをすることはできません。
(2)労働組合に相談
労働組合に加入している場合、労働組合に相談する方法もあります。労働組合による交渉は、集団的な力を活用して労働条件の改善を図る方法です。
36協定の協定や就業規則の変更、残業代が支払われていない場合、年間休日の増加を目指したい場合などで、労使間交渉を行うことができます。
(3)弁護士に相談
1日8時間、週40時間を超える労働を行っているのに残業代が支給されない場合や、休日労働を行っているのに割増賃金が支払われない場合などでは、未払い給与を請求することができます。
自分で人事部門などに支払いを請求することもできますが、それでも解決しない場合には、労働問題を扱っている弁護士に相談する方法があります。
弁護士に相談することで、法的な観点から問題を整理し、具体的ケースに応じた適切なアドバイスを受けることができるでしょう。
(4)転職する
労働環境の悪い職場から、心機一転転職することも有力な対処法です。
実際に、残業代が支払われない職場に対して、退職に合わせてそれまでの未払い残業代を請求する人は多いです。
自分の労働力が搾取されていることに甘んじる必要はありません。
転職する際には、残業代が発生している証拠(タイムカードのコピー、ウェブ打刻のスクリーンショット、雇用契約書、就業規則など)を集めてから辞めるとよいでしょう。
【まとめ】年間休日100日以下の労働環境は、労働基準法違反の可能性あり
時間外労働を行っているのに残業代が支払われない場合などでは、自分で人事部門と交渉したり、労働基準監督署や労働問題を扱っている弁護士に相談して解決を目指すとよいでしょう。