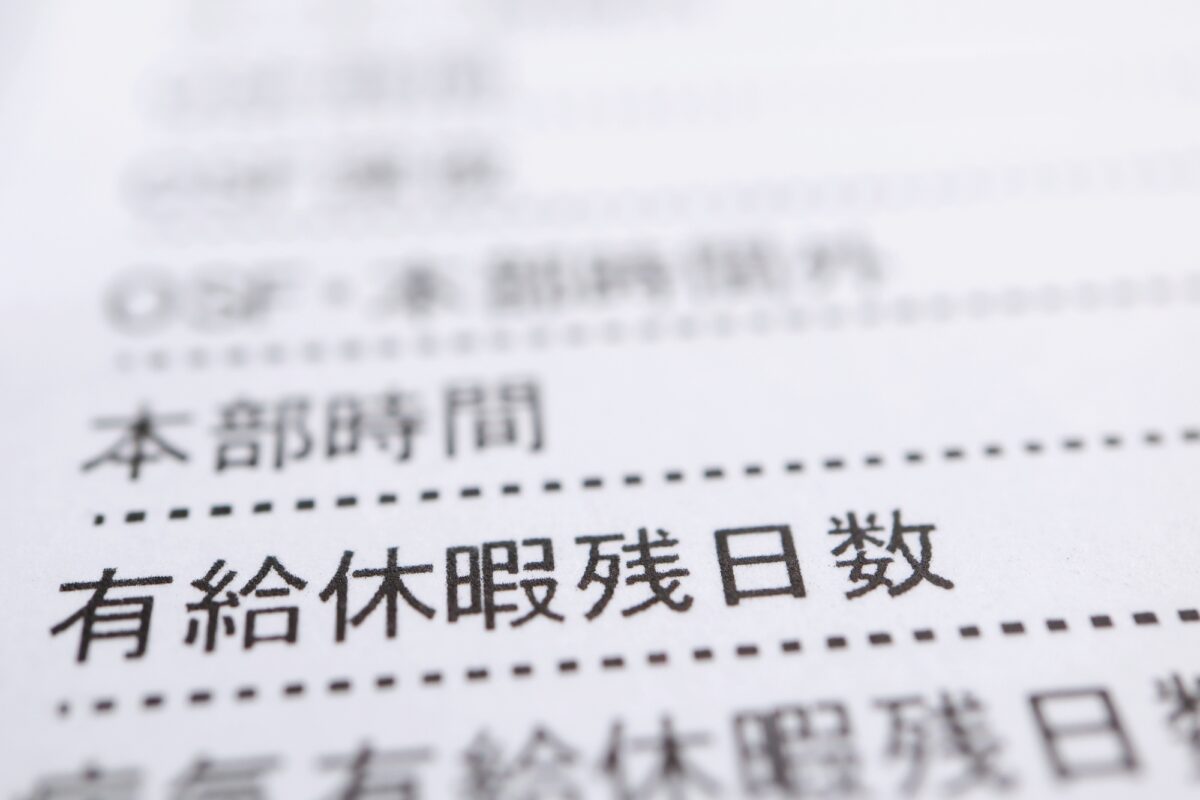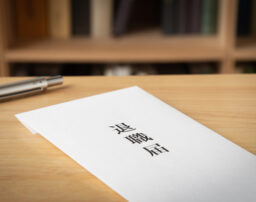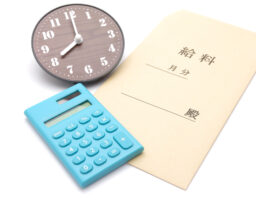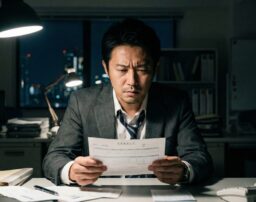退職を決意したあなた、残った有給休暇はどうするつもりですか?
「せっかくだから全部消化したい。」
「でも会社に迷惑をかけたくない。」
「そもそも取得を拒否されたらどうしよう。」
そんな不安や疑問を抱えていませんか?
この記事では、退職時の有給消化の法的根拠から具体的な申請方法、さらには取得拒否された場合の対処法まで解説していますので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 有給とは
- 有給取得の方法
- 有給取得を拒否されたときの対処法
ここを押さえればOK!
1. 残有給日数を正確に把握する
2. 退職日と有給消化期間を設定する
3. 適切な業務引継ぎを行う
早めに退職と有給取得の意思を明確に伝えましょう。
有給取得を拒否された場合は、冷静に、法律上有給取得が可能であることを伝えて交渉します。必要に応じて労働基準監督署や弁護士への相談も検討します。
有給買取りは原則違法ですが、退職時の未消化分については例外的に認められると考えられています。
円満退職のためには、会社側とのコミュニケーションを大切にしながら、計画的に有給を消化することが重要です。退職させてもらえない、有給を取得させてもらえないなどお困りの方は、一度退職代行を扱っている弁護士にご相談ください。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
退職時の有給消化は原則労働者の自由
有給休暇は、次の2つの条件を満たしている労働者に認められています(労働基準法39条1項)。
- 雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務している
- 全労働日の8割以上出勤していること
この条件を満たしている労働者であれば、正規雇用・非正規雇用ともに有給休暇を取得できます。
有給休暇は、基本的に労働者が希望する時期に取得することができ、これは退職時でも変わりません(労働基準法39条5項)。
例えば3週間後が退職予定日で、10日有給が残っていれば、基本的にすべて取得することができます。ただし、3週間後が退職予定日で、20日有給が残っている場合には、退職日まですべて有給取得したとしても有給が残ってしまうので(週休2日で計算)、残った有給は取得できません。
(1)会社は有給取得時季を変更するよう請求できる
会社は、労働者の希望通りに有給を取得させると、「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ、労働者に有給取得の時季の変更を求めることができます。
これを「時季変更権」といいます(労働基準法39条5項但書)。
ただし、時季変更権の行使が認められるのは、同じ日に多くの労働者が同時に有給取得を希望した場合などに限られます。単に「忙しくて休んでほしくないから」という理由だけでは、時季変更権は行使できません。
また、退職予定日が決まっているのに、会社が時季変更権を行使して退職予定後に有給取得をするよう請求することはできません。
退職時の有給消化は原則労働者の自由ですし、有給取得期間は次のキャリアへの準備期間としても活用できる貴重な機会です。
そのために、退職時の有給取得は、会社側と十分なコミュニケーションを取ったうえで、計画的に取得するようにしましょう。
(2)有給取得可能日数の計算方法
通常の1年の有給休暇の日数は次の通りです。
【1年の有給休暇の日数の計算方法】
- 雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日付与
- 以降、1年ごとに勤続年数に応じて付与日数が増加
- 最大20日まで付与(勤続6年6ヶ月以上)
【具体例】
- 勤続6ヶ月:10日
- 勤続1年6ヶ月:11日
- 勤続2年6ヶ月:12日
- 勤続3年6ヶ月:14日
- 勤続4年6ヶ月:16日
- 勤続5年6ヶ月:18日
- 勤続6年6ヶ月以上:20日
週所定労働日数4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者は、有給休暇の日数は上記よりも少なくなるので注意してください。
参考:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
退職前の有給消化計画:スムーズな取得のための3ステップ
退職前の有給消化を円滑に進めるには、計画的なアプローチが不可欠です。以下の3ステップを踏むことで、会社との良好な関係を維持しつつ、自身の有給を適切に消化できるでしょう。
- 残有給日数の正確な把握
- 退職日と有給消化期間の戦略的な設定
- 効果的な業務引継ぎ計画の立案と実行
以下、詳しく説明します。
STEP1:残有給日数の正確な把握方法
残有給日数を正確に把握することは、有給消化計画の第一歩です。以下の手順で確認しましょう。
- 人事部門への確認
- 現在の有給休暇残日数を書面で確認
- 退職日までに新たに付与される日数も確認
- 自己管理記録との照合
- 自身で記録している有給取得履歴と照合
- 差異がある場合は人事部門に確認
- 時効の確認
- 付与から2年を経過した有給休暇は失効
有給は、法律上の要件を満たせば必ず発生するものであり、会社は労働者に法律上定められた日数の有給を与える義務があります。
使用者は労働者の有給休暇の取得状況を把握しているはずですので、何日残っているかわからない場合には、人事部門などに問い合わせてみましょう。
STEP2:退職日と有給消化期間の戦略的な設定
退職日と有給消化期間を戦略的に設定することで、円満な退職と十分な休養時間の確保を両立できるかもしれません。以下のポイントを考慮しましょう。
- できれば業務の繁忙期を避ける
- 会社のスケジュールを確認し、繁忙期を避けて設定
- 可能であれば、閑散期に有給消化を集中
- 長期休暇と組み合わせる
- ゴールデンウィークや年末年始と組み合わせて効率的に消化
- 段階的な消化も検討
- 一括消化が難しい場合、週1〜2日ずつ段階的に消化
- 業務の引継ぎも行う
- 退職日の設定
- 残っている有給消化の最終日を退職日に設定
基本的に、有給は労働者が自由に取得できるものですので、退職までにすべての有給を消化したいところです。
退職予定日から逆算して、どのように有給を取得すべきか戦略的に考えるとよいでしょう。
STEP3: 業務引継ぎ計画の立案と実行
効果的な業務引継ぎは、円満な退職のために必要です。自分だけしか業務の内容を知らないなどの事情がある場合には、可能な限り引継ぎを行って退職すると、円満退職に繋がります。引継ぎは、以下の手順を参考にしてください。
- 引継ぎ書類の作成
- 業務マニュアルの整備
- 進行中のプロジェクトの状況整理
- 重要な連絡先リストの作成
- 引継ぎスケジュールの設定
- 有給消化を考慮したうえで十分な引継ぎ期間を確保
- 後任者が決まっている場合は、直接引継ぎの時間を設定
- 段階的な引継ぎの実施
- 重要度や緊急度に応じて優先順位をつける
- 日常業務から順に引継ぎ、最後に特殊なケースや注意点を説明
適切な業務引継ぎを行うことで、会社の業務に支障をきたすことなく有給消化が可能になるでしょう。丁寧な引継ぎは、円満退職に繋がりますし、将来的なキャリアにも良い影響を与えることでしょう。
有給消化の具体的な申請方法
有給消化の申請方法は、勤め先の就業規則などに「2週間前までに申し出る」などと定められていることが多いです。
基本的には、勤め先のルールに従って申請しますが、一般的に次のようなポイントを押さえておくと、トラブルを回避し、円満な退職に繋がることでしょう。
- 早めの意思表示
- 退職の意向を決めたら、できるだけ早く上司・人事部門に伝える
- 「〇月〇日までに、〇日の有給休暇をまとめて取得したいと考えています」など、有給消化の具体的な希望も同時に伝える
- 明確かつ丁寧な説明
- 感情的にならず、冷静に対話を進める
- 柔軟な姿勢
- 会社側の事情も考慮し、妥協案を用意する
- 例:有給の一括消化がどうしても難しい場合、分割取得を提案
正社員だと期間の定めのない雇用契約であることが多いですが、その場合は、法律上、2週間前までに退職の意思を伝えれば退職することが可能です。ただし、就業規則では「1ヶ月前までに退職を申し出る」と定められていたり、業務の引き継が必要だったりもしますので、早めに退職の意思を伝えて退職の準備をした方が、円満退職しやすいでしょう。
有給消化を拒否された場合の対処法
残念ながら、会社に退職の意思を伝えたところ、引き止められたうえで、「辞めるなら有給取得は認めない」など、退職時の有給取得を拒否されることもあります。
そのような場合、以下のポイントを参考に、有給取得できるよう交渉してみましょう。
- 冷静な対応
- 感情的にならず、事実関係を整理する
- 拒否の理由を明確に確認する
- 有給取得の根拠を確認
- 有給取得は基本的に労働者の自由であること(労働基準法39条)を理解する
- 有給取得に関する会社の就業規則や労使協定を確認する
- 段階的な交渉
- まずは直属の上司と話し合う
- 解決しない場合、人事部門や上級管理職に相談
- 妥協案の提示
- 分割取得や時期の変更など、柔軟な提案を行う
- 業務への影響を最小限に抑える方法を提案
- 書面での記録
- メールや書面でのやり取りを心がける
- 外部機関への相談
- 労働組合がある場合は相談する
- 必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談
これらの手順を踏むことで、会社が、基本的に有給取得は労働者の自由であることを理解できれば、多くの場合は有給を取得することができるでしょう。
ただ、退職を告げることや、有給取得について会社と交渉すること自体ストレスだと感じるかもしれません。
そのような場合には、弁護士が行っている退職代行サービスの利用を検討ください。
契約内容にもよりますが、退職の意思を伝えることに加えて、有給取得の交渉などを行ってもらえるケースがあります。
有給買取りの可能性と注意点
有給休暇の買取りは、原則違法だと考えられています。
有給休暇の買取りを認めれば、労働者が休めなくなりますので、労働者に有給休暇を与えることを定めた労働基準法39条1項の趣旨に反するからです。
しかし、例外的に、退職日までに有給休暇を消化しきれなかった場合などでは適法だと考えられています。
ただし、会社側に有給休暇を買い取る義務はありませんので、買い取りが難しいようであれば、通常通り退職日までに有給消化できるようスケジュールを検討しましょう。
【まとめ】有給消化は原則労働者の自由!計画的な有給消化で円満退職を
退職時の有給消化は、原則労働者の自由です。
ただし、会社側の事情にも配慮して、早めに退職・有給取得の意思を伝えて引継ぎなどを行うと、円満退職しやすいでしょう。
もし、「退職したいけど退職させてくれない」「退職したいと伝えたら有給取得を拒否された」などお悩みの方は、1人で悩まず、一度弁護士にご相談ください。
法律事務所が行っている退職代行サービスを利用すると、契約内容にもよりますが、弁護士があなたの代わりに退職の意思を伝えるだけでなく、有給取得の交渉なども行うことができます。
アディーレ法律事務所では退職代行に関するご相談は何度でも無料です(2025年1月時点)。
「辞めたいのに自分では言いにくい」とお悩みの方は、退職代行を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。