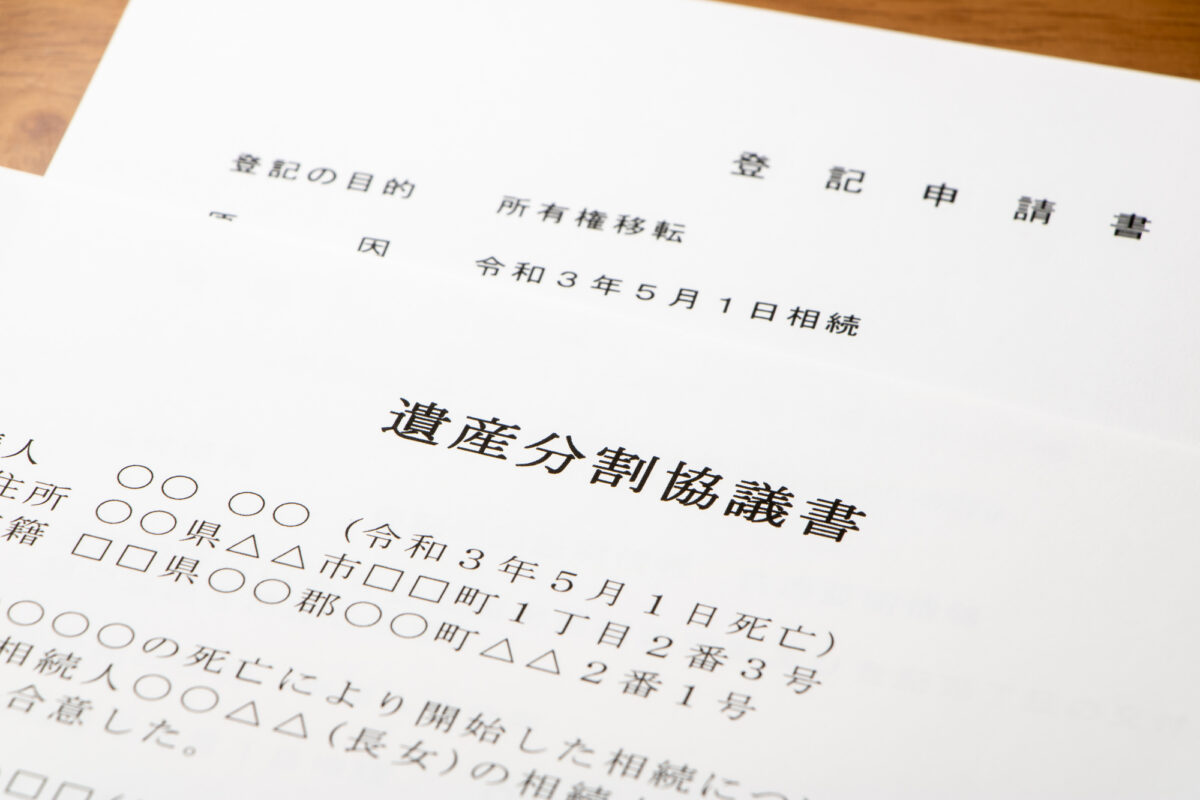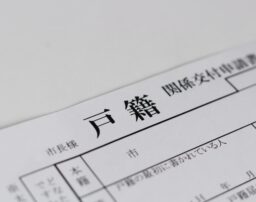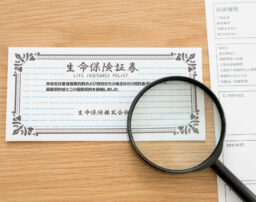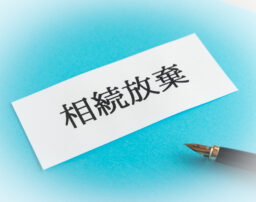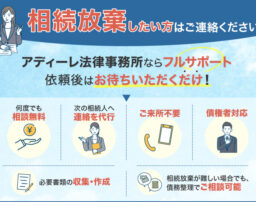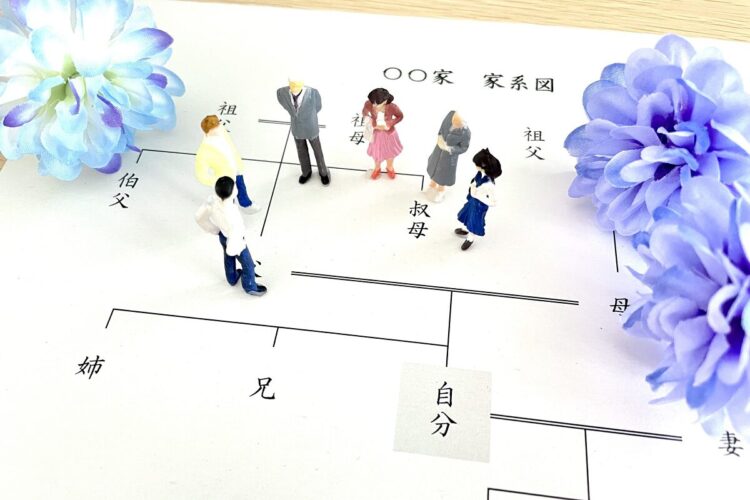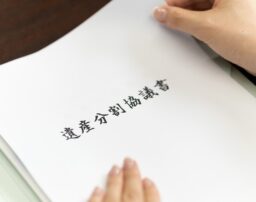相続人が、遺産の分け方を話し合って合意したら、通常「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書を作成すると、遺産分割の合意内容を明確にして、亡くなった方の預金を引き出したり、相続した不動産の登記名義を変更したりする場面で活用できます。
この記事を読んでわかること
- 遺産分割協議書の作成手順
- 遺産分割協議書の使いどころ
- 自作のメリットとデメリット
ここを押さえればOK!
次に、相続財産を調査し、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて全てリストアップします。
相続を希望しない場合は相続放棄の手続きを行います。
そして、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意を得たら遺産分割協議書を作成し、署名・押印します。協議書には被相続人の情報、相続人全員が協議を行ったこと、相続財産の詳細、後日発見された財産の取り扱い、作成日、作成通数、相続人全員の情報を記載し、署名押印、契印と割印をします。
遺産分割協議書は預貯金の払い戻し、有価証券や自動車、不動産の名義変更、相続税の申告などの相続手続きで提出が必要です。
自分で作成するメリットは主に費用の節約ですが、デメリットとして法律知識が不足していると無効な協議書を作成するリスクがあります。話し合いが進まない場合や手続きが煩雑だと感じた場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。
自分で遺産分割協議書を作成する流れ
亡くなった方の法定相続人は、遺産をどのように分け合うのか話し合う必要があります。
この話し合いのことを、「遺産分割協議」と言います。
協議した内容を書面にしたものを、「遺産分割協議書」と言います。
遺産分割協議や協議書の作成は、弁護士に依頼して代理で行ってもらうこともできますが、自分で行うこともできます。
自分で遺産分割協議書を作成する場合の流れについて、順に説明します。
(1) 遺言書があるかどうか確認
まず、亡くなった方=被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。
法的に有効な遺言書が存在する場合、基本的に、遺産はその遺言書の内容に従って、相続人に分割されることになるためです。
遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書の探し方や、遺言書があった場合の相続手続きについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)法定相続人は誰か調査して確定
遺言書がない場合、法定相続人全員で話し合って遺産分割をする必要があります。
そこで、法定相続人を確定するために、相続人の調査をします。
法定相続人の調査は、亡くなった方の戸籍を死亡時から出生までさかのぼって取得して行います。
法定相続人には、配偶者、子などが含まれます。
特に、法定相続人が多い場合や複雑な家族構成の場合は、調査だけでも時間と労力がかかります。労力や時間を節約して遺産分割協議をしたい人は、弁護士に相談・依頼することを検討しましょう。
相続手続きに必要な戸籍の取得方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)相続財産の調査
法定相続人の調査と同時並行で、相続する遺産を調査します。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)を含めてすべて調査していきます。
不動産、預貯金、有価証券、動産など、全ての財産をリストアップし、その評価額を確認します。
この作業により、相続財産の全体像を正確に把握します。
財産別の遺産の調査方法について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
ただし、遺産には、遺産分割の対象になるものとならないもの、合意により対象にできるものがあることに注意が必要です。
例えば、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産となりますので、遺産分割の対象とはなりません。
生命保険金について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
(4)相続したくなければ相続放棄
自身が法定相続人だとしても、相続したくなければ、相続放棄という方法があります。
相続放棄をすれば、相続人でなかったことになりますので、プラスの遺産もマイナスの遺産も、一切相続しません。
相続放棄の手続は、可能な期間や、してはいけないことなどの注意点があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(5)法定相続人全員で、遺産分割協議
法定相続人を確定し、遺産の調査が終了したら、全員で遺産分割協議を行います。
全員が納得する形での分割方法を話し合い、合意を得ます。
協議の際には、感情的な対立を避けるために冷静な話し合いを心掛けることが重要です。
しかし、率先して取りまとめる人がいないと、なかなか遺産分割協議が進まないことも多いです。
遺産分割協議が進まない場合には、弁護士に依頼し、代理人として協議に参加してもらい、積極的に進めてもらうこともできます。
いつまでに遺産分割協議を成立させればよいか
法律上、遺産分割協議を成立させる期限について、決まりはありません。
しかし、確定申告を必要とする人が亡くなると、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、相続人が代わりに所得税の申告を行わなければなりません(準確定申告)。
また、一定以上の資産がある場合には、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告・納付を行う必要があります。
相続税の申告・納付が必要な場合、期限を過ぎると加算税や延滞税が課されます。
税の申告が不要であっても、協議が長引くと相続人が亡くなり、分割協議に参加する相続人が増えたりして、手続きが煩雑になるリスクがあります。
さらに、10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分ではなく、法定相続分等画一的に行うことになります(ただし相続人全員の合意があれば別)。
話し合いを長引かせると、さらに相続が発生したりして法定相続人が増え、話し合いが困難になることがあります。10ケ月程度の合意成立を目安に進めると良いかもしれません。
複雑で面倒な相続手続きは、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
(6)全員の合意取得
法定相続人全員で、遺産分割協議の合意をします。
法律で法定相続分が定められていますので、その相続分を基準に話し合えば、感情的な対立も少ないかもしれません。
合意により、法定相続分と異なる相続分と定めることも可能です。
しかし、1人でも反対すれば、遺産分割協議は成立しません。
話し合いでまとまらない場合には、どうすべきでしょうか。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、第三者である調停員仲介の下、さらに話し合いでの合意を目指します。
調停で合意できるケースもありますし、できない場合には審判に移行して、裁判所は相続分や分割方法などを決定して審判を行います。
(7)遺産分割協議書を作成して署名・押印
全員の合意が得られたら、合意した内容で遺産分割協議書を作成します。
相続人全員が内容を確認したうえで、署名・押印します。
また、押印した印鑑についての印鑑証明書を取得し、協議書に添付します。
どのような内容を記載すべきかについては、次で詳しく説明します。
遺産分割協議書に必要な記載事項と注意点
遺産分割協議書には、一般的に、以下の事項を記載します。各項目について詳しく解説します。
(1)被相続人の情報
被相続人(亡くなった方)を特定するために、次の事項を記載します。
- 氏名
- 生年月日
- 死亡年月日
- 最後の本籍地
- 最後の住所地
(2)相続人が遺産分割協議を行ったこと
相続人全員を一人ひとり明記したうえで、遺産分割協議を行ったことを記載します。
これにより、協議が全員の合意のもとに行われたことを明確にします。
【例】
上記被相続人〇〇(以下「被相続人」という)の死亡により開始した相続について、相続人である□□(以下「甲」という)及び△△(以下「乙」という)は、被相続人の遺産の分割について協議し、以下のとおり合意する。
(3)相続財産の詳細
相続財産について、「どの相続人がどの遺産をどれだけ相続するのか」について、具体的に明確に記載します。
具体的には、別紙で遺産目録を作成して遺産をリストアップし、そのリストアップした遺産を相続する、という内容で協議書に記載する方法があります。
財産は特定できるように、詳しい情報を明記する必要があります。
例えば、預貯金は、銀行名、支店名、口座種別、口座番号などで、下記2のように特定します。
不動産は、不動産全部事項証明書を取得し、下記例4のように表題部に記載されているとおりに記載して特定します。
【別紙・遺産目録の例】
1 現金
〇〇円
2 預貯金
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
3 有価証券
株式会社〇〇の株式 〇〇株
4 不動産
(1)土地
所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇. 〇〇平方メートル
(2)建物
所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番
家屋番号 〇〇番〇〇号
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 〇〇. 〇〇平方メートル
2階 〇〇. 〇〇平方メートル
【相続する遺産の特定の例】
甲は、以下の遺産を取得する。
(1)別紙遺産目録記載1の現金全部
(2)別紙遺産目録記載2(1)の預貯金全部
(3)別紙遺産目録記載3の有価証券全部
乙は、以下の遺産を取得する。
(1)別紙遺産目録記載4(1)の土地
(2)別紙遺産目録記載4(2)の建物
(4)後日発見された財産の取り扱い
後日発見された財産の取り扱いについても記載します。これにより、将来のトラブルを防ぐことができます。
【特定の相続人が取得する場合の例】
今後、別紙遺産目録に記載されていない遺産が判明した場合には、当該遺産は、乙が取得する。
【あらかじめ特定の相続人が取得すると決められない場合の例】
今後、別紙遺産目録に記載されていない遺産が判明した場合、甲及び乙は、当該遺産の分割について別途協議する。
(5)作成日、作成通数と誰が保管するのか
遺産分割協議が成立した日付を明記します。
相続人がそれぞれ遠方に住んでいる場合には、遺産分割協議書を送付して持ち回りで署名押印するケースがあります。
その場合、最後の相続人の署名時点で遺産分割協議の合意が成立すると考え、最後の署名者が日付を記載することが多いでしょう。
【例】
甲及び乙は、上記協議内容を証するため、本協議書を2通作成し、各々1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(6)相続人全員の情報と署名押印
遺産を相続する相続人全員の氏名、住所を記載します。
住所は、印鑑証明書に記載されているとおりに、正確に記載します。
また、それぞれ署名し、実印で押印を行います。
【例】
甲 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇番地
氏名 実印
乙 住所 東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇番地
氏名 実印
(7)契印と割印を忘れずに
法律上の要件ではありませんが、遺産分割協議書が複数ページにわたる場合には、連続性を示して文書の改ざんを防止するために、契印を施します。
製本テープで製本したときには、テープと文書を跨り、相続人全員の実印で契印します。そうでなければ、各ページに跨り、相続人全員の実印で契印します。
また、遺産分割協議書を複数発行する場合には、それぞれが同じであることを証明して改ざんを防ぐために、割印を施します。
複数部作成した遺産分割協議書の上部を少しずらして、すべての文書に印鑑が被るように、相続人全員の実印で割印します。
遺産分割協議書を提出する場面
遺産分割協議書は、相続手続きの以下のような場面で提出が必要です。
相続手続きには、遺産分割協議書の他、印鑑証明書や亡くなった方の戸籍謄本など、必要書類がケースによって異なります。
印鑑証明書は発行から3ヶ月以内という制限があるときも多いので、あまり早く取得しないように注意しましょう。
また、基本的に亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)は、原本の提出が必要です。ただし、コピーも提出して原本の返還を依頼すれば、通常原本は返還されますのでコピーも準備するとよいでしょう。
法務局に相続関係一覧図(法定相続情報一覧図)と、戸籍謄本等などの書類をまとめて提出すれば、登記官が認証文を付した一覧図の写しを交付してくれます。金融機関からの預金払い戻しなどでは、この法定相続情報を戸籍謄本の代わりに提出できる場合もあります。
(1)預貯金の払い戻し等
銀行や信用金庫など、金融機関での相続手続きに必要な書類は、金融機関によって異なります。
遺産分割協議が成立している場合、通常、身分証明書、故人の通帳やキャッシュカード、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人の印鑑証明書(全員分)、遺産分割協議書、相続届(各金融機関のフォーマット)などが必要です。
事前に問い合わせて、必要な書類を確認するようにします。
書類提出後、すぐに払い戻しできるわけではなく、数週間かかることもあります。
(2)有価証券の名義変更
証券会社の口座の有価証券の相続手続きには、通常、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人の印鑑証明書(全員分)、遺産分割協議書、相続届(各証券会社のフォーマット)などが必要となります。
また、相続人が同じ証券会社に口座を保有していない場合、相続人名義の管理口座を開設する必要があります。相続手続きにより名義が変更された有価証券は、その管理口座に移されます。
細かい相続手続きについては、該当の証券会社に連絡して案内してもらうようにしましょう。
(3)自動車の名義変更
自動車の相続手続きは、陸運局(運輸支局)で移転登録申請を行います。
移転登録申請には、申請書、手数料納付書、車検証、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)等が必要です。
詳しくは、下記地方運輸局のサイトをご確認ください。
(4)不動産の名義変更
2024年4月1日から、不動産の相続人は、法律上、相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。
それ以前に相続したことを知った不動産については、2027年3月末までに登記が必要です。
不動産の相続手続きは法務局で行います。登記申請書、不動産を取得する者の住民票のコピー、固定資産評価証明書、相続関係説明図、遺産分割協議書、印鑑証明書(相続人全員分)などが必要です。
相続登記申請は、必要書類が多く、申請書の作成にも法律や登記の知識と経験が必要な分野なので、弁護士や司法書士に依頼することがほとんどです。
遺産分割協議を弁護士に依頼している場合には、登記申請を代理でしてもらえないか相談してみましょう。
参考:【法務省/相続登記の義務化】不動産を相続したらかならず相続登記!|法務省
(5)相続税の申告
一定額以上の遺産がある場合、相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ケ月言内に、相続税の申告と納付をしなければなりません。
申告の際には、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)、亡くなった方の住民票除票、遺産分割協議書の写し、各相続人の印鑑証明書、相続人全員の身分証明書(マイナンバーカードの写しなど)など、様々な書類を提出します。
相続税申告は、書類の準備の他、遺産を評価したり、税金を計算したり、特例の有無を確認したり、専門的な知識が必要とされます。
遺産分割協議を弁護士に依頼した場合には、相続税の申告もお願いしたいと伝えてみましょう。代わりに計算してくれたり、対応できる税理士を紹介してくれることがあります。
遺産分割協議書を自分で作成するときのよくある疑問
遺産分割協議書の作成に関するよくある疑問と回答を紹介します。
(1)遺産分割協議書に「相続しない」と記載すれば相続放棄できる?
ときどき誤解されている方がいますが、「相続しない」と記載するだけでは相続放棄にはなりません。
相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」とともに、戸籍謄本などの必要書類などを提出して行います。
原則として、被相続人の相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に行う必要があります。
相続放棄の手続きの流れや注意点について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)話し合っても全員で合意できなかったら?
遺産分割の話し合いは、お金や感情が絡む問題であり、話し合っても折り合いがつかないことがあります。
その場合には、1人又は複数人の相続人が、他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停では、裁判官と調停委員で構成された調停委員会が、当事者から話を聞き事情を把握したうえで、助言や解決案を提示します。
調停も、あくまで話し合いでの合意を目指す手続きです。
もし調停でも話し合いが決裂した場合には、調停は不成立になります。そのような場合には、遺産分割審判に移行し、最終的に、裁判所が審判という形で遺産をどのように分割するかを決定します。
(3)疎遠な親戚と連絡が取れない場合は?
疎遠な親戚と連絡が取れなかったり、相続人が多くて話し合いが困難だったりする場合にも、遺産分割調停を利用することができます。
話し合いができないまま放置してしまうことは、問題を後延ばしにするだけで決して良いことではありません。
遺産分割調停では、調停委員がそれぞれの話をまとめたうえで、実務や裁判例に従って調整してくれますので、冷静な話し合いが可能になるでしょう。
親戚と疎遠な場合、そもそも法定相続人が誰になるのか分からない、というケースもあります。
法定相続人の調査は、亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼって取得して行いますが、本籍が移動していたり、結婚や離婚を繰り返したりしている場合には、戸籍の収集も労力と時間がかかる作業です。
相続手続きについて弁護士に依頼すれば、戸籍の収集も代わりに行うことができますので、お困りの方は一度ご相談ください。
自分で遺産分割協議書を作成するメリットとデメリット
自分で遺産分割協議書を作成することを考えている方は、事前にそのメリットとデメリットを把握するようにしましょう。
(1)メリット
まず、弁護士などに依頼する費用を節約できる点があげられます。ただしその分、自分や他の相続人には、労力や時間が必要になります。
また、外部の者を入れず家族だけで話し合うので、大げさにせず遺産分割を円満に行える可能性があります。
ただし、相続人が「自分が全部相続すべきだ」など、法定相続分と乖離した主張に固執したりしていると、家族だけで冷静に話し合うことが困難なので、外部の者を入れて一度冷静になった方がいいこともあります。
(2)デメリット
遺産分割協議について、法律や実務の知識が不足している場合、無効な協議書を作成してしまうリスクがあります。
法的に有効な協議書を作成するためには、一定の知識が必要です。
また、遺産分割の協議や、書面の作成、その後の預金の払い戻しなどの相続手続きは、煩雑で時間と労力がかかります。
(3)遺産分割協議は弁護士に相談を
「話し合いが進まない」「疎遠な親戚とあまり話したくない」「仕事で忙しい」
など、遺産分割協議でお悩みの方は、相続を扱っている弁護士に相談しましょう。
弁護士は、あなたの代わりに相続人や遺産を調査したり、遺産の分け方について他の相続人と話して合意を目指します。
遺産分割調停や審判では、合意を目指して適切な資料を提出し、主張を行います。
【まとめ】遺産分割協議書は自分で作成できるが、心配な場合は相談を
遺産分割協議書を自分で作成する際には、遺言書の確認、法定相続人の調査、相続財産の詳細な把握、全員の合意取得という流れを経たうえで、必要な記載事項を漏れなく記載することが重要です。
費用を節約しつつ、家族間の争いを避け、円滑な遺産分割を実現できるかもしれません。
しかし、近しい関係であればあるほど、感情的になりお互いに不信感をもって話し合いが進まなくなってしまうことがあります。
そのような場合には、弁護士に代理で話し合いをしてもらったり、遺産分割調停を申し立てた方が、冷静に話し合いができることも多いです。
アディーレ法律事務所は、相続について積極的にご相談・ご依頼を承っておりますので、一度お気軽にご相談ください。