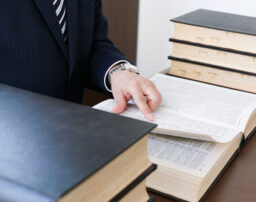高齢者ドライバーによる交通事故は、社会問題となっています。
高齢者ドライバーがアクセルとブレーキを踏み間違えて、幼い子が犠牲になった……。
そんな悲しいニュースも耳にすることが増えました。
また、家族など身近に高齢者ドライバーがいて、「運転をやめてほしい…」と考えている方も多いことでしょう。
今回の記事では、次のことについて弁護士がご紹介します。
- 高齢者ドライバーの事故の実態
- 高齢者が安全に運転する方法
事故全体における高齢者ドライバーの事故割合
高齢者ドライバーの事故がニュースで話題になる事も多くなりました。
では、実際には高齢者ドライバーはどのくらい事故を起こしているのでしょうか。
警視庁のデータによれば、少なくとも2012~2019年にかけて、全体の交通事故件数に占める高齢者ドライバー(65歳以上)による事故割合は、右肩上がりです(2020年からは、減少に転じています)。
同データによれば、2022年には全体の事故のうち約15%が高齢者ドライバーによるものになっています。
高齢者ドライバーによる事故は、今や社会問題です。
高齢者ドライバーの事故要因
では、高齢者ドライバーの事故の要因は何でしょうか。
警視庁の資料によると、高齢者ドライバーの事故要因1位は「発見の遅れ」です。
「発見の遅れ」は、高齢者ドライバー全体の事故要因の80.6%も占めています。
その他に、高齢者ドライバーの事故要因としては、判断の誤り、操作上の誤りなどがあります。
高齢者ドライバーが「発見の遅れ」を起こしやすいのは、一般的に次のようなことが原因と考えられます。
- 動体視力の衰え
- 注意力・集中力の低下
- 瞬発力の低下
加齢により、自分でも気づかない内に身体能力は低下していきます。
「今まで交通事故を起こさなかったのだから大丈夫」という過信は禁物です。
高齢者ドライバーの自己評価と現実のズレ
自動車安全運転センターの調べでは、高齢者ドライバーの約9割は、「安全運転」や「平均的な運転」をしていると自己評価していますが、現実には、追い越し時に事故に遭いかけた経験のある高齢者ドライバーが約2~3割いるなど、自己評価と現実にズレが生じています。
参考:高齢運転者に関する調査研究(Ⅲ)|自動車安全運転センター
死亡事故を起こす高齢者ドライバーに多い違反とは
死亡事故を起こす高齢者ドライバーに多い違反と何でしょうか。
警察庁によれば、死亡事故を起こす高齢者ドライバーに最も多い違反は漫然運転です(14.5%)。
漫然運転(※)が死亡事故に多いのは他の世代でも同じ傾向にありますが、一時不停止、ハンドル・ブレーキなどの運転操作間違い、通行区分違反、優先通行妨害も、高齢者ドライバーよりも他の世代のドライバーより多くなっています。
※漫然運転:歩行者や他の自動車が近くにいても、注意を払うことなく運転すること
特に、ハンドルやブレーキなどの操作間違いによる交通事故の割合は、75歳以上の高齢者ドライバーが一般ドライバーの約2倍にも上っています(2015年警視庁調べ)。
参考:第3節 超高齢化社会への対応|警察庁
参考:運転免許を自主返納する高齢ドライバーが増えています|警察庁
高齢者ドライバーが安全運転するためのポイント
高齢者ドライバーによる交通事故割合は増加傾向にあり、たびたびニュースにもなっています。高齢者が安全に運転をするため、気をつけるべきポイントをご紹介しますので、家族に高齢者ドライバーがいる場合は、安全のための声掛けをお願いします。
(1)高齢者標識(もみじマーク)をつける
高齢者ドライバーは高齢者標識(もみじマーク)をつけて、高齢者ドライバーであることを周りの人に示し、注意をしてもらいましょう。
道路交通法では、もみじマークにつき、次のように定めています。
【70歳以上75歳未満】もみじマークをつけるよう努力
普通自動車の免許を持つ方で、70歳以上75歳未満の方で、加齢による身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、普通自動車の前と後にもみじマークをつけて普通自動車を運転するよう努力しなければなりません(道路交通法第71条の5第4項)。
【75歳以上】もみじマークをつけるのは義務
普通自動車の運転免許を持つ75歳以上の方は、普通自動車の前と後ろにもみじマークをつけて、普通自動車を運転しなければならないという義務があります(道路交通法第71条の5第3項)。
75歳以上の高齢者ドライバーはもみじマークを付けるのは義務ですので、運転するときは忘れずにつけましょう。
(2)定期的に眼科で検診を受ける
視力の低下など目の不調が原因で車の運転に支障が出ることもあります。
眼科検診で不調が見つかれば、医師の指示に従って治療しましょう。
(3)事故を防げる車に買い換える
自動ブレーキや踏み間違い防止などの機能を備えた車を購入することも検討しましょう。
例えば、「衝突被害軽減ブレーキ」というものが搭載されている自動車があります。
これは、衝突しそうになったら警報が鳴ったり、自動でブレーキが作動するというものです。
また、「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」というものが搭載されている自動車もあります。
これは、停まっているときや、低い速度で走っているときに、前・後ろに壁や車がある状態で、アクセルを踏み込んだときに、急発進することを防ぐ装置です。
その他にも、車線からはみ出しそうになったら警報が鳴る装置がついていたり、ヘッドライトを自動で切り替える装置(ハイビームからロービームなど)がついていたりする自動車もあります。
技術を体感するため、試乗会に参加してみるとよいでしょう。
(4)家族で話し合う

高齢者ドライバー自身が運転に気をつけるだけでなく、家族とも話し合うことが大切です。
家族で運転を代われる人がいれば、高齢者ドライバーが運転する機会を減らすとよいでしょう。
(5)免許の返納を提案する
高齢者ドライバーの事故を無くすため、最も効果的なのが免許返納です。
運転免許を自主的に返納すると、運転経歴証明書を交付してもらうことが可能です(交付には手数料が必要です)。
運転経歴証明書は、公的な身分証明書になるほか、バス・タクシーの乗車運賃割引などの特典を受けることも可能です。
2023年に自主返納された件数は38万2957件にも上っています(75歳未満・75歳以上の合計)。
なお、運転免許を返納したことを忘れて運転してしまう高齢者もいるので、家族は注意が必要です。
参考:運転免許の申請取消(自主返納)件数と運転経歴証明書交付件数の推移|警察庁
参考:運転免許を自主返納する高齢ドライバーが増えています|警察庁
【まとめ】高齢者ドライバーの方は運転に注意が必要
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 高齢者ドライバーの事故要因1位は「発見の遅れ」
- 加齢により身体能力は低下するため、「今まで交通事故を起こさなかったのだから大丈夫」という過信は禁物
- 高齢者ドライバーの場合、ハンドルやブレーキなどの操作間違いによる交通事故の割合が多い
高齢者ドライバーが安全運転するためのポイント
- 高齢者標識(もみじマーク)をつける
| 70歳以上75歳未満 | もみじマークをつけるよう努力しなければならない |
| 75歳以上 | もみじマークをつけるのは義務(必ずつけなければならない) |
- 定期的に眼科で検診を受ける
- 事故を防げる車に買い換える
- 家族で話し合う
- 免許の返納を提案する
高齢者ドライバーによる交通事故は、近年大きな社会問題となっています。
高齢者ドライバーの事故要因の多くは発見の遅れです。
高齢者ドライバーは加齢とともに身体能力が衰え、自分でも気づかないうちに運転技術が低下していることがあります。
事故を防ぐためには、高齢者ドライバーの状況に合った対策が必要です。