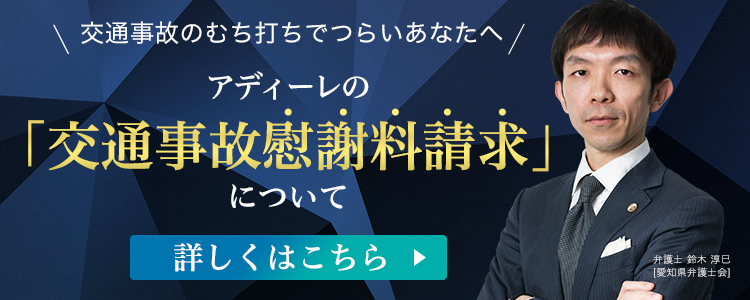交通事故により負うケガとして多いのがむち打ちです。
交通事故でむち打ちを負った場合、加害者に請求できる慰謝料の種類とその相場は決まっており、また増額できるポイントもあります。
そこでこの記事では、
- 交通事故でむち打ちになったときの慰謝料について知っておきたいこと
- 交通事故でむち打ちになったときの傷害慰謝料の相場
- 交通事故でむち打ちになったときの後遺症慰謝料の相場
- 交通事故でむち打ちになったときに慰謝料を増額するためのポイント
- 弁護士に依頼したことにより慰謝料が増額した事例
について解説します。
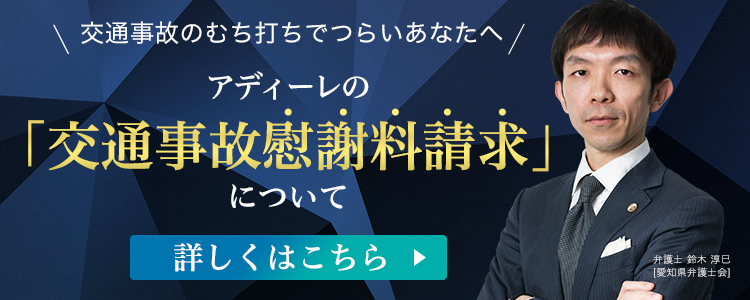
交通事故でむち打ちになったときの慰謝料について知っておきたいこと
まずは前提知識として
- 交通事故慰謝料の算定基準
- 請求できる慰謝料の種類
- その他賠償金の種類
について説明します。
(1)交通事故の慰謝料を算定する3つの基準
交通事故でケガなどの被害を受けた際、加害者に請求できる慰謝料を算定する基準は3つあり、どの基準を採用するかで金額が変わってきます。
3つの基準とは以下のとおりです。
- 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令で定められた、最低限の賠償基準
- 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
- 弁護士の基準……これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したもので、通常、弁護士が交渉や裁判をするときに使う基準(裁判所基準ともいいます)
これらの3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般的に
弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準
となります。
(2)むち打ちになったときに請求できる慰謝料の種類
交通事故によるむち打ちで請求できる慰謝料には
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます)
- 後遺症慰謝料
があります。
(事故が原因で死亡した場合は、さらに死亡慰謝料も請求できますが、ここでは割愛します。)
それぞれの内容は次のとおりです。
- 傷害慰謝料:交通事故でケガを負ったことによる精神的苦痛への金銭的補償。入通院した場合に請求できる
- 後遺症慰謝料:事故によって負ったケガが完治せず、後遺障害(※)が残ってしまったことによる精神的苦痛への金銭的補償。後遺障害が残り、後遺障害等級認定を受けた場合に請求できる
(※)後遺障害とは
交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。
「後遺障害」とは、このように交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。
後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。
各等級で、眼・耳・四肢・精神・臓器などの部位、障害の系列などに応じた障害の認定基準(各号)が定められています。
(3)慰謝料以外に請求できる賠償金
上で述べた慰謝料は、被害者が請求できる損害賠償の一部です。
慰謝料の他に請求できる賠償金としては、次のものがあります。
- 治療費
- 通院費用(通院のためにかかった交通費など)
- 休業損害(ケガにより就労できず得られなくなった収入)
- 入院雑費
- 付添看護費
- 葬儀関係費
- 車両の修理費
- 逸失利益(後遺障害や死亡により得られなくなった将来の収入など)
交通事故で加害者に請求できる損害賠償の種類について、詳しくはこちらの記事もご参照ください。
交通事故でむち打ちになったときの傷害慰謝料の相場
では、交通事故でむち打ちになった場合、慰謝料は実際にどれくらい請求できるのでしょうか。
まず、傷害慰謝料の相場を紹介します。
(1)自賠責の基準
自賠責保険の入通院慰謝料は、次のイ・ロのうち少ないほうの金額となります。
(いずれも、2020年4月1日以降に起きた事故の場合)
イ 実入通院日数×2×4300円
ロ 入通院期間×4300円
例えば、通院期間6ヶ月、実通院日数が60日(入院なし)だった場合、
イ 60日(実通院日数の合計)×2×4300円=51万6000円
ロ 180日×4300円=77万4000円
イとロを比べると、イのほうが少ないため、イの51万6000円が採用されます。
(2)任意保険の基準
任意保険の基準は、事故の相手側の任意保険会社が賠償額を提案してくる際に用いられる基準です。
自賠責の基準で算出したものよりは少し高くなりますが、次に紹介する弁護士の基準で算出したものよりは安くなるケースが多いです(金額そのものは非公開となっています)。
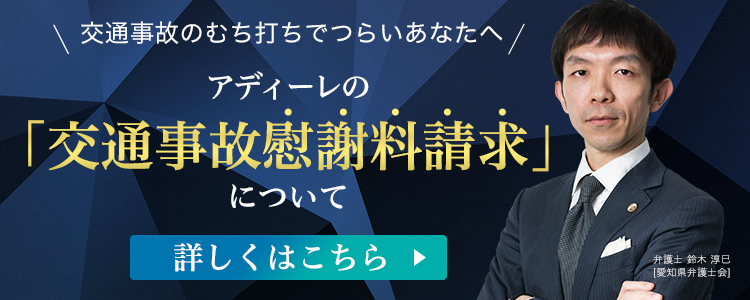
(3)弁護士の基準
弁護士に交通事故の示談交渉を依頼した場合、弁護士の基準で相手側との交渉をスタートします。
弁護士の基準では、入院と通院の期間によって定められた算定表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。
2種類の算定表があり、骨折などの場合と、むち打ち症で他覚的所見がない場合とでは異なる算定表を用います。
骨折などの場合は別表Ⅰ、むち打ち症で他覚的所見がない場合は別表Ⅱを用います。
縦軸が通院期間、横軸が入院期間で、それぞれの期間が交差する箇所が慰謝料額の目安となります。
傷害慰謝料(別表Ⅰ)(単位:万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
傷害慰謝料(別表Ⅱ)(単位:万円)
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
例えば、通院期間6ヶ月、実通院日数60日(入院なし)の場合、別表Ⅱ(他覚的所見なし)で算出すると89万円となります。
むち打ちによる傷害慰謝料の相場(ひと月の通院回数が10日の場合)について、自賠責の基準と、弁護士の基準を比較すると次のようになります(任意保険の基準は非公開のため掲載していません)。
【むち打ちによる傷害慰謝料の相場(ひと月の通院回数が10日の場合)】
| 通院期間 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 8万6000円 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 17万2000円 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 25万8000円 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 34万4000円 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 43万円 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 51万6000円 | 89万円 |
(2020年4月1日以降に起きた事故の場合。)
このように、弁護士の基準のほうが高額になることがお分かりかと思います。
弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
交通事故でむち打ちになったときの後遺症慰謝料の相場
続いて、後遺症慰謝料についてです。
交通事故でむち打ちになったときの後遺症慰謝料の相場を紹介します。
(1)後遺症慰謝料の相場は等級によって異なる
後遺症慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級によって異なります。
むち打ちの場合、
- 12級13号
- 14級9号
のいずれかに認定されるケースが多くなります。
それぞれの等級における後遺症慰謝料の目安は次のとおりです。
| 等級 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
※いずれも、2020年4月1日以降に起きた事故の場合。
上記の表のとおり、自賠責の基準よりも弁護士の基準のほうが金額は高くなります。
後遺症慰謝料における「自賠責の基準」「弁護士の基準」について、詳しくはこちらもご参照ください。
(2)12級13号と14級9号はどう違う?
では、12級13号と14級9号にはどのような違いがあるのでしょうか。
12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すもののうち、障害の存在が医学的に説明可能なものをいいます。つまり、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経の圧迫が認められ(他覚的所見あり)、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できるものです。
痛い・しびれるなどの自覚症状があっても、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経
これに対し、圧迫が確認できない場合(他覚的所見なし)や、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できない場合は、12級13号は認められず、14級9号になることが多くなります。
14級9号の認定を受けるためには、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査を受けることが重要となります。
むち打ちの症状がある場合、必要な検査を受け、自覚・他覚症状を的確に診断書に記載してもらい、必要な資料を揃えて申請することが大切です。
むち打ちの場合の後遺障害等級認定について、詳しくはこちらもご参照ください。
交通事故でむち打ちになったときに慰謝料を増額するためのポイント

交通事故によるケガでむち打ちの症状が出ている場合に、慰謝料を増額する(=被害に見合った慰謝料を受け取る)ためのポイントとして以下の2つを紹介します。
(1)弁護士の基準での交渉
まずは、上でご紹介した慰謝料の3つの算定基準のうち、一般に最も高額な「弁護士の基準」で交渉することが大切です。
交通事故の被害者が、加害者に対して慰謝料などの賠償金を請求する場合、その金額について、通常は加害者が加入する保険会社と示談交渉を行うことになります。
その際、被害者本人(加入する保険会社の示談代行サービスを含む)が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保の険基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。
これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、一般に最も高額な弁護士の基準を用いた主張を行います。
これにより、賠償金の増額が期待できます。
【3つの基準による一般的な慰謝料額のイメージ】
弁護士の基準
>
任意保険の基準
>
自賠責の基準
「弁護士費用特約」で弁護士費用の負担を抑えられる
なお、示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。
この弁護士費用は、自動車保険などの「弁護士費用特約」によりまかなえる場合があります。
被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、「弁護士費用特約」が利用できることがあります。
「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。
この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。
ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、
- 配偶者
- 同居の親族
- ご自身が未婚の場合、別居の両親
- 被害にあった車両の所有者
のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
また、弁護士費用特約を使っても、等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。
ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。
(2)適正な後遺障害等級の獲得
被害に見合った慰謝料を受け取るためには、症状を的確に反映した後遺障害等級を獲得することも重要です。
後遺障害等級の認定申請は保険会社に任せることもできますが(事前認定)、各種資料をご自身で揃えて申請する方法(被害者請求)のほうが納得できる結果を得やすくなります。
また、むち打ちで後遺症が残った場合、自覚症状を正しく医師に伝え、等級認定に有利な証拠を揃えることのほか、必要な治療と検査を適切なタイミングで受けることも大切です。
これらについても、弁護士に依頼することで、有益なアドバイスを受けられます。
後遺障害等級の認定申請について、詳しくはこちらもご参照ください。
弁護士への依頼で交通事故によるむち打ちへの慰謝料が増額した事例
最後に、むち打ちによる慰謝料請求を弁護士に依頼したことにより、慰謝料が増額した事例を紹介します。
(1)弁護士の基準の満額で後遺症慰謝料を獲得、賠償金総額は630万円以上に!
Nさん(女性・45歳・兼業主婦)は車を運転中、右折待ちで停車していたところ、前方不注意の車に後方から追突されました。
この事故でNさんは、外傷性頸部症候群、頸椎捻挫(むち打ち)と診断されて、通院による治療を続けていました。
Nさんは、今後の治療や示談までの流れ、後遺症が残ってしまったときにはどうすればよいかなどを、交通事故に詳しい弁護士に聞いてみたいと、弁護士に相談されました。
弁護士によるアドバイスや証拠の収集の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
認定後、弁護士は加害者側の保険会社と示談交渉を開始し、後遺症慰謝料は弁護士の基準の満額となる110万円を獲得して、賠償総額630万円以上で示談が成立しました。
(2)弁護士のサポートで治療打ち切りを回避し、賠償金総額は540万円以上に!
Sさん(男性・40歳・会社員)は、自動車を運転中、左折するために徐行していたところ、後方から自動車に追突されてしまいました。
この事故で、頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。
Sさんは通院治療を続けていましたが、事故から約8ヶ月経過したところで、加害者側の保険会社が、立て替えている治療費の打ち切りを求めてきました。どう対応していいのかわからなかったSさんは、弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、Sさんに対し、事故から3~6ヶ月経過すると、加害者側の保険会社は慰謝料を抑えるために治療費の打ち切りを求めてくることがあるが、医師の判断に従うべきであるとアドバイスしました。
その結果、事故から約10ヶ月後、Sさんは症状固定となり、これまでの後遺障害の認定事例に基づいて、後遺障害診断書を徹底的にチェックするなどのサポートを行った結果、14級9号が認定されました。
また、弁護士は相手側の保険会社と傷害慰謝料・後遺症慰謝料について弁護士の基準による賠償を認めるよう強く主張した結果、ともに弁護士の基準の満額が認められました。
また、弁護士は、逸失利益についても粘り強く交渉し、その結果、最終的な賠償金額の総額は、保険会社の初回提示額から260万円以上増額した540万円以上で示談が成立しました。
【まとめ】交通事故によるむち打ちの慰謝料は、弁護士の基準で算出すれば増額が可能に。むち打ちでお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください
この記事のまとめは次のとおりです。
- 交通事故でむち打ちになった場合に請求できる慰謝料には、傷害慰謝料と後遺症慰謝料の2つがある。
- 交通事故でむち打ちになったときの慰謝料額の算定基準は、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準」の3つがあり、一般に「弁護士の基準」によれば最も高額となる。
- 加害者側との示談交渉を弁護士に依頼すれば、「弁護士の基準」を用いた交渉により賠償額の増額できる可能性がある。
交通事故のむち打ちでお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。