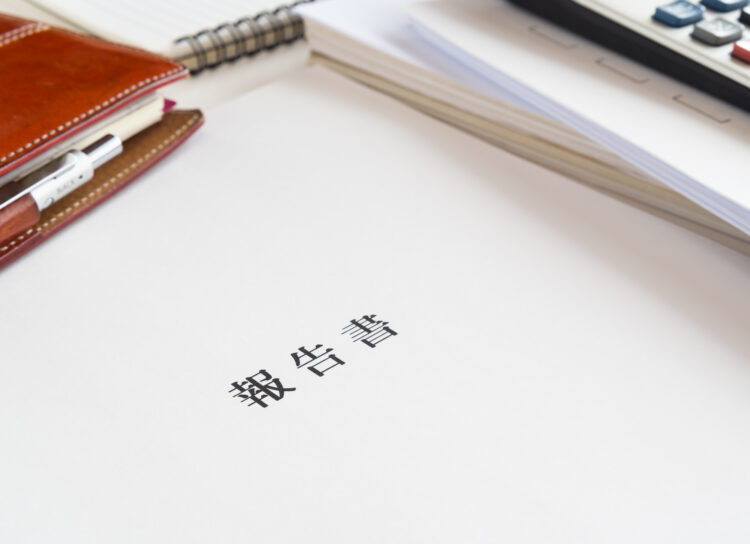「源泉徴収票をなくしてしまった…再発行できるのかな?」
源泉徴収票は、確定申告や保育園の入園申請など、様々な場面で使うことがあります。
ところが、源泉徴収票は紙が小さく、なくしてしまうことも珍しくありません。
源泉徴収票は、再発行できます。
その方法は、勤務先に依頼するなどです。
このことを知っていれば、源泉徴収票が必要なのになくして見つからないという場合であっても安心して再発行してもらうことができます。
この記事を読んでわかること
- 源泉徴収票を再発行する方法
- 再発行を拒否された場合の対処法
- 源泉徴収票が必要になるのはどんな場合か
源泉徴収票とは?
「源泉徴収票」とは、年間の給与・賞与・年金などの所得についてまとめられた書類です。
源泉徴収票を見ることで、「会社からいくらのお金をもらったのか」「自分がいくらの税金を支払ったのか」などが分かります。
源泉徴収票は、原則として、会社が年末調整を行った後に作られます。
源泉徴収票を再発行する方法
源泉徴収票は再発行できるの?どうやればいいの?
源泉徴収票は再発行できます!
源泉徴収票をなくした場合、勤務先などに依頼すれば源泉徴収票の再発行が可能です。
次の3つの場合に分けて事例を紹介します。
- 給与所得者の場合
- 公務員の場合
- 年金受給者の場合
(1)給与所得者の場合
源泉徴収票の再発行は、勤務先の経理担当者などに依頼します。
申請方法は会社によってルールが定められていることがありますので、経理担当者などに申請方法を確認すると良いです。
すでに退職した会社の源泉徴収票の再発行は、その退職した会社に依頼します。
| 再発行したい源泉徴収票 | 依頼先 |
|---|---|
| 現在勤務している会社の源泉徴収票 | 現在勤務している会社に依頼 (経理担当者など) |
| 過去に勤めていた会社の源泉徴収票 | 過去に勤めていた会社に依頼 |
税務署や役所では源泉徴収票を発行してくれないの?
税務署や役所では源泉徴収票を発行できません!
発行元である会社に依頼しましょう。
(2)公務員の場合
公務員の方の場合、源泉徴収票の再発行は、勤務先の給与担当者に依頼することになります。
また、共済組合に直接連絡しても源泉徴収票を再発行してもらえます。
- 国家公務員の方の場合:国家公務員共済組合委連合会に依頼
- 地方公務員の方の場合:地方職員共済組合など、それぞれが加入している共済組合に依頼
参考:Q源泉徴収票を紛失してしまいましたが、再発行してもらえるのでしょうか。|国家公務員共済組合委連合会
参考:源泉徴収票について|地方職員共済組合
(3)年金受給者の場合
年金受給者の方の場合は、受け取っている年金の種類に応じて、次の表のとおりの依頼先に依頼します。
| 受け取っている年金の種類 | 再発行の依頼先 |
|---|---|
|
|
| 共済年金 | 加入している共済組合 |
| 発行元の企業 |
| 企業年金連合会からの年金 | 企業組合連合会 |
参考:源泉徴収票をなくしたとき|日本年金機構
参考:源泉徴収票再発行サービス|企業年金連合会
源泉徴収票の再発行を拒否された場合はどうしたらいい?
源泉徴収票は、原則として依頼すれば再発行してもらえます。
しかし、何らかの理由により会社が源泉徴収票の再発行を拒否することもありますが、源泉徴収票の再発行拒否は違法となる可能性があります。
所得税法226条によって勤務先には源泉徴収票の発行が義務付けられているからです。
源泉徴収票の発行を拒否すれば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(所得税法242条6号)。
源泉徴収票の発行をしてもらえない場合には、つぎのように対応しましょう。
- 退職後に会社が倒産していたときは破産管財人に依頼
- 会社が再発行を拒否したら提出先に相談
これらについてご説明します。
(1)退職後に会社が倒産していたときは破産管財人に依頼
退職後に会社が倒産していたら、破産管財人(裁判所から選任されて倒産手続きを行う弁護士)に源泉徴収票の再発行を依頼できます。
(2)会社が再発行を拒否したら税務署に相談
源泉徴収票は、給与を支払った会社が発行しますので、会社が再発行を拒否したら源泉徴収票を入手することができません。
確定申告の際に源泉徴収票に記載された情報が必要な場合には、所轄の税務署に相談してみましょう。
その他、源泉徴収票の提出が必要とされている場合、給与明細などで代替できることもありますので、提出先に相談してみるとよいでしょう。
なお、そもそも会社が一度も源泉徴収票を発行してくれていない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」を会社の所轄の税務署に提出することで、税務署から会社に源泉徴収票を発行するよう指導がなされることが多いです。
会社が再発行を拒否したときも、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出し、事情を説明したら、税務署によっては、会社に再発行をするよう促してくれるかもしれません。
源泉徴収票が必要になる場合とは
源泉徴収票の再発行方法が分かって一安心。
ところで、源泉徴収票が必要になる場合ってどんなケースがあるんだろう?
源泉徴収票が必要になる場合は、確定申告の手続きをするときなど、いろいろあります。
源泉徴収票が必要になるケースには、次のような場合があります。
• 確定申告の手続きをするとき
• 転職(再就職)するとき
• 健康保険の扶養家族になるとき
• 住宅ローンなど借金をするとき
• 子どもを保育園に入園させるとき
• 離婚に伴い、婚姻費用や養育費の取り決めをするとき
• 交通事故にあって休業損害証明書を保険会社に提出するとき
• 民事再生手続きや破産手続きをするとき
これらについて解説いたします。
(1)確定申告の手続きをするとき
確定申告の際には、源泉徴収票に記載されている内容を確定申告書に記載する必要があります。
給与所得者は年末調整をすれば原則として、確定申告は必要ありません。
しかし、各種の所得控除を受けたい場合や、収入を2ヶ所以上から得ている場合などは確定申告することになります。
【確定申告をする例】
1.各種の所得控除を受けたい方
- 医療費がたくさんかかったから医療費控除を受けたい場合
- ふるさと納税をしたので、寄付金控除を受けたい場合(ワンストップ特例制度の適用外の場合)
ワンストップ特例制度の申請書を自治体に郵送することで、確定申告の手間を省くことができます。もっともワンストップ特例制度が適用されるためには、様々な条件(寄付した自治体数が5自治体以内など)がありますので、条件を満たさない場合は確定申告が必要となる場合があります。
2.確定申告の義務がある方
- 給与が年間2000万円を超えている場合
- 2ヶ所以上から一定の給与をもらっていて、収入の合計が一定額以上の場合
- 一定の給与以外にも副収入(公的年金など)があり、収入の合計額が一定額以上の場合
(2)転職(再就職)するとき
転職先が会社の場合、前職の源泉徴収額と、転職先での源泉徴収額を合算して年末調整を行います。
このため、転職先の会社に源泉徴収票の提出が必要となることがあります。
また、フリーランスや自営業に転職した場合には、確定申告の必要がありますので、確定申告の際に源泉徴収票を使用することになります。
(3)健康保険の扶養家族になるとき
健康保険の扶養家族になるときに、源泉徴収票の提出が必要となることがあります。
(4)住宅ローンなど借金をするとき
住宅ローンなど借金をするときに、返済能力の審査のための資料として、ローンの申し込み時に源泉徴収票の提出が求められることがあります。
(5)子どもを保育園に入園させるとき
保育園の入園時に必要な書類は、自治体などによって異なりますが、親が働いていることや収入を証明するために、源泉徴収票の提出が必要となることがあります。
また、失業したことを理由に、保育料の減額を申請するために源泉徴収票が必要となる場合があります。
参考:申込みに必要な書類|豊島区
参考:保育料減額申請書|足立区
(6)離婚に伴い、婚姻費用や養育費の取り決めをするとき
離婚をしようとすると、「婚姻費用」や「養育費」を取り決める必要が出てくるときがあります。
「婚姻費用」とは、離婚するまでの間、配偶者の一方が、他方の配偶者と子どものために負担する生活費のことをいいます。
子どもがいなくとも離婚するまでの間は、婚姻費用が発生します。
また、「養育費」とは、未成熟子(社会人として自立できない状況の子)が、社会人として自立して生活できるまでの間、必要とされる費用のことをいいます。
この婚姻費用と養育費を決める上では、夫婦の収入がポイントです。収入を証明するための資料として、給与所得者の方(かた)の源泉徴収票の提出が求められる場合があります。
(7)交通事故にあって休業損害証明書を保険会社に提出するとき
交通事故でケガをしたせいで、被害者が仕事を休まざるを得なくなり、その間、収入が減ることを「休業損害」といいます。
この休業損害の状況を証明するために、給与所得者の方が勤務先に作成してもらう書類を「休業損害証明書」といい、作成してもらった休業損害証明書は保険会社に提出することになります。
そして、休業損害証明書を保険会社に提出する際、通常は、事故の前年度分の源泉徴収票を添付して、加害者の保険会社に提出する必要があります。
(8)民事再生手続きや破産手続きをするとき
「民事再生手続き」とは、自力での負債(借金等)の返済が困難となってきたときに、原則として、負債の一部を減らして払っていくため、裁判所に申立てて行う手続きです。
「破産手続き」とは、自力での負債の返済が不可能となったときに、原則として負債の支払いを免除してもらうべく、裁判所に申立てて行う手続きです。
※なお、養育費や税金など一部の負債は、民事再生や破産をしても、減ったり、なくなったりしません。
この民事再生手続きや破産手続きは、申立てをしようとする人の収入状況がポイントとなりますので、給与所得者の方は、直近2~3年分の源泉徴収票を裁判所に提出するよう求められることが多いです(申立てをする裁判所によって提出書類は異なります)。
参考:新型コロナウイルス感染症の影響により借金等の返済が困難となった方へ|法務省
【まとめ】源泉徴収票は会社に依頼するなどの方法で再発行できる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 源泉徴収票とは、年間の給与・賞与・年金などの所得についてまとめられた書類のこと。
- 源泉徴収票は再発行できる。
例えば、給与所得者が現在勤務している会社の源泉徴収票を再発行してもらう場合には、勤務先の経理担当者などに依頼する。
税務署や役所では源泉徴収票を発行できないので、発行元である会社に依頼する。 - 会社に源泉徴収票の再発行を拒否された場合には、税務署に相談すると良い。
- 源泉徴収票が必要になる場合として、確定申告の手続きをするときや転職(再就職)するときなどがある。
源泉徴収票が必要なのになくしてしまうと、どうしたらいいのか不安になってしまいますよね。
ですが、安心してください。
源泉徴収票は再発行できます。
もしも会社が源泉徴収票を再発行してくれないといったトラブルを抱えてお困りであれば、最寄りの税務署に相談しましょう。