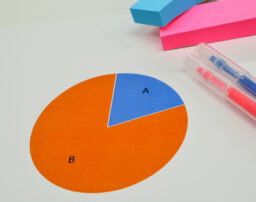自転車事故は誰にでも起こりうる身近なリスクです。
しかし、その事故がもし大きな被害を伴うものだった場合、加害者は未成年であっても、想像以上に重い責任を負う可能性があることをご存知でしょうか。
このコラムでは、自転車事故の加害者が負う刑事上の責任と民事上の責任について、未成年が加害者となった場合に特に焦点を当てて詳しく解説します。さらに、高額な賠償が認められた事例や、未成年者による自転車事故の当事者が知っておくべき重要なポイントについてもご紹介します。
ここを押さえればOK!
民事上の責任は、被害者への損害賠償です。未成年が加害者となった場合、おおむね12歳以上で責任能力があると判断されれば本人が賠償責任を負います。しかし、未成年者に賠償金を支払う資力がない場合は、監督義務を怠った親が代わりに賠償責任を負う可能性があります。すでに交通事故の被害に遭い、お困りの方は、アディーレへご相談ください。
弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
自宅でらくらく「おうち相談」
「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」
アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
自転車事故の加害者が負う2つの責任
自転車事故を起こし他人にケガなどをさせてしまった場合、法律上、「刑事上の責任」と「民事上の責任」の2つの責任を負うことになります(※)。
それぞれの内容を見ていきましょう。
(※)悪質な自転車事故を起こした場合、それを理由に自動車運転免許停止処分という行政上の責任も負うことがありますが(道路交通法103条第1項8号)、ここでは省略します。
(1)自転車事故における刑事上の責任
「刑事上の責任」とは、刑事法により定められた犯罪行為を行い、懲役刑や禁固刑(※)、罰金刑などの刑事罰に処されることをいいます。
- 不注意により他人にケガをさせてしまった場合
→過失傷害罪(30万円以下の罰金または科料) - 不注意により他人を死亡させてしまった場合
→過失致死罪(50万円以下の罰金) - 重大な不注意により他人を負傷、または死亡させてしまった場合
→重過失致死傷罪(5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)
さらに、自転車事故後に被害者を救護する義務や事故を警察に報告する義務を怠った場合には、次の刑事責任を問われる可能性もあります。
- 事故後に被害者を救護する義務を怠った場合
→道路交通法上の救護義務違反(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金) - 事故を警察に報告する義務を怠った場合
→報告義務違反(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
刑事上の責任を負うのは、14歳以上であるとされています。
なぜなら、14歳未満には刑事責任能力がないとされているからです。ただし、14歳未満であっても、一定の場合は警察から調査を受ける可能性があります。
※2022年6月の刑法改正により、懲役刑と禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されました。2025年頃までに施行される予定です。
(2)自転車事故における民事上の責任
「民事上の責任」とは、被害者に与えた財産的・精神的損害を賠償する責任です(民法709条)。
「民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
引用:民法709条
民法709条により、故意または過失(不注意)により他人の生命や身体・財産などを傷つけた加害者は、これによって生じた損害を賠償しなければならないとされています。例えば、自転車の運転中に、不注意により他人にケガなどを負わせた場合には、民法709条に従い、加害者は被害者に対し、ケガの治療費などお金で賠償しなければなりません。
そして、自転車事故により被害者を死亡させたり、重い後遺症が残ってしまったりした場合には、自転車事故か自動車事故かは関係なく、賠償金額は高額になります。
未成年の加害者に民事上の責任(賠償責任)を追及できる?
ここでは、未成年者の責任能力と未成年者に対する賠償請求について解説します。
(1)未成年者に賠償請求するには責任能力が必要
加害者が未成年者の場合、賠償請求ができない可能性があります。民法上、未成年者に賠償請求ができるのは未成年者に「責任能力(自己の行為の責任を弁識するに足りる知能)」がある場合とされているかです。
「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」
引用:民法712条
未成年者(18歳未満の者。なお、2022年3月までは20歳未満の者)は、大人に比べ自己の行為を、責任をもって行う能力が未熟です。
そのため、民法は、未成年者が不法行為を行った場合、「責任能力(自己の行為の責任を弁識するに足りる知能)」を備えているときに限り賠償責任を負わせることとし、未成年者を保護しているのです。
(2)未成年者の責任能力は、おおむね12歳ころ
未成年者がこの責任能力を備えるのはおおむね12歳頃とされています。
一つの目安として、中学生以上であれば未成年者の加害者自身が事故の賠償責任を自ら負うことになります(ただし、12歳というのは絶対的な基準ではなく、あくまで目安であり、個別に判断されることになります)。
一方、加害者に責任能力がない(おおむね12歳未満の)場合は、未成年者本人は賠償責任を負わず、未成年者の監督義務者である親権者(親)が未成年者に代わって賠償責任を負うことになります(民法714条)。
(3)未成年の加害者に対する損害賠償請求
自転車事故の加害者がおおむね12歳以上の場合は、加害者本人に損害賠償を請求することが可能です。
しかし、そうは言っても、例えば15歳の中学生に対して治療費や高額な慰謝料を請求したところで、本人がそれを支払えるだけの資力を有していることはまれです。
そこで、これまでの裁判例では、加害者である未成年者が責任能力を有していた場合(例えば15歳の中学生の場合)でも、本人が事故を起こしたことについて親に監督義務違反があり、その義務違反と事故との間に因果関係が認められるときは、親も賠償責任を負うとされています(最高裁判決昭和49年3月22日)。
例えば、次のような事情がある場合には、未成年者が12歳以上で責任能力があるとされた場合でも、親が賠償責任を負わなければならないとされる可能性があります。
<具体例>
- 親が子の自転車のブレーキが故障していることを知りながら、修理せずに放置した。その結果、自転車のブレーキが効かずに、事故が発生した。
- 親が、子が高速度で自転車に乗るなど交通ルールを遵守していないことを知りながら、交通ルールを守るように指導しなかった。その結果、子が交通ルールを守らず自転車に乗り、事故が発生した。など
未成年が加害者となった自転車事故の事例を紹介
未成年者が加害者となった自転車事故で、高額な損害賠償が請求された事例は少なくありません。
ここでは、裁判で高額賠償が認められた事例についていくつかご紹介します。
【事例1】
男子高校生が自転車で車道を斜めに横断したところ、同じく自転車で対向車線を直進してきた男性(24歳・会社員)と衝突。男性に言語機能の喪失などの重大な障害が残り、賠償額は9266万円となりました(東京地方裁判所判決平成20年6月5日)。
【事例2】
小学5年生の男子児童が自転車で坂道を下っていたところ、散歩中の女性(67歳)と衝突。女性ははね飛ばされて頭を打ち、植物状態となってしまいました。この事故での賠償金は9520万にも上りました。
なお、この事故では男子児童がヘルメットを着用していなかったことなどから、母親が十分な指導や注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていなかったとして、母親の責任が認められました(神戸地方裁判所判決平成25年7月4日)。
未成年による自転車事故の当事者が知っておくべきポイント
ここでは、未成年者による自転車事故の当事者が知っておくべき5つのポイントを説明します。
- 警察に事故の報告を忘れずに行う
- 保険未加入の場合、示談交渉は自分で行う
- 保険未加入の場合は賠償金を自費で支払う
- 当事者同士での過失割合の算定は難しい
- 加入する保険が自転車事故を対象としていないかを確認する
それぞれ説明します。
(1)警察に事故の報告を忘れずに行う
自転車事故を起こしたらまず、ケガをしていないかを確認し、ケガをしていればすぐに救急車を呼びましょう。また、最寄りの警察に事故があったことを報告します。
ケガをした被害者がいた場合、救護せずにその場から立ち去ると道路交通法上の救護義務違反に、警察に報告しないと報告義務違反に該当し、刑事罰を科せられてしまう可能性がありますので注意が必要です。
個人賠償責任保険や、自転車事故も対象となる自動車保険などに加入している場合は、保険会社にも忘れずに、「自転車事故を起こしたこと」の連絡をしておきましょう。
(2)保険未加入の場合、示談交渉は自分で行う
自動車の場合は任意保険に加入するのが一般的ですが、自転車の場合は保険に未加入であることが少なくありません。
自転車事故も対象とする保険に加入している場合は、通常は保険会社が示談を代行してくれますが、自転車事故も対象とする保険未加入の場合、当事者(未成年者の場合には親)が示談交渉をしなければなりません。
示談交渉で合意した内容は、口約束だけで済ませず必ず書面(示談書)を作成し、当事者双方が署名・押印するようにしましょう。口約束では、後々に、言った、言わなかったなどトラブルになってしまうケースもあります。
(3)保険未加入の場合は賠償金を自費で支払う
自転車事故を対象とする保険に未加入の場合、賠償金は自費で支払わなければなりません。
加害者が未成年で親の責任が認められた場合には、未成年者に代わり親が自費で賠償金を支払うことになります。もし、この場合に支払いを無視すると、親の預金や給料を差し押さえられて支払いを強制されるケースもあります。
(4)当事者同士での過失割合の算定は難しい
示談交渉の際に保険会社が間に入らない場合、過失割合(事故の責任の度合い)は当事者どうしで決めなければなりません。しかし、過失割合の算定には専門的な知識が必要となるため、当事者だけでの適正な過失割合の算定は非常に困難となります。
(5)加入する保険が自転車事故を対象としていないかを確認する
自転車事故を対象としている保険には、次のようなものがあります。
(5-1)自転車保険
自転車事故のみに特化した保険。
自転車運転中に相手にケガなどを負わせてしまった場合の損害賠償と、自転車運転中のケガで自ら入院・通院した場合の補償がセットになっているのが一般的です。
(5-2)個人賠償責任保険
自転車事故を含め、他人に損害を負わせてしまった場合の損害賠償について広く補償する保険です。
クレジットカードにサービスとして付帯されている場合や、傷害保険や火災保険の特約として付帯する場合が多いです。
(5-3)自動車保険に付帯する自転車特約
自身が加入している自動車保険に特約として付帯するものです。
加入者本人だけでなく、家族が起こした事故についても補償されるのが一般的です。
自転車特約は、相手方への損害賠償についての補償をメインとするものと、自身のケガについての補償をメインとするものとがあります。自転車保険と異なり、両方の補償を兼ね備えているとは限りません。契約書をよく読んで、どこまでカバーされているのか確認する必要があります。
親が加入している自動車保険の特約で、子の自転車事故の補償をカバーしている場合もあるので、忘れずに確認しておきましょう。
【まとめ】自転車事故加害者は未成年であっても、刑事・民事責任を負う可能性あり
自転車事故の加害者は、年齢に関係なく刑事上・民事上の責任を負う可能性があります。
特に、被害者が死亡したり重い後遺症が残ったりした場合には、未成年が起こした事故であっても、監督責任を問われた親権者が1億円近い高額な賠償金を支払うことになった事例もあります。もしもの時に備えるためにも、自転車保険への加入を検討しましょう。
すでに交通事故の被害に遭い、お困りの方は、アディーレへご相談ください。