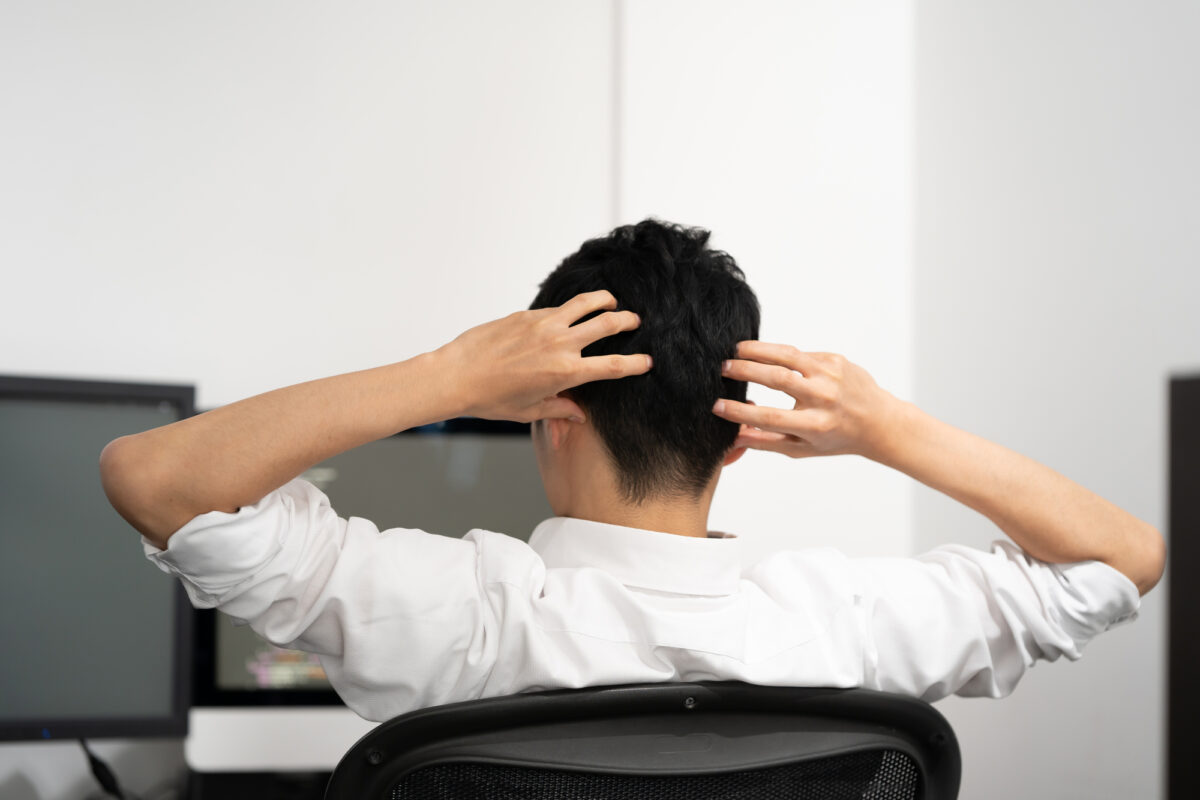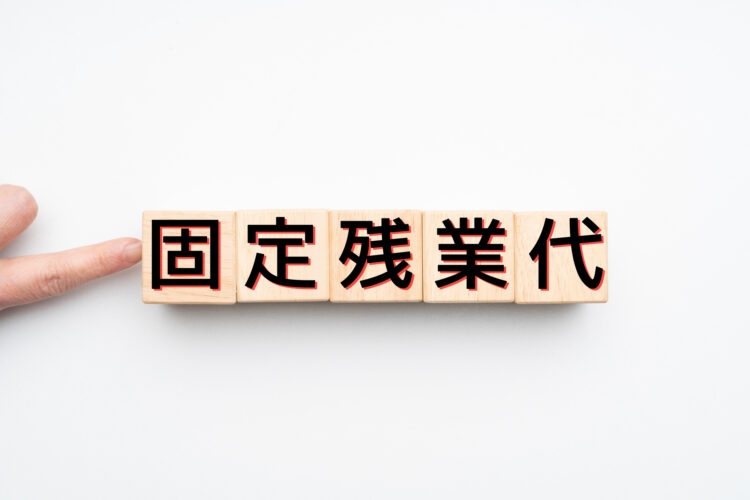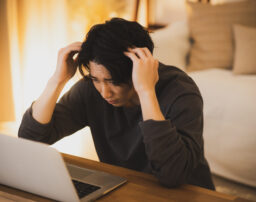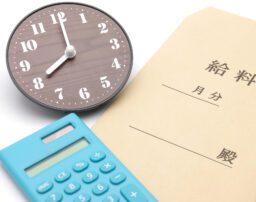「管理職に昇進して給与が上がると期待していたのに、昇進前より下がってしまった……!管理職は残業代がもらえないからと聞いたけれど、本当?」
確かに、労働基準法のルールでは、会社は「管理監督者」に対し、深夜割増賃金を除く残業代を払う義務がありません。
しかし、「管理職」=「管理監督者」ではありません。
すなわち、部長など管理職の肩書がついていても「管理監督者」にはあたらないため法律上残業代を払わなければならないケースも多くあります。
それにもかかわらず、「管理職」という肩書がついているものの実態は管理監督者でない人に対して、残業代を違法に払わないというケースが多く発生しています(いわゆる「名ばかり管理職」)。
「管理監督者」の正しい意味や、「管理職」と「管理監督者」の違いを知っておくことで、違法な残業代の不払いを防ぐことができます。
この記事を読んでわかること
- 管理監督者とは何か(管理職との違い)
- 名ばかり管理職とは
- 管理監督者とされるための判断基準
- 管理監督者とされないための具体的要素
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!
些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!
自宅でらくらく「おうち相談」
「仕事が忙しくて時間がない」
お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!
管理監督者とは?
まず、「管理監督者とは何か」という点について、解説していきます。
(1)労働基準法における管理監督者
労働基準法41条は、労働時間、休憩及び休日に関する同法の適用が除外される例外的な労働者を列挙しています。
そして、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)も、この例外的な労働者として列挙されています(同条2号)。
したがって、管理監督者に該当する労働者に対しては、使用者(会社)は、時間外労働や休日労働に対して割増賃金の支払いをする義務がありません(深夜労働に対しては割増賃金を支払う義務があります)。
そして、「管理監督者」とは、行政解釈によれば、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」のことをいうとされています。
またそれは、名称や肩書き、就業規則の定めのいかんにとらわれず、実態に即して客観的に判断されるべきであるとされます。
参考:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省
(2)管理監督者の実質的判断要件
実際に管理監督者にあたるか否かを判断するにあたっては、次の3要件をみたしているかについて、実態に即した具体的な審査が行われます。
裁判例などでは、次のそれぞれの点を総合的に考慮して、管理監督者該当性が判断されます(詳しくは後述)。
- 経営者と一体性を持つような職務権限を有しているか(職務権限)
- 厳密な時間管理を受けず、自己の勤務時間に対する自由裁量を有しているか(勤務態様)
- その地位にふさわしい待遇を受けているか(待遇)
これらの実態がないとして管理監督者にあたらないと判断されれば、労働時間・休憩・休日に関する規制が、通常の労働者と同様に適用されることになり、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いも必要となります。
参考:日本マクドナルド事件 東京地裁判決平成20年1月28日労判953号10頁│裁判所 – Courts in Jap
管理監督者と管理職の違いは?
そもそも「管理職」と「管理監督者」はどう違うの?
「管理職」と「管理監督者」は、似た言葉ですが別の意味の言葉です。混同しないように注意しましょう。
一般に「管理職」とは、会社が独自に決めた「部長」「課長」などの肩書きを持つ、組織の中で管理業務を行う者とされています。あくまで会社内での地位を示すものであって、法的に何らかの定義がなされた概念ではありません。
他方で、「管理監督者」は、労働基準法で定められている概念です。
管理監督者に該当すれば、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の適用が除外されることになり、使用者は時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払い義務を負わなくなります。
したがって、割増賃金の有無という観点からして重要なのは、管理職であるか否かではなく、「管理監督者であるか否か」であるということになります。
管理監督者該当性は、肩書きにとらわれず、実質的な要件をみたしているか否かによって判断されます。
ここで問題となってくるのが、管理監督者に該当しないにもかかわらず、「管理職だから時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払わない」などと会社に言われてしまうケースがあることです。
それが「名ばかり管理職」と呼ばれる問題です。
(1)名ばかり管理職とは?
名ばかり管理職とは、部長や課長といった管理職の肩書がついているだけで、管理監督者としての実態がないにもかかわらず、「管理監督者」であるとして、時間外労働や休日労働に対する割増賃金が支払われていない労働者のことをいいます。
しかし、企業内で管理職とされていても、労働基準法上の管理監督者の実態を有していない場合には、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
(2)管理監督者該当性を否定する判断要素
管理監督者であるか、名ばかり管理職であるかを区別する上で重要なのは、肩書きではなく、労働の実態です。
そこで次に、管理監督者該当性を否定する、3つの判断要素について解説いたします。
(2-1)判断要素1|職務内容や権限
「経営者と一体性を持つような職務権限を有しているか」という基準です。
経営上の決定に参画していたのか、労務管理上の決定権限があったのかが問題とされます。
例えば次の事実が認められれば、管理監督者としての職務内容や権限がないと判断されやすくなります。
- 経営会議等に出席したことがないこと
- 会社の重要部門の管理(人事や経営といった部門のみならず、複数の店舗を含むエリアや基幹となる支店の管理も含む)を委ねられていたとはいえないこと
- 職場のパートやアルバイトの採用権限や解雇の権利がないこと
- 部下の人事考課に関する権限がないこと
- 職場におけるシフトの作成や時間外労働を命ずる権利がないこと
(2-2)判断要素2|勤務態様
「厳密な時間管理を受けず、自己の勤務時間に対する自由裁量を有しているか」という基準です。
遅刻や早退をした場合に減給などの制裁、人事考課での不利益がある場合は、管理監督者としての勤務態様ではないと判断されやすくなります。
注意すべきは、過重労働による健康被害防止などの観点から労働時間の管理を受けている場合には、そのような管理を受けているというだけで管理監督者性を否定することはできないという点です。
また、次のような事情がある場合にも、管理監督者としての勤務態様ではないと判断される可能性があります。
- 実際には長時間労働を余儀なくされている場合のように、労働時間を自由に決定する裁量がほとんどないと認められる場合
- 会社が配布したマニュアルなどに従った業務に従事しているといった、労働時間の規制を受ける一般社員と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める場合
(2-3)判断要素3|待遇
「賃金等の面で、その地位にふさわしい待遇を受けているか」という基準です。
次のような事情がある場合、管理監督者としての待遇ではないと判断されやすくなります。
- 時間単価に換算した賃金が、アルバイトやパートなどの賃金額に満たない場合(特に時間単価換算した賃金が最低賃金額に満たない場合、極めて重要な否定要素となる)
また、次のような事情がある場合にも、管理監督者としての勤務態様ではないと判断される可能性があります。
- 基本給・役職手当が不十分な場合
- 特段の事情がないにもかかわらず、1年間に支払われた賃金の総額が一般の従業員の賃金総額と同程度以下である場合
管理監督者の残業代と有給休暇についての考え方
会社は、管理監督者に対し、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払う義務はありませんが、深夜労働に対する割増賃金を支払う義務はあります。
また、会社は、管理監督者であっても、有給休暇を付与しなければなりません。
これらにつき解説いたします。
(1)管理監督者の残業代について
会社は、管理監督者に対し、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払う義務はありませんが、深夜労働に対する割増賃金を支払う義務はあります。
労働基準法第37条に定められる深夜労働の割増賃金に関する規定は、管理監督者にも適用されるのです。
深夜労働に対する割増賃金とは、22~5時までに働いた場合に払われるもので、25%割増分の賃金のことをいいます。
なお、労働基準法上、会社が支払う義務があるのは通常賃金(1時間あたり)×25%分であって、125%分ではないことに注意が必要です。
管理監督者の場合、所定賃金に深夜労働に対する通常の賃金(100%分)も含まれているからです。
(2)管理監督者の有給休暇と36協定について
まず、管理監督者であっても有給休暇は付与されます。
労働基準法第39条の有給休暇に関する規定は、管理監督者にも適用されるためです。
他方で、管理監督者は36協定(さぶろくきょうてい)は対象外です。
管理監督者については労働基準法の労働時間に関する規定が適用されないため、36協定は適用対象外となるのです。
管理監督者や名ばかり管理職の残業代トラブルの裁判例
それでは、具体例として、管理監督者をめぐる裁判例についてご紹介しましょう。
裁判例|アクト事件(東京地判平成18年8月7日・労判924号50頁)
地位:飲食店のマネージャー
争点:時間外労働および深夜労働に対する割増賃金支払い義務の存否
- マネージャー本人にはアルバイトの採用などについて決定権がなく、決定権を持つ店長を補佐していたに留まる
- 勤務時間に裁量がなく、アルバイトと同様の業務を行なっていた
- 基本給の厚遇がなく、役職手当なども不十分だった
判決:管理監督者に該当しない
【まとめ】管理監督者にあたらなければ残業代をもらえる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理において、経営者と一体的立場にある者のこと。肩書だけでは決まらず、実態が大事
- 管理職とは、会社が独自に決めた役職による区分で、法的に意味のある概念ではない
- 労働基準法における管理監督者には、基本的には時間外労働・休日労働に対する割増賃金は支払われないが、深夜労働に対する割増賃金は支払われる
- 会社内で「部長」や「課長」などの役職がついていても、その業務の実態について管理監督者といえない場合は、「名ばかり管理職」であって、一般の労働者と同様に時間外労働や休日労働に対する割増賃金をもらう権利がある
管理監督者でなければ、労働基準法に従って残業代をもらえます。
実は管理監督者ではないのに、誤ってそうだと扱われて残業代がもらえていなければ、それはとても残念なことですよね。
管理監督者ではないのに管理職であることを理由に残業代がもらえずお悩みの方は、弁護士への相談をお勧めします。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。