「長時間労働が続いていてしんどい……労働時間の上限ってあるのだろうか?」
実は、残業は無制限に許されているわけではなく、法律で定められた上限の範囲内でのみ許されています。
このことを知っておけば、法律で定められた上限を超えるような長時間労働に対しても適切に対応することができます。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 法律上の労働時間と所定労働時間との違い
- 法定労働時間を超える場合の36協定とそれを締結した場合の時間外労働の上限
- 変形労働時間制における労働時間の上限
法律上の労働時間と所定労働時間の違い
まずは、法律上定められた労働時間と、契約上定められた労働時間との違いについて解説します。
(1)法定労働時間とは?
法定労働時間とは、労働基準法32条で定められた労働時間の上限のことをいいます。
労働基準法32条において、原則として、1日8時間・週40時間が労働時間の上限であると定められています。
この原則1日8時間・週40時間という時間が、法定労働時間です。
法定労働時間を超えて労働をさせると、原則として労働基準法32条に違反することとなります。
したがって、会社は原則として、法定労働時間を超えて労働をさせることはできません。
労働基準法32条に違反して、法定労働時間を超えて労働をさせた場合については、刑事罰が規定されています。
具体的には、法定労働時間の規制に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります(労働基準法119条1号)。
(2)所定労働時間とは?
法定労働時間と混同しやすいのが所定労働時間です。
所定労働時間とは、会社の就業規則や契約書によって定められた契約上の労働時間のことをいいます。
所定労働時間は契約上の労働時間であるため、労働者や会社ごとに異なることがあります。
法定労働時間を超えて労働をさせた場合、労働基準法に反して違法になることから、通常は所定労働時間を決める際には法定労働時間の範囲内で定めることとなります。
所定労働時間を超えて働いた場合、原則として、残業ということになり、その分の残業代をもらうことができます。
もっとも、所定労働時間が法定労働時間よりも少ない場合のように、残業をしたとしてもそれが法定労働時間の範囲内であれば、基本的に、残業代として時間外労働の割増分を上乗せした割増賃金を支払う必要がありません。
時間外労働の割増賃金が発生するのは、原則として、法定労働時間を超える残業に限られます。
ただし、就業規則や個別の契約により、法定労働時間を超えていなくても、所定労働時間を超えて労働すれば割増賃金を支払う定めとなっていることもあります。
このため、所定労働時間を超えて残業をした場合に、残業代に割増がつけられるのかどうかは、就業規則や個別の契約も参照して判断する必要があります。
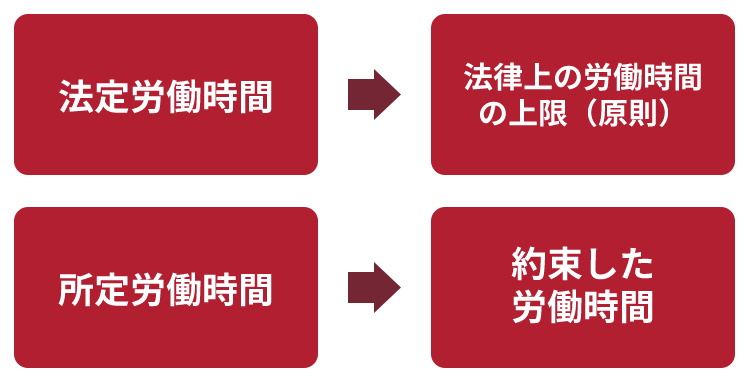
法定労働時間の上限を超える場合は36協定が必要
36協定を締結して労働基準監督署に届け出ることにより、原則1日8時間・週40時間という法定労働時間の上限を超えて労働をさせることができるようになります。
では、36協定について詳しく解説します。
(1)36協定とは?
先ほどご説明したとおり法定労働時間を超える残業(時間外労働)は、原則として、労働基準法32条に違反することになります。
しかし、労働者側と会社側との間で時間外労働をさせることについて所定の様式を満たした労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、一定時間、時間外労働をさせてもそのことが労働基準法に違反しないことになります。
このようなルールは、労働基準法36条において定められています。
このことから、このような時間外労働を可能にする労使協定のことを「36協定」(サブロク協定またはサンロク協定)とも呼びます。
(2)36協定による時間外労働の上限
36協定によって時間外労働をさせることが可能になったとしても、このような時間外労働は無制限にさせることができるわけではありません。
時間外労働についても、法律によって上限が定められています。
36協定が特別条項付きのものでない場合、時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年360時間と定められています(労働基準法36条4項)。
さらに、臨時的な特別な事情がある場合についての特別条項付き36協定を締結すれば、この月45時間・年360時間という制限を超えて時間外労働をさせることができます。
しかし、このような臨時的な特別な事情がある場合であっても、超えられない法律上の上限があります。
この上限に違反して労働をさせた場合、刑事罰が科せられることもあります。
臨時的な特別な事情がある場合に時間外労働をさせるには、原則として次のような条件を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内であること
- 時間外労働が休日労働を含めて2~6ヶ月平均80時間以内であること
- 時間外労働が休日労働を含めて月100時間未満であること
- 時間外労働が月45時間を超えるのは年6ヶ月までであること
また、これに違反した場合の刑事罰は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です(労働基準法119条1号)。
※なお、自動車の運転業務など業種によっては上記36協定の規制内容が異なることがあります。
変形労働時間制における労働時間の上限
変形労働時間制を採用した場合には、労働時間の上限について、ご説明した法定労働時間のルールとは異なるルールが適用されるようになります。
ここでは、変形労働時間制の概要や変形労働時間制の労働時間の上限について詳しく解説します。
(1)変形労働時間制とは?
変形労働時間制とは、特定の日または特定の週における労働時間が法定労働時間を超えたとしても、一定の期間を平均して週あたりの労働時間を40時間以内に定めれば、労働基準法32条に違反しないとするものです。
1日8時間・週5日などと労働時間を固定せず、月単位や年単位で労働時間を調整することが可能となります。
繁忙期と閑散期がある業種では、忙しい時期に労働時間を多くすることができるため、変形労働時間制を採用することがあります。
一定の期間を平均して週あたりの労働時間を40時間以内に定めることが必要でありますが、繁忙期における1日の所定労働時間を10時間とすることもできます。その日に実際に働いた時間が8時間を超えても、所定労働時間の10時間以内でありましたら、時間外労働の残業代は発生しません。
(2)【単位別】変形労働時間制の労働時間の上限
1週間単位、1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制の概要と、それぞれの労働時間の上限について、解説します。
(2-1)1週間単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制は、日ごとの業務の忙しさの差が著しく、労働時間を特定することが困難な零細事業者のために認められた変形労働時間制です。
1週間単位の変形労働時間制を採用することができるのは、労働者数が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店です。
1週間単位の変形労働時間制を採用した場合、1週間単位で週の労働時間が法定労働時間内に収まっている限り、1日10時間まで労働させることができます。
(2-2)1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制は、月初や月末に忙しくなる会社に適しています。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、原則として、1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内に収まる場合には、1週40時間・1日8時間を超えて労働させることができる制度です。
1ヶ月単位の変形労働時間制における月ごとの法定労働時間の総枠は、次の表のとおりです。
1ヶ月単位の変形労働時間制における月ごとの法定労働時間の総枠
1ヶ月あたりの法定労働時間の総枠
| 1週間の法定労働時間 | ||
| 1ヶ月当たりの暦上の日数 | 40時間の場合 | 44時間の場合 |
| 28日 | 160.0時間 | 176.0時間 |
| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |
| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |
| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |
なお、1ヶ月単位の変形労働時間制は、労使協定または就業規則で定めればよく、労働基準監督署へ届け出る必要はありません。
(2-3)1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内であれば、特定の日や週に1日8時間・1週40時間を超えた一定の限度で労働させることができる制度です。
1年単位の変形労働時間制は、休日が繁忙期であったり季節ごとに忙しさが変わるという業種に適しています。
1年単位の変形労働時間制において、法定労働時間の総枠は、365日当たり2085.7時間、うるう年には366日当たり2091.4時間となります。
また、労働時間の限度は、原則として、1日10時間、1週52時間、連続して労働させることができる日数は6日、期間内の所定労働日数の上限は1年280日とされています。
参考:週40時間労働制の実現 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制|厚生労働省
1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月単位の変形労働時間制とは異なり、労使協定を締結したうえで労働基準監督署へ届け出る必要があります。
【まとめ】労働時間には法律で定められた上限がある
この記事のまとめは、次のとおりです。
- 法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限のことをいう。
原則として、1日8時間・週40時間が労働時間の上限であると定められている。 - 所定労働時間とは、会社の就業規則や契約書によって定められた契約上の労働時間のことをいう。
- 36協定を締結・届出することで、法定労働時間を超える残業(時間外労働)が可能になる。
- 36協定による時間外労働にも上限があり、原則、月45時間・年360時間とされている。
- 変形労働時間制とは、1日8時間・週5日などと労働時間を固定せず、1週間単位、1ヶ月単位、1年単位で労働時間を調整する方法。
1週間単位、1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制でそれぞれ適用されるルールが異なる。
長時間労働が多いなどのために労働時間に関して困っている方は、次の窓口など公的機関に相談するとよいでしょう。
また、長時間労働を強いられている場合、残業代が未払いになってしまっていることも少なくありません。
未払い残業代があるかもしれないという場合には、弁護士に相談することがおすすめです。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からのお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年3月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。



