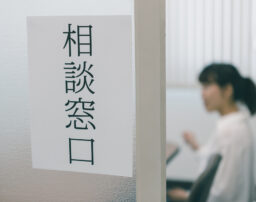夫婦間のコミュニケーション不足は、夫婦関係の悪化を招く大きな要因です。
特に妻が夫との会話を避ける場合、夫はその原因を理解し、適切な対策を講じる必要があります。この記事では、妻が会話を避ける典型的なケースとその背景、そして関係修復に向けた具体的なアプローチを解説します。
夫婦間の親密さや絆を取り戻し、家庭の雰囲気を良くするためのヒントを紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでわかること
- 会話をしない妻の典型的なケース
- 会話をしない妻との関係修復のアプローチ法
- 妻との関係修復が困難なときの対処法
ここを押さえればOK!
妻が会話を避ける典型的なケースとしては、コミュニケーションを諦めている、夫からの謝罪を待っている、仕事や家事育児で疲れている、夫に対する愛情がなくなった、夫の浮気がバレた、妻が浮気している場合があります。
関係修復のための具体的なアプローチとして、日常的にコミュニケーションを増やす、傾聴と共感の姿勢で聞く、妻の「自分時間確保」に協力することが効果的です。
これらの方法を試しても改善が見られない場合、夫婦カウンセリングや別居という対処法もあります。
最終的に離婚を考える場合、親権、養育費、面会交流、財産分与などについて事前に検討し、弁護士に相談することが重要です。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
「会話をしない妻」の典型的なケース
妻が夫と会話をしない典型的なケースを5つ紹介します。
(1)夫とのコミュニケーションをあきらめている
妻が夫とのコミュニケーションをあきらめている場合には、もはや夫と会話をしようとはしないでしょう。
長年のコミュニケーションの不満が積もり積もって、このような状態に至ります。
不満の原因は様々です。
「話したかったが聞いてくれない」
「夫に会話を拒否された」
「話しても否定されるばかりで会話が楽しくない」
妻としては、不満や問題点について何度も話し合いを試みたかもしれません。それでも解決に至らず、絶望し、最終的に話すこと自体をあきらめてしまうのです。
(2)夫からの謝罪を待っている
妻が会話を避ける理由の一つに、夫からの謝罪を待っているケースがあります。
謝罪を求める理由は様々です。夫が妻を傷つける発言をしたかもしれないし、夫婦喧嘩の理由が夫にあると思っているかもしれません。
暗に夫を責める趣旨で、妻から会話をせず、夫に反省を促しているのです。
(3)仕事や家事、育児で忙しく疲れている
妻は、毎日終わりのない家事や育児、仕事で忙しく、ただただ疲れており、夫と会話する気力や時間がないことがあります。
分刻みのスケジュールをこなす毎日で、夫との会話に費やす時間が、ついつい後回しになってしまっているのかもしれません。それでも、夫との会話が楽しかったり、ストレス解消になったりする場合には積極的に夫と話すでしょう。
しかし、夫との会話で逆に疲れるようなら、あえて話をする理由がありません。
(3)妻の夫に対する愛情がなくなった
妻が夫に対する愛情を失った場合、会話を避けることがあります。
ある時何かをきっかけに突然愛情を失うこともありますが、多くのケースでは、夫の関係が悪化する中でだんだんと愛情を失っていきます。
家族として必要な最低限の伝言はするかもしれませんが、積極的な会話をしなくなったのであれば、妻の夫に対する愛情がなくなったのかもしれません。
(4)夫が浮気しているのが妻にバレた
夫の浮気に気づいた場合、妻はショックや怒りから夫との会話を避けることがあります。
会話がなくなるだけでなく、突然身体的な接触を拒まれた場合には、生理的な拒否反応も生じているおそれがあります。
夫が疑われるような行為をしていないか、顧みる必要がありそうです。
(5)妻が浮気している
妻が浮気をしている場合、罪悪感や秘密を抱えているため、会話を避けることがあります。また、不倫相手に夢中で夫に対する愛情が薄れ、会話をしたくなくなっているかもしれません。
しかし逆に、妻が浮気によって精神的に満たされていることで、夫にやさしくできるというケースもあるようです。
「会話をしない妻」との関係修復に効果的な具体的アプローチ
会話をしない妻との関係を改善したいと思ったら、関係修復のために何らかの行動をとる必要があります。
「妻が態度を改めるべきだ」と思うかもしれませんが、妻が会話をしないと決めたのであれば、待っていても状況は改善しないでしょう。
具体的なアプローチ方法を紹介します。
(1)日常的にコミュニケーションをとる回数を増やす
妻と会話をして状況を改善したいのであれば、夫の方から何かとコミュニケーションを取るようにしてみましょう。
「おはよう」「おやすみ」の挨拶、何かをしてもらった時の「ありがとう」というお礼、用意されたご飯がおいしかったときに「これおいしいね」という作り手への配慮の言葉など、声をかけるきっかけはたくさんあります。
そのきっかけから、会話の幅が広がり、妻の心も開ければ、「会話をしない妻」との関係から脱却できるかもしれません。
(2)傾聴と共感の姿勢で聞く
妻が会話をしたら、「9割聞いて1割返事をする」というイメージで、話の腰を折らず、傾聴の姿勢で話を聞きましょう。
うなずいたり、相づちをうったり、「それで?」と続きを促したりすると、妻は「話を聞いてもらえている」と実感できますので、より会話が弾むかもしれません。
そして、妻の話は、否定や議論をするのではなく、受け入れて共感するようにしましょう。
自分の話したことを否定されたり、議論したいわけでもないのに論争的な会話になってしまったりしたら、話していても楽しくありません。
妻の、「夫が自分の話を聞いてくれた」「夫が自分の気持ちを理解してくれた」という感情は、また話してみようかなという動機づけにもつながります。
最後に、「話してくれてありがとう」という気持ちを伝えるのもよいでしょう。
(3)妻の「自分時間確保」に協力する
妻が仕事や家事育児で忙しく、ストレスがたまっていて夫と会話する余裕もないような場合には、妻の「自分時間確保」に協力しましょう。
一日に、妻がどれだけ自分の時間を確保できているか、冷静に観察してみましょう。
想像以上に家族に費やしている時間が多く、びっくりする方も多いと思います。
自分のためのプライベートな時間を過ごすことは、ストレス解消に繋がりますし、何よりも自分が自分らしくいるために必要です。
自分時間を確保して、自分の気持ちに余裕ができれば、他人とコミュニケーションをとる気持ちになるかもしれません。
いつも妻がしている子どもの世話を引き受ける、子どもを公園や外食に連れ出す、洗濯や掃除などの家事を引き受ける、などして、妻が1人で好きなことをできる時間を確保できるよう協力してみましょう。
妻との会話回復が困難な場合の対処法
「しきりに話しかけ、何か悪いことをしたかもしれないと謝ったし、感謝の気持ちを伝えて贈り物をしてみた。それでも妻は会話をしない」
関係修復のために様々なアプローチしたけれども、期待していたような効果が見られないこともあります。
そのような場合には、次のような対処法があります。
(1)夫婦カウンセリング
夫婦の問題は、夫が考えているよりもっと根深いのかもしれません。
プロの手を借りることも視野に入れましょう。
夫婦カウンセリングは、カウンセラーの助けを借りて夫婦の問題を把握し、夫婦関係を改善するために有効なことがあります。
カウンセリングを受ける際は、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。
口コミや紹介を参考にし、夫婦双方が納得できるカウンセラーを選びましょう。
もし妻の協力が得られない場合には、夫だけで参加しても、解決の糸口が得られるかもしれません。
(2)別居
いろいろ努力したが関係修復が難しい場合、お互い離れて冷静に問題を把握するために、別居を検討することも一つの選択肢です。
ただし、法律上、夫婦には「同居」「協力」「扶助」の義務がありますので(民法第752条)、別居する際には同意を得るようにしましょう。また、別居していても、収入のある方は相手に婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。
また、別居により物理的に離れることで、夫婦として関係が破綻してしまい、離婚やむなしという状況になる可能性があることに注意が必要です。
実際に、離婚前に別居する夫婦は多いです。
あなたに不倫などの有責行為があったケースを除き、一定期間別居をすると、妻が離婚を拒否したとしても、裁判で「婚姻関係は破綻している」として離婚が認められる可能性が高まるためです。
「会話をしない妻」と離婚するには
努力したけれども、どうしても妻が会話しない、夫を無視するという状況で、妻とは離婚したいと考える方もいるかもしれません。
話し合いによる離婚の場合は、離婚の理由は問われません。妻と離婚について合意できれば、離婚することができます。
しかし、妻が離婚を拒否した場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。離婚調停でも離婚に合意できなければ、離婚訴訟を提起しなければなりません。
離婚訴訟で裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定の離婚事由が必要です。
「妻が会話をしない」という事実だけでは、通常、法定の離婚事由ということは困難ですので、別居期間が長年にわたり夫婦関係は破綻している、妻が肉体関係を伴う不倫をしているなどの事情が必要です。
離婚する際に検討すべきこと
離婚する際に、検討すべきことはたくさんあります。
離婚条件は、離婚前にしっかり検討しておきましょう。
(1)子どもに関すること
未成年の子がいる場合、子どもについて話し合って決めておくべきことは次の3つです。
(1-1)親権
「親権」とは、未成年者の子どもを監護・養育し、子どもの財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことです。
結婚中は、夫婦が共同で親権を持ちます。
離婚後は、どちらが未成年の子の親権を持つかを決め、離婚届の際にどちらか一方を指定します(※)。
※2024年5月、離婚後も共同親権を選択できるよう法改正がなされました。改正法が施行されたあとは、協議により、単独親権とするか、共同親権とするかを選択することができます。親権者について争いがあり、調停又は審判の申立をしている場合には、親権者を定めなくても離婚することが可能です。
(1-2)養育費
「養育費」とは「未成熟子(社会的経済的に自立していない子)の監護や教育のために必要な費用」のことです。
一般的に子どもと離れて暮らす親が、子どもと暮らす親に支払うものです。
養育費の金額に決まりはなく、話し合いで自由に決めることができます。
離婚時にきちとんときめておくことが大事です(※)。
なお、裁判や調停では、「養育費算定表」と呼ばれる養育費の目安金額があります。話し合いでも「養育費算定表」を参考に養育費を決めると、養育費を支払う側にとっても養育費の金額に納得を得やすく、合意が成立しやすくなります。
こちらのツールで、養育費のシミュレーションができますのでご利用ください。
※2024年5月、夫婦の合意がなくても、離婚の日から法務省令により定められた額について、養育費を請求できるよう法改正がなされました。改正法の施行後は、養育費の合意がなくても一定額を請求できるようになります。
(1-3)面会交流
「面会交流」とは、子どもと一緒に暮らさない親が子どもに会ったり交流したりすることです。
面会交流の頻度や方法については、父母が子どものことを考えて話し合いで決めます。
1ケ月に1回程度が多いようですが、回数や内容については、夫婦の話し合いによって決めることができます。
(2)財産に関すること
離婚する際には、財産の取り扱いもしっかり確認しておきましょう。
(2-1)婚姻費用
婚姻費用とは、婚姻期間中の生活費のことです。
法律上は夫婦である以上、仮に別居していても、相互に生活費を分担する義務があります。
また、仮に、別居している場合であっても、生活費は分担する義務があります。
婚姻費用は、収入が高い方が低い方に支払うもので、夫婦の収入の差や、子どもの年・人数によって異なります。
婚姻費用は、夫婦の話し合いによって決めることができますが、実務では裁判所が公表している婚姻費用算定表を利用して算定することが多いです。
次のツールでも、婚姻費用をシミュレーションできますのでご利用ください。
(2-2)財産分与
「財産分与」とは、結婚後、夫婦でこれまで築いてきた財産を二人で分けることです。
夫婦の共有名義になっている財産だけでなく、夫婦どちらか一方の名義の財産も対象に含まれます。
また、財産というと、お金をイメージするかもしれませんが、お金以外の不動産、自動車、投資信託、退職金などの財産も対象となります。
夫婦の財産について、調査確認したうえで、どのように分けるか考える必要があります。
原則、分割の割合は2分の1ですが、話し合いによりどちらかの財産を多くすることもできます。
(3)離婚協議における弁護士の重要性
離婚協議を進める際は、事前に弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士はあなたの具体的な状況に応じて、法的なアドバイスを提供してくれるでしょう。
また、当事者同士で冷静に話し合うことが難しい、直接話し合いたくない、離婚条件がまとまらないなど、お悩みの方は、離婚協議を弁護士に依頼して、弁護士に代わりに妻と話し合ってもらうこともできます。弁護士は、離婚協議書も作成できますし、調停などの手続も代理で行います。
電話で相談できる事務所も多くなっていますので、一度相談する事をお勧めします。
【まとめ】「会話をしない妻」との関係改善をあきらめない!どうしても関係修復が困難で離婚を考える場合は準備を
会話をしない妻との関係を改善するためには、夫自身の努力と理解が不可欠です。今すぐ、妻とのコミュニケーションを見直し、具体的なアクションを始めてみましょう。小さな一歩が、大きな変化をもたらします。
努力してもどうしても関係を改善できず、離婚を希望する方は、事前に離婚条件について検討し、弁護士に相談してアドバイスを求めるとよいでしょう。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2025年1月時点)。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。