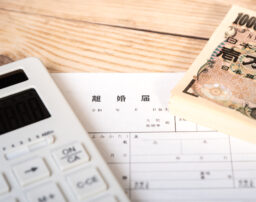離婚慰謝料の請求を考えているものの、「もう時間が経ってしまったから無理かも…」と時効について不安を感じていませんか?
離婚慰謝料には法律で定められた時効期間があり、それを過ぎると請求が難しくなります。しかし、時効の進行を止める方法や、たとえ時効が過ぎたと思っても慰謝料を請求できるケースも存在します。
この記事では、離婚慰謝料の時効に関する基本的な知識から、時効の進行を止める方法、そして時効が過ぎてしまった場合の対処法まで、あなたが抱える疑問を解消し、適切な行動をとるための具体的な情報をお伝えします。
ここを押さえればOK!
不倫が原因で離婚した場合、原則として、離婚慰謝料を請求できるのは(元)配偶者だけで、不倫相手には請求できません。不倫相手に請求できるのは、不貞行為を原因とした慰謝料で、不倫の事実と加害者を知った時から3年で時効にかかります。
もし時効の完成が迫っていても、適切な手続きで進行を止めることが可能です。例えば、内容証明郵便を送付すれば請求から6ヶ月間、時効の完成を一時的に猶予できます。
また、相手が慰謝料の支払いを認めたり、一部を支払ったりした場合は「時効の更新」となり、時効期間がリセットされます。
たとえ時効期間が過ぎてしまっても、相手が「時効の援用」を主張しない限り、法的には請求権は消滅しません。ただし、通常は相手が時効を援用するため、請求の難易度は格段に上がります。
弁護士に相談・依頼することで、慰謝料請求の時効期間の判断、時効阻止のための法的手続き、冷静な相手方との交渉を進められるでしょう。精神的な負担の軽減も期待できます。
離婚慰謝料や、不倫相手へ慰謝料請求を考えている方は、1人で悩まず、早めにアディーレ法律事務所にご相談ください。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
離婚慰謝料を請求できる権利は離婚後3年で時効にかかる
民法では、権利があるのにそれを行使しないまま放置している場合、一定期間の経過により権利が消滅するという制度(消滅時効)が設けられています。
離婚慰謝料の請求権については、離婚が成立した日から3年で時効が完成します。
これは、民法724条1号に規定されている「損害および加害者を知った時から3年間行使しないとき」には、「時効によって消滅する」という条文に基づきます。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
引用:民法第724条|e-gov
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
この条文は、「損害及び加害者を知ったときから3年」「不法行為の時から20年」のいずれか早い時点で時効は成立する、という意味です。
離婚慰謝料の場合は、「離婚の日」から3年で時効にかかることになります。時効期間を過ぎてしまった場合、(元)配偶者に対して離婚慰謝料を請求するのは難しくなります。
したがって、離婚後に慰謝料を請求したい場合は、この期間を強く意識する必要があります。
離婚慰謝料は不倫相手には請求できない
「離婚は不倫が原因だから、離婚慰謝料を不倫相手にも請求したい」と思われるかもしれません。
しかし、不倫相手には、原則として「離婚慰謝料」を請求することはできません。
2019年に、最高裁で、基本的に不倫相手には離婚慰謝料を請求できないという判決が出ています。これは離婚した原因に不倫相手が関係していても、離婚を決断したのは夫婦の問題なので不倫相手は関係ないという考え方によるものです。
離婚慰謝料を不倫相手に請求できるのは、次のような「特段の事情」がある場合に限られます。
単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる
引用:最高裁判決平成31年2月19日|裁判所 – Courts in Japan
不倫相手への慰謝料請求権は不倫の事実と加害者を知ってから3年で時効
不倫相手も不倫をしたことについて責任を負いますので、不倫をされた配偶者は、不倫相手に対し、不倫に対する慰謝料請求をすることができます。
この不倫慰謝料の請求は、「不倫(肉体関係)のあった事実」及び「不倫相手の名前」を知ったときから3年で時効にかかります。
不倫があった時点から20年経過している場合には、不倫を知らず、また不倫相手が誰だか分からないままでも時効は成立します。
離婚慰謝料の時効の進行を止める方法
時効の完成を阻止し、慰謝料請求の機会を失わないための法的な手段(完成猶予・更新)が民法には定められています。
時効が迫っている場合には、次のような時効の進行を止める方法をとりましょう。
適切に行わなければ、時効の完成を阻止できないリスクがありますので、不倫の慰謝料請求や離婚慰謝料の請求を扱っている弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
(1)時効の「完成猶予」をする
時効の「完成猶予」とは、時効の完成が一時的に猶予され、その期間中は時効が完成しない制度です。時効の完成を一時的に猶予します。猶予されている期間は、時効が成立しません。
時効の完成猶予をする主な方法は次のとおりです。
(1-1)内容証明郵便で慰謝料請求する
内容証明郵便など確定日付のある書面によって慰謝料の請求書を送付(催告)することで、時効の完成を先延ばし=完成の猶予をすることができます。
先延ばしできる期間は、慰謝料を請求してから6ヶ月で、その期間は時効が完成しません。
ただし、内容証明郵便による時効の先延ばしは1回だけです。
さらに時効の完成の先延ばしをするためには、6ヶ月以内に裁判を提起するなどの手段を取る必要があります。
(催告による時効の完成猶予)
引用:民法第150条|e-Gov 法令検索
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
(1-2)慰謝料について話し合う合意をする
慰謝料について話し合いを行う内容の合意を、書面又は電磁的記録でしたときは、次の1~3のうちいずれか早いときまでの間、時効の完成が先延ばし(完成の猶予)されます。
- 慰謝料について話し合いを行う合意があったときから1年を経過したとき
- 合意において定められた話し合い期間(1年未満に限る)を経過したとき
- どちらかが話し合いの続行を拒絶する内容の書面の通知をしたときから6ヶ月を経過したとき
話し合いの合意をして時効完成が猶予されている間に、再度話し合いの合意をした場合には、再度時効期間は先延ばしされ時効完成は猶予されます。ただし、その期間は、時効完成が猶予されなければ時効が完成していた時期から、5年を超えることはできません。
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
引用:民法151条|e-gov
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
(2)時効の「更新」をする
時効の「更新」とは、時効が新たに進行し始める制度です。
例えば、時効が2年6ヶ月進行していたとしても、時効の更新があれば、その時点から新たに時効期間が進行します。時効の更新をする主な方法は次のとおりです。
(2-1)相手に慰謝料の支払いを認めさせる
相手が慰謝料の支払い義務を認めた場合には、時効が更新され、その時から新たに時効が進行します。
その際には、慰謝料の支払いに関する書類を準備して、署名捺印させましょう。相手が慰謝料の支払いを認めた証拠となります。
また、相手が慰謝料の一部を支払った場合、慰謝料の支払い期限の延長を求めてきた場合、減額を求めてきた場合も、慰謝料の支払いを認めたものとして、時効の更新事由になります。
(承認による時効の更新)
引用:民法152条|e-gov
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
(2-2)慰謝料の支払いを求めて裁判所に訴える
裁判所に慰謝料請求の訴えの提起(もしくは支払督促、調停)することで、時効の完成が猶予されます。
そして、「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したとき」、言い換えると、「確定判決が出た時もしくは裁判上の和解をした時」から、新たに時効が進行(更新)します。
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
引用:民法第147条|e-gov
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
離婚慰謝料の時効が過ぎてしまったら?
時効が完成した後にどのように対処すべきか、また時効が成立した後でも慰謝料請求が認められるケースがあるのかについて解説します。
(1)時効が過ぎた慰謝料は請求できない?「時効の援用」とは
時効期間が経過したからといって、自動的に慰謝料請求権が消滅するわけではありません。時効によって請求権を消滅させるためには、相手方(元配偶者など)が「時効を援用する」必要があります。
時効の援用とは、時効の完成によって得られる利益を享受する意思を相手方に伝えることです。時効を援用しない限り、法的には慰謝料請求権は消滅せず、請求自体は可能です。
しかし、通常は相手方が時効の援用を主張してくることが予想されるため、時効期間が経過した場合は、請求の難易度が格段に上がります。
(2)時効期間経過後でも慰謝料請求が認められるケース
例えば、相手方が時効期間経過後に慰謝料を支払う意思を示したり、一部でも支払いに応じたりした場合は、「債務の承認」とみなされ、また新たな時効期間が進行することになります。
時効期間経過後に支払いを求める場合には、支払う意思を示した証拠が残るように通話を録音するなど、証拠が残る手段を事前に検討すべきでしょう。
離婚慰謝料請求は弁護士への相談がおすすめ
離婚の際には、有責配偶者に対する慰謝料だけでなく、財産分与や養育費など、様々な取り決めを行う必要があります。
法律や実務の知識がなければ適切な判断が難しく、結果として損してしまうかもしれません。離婚を検討している方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
離婚後の慰謝料請求も、弁護士に相談・依頼することで、様々なサポートを受けることができます。
まず、あなたのケースにおける正確な時効期間と起算点を特定し、時効の完成日を明確に判断してもらえます。その上で、時効の完成猶予や更新のための適切な法的手続き(内容証明郵便の送付、調停申立て、訴訟提起など)を迅速に実施してくれます。
これにより、時効による請求権の消滅を防ぎ、慰謝料を請求できる状態を維持することが可能になるでしょう。
また、相手方との交渉や調停、訴訟といった手続き全般を弁護士が代理することで、あなたの精神的な負担を大きく軽減することが期待できます。
【まとめ】
離婚慰謝料は、離婚後3年で時効にかかり請求が難しくなります。
しかし、時効が間もなく完成してしまうという段階でも、適切な手続きを取ることにより、時効の完成を一時的に猶予することは可能です。
「離婚してから2年たったけどまだ1年ある」と思っていても、元配偶者の住所や連絡先を調べたり、証拠を精査したりするのも時間が必要ですので、ゆっくりはできません。
離婚後に離婚慰謝料の請求を考えている方は、なるべく早く弁護士に相談する事をお勧めします。
アディーレ法律事務所では、不倫相手の慰謝料請求、(元)配偶者に対する離婚慰謝料請求を扱っておりますので、一度是非ご相談ください。