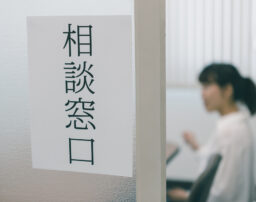「家事をしない夫」に悩んでいる方は少なくありません。
共働きの世帯が増えているとはいえ、買い出し、食事の準備や片付け、洗濯、掃除など、主な家事の負担は妻に偏っているのが現状ではないでしょうか。
妻が家事の負担の大部分を担うことで、妻に「私も働いているのに夫は家事をしない」「言ってもやってくれない」とストレスが溜まり、夫に対する怒りやあきらめ、失望などから夫婦関係が悪化することもあります。
この記事では、「家事をしない夫」に家事をさせるためのアプローチ法と、家事をしない夫と離婚するときの注意点などを解説します。
この記事を読んでわかること
- 家事分担の法的位置づけ
- 家事をしない夫に家事をさせるためのアプローチ
- 家事をしない夫と離婚する方法
ここを押さえればOK!
家事分担の協力は、民法752条に基づく夫婦の協力義務に基づくもので、家事の協力を要請することには法的根拠があります。夫が協力を拒否し続ける場合、家庭裁判所での調停を申し立てることが可能です。
夫が家事分担の協力を拒否し続ければ、その事実が「婚姻を継続しがたい重大な事由」の事情として考慮されるでしょう。
夫に家事をさせるための具体的な方法としては、夫婦間の話し合いや家事分担契約の締結があります。話し合いでは、夫を一方的に責めず、協力して家庭を築く姿勢を持つことが重要です。また、夫が家事をした際には大げさに感謝の気持ちを示すことで、夫の自主的な家事参加を促しましょう。
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があり、財産分与や養育費についてもきちんと取り決めることが重要です。離婚を考える場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
家事分担の法的位置づけ:夫婦の義務と権利
「夫婦は協力し合うべき」と言われます。夫婦として家庭を築いていくには、夫婦間に協力が必要なことは、当然のことです。
しかし、実はこれには法的な根拠があります。
(1)民法における夫婦の協力義務とは
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法752条では、夫婦が互いに負う義務について次の3つを定めています。
① 同居義務
② 協力義務
③ 扶助義務
家事分担で関わるのは、2の義務です。2の義務には夫婦の家事分担に協力する義務も含まれると考えられています。つまり、夫婦の一方は、他方に対して、法律の根拠をもって家事分担の協力を求めることができるのです。
(2)家事分担の協力義務に違反する効果
では、例えば妻が夫に対して「食べ終わったお皿を下げないので下げるように協力を要求した」のに対し、夫が拒否し続けて話し合いでまとまらないとしたら、その法的な効果はあるのでしょうか。
協力義務について夫婦で話し合っても合意できない場合、家庭裁判所に、調停や審判を申し立てて、調停委員の仲介のもとで、協力義務について夫婦で話し合うことはできます。
しかし、話し合いでまとまる調停ならともかく、審判で、裁判所が夫に対して「食べ終わったお皿は毎回下げること」と命じることは、考えにくいです。
協力義務にかかわる夫婦げんかについて、裁判所が一方に具体的な行動を命じること(審判)は適切といえるのか、という問題があるためです。そのような段階にある夫婦は、もはや夫婦としては破綻していると言わざるをえないのではないでしょうか。
「じゃあ、拒否しても何も法的な効果はないのか」と思われるかもしれませんが、あながちそうとも言えません。
なぜなら、夫婦協力義務に関して、協力を拒否し続ければ、法定の離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)で考慮されるからです。
つまり、妻が夫に家事分担の協力を要請し続けているのに、拒否し続けられたことで、夫婦関係が悪化して離婚やむなしという判断に陥ったとすれば、その事情も「婚姻を継続しがたい重大な事由」で考慮されることで、裁判上の離婚請求が認められる可能性があります。
家事をしない夫に家事をさせるための法的アプローチ
妻は、「どうすれば夫は家事をしてくれるのだろう」と頭を悩ませています。
あきらめて「全部自分でやると決めた方がストレスがない」という境地に達している妻もいるかもしれません。
「弁護士が法的に家事分担を改善する案を考えてみた」ということで、法的なアプローチ方法を下記で紹介しますが、現実的には利用しにくいと思われます。
家事分担は、やはり夫婦の話し合いにより、臨機応変に自主的に行われるべきもので、「契約で縛らなければ協力義務を実践しない」という夫婦の状況は、すでに離婚やむなしという状態まで夫婦関係は破綻しているのではないか、と疑わざるを得ないからです。
夫婦間での家事分担契約を締結する
家事分担について夫婦間で契約することで、夫婦間の家事分担を明確にすることができ、契約に基づいて相手に家事を請求することができるでしょう。
仮に、法的な拘束力がない内容であっても、夫婦が任意に従うことはできますので、夫婦間で取り決めする意義はあります。
契約書に記載すべき内容としては、次のようなものが考えられます。
- 家事の具体的な内容と担当者
- 家事の役割分担の期間
- 契約違反時の罰則
- 当事者の署名押印
- 契約日
誤解のないよう、話し合いながら明確に定めるとよいでしょう。
家事をしない夫に対して家事をさせるための実践的方法
家事をしない夫に対して、家事をしてもらうために考えられる実践的方法を紹介します。
(1)夫婦の話し合い
まず、基本的方法として考えられるのが夫婦の話し合いです。
夫婦とはいえ育った環境も価値観も異なります。問題があれば、そのたびに話し合って価値観をすり合わせたうえで、譲歩しあう必要があります。
せっかく縁あって夫婦となったのですから、コミュニケーションをとることをあきらめず、改善のために話し合ってみましょう。
話し合う際には、次の点に注意してみましょう。
- 夫を一方的に責めない
- 大変だから二人で努力して乗り切るという姿勢で話す(夫と敵対するのではなく、協力して家庭を築く)
- 妻に意見があるように夫にも意見があるので、夫の意見も聞く
- 抽象的に「大変」と言っても伝わりにくいので、具体的に、見えない家事などについても説明する
(2)夫が自主的に家事をするための戦略
家事をしてくれない夫に対して、「なんでやらないの」「やってって言ったよね」とついついイライラして責めることはありませんか。
しかし、自分の意見や考えのある対等な立場である大人が、このような一方的な指示や批判を受けても、心理的な抵抗感から、指示に従わないということも十分考えられます。
夫に「●●をやって」と指示を出す限り、やはり夫は心理的な抵抗を感じ、あまり家事分担は進まないかもしれません。
そんなときは、夫がしてくれた家事について、大げさに喜びや感謝の気持ちを示してみてはどうでしょうか。
「ありがとう」「うれしい」といわれて、嫌な気がする人はいません。
夫は、「こんなに喜んでくれるならもうちょっと家事をしてみよう」と思い、家事をするモチベーションにつながるでしょう。
家事をしない夫について最終手段としての離婚
いろいろ努力したけれども、やはり夫は家事をしない、離婚したいという方もいます。
ここでは、離婚の種類や、手続きについて説明します。
(1)離婚の種類と手続きの概要
離婚には、次の協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。ほとんどの方が協議離婚(話し合いによる離婚)で離婚が成立します。
• 協議離婚:夫婦間の合意による離婚
• 調停離婚:家庭裁判所に調停を申し立てて調停で離婚
• 裁判離婚:裁判所の判決による離婚
しかし、夫が話し合いでの離婚に応じないとなると、調停や裁判で離婚を求めていく必要があります。
(2)財産分与と養育費に関する法的知識
離婚に際しては、今後の生活にも関わりますので、お金に関すること、特に財産分与と養育費についてきちんと取り決めをすることが重要です。
財産分与は、基本的に婚姻中夫婦の協力で築き上げた共有財産を、公平に(2分の1ずつ)分配します。
養育費は、離婚後の未成熟子とともに暮らす側が、離れて暮らす側の親に対して生活費を請求し、子どものための生活費とします。
離婚後も話し合うことは可能ですが、物理的に離れてしまうと話し合い自体が困難になることもありますので、離婚前に、夫婦で話し合うようにしましょう。
「夫とは話し合いたくない」「冷静に話し合うことができない」というときは、離婚を扱う弁護士に依頼すると、本人に代わり夫と離婚について交渉してもらえます。
【まとめ】
「家事をしない夫」をあきらめてしまう前に、再度、話し合う、大げさに褒め称えるなどして夫に自主的に家事をしてもらえるよう、コミュニケーションをとってみましょう。
他人を一方的に変えることは困難です。「自分がまず変わることで、他人に影響を及ぼす」という考えで取り組むと、よいかもしれません。
この記事がよりよい夫婦関係、より良い家庭環境を築くきっかけになればと思います。
夫婦関係の修復が困難で、離婚を考えている方は、一度弁護士に相談してみましょう。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます)。
また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2025年2月時点)。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。