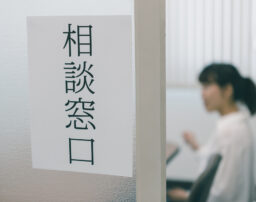「夫婦が生活費を折半するのはおかしいのでは?」と感じていませんか。
共働き、専業主婦(夫)など、夫婦の形によって夫婦の家計のあり方も様々ですが、生活費の負担割合についての悩みが尽きない夫婦もいるかもしれません。
この記事では、夫婦の生活費折半が「おかしい」と感じる理由や、適切な負担割合の決め方、円満な家計管理法について詳しく解説します。
この記事が、夫婦間の金銭トラブルを未然に防ぎ、より良い家計管理の実現に繋がれば幸いです。
この記事を読んでわかること
- 夫婦の生活費折半がおかしいと感じる理由
- 夫婦の生活費折半のメリットとデメリット
- 状況別生活費折半がおかしいと感じやすいケース
- 夫婦の円満な生活費負担割合の決め方
ここを押さえればOK!
生活費折半のメリットには、支出の負担割合が明確で節約に繋がる点があります。しかし、デメリットとして収入差や家事育児の負担の偏りにより不公平感が生じやすいことが挙げられます。
専業主婦(夫)世帯では、生活費折半は現実的ではなく、共働きで収入差がある場合は収入に比例した負担割合が公平です。また、家事育児の負担が一方に偏る場合は、生活費の負担割合を調整することが重要です。
夫婦の財産管理法として、共通財布制、別財布制、一方負担制があります。それぞれの方法にメリットとデメリットがあり、夫婦の状況に応じて選ぶことが大切です。
最後に、生活費の負担や家計については、適宜夫婦で話し合いを行い、柔軟に対応することが重要です。収入差や家事育児の負担を考慮し、公平で円満な家計管理を目指しましょう。
夫婦の生活費折半が「おかしい」と感じる理由とは?
夫婦の生活費を折半することが「おかしい」と感じる主な理由は、次の2つです。
- 収入差があるのに生活費折半はおかしい
- 家事育児の負担が大きいのに生活費折半はおかしい
夫婦の収入差が大きい場合、生活費として同じ額を負担することは不公平だと感じられることがあります。また、家事や育児の負担が一方に偏ると、生活費も折半しなければならないとなると不合理だと感じることもあります。
このような「おかしい」と感じる理由を放置していると、夫婦間で不満が生じやすくなります。
夫婦の生活費折半のメリット
生活費折半には次のようなメリットがあります。
- 家計の支出の負担割合が明確でわかりやすい
- 折半しなければならないので節約につながる
夫婦が生活費折半に納得しているのであれば、わかりやすい家計管理方法です。
生活費折半のデメリット
一方で、生活費を折半することには次のようなデメリットも存在します。
- 収入差がある場合の不公平感
- 家事や育児の負担が一方に偏る場合に不満がたまる
- 収入や生活の変化に対応しづらい
これらのデメリットが原因で、夫婦間の一方が不満を抱え、それが夫婦間の不仲につながるなどトラブルが生じることがあります。
夫婦の状況別:生活費折半がおかしいと感じやすいケース
夫婦の状況別に、生活費折半がおかしいと感じやすいケースについて対処法を紹介します。
(1)専業主婦(夫)世帯
専業主婦(夫)世帯では、夫婦が生活費を折半することは現実的ではありません。
一方に収入がないのですから、生活費を出さなければならないとなると、独身時代の貯金を切り崩すことになります。しかし、いつか貯金もなくなります。このような状況を強いられる専業主婦(夫)のストレスは非常に大きく、夫婦仲に影響しないとは考えにくいです。
夫婦の合意で一方が専業主婦(夫)となっているのであれば、一般的には、収入を得ている側が生活費を全額負担しているでしょう。
「一方が専業主婦(夫)であることに反対だが、働いてくれない」という不満を抱える方もいるかもしれません。
そのような場合には、相手の気持ちにも配慮しながら、働いてほしい理由について、しっかりと伝えて話し合ってみてください。
仕事を見つける方法、どんな仕事が向いているかなど具体的にアドバイスしてあげられると、配偶者も動きやすくなるでしょう。
(2)共働きだが夫婦の収入差が大きい世帯
共働きで双方収入があるが、収入差が大きい場合、収入に比例した負担割合を採用することが公平です。
例えば、収入が2倍の差がある場合、高収入の側が2倍の生活費を負担する方法が考えられます。
(3)共働きでも家事育児の負担に差がある世帯
共働きで収入もほぼ同じであれば、生活費折半も納得できるかもしれませんね。
しかし、家事育児の負担に差がある場合、収入が同じであっても、生活費の折半は不公平に感じられ、不満がたまることがあります。
この場合、家事育児負担が公平になるよう話し合うとよいでしょう。
しかし、一方が帰宅が遅かったりすると、物理的に家事育児の負担を公平にするのは困難かもしれません。そのようなときは、家事育児の負担を考慮して、生活費の負担割合を調整すると、夫婦ともに納得しやすいでしょう。
夫婦の財産管理法
夫婦の財産管理には、大きく「同じ財布で管理する」か、「別の財布で管理する」か、「一方の財布だけ利用する」かの3種類あります。それぞれ紹介します。
(1)共通財布制
共通財布制は、夫婦が収入を一つの口座にまとめ、そこから必要な生活費やお小遣いなどを支出する方法です。
メリットとして、家計の一元管理がしやすくなる点が挙げられます。
口座の預金がいくら増えたのか、いくら減ったのかも、一目見て明らかです。
節約による財産増加の喜びも共有できますので、効率的な資産増加にもつながる可能性があります。
(2)別財布制
別財布制は、夫婦それぞれが自分の収入を管理し、生活費を分担する方法です。
生活費の分担方法は、割合で決めることもありますが、家賃や光熱費は夫負担だが、食費と子ども関係は妻負担など、項目により一方が全額負担することもあります。
共働きの夫婦で、多く利用されているようです。
しかし、生活費を分担した残りについて、自分の自由に使えるお金と考えてしまうと、浪費につながり、家計単位での資産増加のスピードが遅くなってしまうことがあります。
生活費の負担を明確にするだけでなく、各自の貯蓄目標も話し合って設定するなど、双方が管理する資産について定期的に話し合いを行うことが大切です。
(3)一方負担制
一方負担制は、例えば夫の収入で生活し、妻の収入は全額貯蓄するなどして財産を管理する方法です。
一方の収入が貯蓄予定額となりますので、計画的に資産形成できる可能性があるでしょう。
ただし、一方の収入が生活費を全額支払える金額以上の収入である必要がありますし、また生活費を支払った残りの額を「自由に使えるお金」と考えてしまうと、浪費につながるおそれもあります。
生活費負担が原因の夫婦トラブルを防ぐコツ
夫婦間で家庭の経済状況やお互いの状況について、適宜話し合い、生活費負担割合について合意することがポイントです。
一度話し合って納得の上で負担割合を決めたからって、問題がないわけではありません。
結婚当時、夫婦で生活費を折半することで合意したかもしれませんが、昇進、転職や妊娠出産などのイベントがあれば、家庭の経済状況やお互いの状況は変わっていきます。
結婚後に、事情の変化があり、生活費を折半することが「おかしい」状況になることも、当然考えられます。
生活費の負担や家計についての不平不満は、適宜、夫婦の話し合いで解決をめざしましょう。
【まとめ】夫婦の状況に合わせた柔軟な生活費負担の話し合いが重要
夫婦の生活費負担は一律に折半するのではなく、収入差や家事育児の負担を考慮した柔軟な方法を採用することが重要です。
夫婦の状況に合わせた財産管理方法を選び、生活費の負担割合を話し合った上で、公平で円満な家計管理を目指しましょう。
ファイナンシャルプランナーのアドバイスを受けることも有効です。
この記事を参考に、まずはパートナーと話し合いを始めてみてください。
不満を抱えたままにせず、話し合いによる家計管理の見直しが、より良い夫婦関係を築く第一歩となるでしょう。