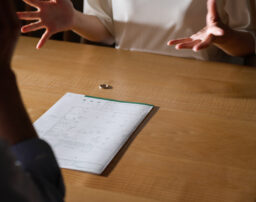昔から、法律上結婚はしないけれども、事実上夫婦として暮らす「内縁」という夫婦関係があります。
現代では、「事実婚」と呼ばれることが多いようです。
しかし、「事実婚はずるい」と感じる人も少なくありません。
この記事では、事実婚の基本から、法律婚や同棲との違い、そしてメリット・デメリットを弁護士が解説します。
さらに、事実婚が「ずるい」と思われる理由やその誤解を解消する方法についても触れます。
事実婚を選ぶことで得られる自由やメリット・デメリットなどを理解し、後悔しないためのポイントを押さえることで、自分たちに最適な選択をするための参考にしてください。
ここを押さえればOK!
事実婚が「ずるい」と思われる背景には、法律婚の責任を回避しているとの誤解がありますが、事実婚も法律婚に準じた責任を伴うことが多いです。事実婚を選ぶ際には、法的な問題や社会的な認知について十分に理解し、パートナーと事前に話し合いを行うことが重要です。事実婚を選択することで、自由なライフスタイルを実現しつつ、夫婦としての生活を共にすることが可能かもしれません。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
事実婚とは?基本的な定義と法律婚との違い
事実婚と法律婚の違いを理解することは、事実婚を選択する上で非常に重要です。
事実婚の基本的な定義と法律婚との違いについて詳しく解説します。
(1)事実婚の基本的な定義
事実婚とは、婚姻の届出をしていないので法律上の夫婦ではないが、婚姻の意思を持ち、事実上夫婦と同様の生活を送り、社会的にも夫婦と認識されているような関係をいいます。
婚姻届を提出しないため、戸籍上は独身のままですが、実質的には夫婦としての生活を送ります。
昔は、婚姻届を出さずに夫婦として暮らす男女の関係を「内縁」と呼んでいましたが、最近は「事実婚」と呼ぶことが多いようです。
(2)法律婚との違い
法律婚は、婚姻届を提出し、法的に認められた婚姻関係です。
これに対して事実婚は、婚姻届を提出せず事実上の夫婦に過ぎませんので、法律婚の夫婦が受けられる法律上の保護や権利が、一部制限されることがあります。
例えば、法律婚では配偶者として法律上相続権が認められますが、事実婚では相続権はありません。したがって、事実婚のパートナーが亡くなっても、遺言がなければ、法律上その方の遺産を受け取る権利がありません。
また、法律婚では配偶者控除などの税制上の優遇措置が受けられますが、事実婚ではこれらの優遇措置が適用されないことがあります。
なぜ「事実婚はずるい」と思われるの?
事実婚が「ずるい」と思われることがあるのはなぜでしょうか。
その背景には、さまざまな社会的な視点や誤解があります。
ここでは、その理由と誤解を解消する方法について説明します。
(1)結婚の責任を回避している?
事実婚は、法律婚を意図的に避けることで、法律婚に伴う責任を回避していると見られることがあります。
確かに、法律に縛られたくない、という理由で事実婚を選ぶ男女もいるでしょう。
事実婚だと相互に相続権はないので、遺言を残さなければ、自分が亡くなったとしてもパートナーに遺産はわたりません。また、事実婚だと戸籍は影響をうけませんので、名字は変わりません。
このように、事実婚は法律に縛られない点もあります。
しかし、事実婚は法律婚に準じる関係として、法律婚と同じような責任を伴う場面も多いです。
事実婚でも、パートナーに生活費を支払う責任がありますし、浮気をすれば、パートナーや浮気相手に慰謝料請求できる可能性があると考えられています。また、事実婚解消時には、法律婚の離婚と同様に、財産分与の必要があるとも考えられています。
(2)いいとこどりしている?
事実婚では、戸籍は変わりませんので、名字が変わりません。
結婚で名字を変えたくない人は、事実婚を選ぶことにより、自分の生まれ持った名字を維持しながら、夫婦として生活を送ることができます。
「名字が変わらない」という点だけ見れば、確かにいいとこどりにも思います。
しかし、事実婚だと、パートナーの相続権はないし、税法上の配偶者控除の対象にもなりません。子どもが生まれても、法律上父子関係を生じさせるためには、認知という法律上の手続きが必要です。
このように、事実婚を選択すれば「いいとこどり」できるとは限りません。
(3)事実婚はずるくない!誤解を解消する方法
事実婚は、婚姻届を提出せずに、社会的にも夫婦として認められる関係を築くことが可能です。しかし、名字を変更しなくてよいなどのメリットがある一方で、相続権がないなどの不利益もあります。
事実婚に対する誤解を解消するためには、本人が事実婚のメリットやデメリットを正確に理解し、周囲に説明することが重要です。
また、事実婚を選択したい理由があれば、パートナーや自分の両親などに共有して、理解を求めるとよいでしょう。
事実婚のメリット5つ
事実婚の主なメリットを5つご紹介します。
(1)戸籍が変わらない
一つ目のメリットは、事実婚では婚姻届を提出しないため、戸籍が変わらないことです。
これにより、名字を変更する必要がなく、個人のアイデンティティを保つことができます。特に、仕事や社会的な活動において、名字を変更することが不便な場合に大きなメリットとなります。
また事実婚を解消しても、そもそも法律婚をしていませんので、戸籍上離婚も記載されません。
法律上は未婚の状態のままですので、その後誰かと法律婚をすれば「初婚」となります。
(2)夫婦別姓である
二つ目のメリットは、事実婚では、夫婦別姓であることです。
法律婚では、夫婦別姓は認められておらず、どちらか一方の姓を名乗ることになりますので、夫婦別姓の事実婚は、夫婦別姓を希望するカップルにとって大きなメリットです。
事実婚を選ぶ理由として、夫婦別姓を挙げるカップルは多いでしょう。
夫婦別姓を選択することで、個々のアイデンティティを尊重しつつ、夫婦としての生活も送ることができます。
(3)法律婚と同じ利益が得られることも
3つ目のメリットは、事実婚でも、法律婚と同じ利益や権利が認められることがある点です。
例えば、条件を満たせば健康保険の扶養に入ることができ、遺族年金を受け取ることができる可能性があります。
また、事実婚であってもお互いに生活費を負担し合う必要があると考えられていますし、不当に事実婚を破棄されれば慰謝料を請求できる可能性もあります。
さらに、事実婚解消の際には、離婚と同じように財産分与を請求できますし、年金分割も可能です。
パートナーに暴力を受けてケガをした際には、法律婚と同じように、裁判所に接近禁止命令などを申し立てることができます。
財産分与について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
離婚の際の慰謝料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(4)夫婦として見られる
4つ目のメリットは、周りからは普通の夫婦として見られる、ということです。
法律婚と事実婚の違いは、婚姻届を提出しているかどうか、という点です。
周りから見れば、法律婚か事実婚かは言わない限りわかりませんので、事実婚も通常の夫婦として認識されることがほとんどでしょう。
(5)面倒な義家族関係が生じない
5つ目のメリットは、法律上、義家族関係が生じないことです。
法律婚だと、法律上配偶者の家族と「姻族(いんぞく)」となり、一定の責任を伴うことがあります。
例えば、配偶者の親に生活できる経済力がない場合、3親等内の親族は、その扶養の義務を負うことがあります(民法877条1項)。
事実婚だと姻族関係が発生しないと考えられていますので、義家族関連の法的な責任や、煩わしいやりとりから離れることができるでしょう。
ただ、義家族と交流を持ち、関係を築くことが法律上制約されているわけではありませんので、積極的に関わることは何ら問題ありません。
事実婚のデメリット4つ
事実婚にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。ここでは、事実婚の主なデメリット4つを詳しく説明します。
(1)お互いを相続しない
事実婚では、法的な婚姻関係がないため、お互いの相続権が認められません。
そのためパートナーが亡くなった場合に、その財産を相続することができません。
お互いに財産を残す方法はあります。
遺言書による遺贈、生前贈与、遺贈などの方法です。
しかし、法律婚をしている配偶者が相続・贈与した場合に受けられる相続税・贈与税の各種特例や控除は、事実婚では受けることができません。
(2)子どもが生まれたら認知が必要
法律上の夫婦の間に生まれた子は「嫡出子」とされ、法律上の父子関係は当然に生じます。
また、両親は子に対して共同で親権を有します。
一方で、法律婚をしていない男女の間に生まれた子(婚外子)は「非嫡出子」とされ、父子関係は法律上当然には生じません。
法律上の父子関係を生じさせるためには、別途「認知」をする必要があります。
また、法律上結婚していないので、親権を有するのは一方のみとなります。通常は母親のみが親権を有しますが、父母で話し合えば父を親権者とすることができます。
(3)病気や入院で家族として扱われないことも
事実婚では、病気や入院時に法的な家族として扱われず、面会や同意書への署名、医師からの説明に立ち会えないなど、不安定な地位におかれます。
これにより、パートナーの医療情報の共有や治療の意思決定などに制約が生じることがあります。
(4)税制上の優遇措置がない
法律婚の場合、所得税の配偶者控除、配偶者控除、所得税の医療費控除など、様々な税制上の優遇措置があります。
しかし事実婚では、パートナーがいたとしても税法上の優遇措置はありません。
事実婚と同棲の違い
事実婚と同棲は似ているようで異なる点が多くあります。
ここでは、事実婚と同棲の違いについて詳しく解説します。
(1)定義の違い
事実婚は、婚姻の意思があり夫婦として生活を共にする形態です。
一方で、同棲は、一般的に婚姻の意思まではないが、カップルとして一緒に住むことを指します。
事実婚は、夫婦としての責任や義務を共有する意識が強いですが、同棲はそのような意識が必ずしも伴わないことがあります。
(2)法律上の取り扱いの違い
事実婚について、住民票の続柄は、通常一方が「世帯主」、他方が「夫(未届)」又は「妻(未届)」と記載されます。
一方で同棲だと、二人とも世帯主となるか、一方が世帯主、他方が同居人となることが多いです。
また、事実婚では、婚姻に準じる関係として法律上の保護や権利が認められることがありますが、同棲ではそのような保護や権利が認められないことがほとんどです(DVの接近禁止命令の申立は可能)。
(3)周りからの扱いの違い
事実婚は、社会的に夫婦として認知されることが多いですが、同棲は単なるカップルの同居として認識されることが多いです。
これにより、事実婚では夫婦としての社会的な扱いを受けることができますが、同棲ではそのような扱いを受けることが難しい場合があります。
事実婚が増加している?
世界的に見ると、特に欧米などで事実婚は増加しているようです。
これは、事実婚をしても法律婚と同じような社会的保証や税制優遇が得られるなど、制度間の差があまりなく、子育てにおいてもデメリットがないためだと考えられます。
個人の価値観やライフスタイルが多様化し、特に結婚に対する考え方が昔とは異なる現代において、法的な手続きを重視しないカップルが増えているのでしょう。
日本では、成人人口の2‐3%が事実婚を選択していると推察されています。
事実婚を選ぶ際の注意点
事実婚を選択する際には、後悔しないための準備と話し合いが重要です。ここでは、事実婚で後悔しないためのポイントについて解説します。
(1)パートナーと事前の話し合い
事実婚を選択する前に、将来の生活設計や法的な問題について十分に話し合い、準備をすることが重要です。例えば、財産分与や相続に関する取り決めを事前に行っておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
婚前契約について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
(2)周囲の理解を得る努力をする
両親など近い家族には、事実婚を選択する理由や背景を説明し、理解を得るための努力が必要です。また、事実婚に対する誤解を解消するために、事実婚でも家族として問題なく幸せであることなど、情報を共有することも有効です。
【まとめ】
事実婚には、戸籍が変わらない、夫婦別姓が可能、一部の法律婚と同じ利益が得られるなどのメリットがありますが、相続権がない、病気や入院時に家族として扱われないなどのデメリットも存在します。事実婚を選択する際には、法的な問題や社会的な認知について十分に理解し、事前に必要な準備と話し合いを行うことが重要です。自由なライフスタイルを実現しつつ、夫婦としての生活を共にする事実婚。自分たちに最適な選択となるといいですね。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求したい方や離婚したい方からのご相談をお受けしております。お悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。