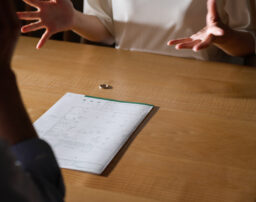離婚という選択を選ぶ夫婦は、もはや珍しくありません。
「自分が住む地域の離婚率はどれくらい?」
「日本でどこが離婚率が高いの?」
など、気になる方もいるでしょう。
2023年のデータによれば、離婚率が高い都道府県は、沖縄県、宮崎県、大阪府と北海道がTOP3です(1000件当たりの離婚件数)。
離婚件数が多いのは、東京都、大阪府、神奈川県の順となっています。
離婚問題における弁護士の役割についても説明しますので、離婚を検討している方はぜひ参考にしてください。
ここを押さえればOK!
離婚率に影響を与える要因として、経済的要因や文化的・社会的要因が考えらます。具体的には、低賃金や生活費の高さ、結婚観の違いなどが離婚の一因となる可能性があります。
一方、離婚件数ランキングでは、人口の多い東京都が最多(20,016件)で、大阪府、神奈川県が続きます。 しかし、全国的には離婚件数と離婚率は減少傾向にあります。この背景には、婚姻件数と婚姻率の減少、晩婚化、結婚前の同棲カップルの増加などが考えられます。
離婚問題に直面した際は、弁護士に相談することが有益です。弁護士は財産分与や慰謝料、親権などの複雑な問題に対するアドバイスを提供し、交渉や法的手続きを代行することで、精神的ストレスの軽減が期待できるでしょう。
離婚でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談下さい。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
離婚率が高い都道府県ランキング
2023年度の離婚率が高い都道府県の上位5位は、次のとおりです。
1位 沖縄 2.20
2位 宮崎 1.74
3位 大阪府 1.71
3位 北海道 1.71
5位 福岡県 1.70
ここでの離婚率は%ではなく、1000人あたり何件離婚しているか、というように見ていきます。
沖縄県の場合は、1000人あたり2.2件、宮崎県では1000人あたり1.74人の離婚が成立しています。
47都道府県の離婚率の順位は次のとおりです。
【2023年 離婚率都道府県ランキング(件数/1000人あたり)】
| 1位 | 沖縄県 | 2.2 |
| 2位 | 宮崎県 | 1.74 |
| 3位 | 大阪府 | 1.71 |
| 3位 | 北海道 | 1.71 |
| 5位 | 福岡県 | 1.7 |
| 6位 | 和歌山県 | 1.66 |
| 7位 | 鹿児島県 | 1.63 |
| 8位 | 高知県 | 1.61 |
| 9位 | 熊本県 | 1.58 |
| 10位 | 大分県 | 1.57 |
| 11位 | 香川県 | 1.56 |
| 12位 | 兵庫県 | 1.54 |
| 13位 | 広島県 | 1.53 |
| 13位 | 愛媛県 | 1.53 |
| 15位 | 愛知県 | 1.52 |
| 15位 | 岡山県 | 1.52 |
| 17位 | 三重県 | 1.51 |
| 18位 | 群馬県 | 1.5 |
| 18位 | 埼玉県 | 1.5 |
| 18位 | 千葉県 | 1.5 |
| 21位 | 茨城県 | 1.49 |
| 21位 | 東京都 | 1.49 |
| 21位 | 神奈川県 | 1.49 |
| 24位 | 栃木県 | 1.48 |
| 25位 | 鳥取県 | 1.47 |
| 26位 | 福島県 | 1.46 |
| 26位 | 静岡県 | 1.46 |
| 26位 | 山口県 | 1.46 |
| 26位 | 佐賀県 | 1.46 |
| 30位 | 山梨県 | 1.44 |
| 30位 | 京都府 | 1.44 |
| 32位 | 長崎県 | 1.43 |
| 33位 | 滋賀県 | 1.42 |
| 34位 | 青森県 | 1.41 |
| 35位 | 宮城県 | 1.4 |
| 35位 | 長野県 | 1.4 |
| 37位 | 岐阜県 | 1.39 |
| 37位 | 徳島県 | 1.39 |
| 39位 | 奈良県 | 1.37 |
| 40位 | 岩手県 | 1.29 |
| 40位 | 福井県 | 1.29 |
| 42位 | 秋田県 | 1.27 |
| 43位 | 島根県 | 1.25 |
| 44位 | 石川県 | 1.24 |
| 45位 | 山形県 | 1.2 |
| 46位 | 新潟県 | 1.19 |
| 47位 | 富山県 | 1.14 |
参考|人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚上巻 10-1 都道府県別にみた年次別離婚件数・離婚率(人口千対) | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
都道府県の離婚率に影響を与える要因
都道府県別に離婚率をみると、一番高い沖縄県で2.20、一番低い富山県で1.14となっています。この2倍近い差は、地域的な次のような要素が、離婚率に影響を与えていると考えられるかもしれません。
(1)経済的要因
離婚率の高い沖縄と宮崎は、全国で秋田県についで最低賃金の額が低くなっています(2024年)。
また、厚労省が公表した賃金構造基本統計調査によれば、2024年の都道府県別の賃金は、沖縄県が266万3000円で44位、宮崎県が259万8000円で47位となっています。また、このような経済的な不安定さが、離婚の一つの要因となっているのかもしれません。
また一方で、福岡や大阪の都道府県別の賃金は、全国の賃金の平均(330万4000円)を超えていますが、離婚率が高くなっています。これは、収入に比して生活費が高くなること、夫婦ともに賃金を得ている場合には離婚後も個人で生活できることなどが、離婚の一つの要因となっているとも考えられます。
参考:令和6年賃金構造基本統計調査結果の概況|厚生労働省
参考:地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省
(2)文化的・社会的要因
地域によって家族間や結婚観が異なることが、離婚率の差につながる可能性があります。
また、都市部では仕事や教育のための移住者が多いと考えられますが、単身赴任による家族への影響、地域になじめないなどの事情で離婚を考える人もいるかもしれません。
離婚件数ランキング
2023年度の離婚件数について、都道府県の上位5位は、次のとおりです。
1位 東京 20,016件
2位 大阪 14,556件
3位 神奈川 13,343件
4位 愛知 10,928件
5位 埼玉 10,697件
| 1位 | 東京都 | 20,016 |
| 2位 | 大阪府 | 14,556 |
| 3位 | 神奈川県 | 13,343 |
| 4位 | 愛知県 | 10,928 |
| 5位 | 埼玉県 | 10,697 |
| 6位 | 千葉県 | 9,151 |
| 7位 | 北海道 | 8,629 |
| 8位 | 福岡県 | 8,512 |
| 9位 | 兵庫県 | 8,060 |
| 10位 | 静岡県 | 5,028 |
| 11位 | 広島県 | 4,103 |
| 12位 | 茨城県 | 4,078 |
| 13位 | 京都府 | 3,561 |
| 14位 | 沖縄県 | 3,170 |
| 15位 | 宮城県 | 3,138 |
| 16位 | 群馬県 | 2,751 |
| 17位 | 岡山県 | 2,750 |
| 18位 | 長野県 | 2,748 |
| 19位 | 栃木県 | 2,732 |
| 20位 | 熊本県 | 2,663 |
| 21位 | 岐阜県 | 2,602 |
| 22位 | 福島県 | 2,563 |
| 23位 | 三重県 | 2,515 |
| 24位 | 新潟県 | 2,511 |
| 25位 | 鹿児島県 | 2,500 |
| 26位 | 愛媛県 | 1,953 |
| 27位 | 滋賀県 | 1,943 |
| 28位 | 山口県 | 1,873 |
| 29位 | 宮崎県 | 1,796 |
| 30位 | 長崎県 | 1,788 |
| 31位 | 奈良県 | 1,751 |
| 32位 | 大分県 | 1,695 |
| 33位 | 青森県 | 1,665 |
| 34位 | 岩手県 | 1,488 |
| 35位 | 和歌山県 | 1,466 |
| 36位 | 香川県 | 1,424 |
| 37位 | 石川県 | 1,356 |
| 38位 | 山形県 | 1,223 |
| 39位 | 秋田県 | 1,151 |
| 40位 | 佐賀県 | 1,150 |
| 41位 | 富山県 | 1,126 |
| 42位 | 山梨県 | 1,118 |
| 43位 | 高知県 | 1,065 |
| 44位 | 徳島県 | 956 |
| 45位 | 福井県 | 942 |
| 46位 | 島根県 | 799 |
| 47位 | 鳥取県 | 781 |
離婚件数が圧倒的に多いのは、最も人口の多い東京です。
日本の人口が多い都道府県TOP5は、東京、神奈川、大阪、愛知、埼玉です。離婚件数の多いTOP5の都道府県にすべて入っています。
離婚件数の多い都道府県は、人口の多い地域であり、離婚率が高いからといって離婚件数が多い、というわけではないようです。
全国の離婚件数と離婚率は減少傾向にある
都道府県別の離婚件数と離婚率について以前と比較すると、離婚件数も離婚率も低下傾向にあります。
例えば、平成17年と令和2年を比較した統計では、全ての都道府県で離婚件数は減少し、離婚率も低下しています。
参考:令和4年度離婚に関する統計の概況 離婚の年次推移|厚生労働省
これには次のような要因があると考えられます。
(1)婚姻件数と婚姻率の減少
結婚件数は、最多の1972年1,099,984組に比べて、2023年は474,717組まで減少しています。また、結婚率(人口1000対)は最高の12.0から、2023年は3.9まで減少しています。
結婚件数と結婚率が減少していることが、離婚件数と離婚率の減少の理由として考えられます。
結婚件数と結婚率の減少にも様々な理由がありますが、その一つとして、非正規の働き方が増えている点があげられます。
1984年は全体の労働者の15.3%を占めるに過ぎなかった非正規雇用労働者は、2024年には36.8%を占めるに至っています。
非正規雇用は、パート、アルバイト、契約社員などを指し、限られた時間で働くことができるというメリットがある一方で、一般的に、賃金が正規雇用よりも安い点が問題視されています。
非正規雇用で収入が低いと、結婚して相手の生活にも責任を持ち、子どもを育てるということを積極的に考えることが難しく、結婚に前向きでない人が増えていると考えられます。
参考:「非正規雇用」の現状と課題|厚生労働省
参考:結婚に関する現状と課題について|子ども家庭庁
(2)晩婚化
1975年の平均初婚年齢は、女性が24.7才で男性が27才。
2022年では女性が29.7才、男性が31.1才まで上昇しています。
このように、初婚年齢は以前より上昇しています。
人々はより経済的・精神的に成熟した年齢で結婚することが多くなっています。成熟した年齢での結婚は、自己理解や人生の目標が明確になっていることが多く、パートナーとの価値観の一致がしやすくなります。
この結果、結婚生活における衝突が減少し、離婚率の低下につながっている可能性があります。
(3)結婚前の同棲カップルの増加
結婚前に同棲を経て結婚する夫婦も少なくありません。
1987年には、30代前半で同棲経験のある男性は5%、女性は4.4%。
この数字が、2015年には男性10.4%、女性11.9%まで上昇しています。
同棲は、パートナーとの生活習慣や価値観の違いを事前に確認する機会を提供します。この試行期間を通じて、カップルは互いの価値観や適合性を評価し、お互いに妥協点を探してすり合わせを行い、もし問題がある場合は結婚を再考することができます。
これにより、結婚後の不一致や衝突が減少し、結果として離婚率が低下する可能性があります。
参考|第15回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)|国立社会保障人口問題研究所
離婚問題への対策と弁護士の役割
離婚問題に直面した際、弁護士に相談することは非常に有益です。
弁護士は、財産分与や慰謝料、年金分割、親権など、個別具体的な状況に応じた複雑な問題に対するアドバイスを提供します。
また、弁護士に依頼すれば、基本的に、相手と離婚問題について直接話す必要はなく、弁護士が代理で交渉しますので、精神的なストレスの軽減が期待できます。交渉が決裂した場合の、調停や訴訟など法的手続きについても、弁護士が行います。
後悔しない離婚を実現するためには、法的な知識と経験が必要です。弁護士に相談することで、感情的な判断を避け、冷静に問題を解決することが可能になるでしょう。
【まとめ】離婚率は地域によって異なるが、全国的には減少傾向にある
離婚率は都道府県によって異なり、それには経済的要因などの地域的な理由が影響していると考えられます。ただ離婚件数と離婚率は、長期的に見ると、全国的には減少傾向にあります。
離婚の際には、財産分与や親権、年金分割など様々なことを話し合いで決めていく必要があります。
離婚を検討している方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。