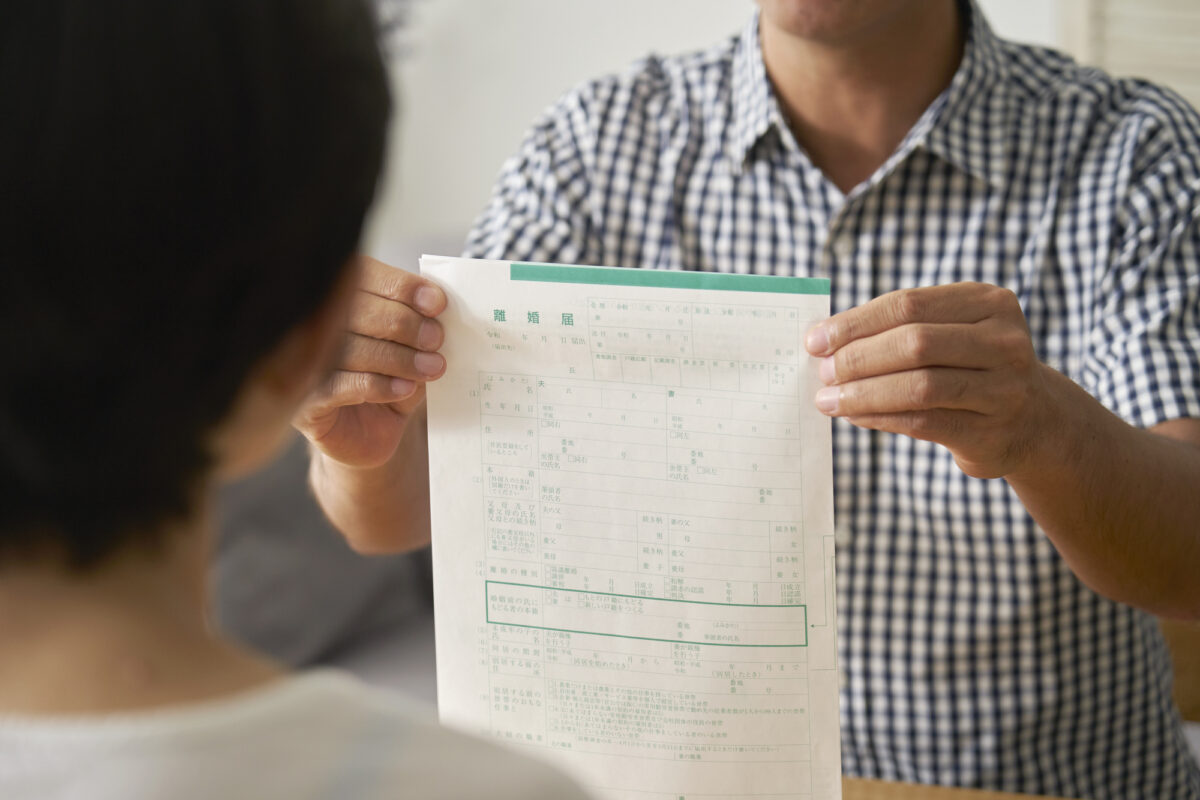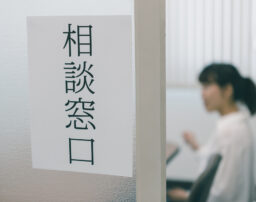配偶者から突き付けられた、突然の「離婚したい」という言葉に、途方に暮れていませんか?しかし、この一言は、夫婦関係を見つめ直し、より良い未来を築くためのターニングポイントにもなり得ます。
本記事では、弁護士が離婚を回避するための具体的なステップから、もしもの時の円満な解決策まで、あなたの「知りたい」にわかりやすくお答えします。これを読めば、冷静に、そして前向きにこの問題と向き合うことができるでしょう。
ここを押さえればOK!
離婚を回避するには、夫婦間のコミュニケーション改善、相手の不満解消への取り組み、専門家のカウンセリング利用が効果的です。パートナーが不満に思っていることを把握したら、すぐに具体的な行動を起こして信頼関係回復に努めましょう。
離婚を避ける法的対応としては、離婚届不受理申出書の提出や夫婦円満調停申立てがあります。
話し合っても夫婦関係の修復ができず、相手の離婚意思が固い場合は、現実な対応策として、円満な別れを目指し、子どもへの適切な説明と心理的ケア、新生活の準備を進めるとよいでしょう。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
「離婚したい」って言われたら、まずどうする?
パートナーから突然「離婚したい」と言われた時、最も重要なのは冷静さを保つことです。感情的な反応は状況を悪化させる可能性があるため、以下の3つのポイントを意識して対応しましょう。
- 冷静に話を聞く
- 効果的な質問をする
- 即答を避け、熟考の時間を設ける
これらの対応により、相手の真意を理解し、適切な判断を下すための時間を確保できるでしょう。慌てて行動する必要はありません。
(1)感情的にならず冷静に話を聞くことの重要性
相手の話を冷静に聞くことは、状況を正確に把握し、適切な対応を考えるための第一歩です。感情的になると、相手の本当の気持ちを理解できず、関係修復の機会を逃す可能性があります。
【冷静に聞くためのポイント】
- 深呼吸をして心を落ち着かせる
- 相手の話を遮らず、最後まで聞く
- 相手の表情や態度にも注目する
例えば、「わかりました。あなたの気持ちをもう少し詳しく教えてください」と言って、相手の話を促すことが効果的です。
(2)相手の本当の気持ちを確認する効果的な質問
相手の真意を理解するためには、適切な質問が不可欠です。オープンエンドの質問を使い、相手が自由に答えられるようにしましょう。
【効果的な質問例】
- 「どうして離婚を考えるようになったの?」
- 「私たちの関係で、どんな点が問題だと感じている?」
- 「どうすれば関係を改善できる?」
これらの質問により、離婚の根本的な理由や、関係改善の可能性を探ることができます。得られた情報は、後の話し合いで重要な役割を果たします。
(3)即答を避け、熟考の時間を設ける
離婚の申し出に対して、売り言葉に買い言葉で「離婚する」と即答することは避けましょう。冷静に考える時間を確保することが、賢明な判断につながります。
【熟考の時間を設けるための対応】
- 「今すぐには答えられない。考える時間が欲しい」と伝える
- 具体的な期限を提案する(例:「1週間後に話し合いましょう」)
- その間、互いに冷静になる時間を持つことを提案する
この時間を利用して、自分の気持ちを整理し、必要に応じて弁護士やカウンセラーなどに相談することができます。離婚したいと言われたからといって離婚しなければならないわけではありませんので、急ぐ必要はありません。
そもそも、なんで「離婚したい」って言われたの?その背景にあるもの
離婚の申し出には、多くの場合、複雑な背景要因が存在します。
主な要因として、コミュニケーション不足、経済的な問題、価値観の相違が挙げられます。これらの要因を理解することで、問題の本質に迫り、解決の糸口を見つけることができます。
これらの要因は単独で存在することもありますが、多くの場合は複合的に作用しています。もしあなたが肉体関係を伴う不倫をしたとしたら、それは法定の離婚事由(民法770条)に該当しますが、法定の離婚事由なく離婚を希望する人も多いのです。
(1)コミュニケーション不足が引き起こす問題
コミュニケーション不足は、多くの夫婦問題の根源となります。日々の会話が減少し、互いの気持ちが伝わらなくなることで、次のような問題が生じます。
- 互いの気持ちや考えが理解できない
- 小さな誤解が大きな問題に発展する
- 孤独感や疎外感が増大する
例えば、「仕事が忙しくて話す時間がない」という状況が続くと、パートナーは「自分のことを大切に思っていない」と感じる可能性があります。このような誤解を解消するためには、定期的な対話の時間を設けるなど、意識的にコミュニケーションを取る努力が必要です。
(2)経済的な不安や不満が及ぼす影響
次のような経済的な問題は、夫婦関係に大きなストレスを与える要因の一つです。家計の管理や将来の経済的見通しに対する不安が、離婚の申し出につながることがあります。
- 浪費や借金による金銭トラブル
- 収入の格差による不満
- 将来の生活設計に対する不安
例えば、一方が無計画な浪費を続けることで、他方が将来の生活に不安を感じ、離婚を考えるケースがあります。
(3)価値観の相違が生む軋轢
次のような場面で現れる価値観の相違は、日常生活から人生の重要な決断まで、様々な場面で軋轢を生み出します。特に、結婚後に明らかになる価値観の違いは、深刻な問題につながることがあります。
- 子育ての方針
- 家事・育児の分担
- キャリアや人生の目標
- 家族との付き合い方
例えば、「子どもの教育方針」について、一方が厳しいしつけを重視し、他方が自由な環境で育てたいと考える場合、日々の育児で対立が生じる可能性があります。
価値観の相違を乗り越えるためには、互いの考えを尊重し、妥協点を見出す努力が必要です。場合によっては、カウンセリングなどの専門的なサポートを受けることも効果的です。
離婚を避けるために、具体的に何ができる?
離婚を回避するためには、積極的かつ具体的な行動が必要です。主に以下の3つのステップを踏むことで、関係修復の可能性が高まります。
- 夫婦間のコミュニケーションを改善する
- 相手の不満を解消するための建設的なアプローチを取る
- 専門家のカウンセリングを受ける
これらのステップを着実に実行することで、離婚の危機を乗り越え、より強固な関係を築くことができるかもしれません。
また、この段階で離婚調停や裁判に至る前に問題解決を図ることで、時間と費用を節約し、互いにとってより良い結果を得られる可能性が高まります。
(1)夫婦間のコミュニケーションを改善する実践的方法
コミュニケーションの改善は、離婚回避の鍵となります。以下の実践的方法を日常生活に取り入れましょう。
- 定期的な対話の時間を設ける
- 例:毎週金曜日の夜を「夫婦の時間」として確保する
- アクティブリスニングを実践する
- 相手の話を遮らず、最後まで聞く
- 相手の言葉を言い換えて確認する 例:「つまり、あなたは〇〇と感じているということね」
- 相手の気持ちに共感する
- 「私メッセージ」を使って感情を伝える
- 「あなたは〜」ではなく「私は〜と感じる」と表現する
- 例:「あなたは仕事ばかり」→「私は寂しさを感じる」
- 非言語コミュニケーションにも注意を払う
- 携帯やテレビを見ながら片手間に話をすると、相手に「尊重されていない」と感じさせる。話すときには、「あなたの話を聞いている」ことが分かるように、アイコンタクト、表情、身振り手振りを意識する。
これらの方法を継続的に実践することで、互いの理解が深まり、問題解決の糸口が見つかりやすくなります。
(2)相手の不満を解消するための建設的なアプローチ
相手の不満を解消するためには、問題を具体化し、段階的に解決していく建設的なアプローチが効果的です。
- 不満の具体化
- 相手の不満を具体的に列挙する
- 優先順位をつける
- 解決策の提案と実行
- それぞれの不満に対する解決策を提案する
- 小さな変化から始め、徐々に大きな変化につなげる
- 定期的な進捗確認
- 週1回など、定期的に改善状況を確認する
- 互いにフィードバックを行い、方法を調整する
例えば、「家事の分担」が不満な場合を考えてみましょう。この場合、具体的なタスクリストを作成し、各自の得意分野を考慮して分担を決めます。そして、1週間試行後、調整を行うなどして不満解消につなげるといいでしょう。
(3)専門家のカウンセリングを受ける意義とタイミング
専門家のカウンセリングは、客観的な視点と専門知識に基づくアドバイスを得られるという意義があります。費用はかかりますが、カウンセリングにより、夫婦関係修復のための建設的な意見をもらえたり、新たな視点に気づいたりするかもしれません。
相手が同意すれば、夫婦でカウンセリングを受ける方法もあります。
「離婚したくない」なら、法的にどうする?
離婚を望まない場合、法的な対応策を講じることで、一方的な離婚を防ぎ、話し合いの機会を確保することができます。主な法的対応策は以下の2つです。
- 離婚届不受理申出書の提出
- 夫婦円満調停申立て
(1)離婚届不受理申出書の提出
離婚届不受理申出書は、配偶者が一方的に離婚届を提出することを防ぐための法的手段です。
居住地の役所で手続が可能ですので、詳しくは窓口に相談してみましょう。
(2)夫婦円満調停申立て
夫婦円満調停は、夫婦関係修復を目的として、裁判所の調停委員を交えて話し合いを行う制度です。
次のようなメリットがあります。
- 中立的な第三者の介入により、冷静な話し合いが可能
- 調停委員の経験に基づいたアドバイスが得られる
ただし、次のデメリットもあります。
- 調停は強制力がないため、相手が応じない場合は調停不成立
- 相手の性格によっては調停を申し立てたことで反感を買い、夫婦関係悪化の原因ともなる
調停を行うかどうかは、慎重に判断しましょう。
弁護士に相談すべきか、どう見極める?
弁護士への相談は、離婚に関連する法的な問題を把握し、適切な対応を取るために重要です。
一方で、夫婦関係を修復したいのであれば、弁護士に依頼せずに当事者同士で話し合って解決した方がいいのも事実です。
以下のような状況では、弁護士への相談をお勧めします。
【弁護士に相談すべき状況】
- 相手が弁護士に依頼した場合
- DV(ドメスティックバイオレンス)や不貞行為がある場合
- 離婚を避けられないが、財産分与や養育費について冷静に話し合うのが難しい場合
弁護士費用が心配かもしれませんが、相談だけであれば30分5500円(税込)程度であることが多いです。まずは相談だけでもしてみましょう。
離婚したくないなら、これだけはNG!やってはいけない行動
離婚を回避しようとする中で、以下の行動は逆効果となる可能性が高いため避けるようにしましょう。
- 感情的な非難や責め
- 一方的な説得や押し付け
- SNSでの過度な発信
これらの行動は、相手との関係をさらに悪化させ、離婚の可能性を高めてしまう危険性があります。冷静さを保ち、建設的なコミュニケーションを心がけることが、時間はかかるかもしれませんが、結局は離婚回避への近道となるでしょう。
(1)感情的な非難や責めが及ぼす悪影響
感情的な非難や責めは、相手の防衛本能を刺激し、対話を困難にします。具体的には、次のような悪影響があります。
- 相手が心を閉ざし、コミュニケーションが取れなくなる
- 互いの感情がエスカレートし、冷静な判断ができなくなる
- 相手の離婚意思をさらに強めてしまう
例えば「あなたは仕事ばかりで、家族のことを全く考えていない!」というのではなく、「最近、家族で過ごす時間が減って寂しい。一緒に時間を作れない?」というのがよいでしょう。
常に冷静さを保ち、建設的な対話を心がけることが重要です。
(2)一方的な説得や押し付けの危険性
一方的な説得や自分の考えの押し付けは、相手の反発を招き、次のように、関係修復の機会を失わせる危険性があります。
- 相手の意見や感情を無視することで、さらなる溝を作る
- 相手の自尊心を傷つけ、協力的な態度を失わせる
- 相手が話し合いそのものを拒否するようになる
例えば「離婚なんて絶対に認めない。子どものためにも絶対に一緒にいるべきだ!」ではなく、「お互いの気持ちを理解し合い、子どものためにも最善の解決策を一緒に考えていきたい。」というのがよいでしょう。
相手の意見を尊重し、互いの気持ちを理解し合う姿勢が重要です。
(3)SNSでの過度な発信がもたらすリスク
SNSでの過度な発信は、プライバシーの侵害や名誉毀損のリスクがあり、法的問題に発展する可能性があります。
例:「夫(妻)が浮気をしていて、離婚することになりました。子どもたちが可哀想です。」
このような投稿は、たとえ事実であっても、相手のプライバシーを侵害し、名誉を毀損する可能性があります。
離婚問題に直面していて誰かに話を聞いてほしい場合には、弁護士や親しい信頼できる人に話すようにし、SNSを利用してプライバシーを公開することは控えた方がよいでしょう。
相手の「離婚したい」気持ちが固いときはどうする?現実的な対処法
相手の離婚の意思が固い場合、家庭内別居や別居をして、表面的な夫婦関係を続ける方法もあります。
一方で、無理に婚姻関係を続けるよりも、夫婦関係が破綻してしまったことを認めて、現実的な対処法を考える道もあります。
現実的な対処法として以下の3点があります。
- 円満な別れを目指す
- 子どもへの適切な説明と心理的ケアを行う
- 新生活に向けた具体的な準備を進める
(1)円満な別れを目指すことの重要性と方法
円満な別れを目指すことは、不必要な争いを避け、将来的な関係性や子どもへの影響を考慮する上で非常に重要です。
2026年5月頃までには離婚後の共同親権を選択することが可能となる予定ですが、円満な別れにより、離婚後の共同親権行使もスムーズになるでしょう。
【円満な別れを目指す方法】
- 感情的にならず、冷静に話し合う
- 相手の立場や気持ちを理解しようと努める
- 共通の目標(例:子どもの幸せ)を設定する
- 必要に応じてカウンセラーや弁護士の助言を得る
例えば、「子どもの将来のために、私たちは離婚するけれども、お互いが良い親であり続けられるよう協力しましょう」という姿勢で臨むことが大切です。
円満な別れを目指すことで、財産分与や養育費の取り決めなどもスムーズに進みやすくなります。
ただし、相手方の主張が正しいかどうか、自分が財産分与で損していないかなどの検討は必要です。
相手方と冷静に話し合える場合であっても、離婚条件については、合意前に一度離婚を扱う弁護士に相談することをお勧めします。
話し合うべき離婚条件について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
(2)子どもへの適切な説明と心理的ケアの必要性
子どもへの適切な説明と心理的ケアは、離婚による子どもへの悪影響を最小限に抑えるために不可欠です。
【子どもへの説明のポイント】
- 両親揃って説明する
- 子どもの年齢に応じた言葉を使う
- 離婚は子どものせいではないことを強調する
- 両親の子どもに対する愛情は変わらないことを伝える
【心理的ケアの方法】
- 子どもの気持ちを丁寧に聞く
- 日常生活の変化を最小限に抑える
- 必要に応じて専門家(児童心理士など)のサポートを受ける
子どもを大切に思う気持ちが共通していれば、親権や面会交流の取り決めにおいても、子どもの福祉を第一に考えた合意形成がしやすくなります。
離婚の子どもへの影響について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)新生活に向けた具体的な準備事項のチェックリスト
新生活に向けた準備を計画的に進めることで、離婚後の生活をスムーズにスタートできます。以下のチェックリストを参考にしてください。
- 住居の確保
□ 新居の選定と契約 □ 引越し業者の手配 - 経済面の整理
□ 財産分与の取り決め □ 養育費の取り決め(子どもがいる場合) □ 年金分割 - 法的手続き
□ 離婚届の提出 □ 戸籍謄本の取得 □ 健康保険など切り替え □復氏する場合は各種名義変更 - 子どもに関する取り決め(該当する場合)
□ 親権者の決定 □ 面会交流スケジュールの作成 - 生活環境の整備
□ 新しい職場の確保(必要な場合) □ 子どもの転校手続き(必要な場合) - 精神的サポート
□ カウンセリングの予約
これらの準備を計画的に進めることで、新生活へのスムーズな移行が可能になります。
特に、財産分与や養育費の取り決めなどの法的側面については、弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。また、これらの取り決めは書面で残し、双方が合意したことを明確にしておくことが重要です。
離婚準備について詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
【まとめ】冷静な対応と具体的行動で離婚危機を乗り越える
離婚危機を乗り越えるためには、感情的にならず冷静に対応することが最も重要です。
相手の気持ちを理解しようと努め、建設的なコミュニケーションを心がけましょう。
そして、話し合いにより関係修復のチャンスがあるのであれば、信頼関係の再構築に向けて具体的な行動を起こしましょう。今すぐできることから始めてみてください。例えば、パートナーとの対話の時間を設けたり、パートナーの不満に寄り添って自主的に家事や育児にかかわったりするのも良いでしょう。
もし「離婚やむなし」ということになったら、離婚問題を扱う弁護士への相談をお勧めします。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2025年6月時点)。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。