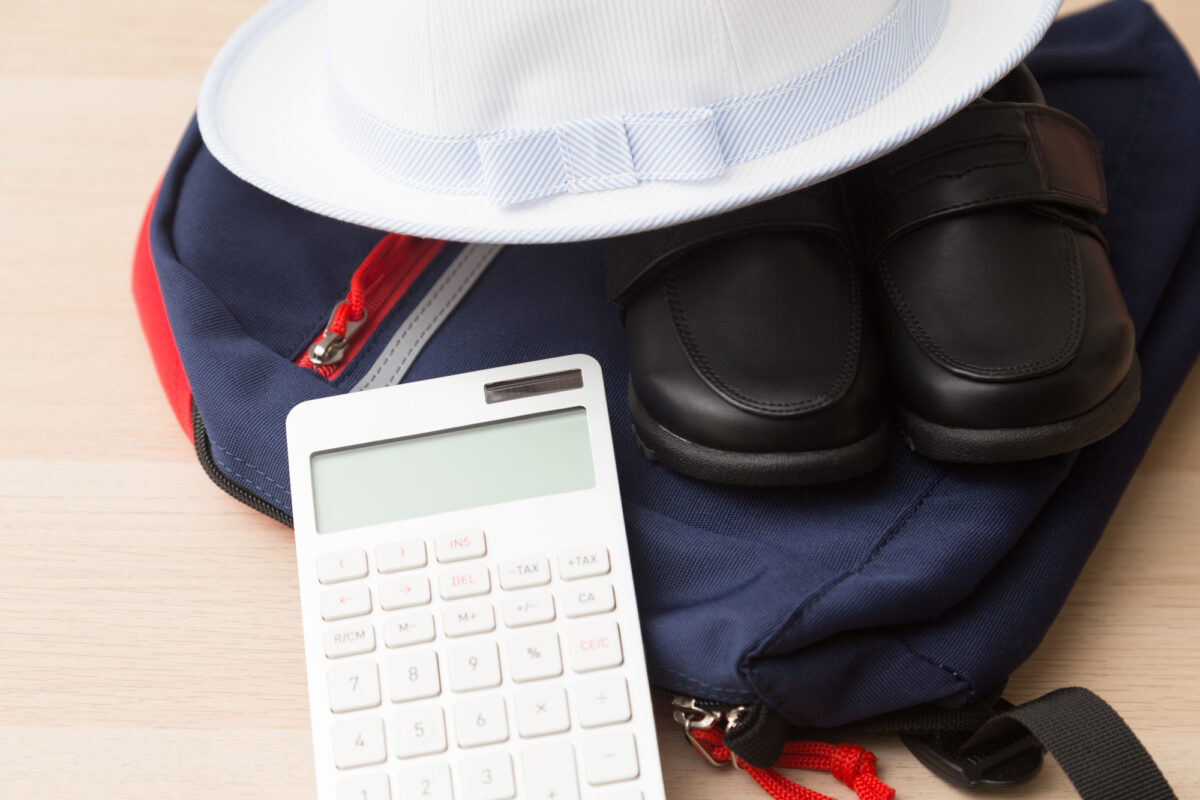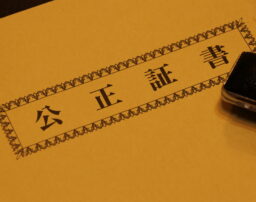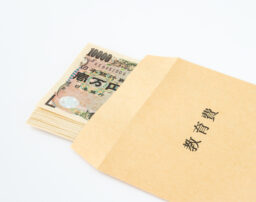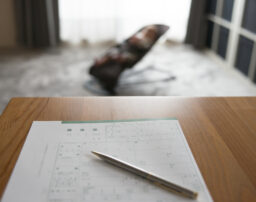「円満に離婚したい」というのは誰もが当然に思う気持ちでしょう。
しかし、実際は、子どものことやお金のことなど、離婚時に夫婦が揉めてしまうことも多いのが実情です。実際、離婚で夫婦が揉めたというケースを友人や知人から聞いたことがある人もいらっしゃるでしょう。
ただ、円満離婚は難しいことではありません。
円満離婚に向けた交渉のポイントを押さえておくことで、円満離婚をしやすくなります。特に、子どもに関する養育費のことは夫婦が揉めやすい要因の一つですので、円満離婚しやすくなるポイントを押さえておくことが重要です。
ここを押さえればOK!
特に養育費については、相手の収入を考慮し、子どもの成長に応じた支出を見積もるなど、双方にとって納得できる金額を設定することが重要です。合意した内容は、養育費の不払いを防ぐためにも、裁判なしで強制執行を可能にする公正証書として残しておくことがおすすめです。
円満離婚には弁護士は不要と思われるかもしれません。しかし、弁護士に相談することで、離婚問題で揉めやすいポイントを回避しながら、話し合いを進めることができるでしょう。離婚問題でお悩みの方はアディーレにご相談ください。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
円満離婚とは
「円満離婚」とは、一般的に、夫婦がお互いに納得のいく条件で協議離婚を成立させることです。
円満離婚をするにあたっては、夫婦で揉めないということも大事ですが、どちらか一方に不満が残る形にはしないということも重要になります。
(1)円満離婚を目指すべき4つのメリット
離婚をするには、「円満離婚」を行うことがおすすめです。
なぜなら、円満離婚には、次の4つのメリットがあるからです。
- 離婚成立までのスピードが速い
- 離婚にかかる費用を抑えられる
- 後悔のない離婚条件を決めることができる
- 離婚後も良好な関係でいられる可能性が高く、子どもに与える影響も少ない
それぞれ説明します。
(1-1)離婚成立までのスピードが速い
円満離婚のメリットとしては、離婚成立までのスピードが速いということが挙げられます。
離婚で揉めた場合には、裁判になり、離婚までに1年以上かかるケースも多くあります。しかし、円満離婚の場合には、夫婦間の合意がまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚ができるため、裁判などを通じて離婚する場合に比べて、短い期間で離婚することができます。
(1-2)離婚にかかる費用を抑えられる
円満離婚の場合には、基本的に離婚にかかる費用はありません。
一方、離婚で揉め調停や裁判になった場合には、裁判所に支払う費用や(弁護士に依頼した場合)弁護士費用が必要となります。
離婚によって、夫婦それぞれ新たな生活がはじまります。新たな生活のためにはお金が必要となる人もいるでしょう。少しでも離婚にかかる費用は抑えましょう。
(1-3)後悔のない離婚条件を決めることができる
円満離婚の場合には、夫婦の話し合いで離婚をしているので、財産分与や養育費など、金銭面においてもお互いに納得している場合が多いのが特徴です。
そのため、離婚後に「もっと養育費をもらうべきだった」「財産分与の方法に納得ができない」など後悔することはあまりありません。
このように、双方にとって納得のできる離婚条件は、後で決めたことがきちんと実行されやすいため、例えば、養育費の不払いといった後々のトラブルを防止できる可能性が高いといえます。
(1-4)離婚後も良好な関係でいられる可能性が高く、子どもへの影響が少ない
円満離婚の場合には、離婚後も相手と連絡を取り合えるような関係でいられることがあり、子どもとも定期的に交流できるなど良好な親子関係を続けられる可能性が高いといえます。
一方、相手と裁判などで争った末に離婚する場合には、離婚成立後に良好な関係を築くことは難しく、子どもに会うことも難しいケースも少なくありません。
離婚後も子どもにとっては父母であることに変わりありません。そのため、離婚後も夫婦がある程度良好な関係を継続している場合には、子どもへの影響も少なくてすむでしょう。
(2)円満離婚のために離婚条件を妥協するのは禁物!
円満離婚をしたいからといって離婚条件を妥協してしまうのは禁物です。
なぜなら、離婚条件を曖昧にしたり、納得のできないまま合意したりしてしまうと、後々トラブルの元になる可能性が高いからです。
- 養育費の金額を決めずにいたら、毎月数千円の振込しかない
- 財産分与について十分な話し合いをしなかったため、家財道具や車を相手に持っていかれて、離婚後の生活が困った
- 慰謝料の金額に決めずにいたら、支払いがない
- 面会交流について十分に話し合わなかったため、子どもと会わせてもらえない など
特に、財産分与、慰謝料といった金銭面の条件や養育費、面会交流といった子供に関する条件はきっちり決めておくべきでしょう。
円満離婚に向けた養育費交渉のポイント
円満離婚の場合であっても、養育費といったお金は離婚後の生活の支えになりますから、しっかりと決めておくのがおすすめです。ただ、お金の話はなかなか相手も折れてくれず、揉める要因ともなりがちです。
養育費交渉を円満に終わらせるためには、あなたの思いや希望を通すだけではなく、相手の意思も尊重することが重要になります。
円満離婚に向けた養育費交渉では、次の4つのポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 相手の収入を把握する
- 子どもの成長に応じた経済的支出の見通しを立てる
- 面会交流に協力的な姿勢を見せる
- 養育費の合意は「公正証書」で行う
それぞれのポイントについて説明します。
(1)相手の収入を把握する
相手の収入を把握したうえで、相手が支払えそうな金額の範囲内で養育費を決めるようにしましょう。
そもそも、養育費の金額は法律で決まっているわけではなく、父母で自由に養育費の金額を決めることができます。ただ、相手が支払えない金額を請求しても、相手から反発を招き、相手と揉めやすくなります。
相手と揉めない円満離婚を実現するためには、相手の収入を把握し、相手の生活費も鑑みた上で、相手が支払える範囲内の養育費を設定することが必要です。このようにすることで、相手も納得しやすく、話合いも円満に終わる可能性を高めることができます。
相手が収入を少なめに申し出てくることもあり得ます。そのため、相手の収入を把握する際には、給与明細や源泉徴収票等できちんとチェックしておくとよいでしょう。
(2)子どもの成長に応じた経済的支出の見通しを立てる
子どもの成長に応じた経済的支出の見通しを立てて、養育費の金額を決めるようにしましょう。
例えば、保育園の期間、小学校や中学校、高校、大学に行くとなると、いくら必要になるかをイメージして養育費を決めるということです。保育園の間は〇万円、小学校の入学時には〇万円など、子どもの成長に応じた金額を決めておいてもよいかもしれません。
なお、母が私立小学校や中学校に通わせたいと思っていても、父が公立でいいと思っている場合などには、父母で想定する養育費の感覚にずれが生じているケースもあります。この場合、話し合いがまとまらず、揉めてしまうケースも多くあります。養育費の話し合いでは父母教育観のすり合わせも行っておくのもよいでしょう。
(3)面会交流に協力的な姿勢を見せる
円満に養育費の話し合いをすすめるためには、面会交流(※)に協力的な姿勢を見せるようにしましょう。
※面会交流とは、子どもと一緒に暮らさない親が子ども会ったり、交流したりすることをいいます。
そもそも、養育費を支払う側としては、養育費を支払うのであれば、子どもの成長を見たい、子どもと定期的に会いたいと考える人が多くいます。
そのため、養育費の支払いを求めながらも、面会交流については拒絶的な姿勢を見せると、養育費を払う側の親から反発を招くことがあります(例:子どもに会えないなら、養育費は払いたくないなど)。
円満に養育費の話し合いをすすめたいのであれば、面会交流については協力的な姿勢を見せるのがよいでしょう。
(4)養育費の合意は「公正証書」で行う
離婚後の養育費不払いといったトラブルを防ぐためには、養育費の合意は「公正証書(交渉尺場で公証人に作成される公文書)」で行うことをおすすめします。
なぜなら、公正証書として残しておくことで、次のようなメリットがあるからです。
- 口頭で合意すると、後から「そんな約束をした覚えはない」などと言い逃れされてしまうこともありますが、きちんと書面に残しておくことで、そのような言い逃れを防ぐことができる。
- 公正証書は、公文書として証明力・証拠力を備えた証書となるため、離婚後、「そんな約束はしていない」「離婚協議書は勝手に作られた(偽造された)」などと言われても、そのような言い逃れを防ぐことができる。
- 公正証書は公証役場で保存されるため、公正証書が破棄・紛失するといった事態を防ぐことができる。
- 公正証書に執行受諾文言が付いていれば、養育費の支払いが滞ったとき、裁判をしなくても強制的に支払いをさせることができる。
特に、最後の「執行受諾文言」をつけておくことは重要です。
そもそも強制執行認諾文言とは、通常、「債務者が本契約の債務を約束通りに履行しなかったときは、直ちに強制執行を服することを承諾する」などという内容で、通常公正証書の最後の条項に記載される文言のことをいいます。
この文言を書いておくことで、本来は裁判をしてからでないとできない強制執行を、裁判をすることなく行うことができます。
残念ながら日本では養育費の未払いを罰する仕組みがなく、離婚後しばらくして養育費の支払いが滞るケースも多いため、「強制執行をしやすくしておく」などある程度の自衛策を備えておくことは重要です。
2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化されます!
公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。
参考:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について|法務省
(1)具体的に何が変わる?
この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。
また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。
同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。
さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。
公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。
(2)デジタル化のメリットとデメリット
デジタル化には大きなメリットもありますが、デメリットもあります。
(2-1)メリット
メリットとしては、次の3点があげられます。
- 電子的な本人確認による申込、Web会議による作成が可能となり、データで受け取ることができるので、公証役場への移動が不要になり、利便性が向上する 。
- 原本が電子データになることで紛失・改ざんリスクが軽減される。
- スケジュール調整が容易になる。
(2-2)デメリット
デメリットとしては、次の3点があげられます。
- リモート方式にはPCやウェブカメラなどの機材が必要で、デジタルデバイドが生じる可能性がある 。
- 厳格な本人・意思確認が要求される公正証書は、ウェブ会議の利用は慎重にすべきとされている。
- なりすましやデータ消失などのセキュリティリスクが懸念される。
(3)手数料の見直し
手数料についても見直しが行われ、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取るときは、1通2,500円が新設されます。紙の場合は、用紙1枚あたり300円です。
また、養育費や死後事務委任契約の作成にかかる手数料はこれまでより軽減されます。
円満離婚を目指すときも弁護士への相談がおすすめ!
弁護士はトラブルになってから相談するイメージをお持ちかもしれません。
しかし、トラブルになっていない段階であっても、弁護士へ相談されることをおすすめします。
なぜなら、離婚問題を取り扱う弁護士に相談しておくことで、例えば、次のような事態を防ぐことができる可能性があるからです。
- 養育費の話し合いをすすめたくても、話し合いに応じてもらえない
- 養育費の話し合いをしたいが、相手が怖くて切り出せない
- 養育費の話し合いを進めているが、相手も養育費についてインターネットなどで調べているようで、相手にいいくるめられてしまいそう(納得のいかない金額になってしまうおそれ)
- 相手に弁護士がつき、納得のいかない養育費額を提示されているが、反論できない など
弁護士はあなたに代わり、相手と交渉します。離婚問題を取り扱う弁護士は離婚問題で揉めやすいポイントを知っていますので、離婚問題で揉めやすいポイントを回避しながら、話し合いを進めることができる可能性があります。
【まとめ】円満離婚のためには相手の意思も尊重することがポイント!
「離婚は揉めて大変そう…」
など、離婚は相手と揉めてしまうイメージをお持ちかもしれません。
実際、お金のこともシビアに話し合わなければならないこともあるため、揉めてしまうケースも多くあります。
離婚問題を取り扱う弁護士は、離婚問題で揉めやすいポイントを知っています。離婚問題を取り扱う弁護士に事前に相談しておくことで、離婚問題で揉めやすいポイントを回避しながら、話し合いを進めることができるでしょう。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。