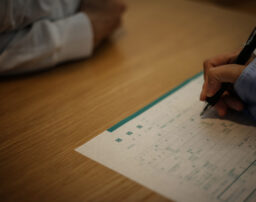「離婚届は全国共通?どこの役所でもらっても大丈夫?」
離婚届に記載すべき事項は戸籍法施行規則で定められており、全国共通です。
そのため、基本的にはどこの役所で入手しても問題ありません。
ただし、各役所で様式が若干異なることがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
不備があると訂正が必要になるため、スムーズな手続を行うためにも記載内容をしっかり確認しましょう。
この記事が、離婚届について正確な知識を身につけ、スムーズな手続を行うために役立てば幸いです。
この記事を読んでわかること
- 離婚届の入手方法(もらい方)
- 離婚届を提出する際の注意点
- 離婚届の記載事項
ここを押さえればOK!
また、一部の市区町村のWebサイトではダウンロードすることも可能です。
離婚届は夫婦の本籍地または所在地の役所に提出しますが、本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本も必要になります。
離婚届の記載事項は全国共通ですが、記載に不備があると不受理となるため、注意が必要です。
勝手に離婚届を提出され、形式的に離婚が成立することを防ぐためには、「離婚届の不受理申出」をしておくとよいでしょう。
協議離婚の場合、離婚日は基本的に離婚届を提出した日(郵送の場合は受付日)になります。
なお、裁判離婚などの場合でも離婚届の提出は必要です。
離婚でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
離婚届は全国共通!どこの役所でも入手可能
まずは離婚届を手に入れましょう。
(1)役所で離婚届を入手するには
離婚届は、市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)の戸籍担当の窓口で入手可能です。
戸籍課、市民課など、名称は役所によって異なるものの、入り口近くにある案内で「離婚届の用紙が欲しい」と言えば教えてくれます。
そして、離婚届の様式は全国の自治体で少し違うこともありますが、書くべきことは共通なので、住んでいる市区町村の役所に限らず、足を運びやすい役所で入手すれば大丈夫です。
また、役所が閉まっている時間でも入手可能です。
夜間・休日受付(当直室、守衛室など)で申し出ると受け取れるよう取り計らってくれます。
(2)ダウンロードも可能
役所に行く時間が取れない方もご安心ください。
一部の市区町村のWebサイトでは、離婚届の様式をPDFファイルでダウンロードできます。
参考:離婚届|大阪市
また、どこの市区町村のWebサイトでダウンロードしたものであっても使用可能です。
ただし、離婚届自体に提出先の自治体名が記載されている場合があるため、提出先の役所と異なる場合には、訂正等が必要になるでしょう。
任意の市区町村のWebサイトからプリントアウトし、必要事項を記入して提出します(*事前に提出先の役所に、ダウンロードした離婚届で受理されるかご確認ください)。
A3サイズでないと受理してもらえない可能性があります。A3サイズの白い用紙にプリントアウトする必要がある点には気をつけてください。
A3サイズは大きめの紙ですから手元にない場合もありますが、その場合にはコンビニのプリントアウトなどで対応可能です。
離婚届提出の際の注意点
離婚届は、夫婦の本籍地または所在地の役所(市役所・区役所・町村役場)に提出します。
もし夫婦が遠方で別居中であっても、どちらか一方の所在地の役所に提出すればいいので、現在、住民登録をしているお住いの地域を管轄する役所に提出すれば足ります。
ただし、本籍地以外の役所に提出する場合、戸籍謄本も提出しなければならない点に注意が必要です。
また、離婚届を提出する際には、窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート等で有効期限内のもの)が必要となります(*裁判離婚等の場合は不要)。
届出人が離婚届に押印した場合には、届出人の印(朱肉を使うもの)も持参するようにしましょう。
その他、必要な持参書類がないか、提出先の役所に予め確認することをお勧めします。
郵送でも提出は可能です。
この場合には身分証明書のコピーを同封してください。
本籍地の役所に郵送で提出する場合、戸籍謄本は不要です。
郵送の場合に、必要書類の不備などがあれば不受理となり、後日役所に行って訂正する必要が生じます。
平日の日中に役所に出向くのは負担が大きいこともあるため、必要書類や離婚届の記載などで不備のないよう、離婚届の書き方をしっかり確認しておきましょう。
離婚届の記載事項
離婚届に不備があると不受理になってしまいます。
その場ですぐに直せる箇所であれば良いのですが、確認のためにいったん持ち帰る必要が出てくるかも知れません。
また、郵送の場合には役所に出向いて訂正する必要があります。
このような二度手間は避けたいところです。
そこで、ここでは離婚届の記載事項について項目ごとに解説します。
ご自身の離婚届を記載する際のチェックリストとしてご使用ください。
(1)届出年月日と届け出先
日付欄には、離婚届を提出する日付を記入してください。
夫婦で離婚届を作成した日ではありません。
郵送の場合には郵送日を記載します。
届出先は、離婚届を提出する夫婦の本籍地または所在地の市区町村です。
(2)氏名・生年月日・住所・本籍
氏名・生年月日については、夫婦それぞれの情報を、戸籍のとおりに記入してください。離婚をして姓が変わる場合であっても、婚姻時の姓を記入します。
生年月日については、戸籍上の生年月日を記載します。和暦・西暦どちらでも問題ありません。
住所は現在住民登録をしている場所を書きます。
別居中で住所変更を行っている場合は、変更後の住所を記載しましょう。
別居中でも住所変更を行っていない場合は、夫婦同じ住所になります。
離婚を機に転居し、離婚届と一緒に転居届を提出する場合、新しい住所と世帯主を記入します。
離婚する相手に住所を知られたくない場合には、住所変更を行う前に離婚届を提出するという方法があります。
なお、本籍は婚姻中のものをご記入ください。
(3)父母の氏名
夫婦それぞれの実の父母の情報を記入します。
ご両親が亡くなっている場合も記入してください。
続柄を書く際は父母との関係を戸籍謄本のとおりに「長男・二男・三男、長女・二女・三女」などと記入します。
次男、次女ではなく、二男、二女と書く点にご注意ください。
(4)離婚届の種別
協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、どのような方法で離婚に至ったかを選択します。
特に裁判所での手続きを介さず、夫婦の話合いのみで離婚するなら「協議離婚」にチェックを入れてください。
この場合は他に書く箇所はありません。
(5)婚姻前の氏に戻る者の本籍
戸籍を抜ける側の離婚後の戸籍をどうするか記入します。
原則として、結婚する際に氏(姓)を変えた側が、離婚後もとの氏に戻ることになります(「復氏」といいます)。
もとの氏に戻る方は、結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選ぶことができます。
もとの戸籍に戻る場合は、結婚する前の戸籍の筆頭者の氏名と本籍地を書きます。
新しく戸籍を作る場合は、本人を筆頭者として、任意の本籍を設定します。
以上は、婚姻前の氏に戻す場合です。
離婚後も婚姻中の氏を使い続ける場合は、この欄は空白にして別に『離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)』を離婚の日から3ヵ月以内に提出しなければなりません。
なお、離婚届だけを先に提出すると、婚氏続称届を提出するまでの間、いったん旧姓に戻ってしまうため、婚氏続称届と離婚届は同時に提出することをおすすめします。
(6)未成年の子の氏名
夫婦いずれかに親権を決めて、未成年の子の名前を記入します。
子どもが複数いる場合には、子ども全員の氏名を記載します。
また、離婚後に子どもを新しい戸籍に入れる場合には、入籍届の提出や子どもの姓を変更するための家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
協議離婚の場合、親権者が決定・記入されていなければ離婚届は基本的に受理されません。
なお、2024年5月、離婚後の共同親権を可能とする改正民法が成立しており、2026年までに施行される見通しです。
離婚後の共同親権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(7)同居の期間
「同居を始めたとき」は、結婚式の日か同居しはじめた日のうちいずれか早いほうを記入します。
ずっと同居している場合には開始日だけ記載すれば大丈夫です。
「別居したとき」は別居を始めた日も記入します。
別居する予定がある場合には、別居予定日を記載してもいいでしょう。
証明を求められるわけではないので、大体の期間がわかれば問題ありません。
(8)別居する前の住所
別居していない場合は空欄にします。
(9)別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
「別居する前の世帯のおもな仕事」については、共働きの場合は収入が多いほうの仕事について記入することになります。
「夫妻の職業」については、5年ごとの国勢調査の年のみ記入するものです(国勢調査は5で割り切れる西暦の年に実施されます)。
(10)その他
父母が養父母の場合は、ここに養父母の氏名を記入します。
(11)届出人
届出人である夫婦の署名・押印です。
この欄については、必ず本人が署名する必要があります。
代筆は許されません。
かつては、必ず押印しなければなりませんでしたが、戸籍法が改正された2021年9月以降、押印は任意となっています。
押印する場合、印鑑は夫婦別のものを押してください。
認印(届け出をしていない個人のハンコのこと)でもいいですが、ゴム印(シャチハタ)は禁止です。
(12)証人
協議離婚の場合は、成人の証人2人に署名(自署)してもらう必要があります。
現在、押印は任意となっています。
証人2人が夫婦であり、それぞれが押印する場合は、印鑑は夫婦別のものを押してください。
証人の選び方や注意点について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
離婚届の提出について知っておきたいこと
離婚届を提出する前に押さえておきたいポイントを見てみましょう。
(1)離婚届を提出するタイミング
協議離婚の場合、離婚日は基本的に離婚届を提出した日(郵送の場合は受付日)になります。
もっとも、離婚の合意だけで離婚届を出してしまうと、のちのち他の条件の面でトラブルが起きるかも知れません。
離婚届を提出する前に、財産分与や慰謝料、子どもがいる場合は養育費と面会交流について話し合い、これらの各条件について合意しておくことをおすすめします。。
離婚条件について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)離婚届を提出できる人
離婚届を提出できるのは、離婚する夫・妻だけではありません。
離婚届に当事者の署名がなされていれば、夫婦以外の人でも提出は可能となっています(*離婚届不受理申出がない場合)。
その際、委任状などは必要ありませんが、窓口で提出する人の本人確認が求められるため、提出する人の身分証明書は必要です。
なお、夫婦以外の人が提出した場合、基本的には後日当事者に郵便で「届出受理通知書」が届きます。
(3)夫婦のどちらかが勝手に離婚届を提出したら?
協議離婚の場合、夫婦の双方が離婚に合意していることが必要です。
配偶者の同意を得ずに、どちらかが勝手に離婚届を作成・提出した場合、離婚は無効になります。
こうした行為は、有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪・公正証書原本不実記載罪などに問われる可能性のある行為であるとともに、勝手に離婚届を提出したことについて相手から損害賠償を請求される可能性もあります。
とはいえ、役所の窓口で夫婦双方に意思を確認する手続はとられないため、勝手に離婚届が提出された場合であっても形式的には離婚が成立してしまいます。
勝手に提出された離婚届を無効にするためには、家庭裁判所での手続が必要です。
つまり、一方が離婚届を勝手に出した場合でも、他方が離婚届を無効にする手続をしなければ離婚は事実上有効だということになります。
いったん形式的に離婚が成立したら、それを無効にするための手続をするのは手間になるため、配偶者が勝手に離婚届を提出しそうな場合は「離婚届の不受理申出」を行うといいでしょう。
離婚届不受理申出について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(4)裁判で離婚する場合なども離婚届の提出は必要
夫婦の話合いで離婚する協議離婚だけでなく、次のような離婚であっても、離婚届の提出は必要です(離婚自体は離婚届を提出しなくても成立します。)。
- 調停離婚
- 審判離婚
- 和解離婚
- 認諾離婚
- 判決離婚
審判・判決で離婚する場合には確定から10日以内、調停・和解・請求の認諾の場合には成立から10日以内に離婚届を提出する必要があります(*)
(*)10日を超えても提出できますが、期限を過ぎてしまうと5万円以下の過料に処される可能性があります。
【まとめ】離婚届に書くべき内容は全国共通!アクセスしやすい場所で入手してOK
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 離婚届に書くべき内容は全国共通
- 離婚届は、基本的には居住地以外の市区町村役所で入手したり、Webでダウンロードして印刷したりすることも可能
- 提出先は夫婦の本籍地または所在地を管轄する市役所・区役所・町村役場
- 協議離婚の場合、離婚届を提出した日(受付日)が離婚した日となる
- 離婚届を提出する前に、離婚条件について夫婦で合意しておくことが大切
- 夫婦以外の人でも離婚届を提出できることがある
- 裁判離婚などの場合であっても離婚届の提出は必要
今回の記事では、離婚届の入手方法などについてご説明しましたが、「離婚条件(慰謝料、財産分与など)に曖昧な部分がある」「納得のいかない離婚条件がある」などの事情はないでしょうか。
早く離婚してしまいたいとしても、これらの事情をすっきりさせないまま離婚届を提出してしまうことはおすすめできません。
「口約束で決めていたことが守られない」「離婚後に納得のいかない部分について話し合いをしたくても、相手が話し合いに応じてくれない」などトラブルが生じてしまうことがあるため、離婚届を提出する前に弁護士に相談しておくと良いでしょう。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2025年1月時点)。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール「0120-554-212」)にご相談下さい。