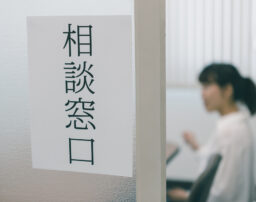家庭内で「何もしない旦那」との生活に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
家事や育児を一手に引き受ける妻にとって、旦那の無関心な態度は精神的にも身体的にも大きな負担となります。
この記事では、そんな「何もしない旦那」を変えるための効果的な対処法や、最終的に離婚を考える際の法的な観点について、弁護士の視点から解説します。
具体的な「何もしない旦那」の行動パターンや心理、対策を知ることで、家庭内のストレスを軽減し、より良い夫婦関係を築く手助けとなるでしょう。
この記事を読んでわかること
- 「何もしない旦那」の典型的な行動パターン
- 旦那が家事・育児をしない根本原因
- 法的観点から見る「何もしない旦那」の問題点
- 旦那の行動を変える効果的アプローチ
- 何もしない旦那と離婚する方法
ここを押さえればOK!
まず、「何もしない旦那」の典型的な行動パターンとしては、家事・育児を手伝わない、共働きでも家庭内の仕事を妻任せにする、指示されないと動かない、約束を守らず後回しにする、妻の体調不良時も無関心であるなどがあります。
旦那が家事・育児をしない根本原因としては、性別役割分担意識の強さ、妻が全てやってくれると思い込んでいること、家事・育児のスキル不足を恥じていることが考えられます。
「何もしない旦那」を法的に考えると、家事をすることは夫婦の協力義務であり、家事育児の分担要請には法的な根拠があります。夫の何もしない態度が離婚原因になったり、親権争いで不利な要素になったりする可能性があります。
旦那の行動を変えるアプローチとしては、夫婦で話し合う、簡単な作業から段階的に任せる、夫の努力を認め具体的に感謝するなどの方法があります。
それでも夫が変わらない場合の選択肢としては、家事代行サービスの利用、別居による冷却期間の設定、離婚があります。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
「何もしない旦那」の5つの典型的な行動パターン
家のことを何もしない旦那、具体的にどんな旦那なのか説明します。
(1)家事・育児を手伝わない旦那
家事・育児を手伝わない旦那がいます。
トイレットペーパーを使い切っても補充しない、シャンプーなどを使い切っても補充しない、自分のお皿も下げない、ごみはテーブルの上に出しっぱなし、子どもが泣いていてもスマホを見て放置…などなど。
妻からしたら、「どうして次の人のことを考えられないのか」「どうして放置していられるのか」と疑問になりますが、注意しても聞き流されてしまうので、結局自分がやることになります。
妻は、子育てや家事などで時間が足りず分刻みでタスクをこなさなければならず、自分のための自由な時間がとれない、という事も多くあります。
一方、夫は家ではソファに座りスマホをいじる時間があるのを見ていると、妻にストレスがたまらない方がおかしいですよね。
(2)共働きでも家庭内の仕事を妻任せにする旦那
共働きにもかかわらず、家事を妻に全て任せて何もしないという旦那もいます。
妻は、仕事が終わった後に、たまった家事や育児を行わなければならず、寝る時まで息つく間もない、という方もいるかもしれません。
平日は夫の帰宅が遅く、家事育児ができないのは仕方ないとしても、休みの日も昼まで寝て、妻が作ったご飯を食べ、妻が掃除洗濯する傍らで夫はソファで横になる…というのには、疑問符がつく妻も多いのではないでしょうか。
(3)指示されないと動かない旦那
自主的には全く家事をしない旦那でも、指示すれば家事をしてくれるのであれば、まだいいかもしれません。
しかし、抽象的に「家事をして」と言われても、具体的に何をすればいいのか、わからない旦那がいます。
「そこまで言わないとわからないの」と感じてしまうくらい、具体的に指示されないと動かない旦那は、妻からしたら「説明する時間がもったいない」「自分でやった方が早い」という判断になりがちです。
(4)約束を守らず後回しにする旦那
妻としたらすぐにやってほしいけど、なぜかすぐ家事をしない旦那。
「やるやる」と言いながら、なぜか他のことをしていて、家事を後回しにします。後回しにしても、家事をしてくれるのであればいいですが、結局約束した家事をやらない旦那もいます。
旦那が家事をするのを待つくらいなら、自分でしてしまった方がストレスもないと考えて、結局妻が家事をする、という家庭も多いかもしれません。
(5)妻の体調不良時も無関心な旦那
妻が体調不良を伝えると、なぜか自分も急に具合が悪くなる夫がいませんか。熱の感じ方は人それぞれですが、平熱の範囲では?という熱で、夫は大げさに具合の悪さをアピール。
また、妻の体調不良に寄り添う気持ちもなく、無関心で、「ご飯はどうすればいいの」「子どもの面倒はみられるよね」と、ほぼ通常営業の家事を要求する夫もいます。
妻の体調不良時まで何もしない夫だと、もう妻が夫に何かを頼むこともなくなってしまい、夫婦関係は冷え切ってしまうのではないのでしょうか。
旦那が家事・育児をしない3つの根本原因
夫がなぜ家事育児をしないのか、その根本原因を3つ紹介します。
(1)性別役割分担意識が強いから
性別の役割分担意識が強い旦那は、「家事や育児は妻の仕事」とみなして、自分は家事育児をしない傾向があります。
伝統的な価値観に固執し、「男性は外で働き、女性は家庭を守る」という意識もあるかもしれません。
しかし、そのような意識がなく共働きのケースであっても、「家事育児は妻の方が得意だから妻に任せて、自分は仕事していれば大丈夫」と、妻に甘えている夫も多いのではないのでしょうか。
(2)妻が全てやってくれると思い込んでいるから
産休育休中は、妻が家にいる時間が長いこともあり、家事育児の主な担い手は妻かもしれません。結婚当初は、共働きなのに、妻が頑張って一人で家事をしていたかもしれません。
しかし、ずーっと妻に負担がかかるだけで、夫が何もしないのでは困りますね。妻も働いているのに、家事育児の負担が妻だけにかかるのはフェアではありません。
(3)家事・育児のスキル不足を恥じているから
家事・育児に参加していない旦那は、当然、妻に比べたら家事育児のスキルは不足しています。
必要な日用品がなにかもわからないし、食器の洗い方もわからない、ごみを捨てる日もわからない。
家事をするためには妻に細かく聞かざるを得ませんが、妻は怒ってダメ出しをしてきたり、「こんなこともわからないの」と責めたりする。妻に聞くこともはばかられ、家事育児をしたい気持ちがあっても、結局、自主的には何もできなくなってしまうのです。
法的観点から見る「何もしない旦那」の問題点
何もしない旦那について、法的に考えてみましょう。
(1)家事をすることは夫婦の協力義務
「夫婦は協力し合うべき」と言われます。夫婦として家庭を築いていくには、夫婦間に協力が必要なことは、当然のことです。
実はこれには法的な根拠があるのです。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法752条では、夫婦が互いに負う義務について次の3つを定めています。
① 同居義務
② 協力義務
③ 扶助義務
家事分担で関わるのは、②の義務です。②の義務には夫婦の家事分担に協力する義務も含まれると考えられています。つまり、夫婦の一方は、他方に対して、具体的に家事分担の協力を求めることができるのです。
(2)離婚原因となる可能性がある
夫婦の話し合いで離婚するのであれば、離婚原因はなんでも構いません。
しかし、一方が離婚を拒否した場合、最終的に裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定の離婚事由が必要です。
妻が夫に家事育児の分担の協力を要請し続けているのに、拒否し続けられたことで、夫婦関係が悪化したときには、その事情が法定の離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)で考慮される結果、離婚が認められる可能性があります。
(3)親権争いでの不利な要素になる可能性
「親権」とは、未成年者の子どもを監護・養育し、子どもの財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことです。
結婚中は、夫婦が共同で親権を持ちます。
離婚後は、夫婦のどちらが未成年の子の親権を持つかを決め、離婚届の際にどちらか一方を指定します(※)。
話し合いで決まらない場合には、調停や審判などで子どもの福祉の観点から親権者を決めることになりますが、そこでは従来の子どもの監護状況についても考慮されます。従来、夫が育児に参加していなかったのであれば、その事情は親権者を決める際にマイナスの考慮要素となるでしょう。
※2024年5月、離婚後も共同親権を選択できるよう法改正がなされました。改正法が施行されたあとは、協議により、単独親権とするか、共同親権とするかを選択することができます。親権者について争いがあり、調停又は審判の申立をしている場合には、親権者を定めなくても離婚することが可能です。
旦那の行動を変える3つのアプローチ
何もしない旦那にも、何らかの理由やきっかけがあるはずです。
そうであれば、何らかのきっかけで、家事育児に取り組む旦那に変わる可能性だってあるはずです。
しかし、他人を変えることは困難です。少なくとも、夫が自分で変わりたいと思わない限り、妻がアレコレ言っても変わることはないでしょう。
旦那と敵対するのではなく、家庭を切り盛りする共同体として、協力し合う観点で以下の対処法を試してみてください。
(1)夫婦で話し合う方法
まず、基本的方法として考えられるのが夫婦の話し合いです。
夫婦とはいえ育った環境も価値観も異なります。問題があれば、そのたびに話し合って価値観をすり合わせたうえで、譲歩しあう必要があります。
せっかく縁あって夫婦となったのですから、コミュニケーションをとることをあきらめず、改善のために話し合ってみましょう。
話し合う際には、次の点に注意してみましょう。
- 「あなたは何もしない」という枕詞を付けると相手も「やっている」と反論したくなるので、建設的ではない批判は控える。
- 大変だから家事をしてほしい」と言っても伝わりにくいので、具体的に何が大変なのか、見えない家事などについても説明する。
- 家事を一覧化したうえで、「この週は何をやってほしい」「この日は何をやってほしい」と具体的に明確に伝える。
(2)簡単な作業から段階的に任せる方法
家事に慣れていない旦那には、簡単な家事を任せて自信を持ってもらうことが、自主的に家事をすることにつながるでしょう。
気になるかもしれませんが、細かな方法は指図せず、一度夫に任せてみましょう。
任せたうえで、「すごいできるじゃない」「ありがとうとっても助かった」と喜びと感謝を伝え、注意点があれば、最後に「次はこの点気を付けてくれるとうれしいな」などと簡単に伝えるようにしましょう。
(3)夫の努力を認め、具体的に感謝する方法
妻が夫に「●●をやって」と指示を出し、夫が指示内容をやってくれる状況は、何もしない夫よりは格段によいですが、できれば、夫には自主的に家事育児をやってもらいたいもの。
そんなときは、夫がしてくれた家事について、大げさに喜びや感謝の気持ちを示してみてはどうでしょうか。
「ありがとう」「うれしい」といわれて、嫌な気がする人はいません。
夫は、「こんなに喜んでくれるならもうちょっと家事をしてみよう」と思い、家事育児をするモチベーションになるかもしれません。
それでも変わらない場合の3つの選択肢
いろいろ努力したけれども、やはり旦那は何もしない、と絶望する方もいるかもしれません。その場合の選択肢を3つ紹介します。
(1)家事代行サービス・ベビーシッターの利用を検討する
妻に一方的にかかる負担を軽減しなければ、いつか妻が倒れてしまいます。
お金はかかりますが、家事代行サービスは、料理準備、掃除、洗濯など頼みたい家事を頼めますので、大変便利です。妻も、自分の時間を確保でき、精神的にも余裕が生まれるでしょう。
ただし、「何もしない夫」は解決できていないので、夫への愛情を維持できるかという問題は残りそうです。
(2)別居による冷却期間を設ける
しばらく別居することも、一つの方法です。
短期間の別居により、夫婦間の物理的な距離を置くことで、冷静に問題を見つめ直すことができるからです。お互いの大切さを再認識できるかもしれません。
ただし、法律上、夫婦には同居義務があり、正当な理由なく一方的に別居すると、この同居義務に違反することになってしまいます(直接の罰則はありません)。
配偶者からDV・モラハラを受けているなどの事情がない場合には、話し合って別居の同意を得たうえで別居するようにしましょう。
(3)離婚を視野に入れる
日本では、夫婦が離婚に合意すれば離婚することができます。
合意できれば、離婚の原因は問われないので、「旦那が家事育児を何もしない」という理由で離婚することは可能です。
しかし、夫が離婚を拒否した場合には、離婚するためには、離婚調停を申し立てたうえで、それでも離婚できなければ離婚訴訟を提起して裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
裁判所の手続となると「夫が家事育児を何もしない」という抽象的な理由だけではでは、離婚を認めてもらうことは難しいでしょう。
夫が家事育児をしない状況が妻にとって過酷であること、妻が夫に家事育児を依頼しても夫が拒否し続けたこと、それにより夫婦関係が悪化し別居が続いていることなど、様々な事情が考慮されたうえで、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとされれば、離婚が認められる可能性があります。
ご自分のケースで離婚できる可能性があるかどうかは、離婚を扱っている弁護士に相談してみるとよいでしょう。
【まとめ】
「何もしない旦那」に悩む多くの妻にとって、家事・育児の負担を公平に分担することは家庭の円満に直結します。
夫と話し合い、具体的な家事分担表を作成し、段階的に旦那に任せ、旦那がした家事育児について大げさに感謝を伝えたりすることで、旦那の行動を変えることができるかもしれません。まずは小さな一歩から始めてみてください。
家庭内のストレスを減らし、より良い夫婦関係を築くために、今すぐ行動を起こしましょう。
何もしない旦那とはもう離婚したいという方は、一度離婚について弁護士に相談することをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、婚姻費用の請求や離婚したいと考えている方からのご相談を承っております(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます)。
「婚姻費用がもらえない」「離婚したいができるかどうかわからない」人によって抱えるお悩みは様々です。
一度そのお悩みを、アディーレにお聞かせいただけませんか。
ご相談はお電話で可能ですので、こちら(フリーコール0120-554-212)までご連絡ください。