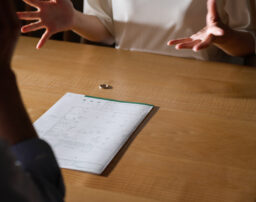育児は喜びと同時に大きなストレスを伴うものです。
特に初めての育児や、頼れる家族がそばにいない親にとって、育児ノイローゼは注意しておいた方がいいでしょう。
この記事では、育児ノイローゼのセルフチェックリストを提供し、その症状や原因、対策について詳しく解説します。さらに、適切な相談先についてもご紹介します。
育児ノイローゼかもしれないと感じたら、ぜひこの記事を参考にして、早期に対策を講じましょう。
この記事を読んでわかること
- 育児ノイローゼとは
- 育児ノイローゼチェックリスト
- 育児ノイローゼの原因
- 育児ノイローゼの対策
- 育児ノイローゼの相談先
ここを押さえればOK!
育児ノイローゼの主な原因として、ワンオペ育児、自分の時間が取れない、他の子や親と比べる、不眠などが挙げられます。これらの原因により、精神的・身体的な負担が増大し、育児ノイローゼに陥るリスクが高まります。
対策としては、パートナーや家族、外部サービスからのサポートを受ける、寝る時間を確保する、自分の時間を確保する、信頼できる友人に相談する、病院を受診するなどが有効です。
また、育児ノイローゼの相談先として、子ども家庭支援センター、日本保育協会の相談窓口、日本助産師会の相談窓口などがあります。これらの窓口を利用して、育児の不安や悩みを相談しましょう。
育児ノイローゼとは
育児ノイローゼとは、育児に伴うストレスやプレッシャーが原因で、精神的・身体的に不調をきたす状態を指します。
特に初めての育児やワンオペ育児(ひとりで育児を行うこと)に直面する親に多く見られるようです。
育児ノイローゼは、放置するとうつ病を発症する可能性があるため、早期のセルフチェックと対策が重要です。
育児ノイローゼのセルフチェック
以下の症状が複数当てはまる場合、育児ノイローゼの可能性があります。
☑子どもの笑顔や成長を喜べない
☑泣いている子どもをどうしても抱っこできない
☑人生がつまらないと感じる
☑子どもをみてイライラする
☑ダメな親だと思う
☑ダメな親で子どもがかわいそうだと思う
☑子どもにやさしくできず自己嫌悪に陥ることがある
☑常に疲れている
☑朝起きられない
☑家事ができない
☑食事がおいしいと思えない
☑頭痛や胃痛などの身体症状がある
☑子どもとの生活に絶望することがある
☑楽しいテレビを見ても楽しめない
☑優しくされても素直に受け入れられない
育児ノイローゼの原因
育児ノイローゼの原因は様々です。主な原因を以下に挙げます。
(1)ワンオペ育児
ワンオペ育児とは、ワンオペレーションで(ひとりで)、家事・育児全般を行うことを指します。
配偶者が仕事で忙しい、または単身赴任中などの理由で、育児・育児を一人で担うことが多い場合、精神的・身体的に大きな負担がかかります。
家事や育児の全てを一人でこなすことは、時間的・肉体的な余裕を奪い、ストレスを増大させます。
これが長期間続くと、育児ノイローゼに陥るリスクが高まります。
「もう一人ではできない」というタイミングがあるはずです。ひとりで頑張ることには限界があります。パートナーや家族に相談し、協力しながら大変な時期を乗り切りましょう。
(2)自分の時間が取れない
特に新生児は、目が離せません。授乳にミルク、おむつや着替え、夜泣きへの対応、昼夜なく起きたり寝たりするのに併せて生活するので、寝不足になります。
細切れの睡眠時間を足しても、数時間にもならない、ということは珍しくありません。
また母親の場合、出産直後でまだ体調も戻っていないのに、子どもの世話で体力や精神力が削られ、体調が戻るのにも時間がかかってしまいます。
また、子ども中心の生活では、音楽や動画を楽しむといった、プライベートな時間はほとんどとれません。
このように、育児に追われ、自分の時間が全く取れない、休めないことで肉体的・精神的に追い詰められます。自分の趣味に使える時間や、リラックスする時間もないので、ストレスも解消できなくなり、疲労が蓄積していきます。
育児にすべての労力と時間を費やすことで、「こんなはずじゃなかった」など、自分自身の存在価値を見失いがちです。
これが精神的な負担となり、育児ノイローゼを引き起こす要因となります。
(3)他の子や親と比べる
特に初めての育児は、不安がつきません。
「ミルクの量が少ないのでは?」「まだ寝返りしないけど大丈夫?」などなど。
時に、他の子どもや親と自分を比較して、自己評価が低くなることがあります。
「あの子はもっと長く寝るのに、うちの子は寝ない」
「あの子は全然泣かないのに、うちの子は夜ずっと泣いてる」
「あの人は家事も育児もちゃんとやれてるのに、自分はダメだ」
このような比較は、自己否定感や劣等感を強めて自分の幸せを遠ざけてしまい、育児ノイローゼの原因となります。
(4)不眠
育児による夜間の授乳やおむつ替えで睡眠不足が続くと、疲れが取れず、精神的・肉体的な疲労が蓄積します。
特に、夜間に何度も起きることが続くと、深い睡眠が取れず、日中の活動に支障をきたすこともあります。
睡眠不足は、集中力の低下やイライラ感を引き起こし、育児ノイローゼのリスクを高めます。
育児ノイローゼの対策
育児ノイローゼを予防・改善するための対策について、以下説明します。
(1)パートナーや家族、外部サービスから育児のサポートを受ける
育児を一人で抱え込んでしまうと、精神的肉体的な負担が大きくなります。
育児は、パートナーや家族に協力を求めることが重要です。
例えば、パートナーに夜間の授乳や夜泣き対応、おむつ替えを手伝ってもらう、週末に家事を分担するなど、具体的なサポートをお願いしましょう。
家族の協力を得ることで、精神的な負担が軽減され、育児ノイローゼの予防につながります。
また、パートナーが単身赴任中で実家や義家族も遠方、家族の助けは得られない、というケースでは、外部サービスの利用を検討しましょう。
家事代行やベビーシッターなどを利用すれば、自分の負担を軽減することができるでしょう。
(2)寝る時間を確保する
慢性的な睡眠不足は、肉体的な疲れを回復できず、精神的な不調を引き起こすことがあります。
そのため、できるだけ寝る時間を確保しましょう。
例えば、子どもが昼寝をしている間に家事をせずに自分も寝る、夜間の授乳は交代で行うなど、工夫して睡眠時間を確保することが大切です。
十分な睡眠を取ることで、心身のリフレッシュが図れ、育児ノイローゼの予防に役立ちます。
(3)自分の時間を確保する
忙しい中でも、自分の時間を確保することは、自分らしくいるためにとても重要です。
パートナーや家族、外部サービスなどを利用して、子どもと離れ自分のための時間を確保する努力をしましょう。
買い物に行くのでもよし、おいしいご飯を食べに行くのでもよし、美容院やマッサージに行くのでもよし。好きなことをします。
1時間でも自由に過ごせれば、精神的ストレスは軽減するはずです。
定期的に自分の時間を確保できるように、パートナーとよく話し合うようにしましょう。
(4)信頼できる友人に相談する
悩みを抱え込まず、信頼できる友人に相談することで気持ちが軽くなることがあります。
友人との会話を通じて、自分の気持ちを整理し、共感を得ることで、精神的な負担が軽減されるためです。
また、友人からのアドバイスやサポートを受けることで、育児に対する新たな視点や解決策を見つけることができるかもしれません。
(5)病院を受診する
不眠が解消できない場合、ストレスが大きく日常生活に支障が出ていると感じる場合、胃痛など身体的症状が出ている場合などでは、なるべく早く病院を受診しましょう。
精神科や心療内科が望ましいですが、自分が出産した産婦人科で話を聞いてもらえたり、病院を紹介してもらえたりすることもあります。
病院を調べたうえで、受診可能か事前に問い合わせてみるようにしましょう。
育児ノイローゼの相談先
育児ノイローゼにならないためには、何よりも育児の悩みや不安を一人で抱え込まないことが大切です。
パートナーや家族、友人に相談できなくても、以下のように、経験や知識のある第三者に相談できる窓口があります。
(1)子ども家庭支援センター
居住する地域には、「子ども家庭支援センター」「こども家庭センター」などという子育ての相談などを受け付ける窓口があるはずです。
ここでは、育児の不安などを対面や電話で相談できます。費用はかかりません(通話料除く)。
LINEで相談できるケースもあるようです。
居住する市区町村役場のホームページなどに記載がありますので、ホームページを確認したり、直接市区町村に連絡先を問い合わせたりして、窓口を確認しましょう。
(2)日本保育協会の相談窓口
社会福祉法人日本保育協会で、育児相談電話窓口を開設しています。
保健師や元保育園長など、子育てについて専門知識を有する方が、乳幼児の子育てについて30分程度相談にのり、アドバイスをしてくれます。
費用はかかりません(通話料除く)。
電話番号:03-3222-2120
相談日:月~金曜日(土日祝・年末年始除く)
時間:10:00~12:00、13:00~16:00
(3)日本助産師会の相談窓口
公益社団法人日本助産師会では、育児だけでなく、思春期の悩みや更年期症状を含めた女性の健康について相談をすることができます。
相談日や相談時間は地域によって異なりますので、ホームページでご確認ください。
【まとめ】育児ノイローゼかも?と思ったら早めに対策を!一人で抱え込まず周りの助けを求めよう
育児ノイローゼは、育児にかかわる人であれば、誰にでも起こり得る問題です。
早期にセルフチェックを行い、適切な対策とサポートを受けることで、育児にかかるストレスを軽減し、家族とともにと健やかで幸せな生活を送りましょう。