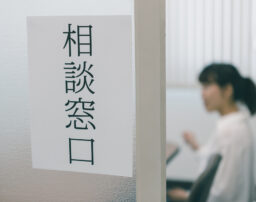離婚を考える女性にとって、何から始めれば良いのか、どのような手続きを踏むべきかを事前に把握することは非常に重要です。
離婚する際には、経済的な不安、子どもの将来への影響に悩んだりして、多くの課題に直面することでしょう。
この記事では、離婚の際の具体的なステップとチェックリストを紹介して、離婚前後にやるべきことを明確にします。
離婚後の生活に向けた準備のお手伝いができればと思いますので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 離婚を決意した女性が最初にすべき3つのステップ
- 離婚前チェックリスト
- 離婚準備中に注意すべきポイント
- 離婚後にすべき重要な手続き
ここを押さえればOK!
まず、冷静に離婚の是非を再考することが重要です。感情的に離婚を決断して後悔しないためです。
次に、できれば信頼できる人や弁護士に相談します。客観的な意見や法的なアドバイスを得て、離婚準備を行っていきます。
最後に、離婚届不受理申出を行います。虚偽の離婚届を提出されて、勝手に離婚されるのを防ぐためです。
また、一般的に、離婚前に女性がやるべきことは、共有財産の特定と分与、離婚後の住居の決定、仕事と収入の見通し、慰謝料請求の可能性、年金分割、離婚後の姓をどうするか、別居中の婚姻費用の取り決め、離婚届の証人の検討などです。
子どもがいる場合は、特に、親権、養育費、面会交流、離婚後の子どもの姓、学校、ひとり親家庭向けの社会保障制度についても事前に調べる必要があるでしょう。
離婚準備中は、証拠収集、離婚協議書の作成、不安・疑問点についての弁護士相談が重要です。
離婚後は住民票・戸籍・印鑑登録の変更、国民年金・国民健康保険の加入、必要な名義変更、ひとり親家庭向けの制度申請を速やかに行いましょう。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
離婚を決意した女性が最初にすべき3つの重要なステップ
「離婚しかない」と思っても、少し立ち止まって、後悔のない離婚のために次の3つのステップを実践しましょう。
(1)冷静に離婚の是非を再考する
「離婚しかない」「もう離婚する」と思ったときには、一度冷静にその是非を再考することが重要です。
感情的に離婚してしまって、あとで後悔することを避けるためです。
具体的には、離婚の理由を箇条書きでまとめたうえで、その一つ一つについて、本当に離婚するしか解決方法がないのか、検討してみてください。
また、離婚後の生活についてじっくり考え、どのような影響があるのか具体的に想像するようにしましょう。
また、子どもがいる場合には、離婚が子どもに与える影響(引っ越しで生活環境が変わる、学校が変わる、経済的余裕がなくなり子どもにも影響するなど)も考慮する必要があります。
このように具体的に検討することにより、感情に流されずに理性的な決断を下すことができるでしょう。
(2)信頼できる人や弁護士に相談する
冷静に考えて離婚を決断したら、次に、信頼できる人や弁護士に相談することが重要です。離婚経験者の友人からは、実践的なアドバイスや経験談を聞けるかもしれません。また、離婚経験のない友人で会っても、第三者の意見により視野が広がり、気づかなかった点に気づくかもしれません。
特に、離婚を扱う弁護士に相談することで、不安を解消したり、法的なアドバイスを受けたりすることができます。離婚手続きを弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに弁護士が、夫と離婚条件について話し合い、離婚を目指すことができます。
(3)離婚届不受理申出を行う
夫婦によりますが、通常離婚までには夫と話し合って決めなければならないことがあります。離婚条件がまとまるまでに、一方的に虚偽の離婚届が提出されてしまうことを防ぐために、離婚届不受理申出を行うとよいでしょう。
離婚届不受理申出を行っておけば、夫が勝手に虚偽の離婚届を提出しても、役所が受理しませんので、離婚は成立しません。不受理申出は、取り下げを行わない限り、将来にわたって有効です。
申出を行える役所は、本籍地か住民票所在地です。申し出の際には本人確認書類が必要ですので、事前に申出を行う役所のホームページなどで手順を確認しておくようにしましょう。
この手続きを行うことで、勝手に離婚されることなく、離婚するために冷静に準備を進める時間を確保することができるでしょう。
【子どもがいる・いない場合共通】離婚前チェックリスト
離婚を考える女性が、一般的に、離婚前にやるべきことは次の通りです。
☑共有財産を特定し、分与について考える
☑離婚後の住居を決める
☑仕事と収入の見通しを立てる
☑慰謝料請求の可能性を調べる
☑年金分割について調べる
☑離婚後の姓をどうするか考える
☑別居中の婚姻費用を取り決める
☑離婚届の証人をお願いする人を検討する
順に説明します。
(1)共有財産を特定し、分与について考える
離婚前にまず行うべきは、共有財産を特定し、その分与について考えることです。
共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持された財産のことです。
例えば、結婚後購入した不動産、車、貯金、株式などが含まれます。
夫または妻一方の名義であっても、実質的に見て、婚姻中に形成された財産と言えれば「共有財産」となります。
一方で、独身時代に取得した個人的な財産や、結婚後に相続で取得した財産などは、共有財産ではありません。
まずは、共有財産を漏れなくリストアップすることから始めましょう。通常、分配の比率は2分の1ですが、慰謝料代わりに一方の分配の比率を多くする、というケースもあります。
そして、一つ一つの共有財産について、どのように分けるかを検討します。ローンが残っている自宅をどうするのか、子ども名義の預金はどうなるのかなど、検討が難しいケースもあります。ご自身のケースに応じて、具体的なアドバイスが欲しいときには、一度離婚を扱う弁護士に相談してみるとよいでしょう。
(2)離婚後の住居を決める
離婚に際して妻が今の家を出る場合、離婚後の住居を事前に決めておかなければなりません。
住居の契約には、敷金、礼金、仲介手数料など、まとまったお金が必要ですので、準備するようにしましょう。あたらしい住居で利用する家電や家具などの費用についても、事前に計算して準備するようにします。
新しい住居を探す際には、あたらしい住居に何を望むのか(通勤時間、立地、スーパーなどの有無、駐車場の有無)などをまとめたうえで、条件に沿う物件を探すとよいでしょう。
また例年3月~4月頃は引っ越し業者も忙しくなるので、引っ越し時期が決まったら早めに業者も確保するようにしましょう。
(3)仕事と収入の見通しを立てる
離婚後、経済的に安定した生活をおくるためには、仕事と収入の見通しを立てることが欠かせません。
現在の職場での継続勤務が可能か、新しい仕事を探す必要があるかを検討しましょう。
必要であれば、スキルアップや資格取得により、収入を上げることも考えましょう。
また、転職により収入が減少する場合には、生活費を見直して生活レベルを下げることや、節約方法を考えることも重要です。
月1万円でも収入を上げたり、逆に支出を下げたりすることができれば、将来的な収入増加・支出減額はかなりの額になります。
(4)慰謝料請求の可能性を調べる
離婚に際して、慰謝料請求の可能性を調べることも重要です。
慰謝料は、夫による不貞行為や暴力などを原因とする離婚について、妻が受けた精神的苦痛を慰謝するために請求できるお金です。
慰謝料の請求には、証拠が重要です。相手が「すまなかった」と不貞行為や暴力を認めることもありますが、「そんなことはしていない」と否定された場合には、不貞行為や暴力の事実を証明する証拠が必要になるためです。
例えば不貞行為であれば、不倫相手との肉体関係があることが分かるメッセージのやり取りや写真、動画などの証拠を事前に収集しておくようにします。
弁護士に相談すると、証拠として十分かどうか、慰謝料額の相場や、具体的な慰謝料請求の手順などについてアドバイスをもらうことができるでしょう。
(5)年金分割について調べる
年金分割制度は、離婚の際に、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の標準報酬月額などの記録を分割する制度です。記録を分ける側は、年金分割により将来の年金額が減少し、記録を受け取る側は、将来の年金額が増加します。
この制度は「国民年金」や「厚生年金基金・国民年金基金」等は対象になりません。
年金分割の方法には「合意分割」と「3号分割」があります。
年金の分割は、夫婦で合意をしただけでは行われず、年金事務所で手続する必要があります。年金分割により受け取る年金が増える可能性のある女性は、離婚日の翌日から2年という期限内に、忘れずに手続きをしましょう。
年金の分割に際し、婚姻期間中の標準報酬額を知るためには「年金分割のための情報通知書」で年金記録を確認したうえで、分割の割合を話し合います。
姻期間中を通して相手方の扶養(国民年金第3号被保険者)になっていた場合は、相手方の合意を必要としない「3号分割」が可能です(2008年4月1日以降の婚姻期間のみ)。
(6)離婚後の姓をどうするか考える
離婚後の姓をどうするかも重要な検討事項です。
離婚後、結婚により姓が変更した側は、法律上当然に結婚前の姓に戻ります。
婚姻時の姓を維持したい場合には、離婚の日から3ヶ月以内に「婚氏続称の届出」を居住地の役所の提出することで、原則として結婚している間の姓を離婚後も名乗ることができます。
婚姻期間が長い場合、婚姻前の姓に戻ることで、さまざまな面で影響が出る可能性があります。自分にとって最適な選択をするために、離婚前に、自分の離婚後の姓をどうするのか考えたうえで、慎重に決定することが重要です。
(7)別居中の婚姻費用を取り決める
離婚前に、一度別居の選択をする夫婦は多いです。
別居中であっても、収入の多い方は、少ない方へ、婚姻費用(別居中の配偶者や子どもの生活費)を支払う義務があります。
したがって、離婚前に別居する場合には、別居中の婚姻費用を取り決めることも重要です。婚姻費用の取り決めは、基本的に夫婦間での話し合いで行います。夫婦間での話し合いで決めることが難しい場合には、家庭裁判所での調停を利用して合意を目指します。
婚姻費用には、裁判所が公表する婚姻費用算定表で算定した相場がありますので、そちらを参考に話し合ってみるとよいでしょう。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所
(8)離婚届の証人をお願いする人を検討する
話し合いで離婚する場合、離婚届に夫婦双方の署名と、証人として、成人(18歳以上)2人の署名が必要です(証人の押印は任意)。
証人は、夫婦どちらかの両親や友人に依頼することが一般的です。
【子どもがいる場合】離婚前チェックリスト
子どもがいる場合に、特に離婚前にやるべきことは次の通りです。
☑親権をどうするか検討する
☑養育費がいくら貰えるのか調べる
☑面会交流の条件を考える
☑離婚後の子どもの姓を検討する
☑離婚後の子どもの学校を検討する
☑ひとり親家庭向けの社会保障制度を調べる
順に説明します。
(1)親権をどうするか検討する
未成年の子どもがいる場合は、親権をどうするかは極めて重要です。
通常、親権を持つ親が子どもと同居し、子どもの生活全般の面倒をみるためです。
親権をどちらが保有するかは、子どもの生活に大きな影響を与えますので、子どもの福祉の観点から、慎重に決定する必要があります。子どもが一定の年齢に達していれば、子どもの意見も尊重されるべきです。
夫婦双方が親権を欲しがるのであれば、話し合いでどちらが親権を保有するのか、決める必要があります。話し合いで決められなければ、家庭裁判所へ調停を申し立てて、合意を目指します。
事前に弁護士に相談することで、親権を得るのに有利な事情は何なのか、あなたのケースでどのような事情を主張して親権を求めるべきなのかなど、具体的な法的なアドバイスを受けることができるでしょう。
※2024年5月、離婚後も共同親権を選択できるよう法改正がなされました。改正法が施行されたあとは、協議により、単独親権とするか、共同親権とするかを選択することができます。親権者について争いがあり、調停又は審判の申立をしている場合には、親権者を定めなくても離婚することが可能です。
(2)養育費がいくら貰えるのか調べる
養育費は、離婚後、通常離れて暮らす親から、子ども(未成熟子:通常20歳以下)と同居する親に対して、子どもの生活費や教育費を補うために支払われます。
養育費の金額は、話し合いで決めます。裁判所が公表している養育費算定表から、夫婦の収入や子どもの年齢、人数などを考慮した相場を知ることができますので、そちらを参考にするとよいでしょう。
話し合いで決められなければ、家庭裁判所へ調停を申し立てて、調停員の仲介の下で合意を目指します。
事前に弁護士に相談することで、養育費の目安、請求の手順や交渉などのアドバイスを受けることができるでしょう。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所
※2024年5月、夫婦の合意がなくても、離婚の日から法務省令により定められた額について、養育費を請求できるよう法改正がなされました。改正法の施行後は、養育費の合意がなくても一定額を請求できるようになります。
(3)面会交流の条件を考える
「面会交流」とは、子どもと一緒に暮らさない親が子どもと会ったりして交流することです。
面会交流の頻度や方法については、父母が子どものことを考えて話し合いで決めます。
1ケ月に1回程度が多いようですが、回数や内容については、夫婦の話し合いによって決めることができます。
面会交流は、離婚後も子どもと同居しない親との関係を維持するため重要です。面会交流の条件については、誤解のないように、具体的に明確に定めておいた方が良いでしょう。
どのような条件を定めればよいのかわからない方、不安な方は事前に弁護士に相談しましょう。
(4)離婚後の子どもの姓を検討する
父母が離婚しても、子どもの姓は当然には変更されません。
母が親権者となったケースを考えます。離婚によって母が旧姓に戻った場合も、何も手続をしなければ子どもの姓は婚姻中の姓のままです。この場合、親権者である母と子どもの氏が異なってしまいます。
母親が婚氏続称の届出をすれば、同じ姓を名乗ることができます。ただこの場合も、自動的に子どもは母親の戸籍に移動しませんので、同じ戸籍に入るためには手続きが必要です。
母が旧姓に戻り、子どもも旧姓に変更したいときには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てて、子どもの姓を母親の旧姓と同じにする必要があります。そのうえで、子どもの戸籍について、母親と同じ戸籍に入れるよう、市町村役場で入籍届を提出する必要があります(姓が違う場合には同じ戸籍には入れません)。
子どもの姓を変更することで、子どもが築き上げた社会的なアイデンティティや学校生活に影響が出ることもあります。子どもの意見や感情を尊重し、子どもにとって最善の選択をすることが重要です。
(5)離婚後の子どもの学校を検討する
離婚に伴う引っ越しで、子どもの学校・保育所を変更する必要がある場合があります。
学区や、転校に伴う手続きや費用については、事前に問い合わせて確認しておくようにしましょう。
夫婦が別居したり、引っ越して生活環境や学校・保育所などが変わったりすると、住み慣れた住環境や友人関係から離れることになり、子どもが精神的に不安定になることがあります。
もちろん、子どもによっては、離婚しても精神的影響を受けないケースもあります。これは、離婚前の夫婦関係や、親との関係、子どもの性格などによるところが多いようです。子どもの気持ちに寄り添って手続きを進めるようにしましょう。
(6)ひとり親家庭向けの社会保障制度を調べる
ひとり親家庭向けの社会保障制度を調べることも重要です。
児童手当やひとり親家庭向けの支援など、さまざまな制度があります。これらの制度を利用することで、離婚後の経済的な負担を軽減することができます。
居住する役所に問い合わせる、ホームページで確認するなどして、利用できる条件や、自分が離婚後利用できるのかなどを調べておくようにしましょう。
離婚準備中に注意すべき3つのポイント
離婚準備中には、「証拠を確保する」「合意内容は離婚協議書という書面にまとめる」「弁護士に相談する」という、3つの大切なポイントがあります。
順に説明します。
(1)証拠収集の重要性
離婚準備中に、自分の主張を裏付ける証拠を確保することはとても大切です。
例えば、夫の不貞行為が原因で離婚するのであれば、不貞行為の事実や、不倫相手は夫が既婚者であることを知っていた事実に関する証拠を集めましょう。
また、夫婦の共有財産に関する証拠として、銀行口座の残高や、証券口座の保有証券、不動産の登記簿などを準備しておきます。
(2)離婚協議書を作成する
離婚の条件については、誤解や「言った言わない」という争いを避けるためにも、離婚協議書という書面に明確にまとめておくようにしましょう。
離婚協議書に記載する内容は、夫婦の状況によってケースバイケースですが、一般的に次のような内容を記載します。
- 離婚の合意がなされたこと
- 離婚届を提出する者の合意がなされたこと
- 子どもに関すること(親権、養育費、面会交流など)
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料(不貞行為などがあるケース)
- 清算条項
- 夫婦の署名押印
- 書面作成日
慰謝料や養育費などの支払いは、残念ながら、支払いが滞ってしまうケースも少なくありません。
このようなトラブルに備え、金銭を支払う約束がある場合には、離婚協議書は、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書にしておく方がよいでしょう。
(3)不安な点はそのままにせず弁護士に相談・依頼する
離婚準備は、それぞれの目標(親権を得るため、離婚後の安定した生活のため、適切な財産分与を実現するためなど)を実現するために、様々な観点から総合的に考慮したうえで進めていく必要があります。
1人で取り組むのは大変なことですので、不安や疑問があれば、一度離婚を扱う弁護士に相談してみましょう。
また、「夫とはもう直接話し合いたくない」「一度話し合ったがどうしても感情的になってしまい交渉は決裂した」などという場合には、弁護士に依頼して弁護士が代わりに交渉することで、冷静な話し合いが可能になることがあります。
弁護士はあなたの強い味方になりますので、一度相談だけでもしてみるとよいでしょう。
離婚後にやるべき重要な手続き
離婚できた後、行うべき重要な手続きをいくつか紹介します。離婚後も必要な手続きは人によって異なりますので、計画的に順序良く行っていくようにしましょう。
(1)住民票・戸籍・印鑑登録の変更を行う
住民票・戸籍・印鑑登録の変更の手続きは、市区町村役場で行います。
日中何度の市区町村に足を運ぶのは大変ですので、離婚届を提出する際、一緒に手続きできるよう準備しておくとスムーズです。事前に役所のホームページなどで必要書類などを確認しておきましょう。
住民票の変更について、市町村内へ引っ越す場合は、転居届を提出します。
違う市区町村へ引っ越す場合は、引っ越し前の市区町村で転出届を提出して転出証明書を受け取り、新しい市区町村で転入届を提出することになります。
また、離婚後も婚姻中の姓を利用したいときは、市区町村役場に「婚氏続称届」を提出します。離婚の日から3ケ月以内の届出が必要ですので、注意しましょう。
(2)国民年金・国民健康保険の加入手続きをする
婚姻中に元夫の扶養に入っていて、国民年金の第3号被保険者だった場合、離婚に伴い元夫の被扶養者から外れますので、手続きが必要です。勤務先の健康保険に加入できる方は、勤務先で必要な手続きをしましょう。
離婚後も仕事をしない方や、勤務時間が短いなどの理由で勤務先の健康保険に入れない方は、市区町村役場の窓口で、国民健康保険に加入する手続をします。
(3)必要な名義変更手続きを行う
財産分与で取得した財産で、元夫名義のものは、名義変更手続きが必要です。勝手に元夫に売却されてしまうなどのトラブルを防ぐためにも、なるべく早く行いましょう。
また、離婚に伴い姓や住所が変わる場合、銀行口座、運転免許証、契約名義など、様々な名義変更も必要になります。変更手続きが必要なものについては、漏れのないようリストを作成したうえで、速やかに変更手続きを行いましょう。
(4)ひとり親家庭に対する制度の申請をする
離婚してひとり親家庭になると、次のような公的支援を受けられる可能性があります。
- 児童扶養手当
- ひとり親家庭の医療費補助
- 就学支援
- 自立支援プログラム など
他にも様々な支援があります。市区町村の窓口で事情を説明して、どのような支援を利用できるのか相談してみるようにしましょう。
【まとめ】離婚前後はやるべきことがたくさん!不安なときは弁護士に相談を
離婚をしたいと思ったら、感情的に離婚を決断するのではなく、冷静に「本当に離婚をしたいのか」「離婚したら生活はどう変わるのか」など、離婚後の生活について具体的に検討してみましょう。
それでも離婚の決意が変わらなければ、次に、共有財産の特定や離婚後住居の確保、仕事と収入の見通しを立てるなど、具体的な準備を進めましょう。
離婚準備を一人で行うのは大変です。弁護士に依頼すれば、弁護士はあなたの強い味方となり、夫との離婚条件の交渉、合意、離婚協議書の作成などを行います。話し合いがまとまらず、調停などの対応が必要になった場合も安心して手続を進めることができるでしょう。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2025年1月時点)。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212 )にご相談下さい。