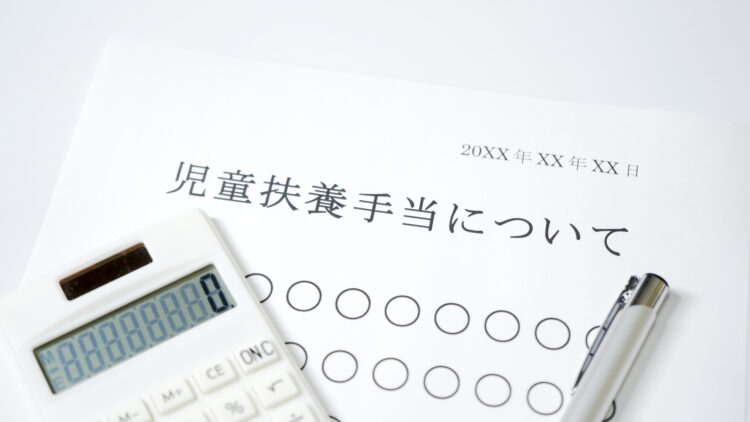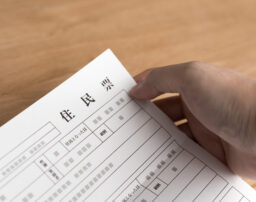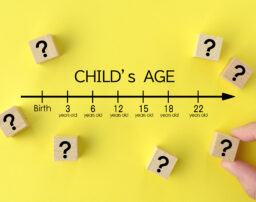養育費が将来にわたって継続して支払われる保証はありませんし、養育費を支払ってもらうために元夫と連絡をとらなければならない精神的ストレスもあります。
令和3年度の調査によれば、現在も養育費を受けとっている母子世帯は28.1%に過ぎません。
養育費を一括で支払ってもらえば、金銭的にも精神的にも安心です。
養育費には原則として贈与税はかかりませんが、それは養育費として「通常必要とされる」範囲内の金銭のやりとりだけです。
通常必要とされる範囲外で養育費として金銭をもらうと、贈与税がかかってしまう可能性があります。せっかく子供のためにもらったお金から税金を支払わなければならなくなってしまうのは、本末転倒です。
この記事では、養育費と贈与税に関する基本的な知識や、贈与税がかかってしまう可能性があるケースについて、わかりやすく解説していきます。
この記事を読んでわかること
- 養育費は原則として贈与税がかからないこと
- 養育費に贈与税がかかるケース
- 一括払いの養育費を非課税にする方法
参考:全国ひとり親世帯等調査 令和3年度全国ひとり親世帯等調査 実数値 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)
ここを押さえればOK!
一括で受け取る場合には、非課税とするための方法として、教育資金贈与信託を利用する方法や、離婚の際に養育費と明示せず財産分与の中に含めて解決する方法があります。
ただし、教育資金贈与信託には細かい条件や決まりがあり、利用には注意が必要です。
離婚の際には、養育費のほかにも財産分与や慰謝料など話し合うべきことが多く、弁護士に相談することも推奨されます。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
原則として養育費に贈与税はかからない
親は、子どもに対して扶養義務があります(民法877条1項)。
親が他方の親に子どものために養育費を支払うことは、扶養義務の履行です。
民法上の扶養義務者相互間で、生活費や教育費などのためにお金の贈与を受けても、「通常必要と認められる」範囲内のものであれば、贈与税はかかりません。
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
(1)養育費には所得税もかからない
贈与税と同じように、もらった養育費には所得税もかかりません。
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
…及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
養育費の取り決め方
養育費は話し合って金額といつまで支払うかなどを決めます。
払う方にとっては、養育費は安い方が経済的メリットがあります。一方でもらう方にとっては、当然高い方が子どものためになりますので、なかなか話し合いに折り合いがつかないことも多いです。
実務では、基本的に裁判所が作成した養育費算定表を利用し、子どもの人数や年齢、両親の年収などを考慮して算定します。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 (courts.go.jp)
自分のケースの養育費の相場はどれくらいか知りたい方は、「養育費自動計算ツール」をご利用ください。子どもの数、年齢、両親の収入を入力すれば、養育費のだいたいの相場を知ることができます。
養育費は話し合いで決めるほか、調停・審判で決める方法もあります。決め方や計算方法について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
養育費に贈与税がかかるケース
養育費が、先ほど説明した「通常必要と認められるもの」とされない場合には、贈与税の課税対象となります。
課税対象となる可能性がある養育費には、次のようなものがあります。
- 将来分を含めた一括払い
- 養育費を貯金している
- 養育費で株式や不動産を購入した
(1)将来分を含めた一括払い
養育費は、今現在生じる子どものための生活費や教育費として毎月請求権が発生しますので、一括払いではなく、月払いが原則です。
扶養義務は、今かかる子どもの生活費や教育費に対して生じるものであり、具体的には扶養義務が生じていない将来の養育費の分まで、当然に一括で請求できるものではないためです。
そこで、将来分の養育費を一括で受け取った場合には、「通常必要と認められる」範囲とは言えず、基礎控除額110万円(その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた合計額)を超える部分について贈与税の課税対象となる可能性があります。
贈与税は累進税率を採用しており、税率は贈与を受けた金額によって異なります。
【贈与税の速算表(一般贈与財産用)】
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
例えば、8歳になったばかりの子が20歳になるまでの養育費を、月5万円として単純計算して一括で受け取るとすると、5万円×12ヶ月×12年=720万円になります(※)。
基礎控除後の課税価格は、720万円 ― 110万円 = 610万円
贈与税額は、610万円 × 40% - 65万円 = 179万円 となります。
※わかりやすくするために、中間利息は控除していません。通常一括で受け取る際には、中間利息を控除しますので、その分単純計算よりも金額は低くなります。
このケースだと、約3年分の養育費相当額を贈与税として納税する必要がありますので、税負担は決して軽いものではありません。
(2)養育費を使わずに貯金している
養育費を生活費や教育費として使わずに貯金した場合、その預貯金は「通常必要と認められるもの」とはされず、課税対象となる可能性があります。
養育費が贈与税の対象とならないのは、生活費や教育費として必要なときに、直接それらに利用するために贈与されたお金だからです。
使わないで貯金すると、生活費や教育費としては必要と認められない、というのが実務の運用です。
参考:相続税法基本通達21の3-5|国税庁
(3)養育費で株式や不動産を購入した
養育費を生活費や教育費として使わずに、株式や不動産を購入した場合、その購入代金は「通常必要と認められるもの」とはされず、課税対象となる可能性があります。
養育費が贈与税の対象とならないのは、生活費や教育費として必要なときに、直接それらに利用するために贈与されたお金だからです。
生活費や教育費として使わずに株式や不動産を購入したのなら、生活費や教育費として必要と認められない、というのが実務の運用です。
参考:相続税法基本通達21の3-5|国税庁
一括払いの養育費を非課税にする方法
「将来不払いになる可能性があるから、どうしても一括で受け取りたい」
不払いへの不安や心配は理解できます。
相手に一括払いできる財力があり、一括払いに同意しているのなら、あとの問題は税金です。
次のような方法をとれは、贈与税の課税対象とはなりませんので、参考にしてください。
(1)教育資金贈与信託
信託銀行で、教育資金贈与信託契約を締結して、必要な書面・資料を提出するなどすると、養育費を支払う側が信託銀行に一括で預けた金額については、非課税となります。
ただし、この制度を使うためには主に次のような条件があります。
- 教育資金の一括贈与に限られること
- 学校等以外に直接払う費用のほかに、学習塾やスポーツ教室、ピアノなどの習い事の費用も社会通念上相当であれば教育資金に含まれる
- 子どもが30歳未満であること
- 非課税は1500万円まで
- 教育資金として利用したことがわかる領収書などを提出する必要がある
- 契約終了後、残額があるときは贈与税の課税対象となる
- 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの特例
参考:教育資金非課税措置Q&A(令和5年4月1日現在)|文部科学省
教育資金の一括贈与に限られるので、支出の理由を問わず、自由に信託財産を使えるわけではありません。
また、贈与税が非課税となるためには、他にも細かな条件があります。信託報酬を支払う必要があり、報酬額は信託銀行によって異なります。
しかし、条件を満たせば一括で贈与を受けた教育資金については、非課税となります。
詳しい手続きについては、実際に教育資金贈与信託を考えている信託銀行に問い合わせてみるようにしましょう。
(2)養育費の一括払いとせず財産分与の中に含める
離婚の際に財産分与や慰謝料として受け取った財産は、通常、贈与税の課税対象とはなりません。
財産分与は、贈与ではなく、夫婦で築き上げた財産を清算するなどの財産分与請求権に基づく給付だと考えられているからです(民法768条)。また、慰謝料も精神的苦痛を慰謝するための給付であり、贈与とは異なると考えられています。
そこで、養育費の一括払いとはせず、離婚の際の財産分与や慰謝料の支払いの中に含めて、まとめて解決することで、非課税とすることができます。
ただし、「財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当である」とされた場合には、過当とされた部分について贈与とされ、贈与税がかかりますので、注意が必要です。
また、「離婚が贈与税や相続税を免れるために行われた」とされる場合には、離婚で受け取った財産すべてに贈与税がかかります。
財産分与についてより詳しくは、こちらの記事をご覧ください。財産分与の基礎知識や注意点、財産分与の対象となる財産などについて知ることができます。
養育費の贈与税に関してよくある質問
(1)養育費を支払った側に贈与税がかかる?
養育費を支払った側に、贈与税はかかりません。
養育費を受け取った側も、原則として贈与税はかかりませんが、ご説明した通り一括で受け取るなど「通常必要と認められる」範囲を超える場合には、贈与税がかかります。
(2)養育費を支払った側に所得税がかかる?
基本的に、養育費を支払った側に、養育費を支払ったことを理由として所得税はかかりません。
ただし、養育費ではなく財産分与として不動産や有価証券などを渡す場合には、その時に譲渡があったものとして、支払った側に譲渡所得があれば課税対象となります。また、一括で養育費を払うために不動産や有価証券を売却してお金を準備した場合には、売却時に譲渡所得があれば課税対象となります。
(3)養育費を支払っている側に扶養控除は認められる?
養育費を支払っている側も、もらっている側も、子どもと「生計を一にしている」といえれば、扶養控除が認められる可能性がありますが、認められるのは一方のみです。
簡単に扶養控除について説明をします。
納税者に扶養親族がいるときは、所得金額から一定の金額を控除することができ、これを扶養控除といいます(所得税法84条)。
扶養親族とは、納税者の配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にし、所得金額が48万円以下の人をいいます(所得税法2条1項34号)。
【扶養控除額一覧表】
| 親族の種類 | 扶養控除額 |
| 一般の扶養親族 (16歳以上19歳未満又は23歳以上70歳未満の人) | 38万円 |
| 特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人) | 63万円 |
| 老人扶養親族(扶養親族のうち70歳以上の人) | ・同居老親等以外 48万円 ・同居老親等 58万円 |
扶養親族かどうかは、その年の12月31日の現況調査によることとなっており、その時点で、子どもの父又は母と「生計を一つにする」と認められれば、父又は母に扶養控除が認められます。
国税庁は、子どもと同居せずに養育費を支払っている側が、「生計を一にする」と認められる場合として、下記の条件を明らかにしています。
1 扶養義務の履行として支払われる場合
2 子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合
参考:生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁
したがって、例えば離婚後の父親が成人まで負担する約束の養育費を、毎月送っているケースでは、「生計を一にする」として父親に扶養控除が認められることがあります。
養育費を支払う側は、離婚するまでは扶養控除を受けて手取りが増えていた人が多いです。離婚後も養育費を支払っていくにも関わらず、扶養控除が受けられずに手取りの収入が減ってしまうことに抵抗を感じる人もいます。
一方で、もらっている側としては、養育費は子どもの生活費をまかなうのに十分な額ではないのに、自分は扶養控除を受けられず、支払っている側が扶養控除を受けるのに不満を感じることも十分理解できます。
離婚後のトラブルを防ぐためには、離婚の際に扶養控除をどちらが受けるかについても話し合っておくことが望ましいです。その際には、養育費は子どもの生活費すべてを賄うには十分でないこと、同居して育てていくのは自分であることを伝え、扶養控除を外してもらうとよいでしょう。
【まとめ】原則として養育費に贈与税はかからないが、一括でもらうときは要注意
この記事のまとめは次のとおりです。
- 養育費には原則として贈与税も所得税もかからない
- ただし、将来分を一括でもらう、使わずに貯金する、株式や不動産を買うなどし、養育費が「通常必要と認められる」範囲外とされると、贈与税の課税対象となる
- 養育費を一括でもらいたいときには、教育資金贈与信託や財産分与の中で解決することを検討する
- 非課税となる教育資金贈与信託には細かい条件があるので、信託銀行に問い合わせて理解したうえで利用する。
離婚の際には、養育費だけでなく、財産分与や慰謝料など話し合って解決しなければならない問題が多くあります。
お互いに信頼関係があれば、話し合いでの解決を目指すこともできます。
しかし、もう信頼関係もなく、話し合うこともできない、生理的に話し合うこともいやだ、という状態に陥ってしまう方も少なくありません。
離婚の悩みを、1人で抱える必要はありません。
弁護士であれば、あなたの不安に寄り添い、あなたの利益を第一に考えて、あなたの代わりに相手と交渉することができます。
一度、相談だけでもしてみませんか。
アディーレ法律事務所では、養育費を含めた離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることはありません(2024年11月現在)。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール「0120-554-212」)にご相談下さい。