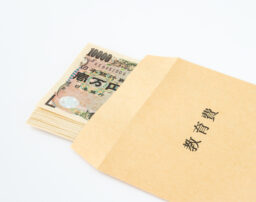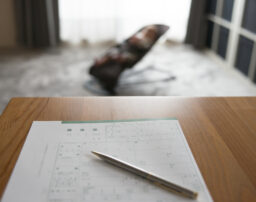再婚を考えている方にとって、再婚相手と連れ子の関係をどう築くかは大きな課題です。
特に、養子縁組をするかどうかは重要な決断となります。このコラムでは、養子縁組をすることで発生するさまざまな影響と、再婚時に必要な手続きについて詳しく解説します。
これを読むことで、再婚相手と連れ子の間で養子縁組を組むかどうかを決める参考になるでしょう。再婚をスムーズに進めるために、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでわかること
- 養子縁組をすることで発生するさまざまな影響
- 養子縁組を組む・組まない場合に必要な手続
- 養子縁組以外で必要な手続
ここを押さえればOK!
養子縁組を行うと、子どもの名字が再婚相手の名字に変わり、互いに扶養義務が発生します。また、再婚相手の相続権も発生し、前の配偶者からの養育費が減額される可能性があります。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、前者は市区町村への届出だけで手続が完了し、実親との親子関係も残ります。
後者は家庭裁判所の審判が必要で、実親との親子関係が消滅しますが、認められるのは限られたケースです。
養子縁組をせずにあなたが再婚相手の戸籍に入る場合、あなたが再婚相手の戸籍に入っても、子どもの戸籍や名字は変わりません。
子どもの戸籍や名字を変更する場合には、家庭裁判所への子の氏の変更を申し立てて役所に入籍届を出す必要があります。
再婚時に養子縁組をするかどうかは、子どもと相談し、慎重に決めることが重要です。
養子縁組を組むかどうか悩んでいるあなたが知っておくべきこと
養子縁組とは、子どもと法律上の親子関係を結ぶ手続のことをいいます。
「再婚相手と連れ子の間で円満な親子関係ができてほしい」とは子連れ再婚者の誰もが望むことですが、養子縁組を組んで、法律上の親子関係まで結んでほしいと思うのは人それぞれです。実際、再婚の際に再婚相手との間に養子縁組を組む方もいる一方で、養子縁組を組まない方もいらっしゃいます。
ここでは、養子縁組を組むことによって変わることを解説します。
(1)養子縁組を組むと子どもの名字が変わる
養子縁組を行うと、子どもの名字が再婚相手の名字に変わります。名字の変更は子どもが嫌がる可能性もありますので、事前に子どもと話し合うなどするとよいでしょう。進学のタイミングなど名字の変更による影響が少ない時期を選ぶのも1つの選択肢です。
一方で、養子縁組を行わない場合、子どもの名字を変更するかどうか選ぶことができます。再婚して親の名字が再婚相手と同じ名字となっても、子どもの名字はそのままということも可能です。
(2)養子縁組を組むと扶養義務が発生する
養子縁組をすると、法律上再婚相手に子どもの間互いに扶養義務が発生します。言い換えると、再婚相手は子どもの生活費や教育費を負担する責任を持ち、子どもも将来的に再婚相手に対して生活費などを負担する責任を負うということです。
もし再婚相手から子どもの生活費や教育費を払ってもらえない場合には、家庭裁判所での調停などを通じて再婚相手に対し子どもの生活費や教育費を請求することができます。
(3)養子縁組を組むと相続権が発生する
養子縁組を行うことで、子どもは法律上再婚相手の相続権を持つことになります。これは、再婚相手が亡くなった場合、子どもが遺産を受け取る権利があることを意味します。
(4)養子縁組を組むと養育費が減額する可能性がある
養子縁組を行うと、前の配偶者から支払われている養育費が減額される可能性があります。これは、養子縁組を組むことで再婚相手が子どもの扶養義務を負うからです。
養育費の減額には前の配偶者との協議や家裁での審判などが必要ですが、もし家裁での審判となった場合、再婚相手と養子縁組をしたとなると、養育費の減額が認められやすい傾向にあります。
養子縁組を組む・組まない場合の手続
連れ子と再婚相手との間で養子縁組を組む・組まない場合の手続の違いを説明します。
(1)子どもを養子にする場合の手続
子どもを養子にする場合、「普通養子縁組」を組むか「特別養子縁組」を組むかによって必要な手続が異なります。特別養子縁組を組むには難しい要件が課されていますので、普通養子縁組を組む人がほとんどです。
(1-1)普通養子縁組とは
養子縁組をすると、新たな親子関係ができ、実親との親子関係はなくなるようなイメージをお持ちかもしれません。
しかし、普通養子縁組では新たな親子関係を結んでも、実親との間の法律上の親子関係は残ります。言い換えると、普通養子縁組を組んだ後も、実親が子どもの扶養義務を負っていたり、子どもが実親の財産を相続する権利を持ったりしたままということです。
<普通養子縁組を組む手続>
再婚相手と連れ子の間に普通養子縁組を組む場合には、市区町村の役場への養子縁組の届出を出すだけで足ります。
子どもが15歳以上の場合には普通養子縁組を組むことについて子どもの同意が必要です。一方、子どもが15歳未満の場合には子どもの法定代理人(親権者など)が子どもに代わって同意をすることが必要となります。
(1-2)特別養子縁組とは
実親との法律上の親子関係をなくす特別養子縁組という制度もあります。しかし、特別養子縁組は、こどもの利益のために特に必要がある場合に限り、家庭裁判所の手続により成立します。そのため、特別養子縁組が認められるのは実親から虐待を受けていたなどの限られた場合が多いといえます。
<特別養子縁組を組む手続>
特別養子縁組を組むには、市区町村の役場への養子縁組の届出を出す前に、家庭裁判所での審判と原則実親の同意が必要です。また特別養子縁組を組むには原則子どもが15歳未満である必要があります。
(2)子どもを養子にしない場合の手続
再婚時に子どもを養子にしない場合に必要な手続を説明します。
(2-1)あなたが再婚相手の戸籍に入る場合
あなたが再婚相手の戸籍に入る場合、婚姻届を提出します。
あなたが再婚相手の戸籍に入った場合、あなたの名字は再婚相手と同じとなりますが、子どもの戸籍や名字は変わりせん。子どもの名字を変更する場合には家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをし、市区町村の役場に入籍届を提出する必要があります。
(2-2)再婚相手があなたの戸籍に入る場合
再婚相手があなたの戸籍に入る場合も、婚姻届を提出します。この場合、子どもの戸籍に変更はなく、再婚相手があなたの戸籍に入るだけです。
養子縁組以外で必要な手続
再婚時に必要な手続きは、養子縁組だけではありません。ここでは、再婚後に必ず行うべき手続きを解説します。
(1)児童扶養手当資格喪失の届出
再婚すると、児童扶養手当の資格を失うことになります。児童扶養手当は、ひとり親家庭を支援するための制度であり、再婚によって新たな再婚相手が生活を支えるようになると支給対象外となります。
そのため、再婚後は速やかに市区町村役場に「児童扶養手当資格喪失届」を提出する必要があります。これを怠ると、不正受給と見なされ、返還を求められることがあります。
(2)健康保険の扶養手続き
子どもを再婚相手の扶養家族とするのであれば、健康保険の扶養に入れる手続きが必要です。具体的には、再婚相手が勤務する企業の健康保険組合に「被扶養者異動届」を提出し、必要な書類を添付します。
(3)金融機関や各種保険の名義変更
再婚に伴い、金融機関や各種保険の名義変更も行う必要があります。これには、銀行口座やクレジットカード、生命保険、自動車保険などが含まれます。
【まとめ】再婚時に養子縁組を組むかは子どもと相談して決めよう!
再婚を考える際、養子縁組をするかどうかは重要な決断です。
養子縁組をすると子どもの名字が変わり、扶養義務や相続権が発生し、場合によっては養育費が減額される可能性もあります。名字が変わりたくないなどの場合には、養子縁組を組まないという選択肢もあり得ます。
子どもが15歳以上であれば養子縁組を組むには子ども自身の署名が必要です。子どもとよく話し合って決めるようにしましょう。
ぜひ、再婚後の生活を安心して始めるために、適切な手続きを進めましょう。